VixenのSUPER-POLARIS-FL-90Sというフローライト鏡筒で撮影してみました。
D=90mmF9 , FL=810mmという鏡筒です。
いろいろ調べたり実験した結果、NLV25mmとLX7のレンズ間距離は1.7mmが最良点
であることが判明。従って、前回11mm切断して短縮したDG-NLV DXアダプターを
更に3mm詰める加工を行いました。

アイピースをねじ1本で固定するために光軸がずれてしまうイヤな構造です。
ズレないように見口のプラ部分に紙を多重に巻いてピッタリと入るように
小細工を行いました。また、DG-NLV DXアダプターは汎用性が高い半面、
やたらと3点固定ネジが多くて間違いやすいです。
そのため、カメラ回転に使う1箇所のみを残してセットビスで固定しました。
DG-NLV DXアダプターの調整ネジはピッチ0.7mmです。
4mm厚の固定リングを入れた状態でアイレンズ←→LX7前玉距離が1mmです。
そこで、1回転、2回転・・・6回転まで試写したところ、1回転目が一番良像
となりました。つまり1.7mmの位置です。
ピント合わせは6X30ファインダーをアイピースに押し当て、γCygを写野中心付近
に置いて行いました。

このピント位置のまま撮影したh,χです。
合成F=1.69 , ISO320 , 60secX1

凄いですねえ~、周辺まで点像ですよ。
フローライトなので色収差もありません。
この星像ならば十分に実用域に達していると思います。
但し、
アイレンズに1.7mmまで近付けているといことは、LX7の前玉に十分な光量が
入射していないことを意味します。つまり、中央集光、周辺減光となります。
このh,χはcs5で新規レイヤーを作って円形レベル補正1回で補正してあります。
素直な光量ムラなので、フラットを適用しなくても作例程度にはなりました。
ところが、M31やバラ星雲など、写野一杯に広がるような対象は苦手です。
周辺の淡い所が出ないのです。そこで、
周辺星像がダメダメになることを覚悟でレンズ間距離を5.2mmまで広げたところ、
全面に十分な光量が入って来て画像も明るく周辺減光もほぼ無くなりました。
その条件で撮ったのが以下の作例です。
撮影地:飯能市郊外で庭撮り。
バラ星雲 ISO800 , 60secX9

M31 ISO800 , 60secX4

M33 ISO800 , 60secX4

M1 ISO800 , 60secX4

M42 ISO800 , 60secX2 + 30secX2 + 15secX2 , 3m30s Total

次回はh,χと同じ正規の位置で撮ってみたいと思います。
つづく
D=90mmF9 , FL=810mmという鏡筒です。
いろいろ調べたり実験した結果、NLV25mmとLX7のレンズ間距離は1.7mmが最良点
であることが判明。従って、前回11mm切断して短縮したDG-NLV DXアダプターを
更に3mm詰める加工を行いました。

アイピースをねじ1本で固定するために光軸がずれてしまうイヤな構造です。
ズレないように見口のプラ部分に紙を多重に巻いてピッタリと入るように
小細工を行いました。また、DG-NLV DXアダプターは汎用性が高い半面、
やたらと3点固定ネジが多くて間違いやすいです。
そのため、カメラ回転に使う1箇所のみを残してセットビスで固定しました。
DG-NLV DXアダプターの調整ネジはピッチ0.7mmです。
4mm厚の固定リングを入れた状態でアイレンズ←→LX7前玉距離が1mmです。
そこで、1回転、2回転・・・6回転まで試写したところ、1回転目が一番良像
となりました。つまり1.7mmの位置です。
ピント合わせは6X30ファインダーをアイピースに押し当て、γCygを写野中心付近
に置いて行いました。

このピント位置のまま撮影したh,χです。
合成F=1.69 , ISO320 , 60secX1

凄いですねえ~、周辺まで点像ですよ。
フローライトなので色収差もありません。
この星像ならば十分に実用域に達していると思います。
但し、
アイレンズに1.7mmまで近付けているといことは、LX7の前玉に十分な光量が
入射していないことを意味します。つまり、中央集光、周辺減光となります。
このh,χはcs5で新規レイヤーを作って円形レベル補正1回で補正してあります。
素直な光量ムラなので、フラットを適用しなくても作例程度にはなりました。
ところが、M31やバラ星雲など、写野一杯に広がるような対象は苦手です。
周辺の淡い所が出ないのです。そこで、
周辺星像がダメダメになることを覚悟でレンズ間距離を5.2mmまで広げたところ、
全面に十分な光量が入って来て画像も明るく周辺減光もほぼ無くなりました。
その条件で撮ったのが以下の作例です。
撮影地:飯能市郊外で庭撮り。
バラ星雲 ISO800 , 60secX9

M31 ISO800 , 60secX4

M33 ISO800 , 60secX4

M1 ISO800 , 60secX4

M42 ISO800 , 60secX2 + 30secX2 + 15secX2 , 3m30s Total

次回はh,χと同じ正規の位置で撮ってみたいと思います。
つづく











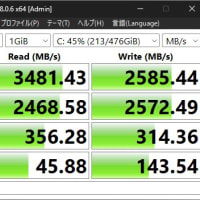
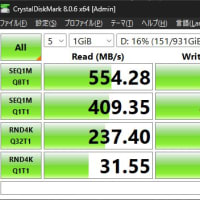













フランジバックが1.7mmのときの星像が鋭いですね。しかし、周辺光量との兼ね合いで5.2mmですか。どちらをとるか悩ましいですね。
しかし、貴重なビクセンの9cmフローライトをお持ちとは、いろいろな種類の望遠鏡を所有されているのですね。
遠征していてお返事が遅くなりました。m(__)m
この時は正規の位置1.7mm→5.2mmとしましたが、ピントを合わせる星は視野中央で
行いました。昨日のデータでは視野端から1/4付近で合わせれば3.1mmの位置で良い
ことが判明しています。やはり、あまり正直に視野中心で合わせるのは得策では
ないようです。
縮小コリメートに興味を持ち、☆男さんのHPを教科書にして、トライしていますが、周辺像が、回転ひずみでうまくいきません。
鏡筒はペンタックス105SDHFでアイピースはビクセンのLV25です。コンデジは
LX-7。
主点のあわせ方が難しく、試行錯誤です。そこで質問ですが、このアイピースの場合、レンズ間の距離は1.7ミリ云々とか書かれていますが、どのように測っているのでしょうか?
アダプター内でノギスで測れないので、?なんです。
あつかましいお願いですが、宜しくお願いします。
周辺部グルグルは望遠鏡の無限遠設定が出来ていない
時に起こりやすいです。ケンコーの4倍モノキュラー
でNLV25mmを覗いて望遠鏡側を無限遠に設定して
ください。目で直接NLV25mmを覗いたのでは
正確に設定出来ません。人間の目はオートフォーカス
が利きますし、体調や個人差で著しくバラツキます。
NLV25mmから射出される光束が平行光になるように
するわけです。
その上で、LX7のマニュアルフォーカスアシストレバー
を操作し、2m~∞マークの中間辺りにセットします。
コレは広角端4.7mmの場合です。
NLV25mmは視野50°で素性の良いアイピースです。
像面湾曲が大きいC-8でもかなり周辺部まで点像に
なりますから、お使いの鏡筒であれば問題なさそうです。
1.7mmなどの距離は正確です。
ノギスでアイピースのレンズ縁段差を測ったり、
LX7のレンズ縁段差を測ったり、切り詰めたアダプターの
ネジピッチを加算したりして決めています。
汎用のユニバーサルアダプターでも上手くやれば
撮影できますが、光軸の再現性は無く、定量性に欠けます。
しかし、実験的に傾向を掴むのには便利です。
やはり、望遠鏡側の無限遠が出ていないのでは
ありませんか?LX7側でピントを合わせているならば、
それは間違いです。LX7側は無限遠のみの一択です。
LX7側でピントを合わせることも出来ますが、
主点がズレて周辺グルグルになります。
モノキュラーは星で無限遠に設定しておく必要があります。
NLV25mmではなくLV25mm出したね。
おそらくは同じ特性だと思いますが、私は使ったことが
無いため、断言はできません。
早速のアドバイスありがとうございます。
ピントは貴殿の通りに、ファインダー(6*30)を使ってあわしたのですが、またカメラ側も実際の星での無限遠にあわせたのですが。もしかしたら アダプターに原因があり主点がまったくあってなかったのかもしれません。
ガラクタ箱を探っていると大昔のコリメートアダプター(LV25がぴったり納まる)
が出てきたので、37φフィルターねじに直結して試してみます。
アドバイスを参考にデジタルノギスで測ったところ、おそらくこの場合レンズ間距離は
4ミリ程度になりそうです。 1.7ミリにするには、そのアダプター内を深く削らねばなりませんが、旋盤は持ってないので、仕方ありません。
休みの日に晴れれば、庭撮りで調べてみて報告します。
アダプターの中でアイピースを固定する際”カメラレンズ側に寄せて固定”
でどうでしょうか(^^♪
ご報告お待ちしております!
今日の月食、当地も晴天で、月食観察はそこそこにして、縮小コリメート主点あわせを再トライしました。ファインダーで無限遠を出しました。 フリップミラーにボーグのSD-1をつけて中にアイピースLV25を入れSD-1のスライドする外筒にバーニヤを貼り、0.5ミリづつずらしながら試写しました。 結果 私の主鏡筒SDHF(ボーグ1.4テレコン使用)では、LX-7の広角4.7ミリでは、レンズ間を2ミリ程度にしても 円形写野が小さくまた周辺減光も大きく、使い物になりませんでした。 35ミリF1.6でやっと写野周辺までほぼ点像になりました。この時レンズ間は多分3.8ミリです。
☆男さんと異なる結果なのは、アイピースと鏡筒が違うからなんでしょうね。
あと 私のLX-7は、広角端からズームすると 鏡胴が多少縮み、レンズ間距離が変わります。ですから ズームするたびに再調整せねばならない、ということになるのでしょうか?
以上 報告でした。
昨日は私もチョットだけ皆既中の月を見ました。
LX7は広角端~ズームアップするとレンズが一旦引っ込み、
再度出て来るという動きをしますね。私のもそうです。
F1.6で使えるなら十分に明るいと思いますから、その組合せではF1.6がベスト
だと思えば良いのではないでしょうか。縮小コリメート撮影法ではズーム可変
はご法度かつ、鬼門となります。F1.6で良かったなら、F1.6固定で使うべきです。
何しろ合成F1.4とかF1.6という、望遠鏡としてはあり得ない明るい光学系に
なる訳ですから、光軸には非常に敏感ですし、レンズ間距離の僅かな違いで
雲泥の差になるんです。なのでユニバーサルアダプターや、Vixenのフリップミラー
のようにぐにゃぐにゃ、ガタガタなアダプターはイカンのです。
アイピースをM3ネジで横から1本止めするような安易な固定方法では、
簡単に光軸がずれ、写野の光量分布が醜いことになります。
アイピースに紙を巻いて偏らないようにするなどの小細工が有効です。
また、
私も初めのころは出来るだけ大きな写野を確保しようと2インチアイピース
や60~70度のアイピースを試して来ましたが、そもそもそんなに広範囲で
良像を叩き出す望遠鏡自体が殆どないのです。
私が使った範囲では60度のPhton25mmが屈折鏡筒との相性も良く、広い写野を
確保できました。価格も安いです。(国際光器)
一番相性が無かったのがVixenのNLV25mmで、写野円は小さいですが
宇宙船の窓から覗いているように見えますし、案外気に行っています。
無理に広写野を狙わないことです。
SDHF75mmなら、PENTAX XW20mmが最適かもしれませんね!
このアイピースは高価ですが、友人のテストではダントツとのことです。
SDHF105mmでしたねm(__)m