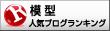昨日掲載記事投稿中に緊急の修正依頼が入った為、その時点で記事をまとめてしまいましたので、今回はその続きです
 フロッサーは、こんな感じで収納されています
フロッサーは、こんな感じで収納されています
予定よりも空間が狭いので、出し入れする際にちょっとコツがいるような仕様になりました。
一応、大きさは計り直しましたが、本体に対するフロッサーの大きさは、これで正解になるので、ポリパーツによるギミックで場所を取り過ぎたのが問題のようです。
 前面からの画像だと分かり難いと思いますので、横から見るとこんな感じに可動しています
前面からの画像だと分かり難いと思いますので、横から見るとこんな感じに可動しています
頭部は60度程度までは倒れるような仕様になっていますが、あまり意味はないですね。
胸部のパネル(外装)部分も、前回は真鍮線で可動させて、固定時に若干のグラつきがありましたが、今回はポリパーツで可動させているので、場所は取りましたが安定性は抜群です。
 ランドブースターを付けた状態で、少し前方に戻りますが、問題無く可動出来、フロッサーの出し入れも大丈夫です
ランドブースターを付けた状態で、少し前方に戻りますが、問題無く可動出来、フロッサーの出し入れも大丈夫です
1/100サイズでやっているので、このサイズでやらなくても良いような気もしますが、同サイズでワークスなんかもあるので、やってみる価値はあると思います。
ちなみにMARKⅡの改造時に、ビュイを造らなかったのは、上部の透明装甲があの大きさと幅でやるのが、ほぼ不可能な感じだったのが要因です。
 武装チェックのラストは、フル装備状態です
武装チェックのラストは、フル装備状態です
関節関係は全てポリパーツで再構成し、可動させないといけない部分は、無理のないレベルで全て可動にしたので、こうしてみると上手くまとまったような気がします。
今更ですが、握り拳が欲しかったような気がしますが、これ以上やっているとキリがないので、止めておきます。
 これもちょっと気になる点なのですが、腕部が垂直状態の時に、普通にシールドを接続すると肩部分に干渉します
これもちょっと気になる点なのですが、腕部が垂直状態の時に、普通にシールドを接続すると肩部分に干渉します
サザビーなんかも同様に、肩部分の張りが大きい機体は腕部を曲げないと、垂直持ちが出来ないのが気になっています。
大型のシールドは恰好は良いのですが、取り回しが困難なのが問題ですね。
 フル装備にサーベルを持った状態、この格好でディスプレイルームに行く予定です
フル装備にサーベルを持った状態、この格好でディスプレイルームに行く予定です
この後、今回の改造時に考慮しておいた、スピリッツとワークスとの合体と収納をチェックします。
ここまでは破損しないで、何とか乗り切ってくれましたので、後数日頑張って欲しい所です。