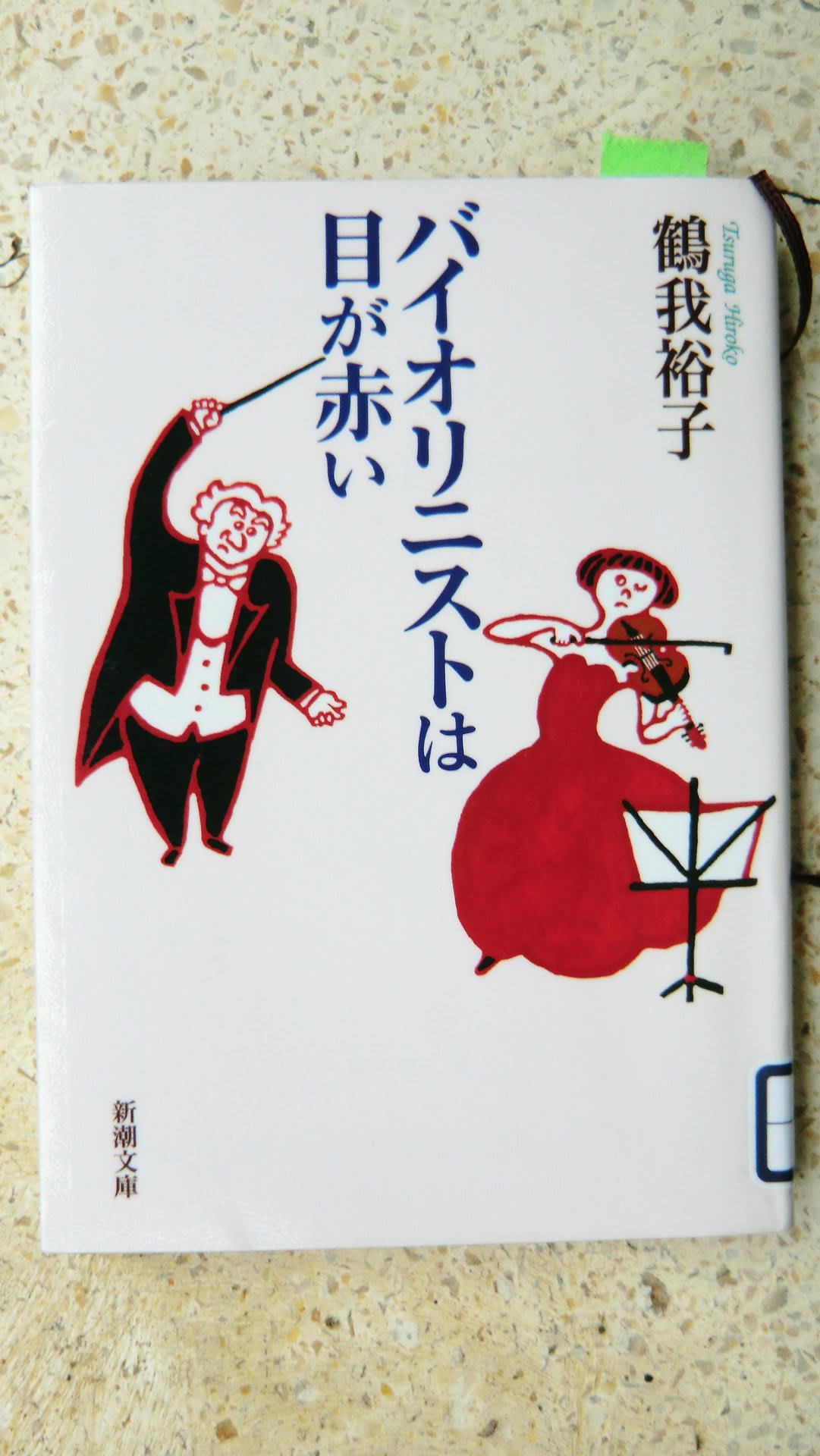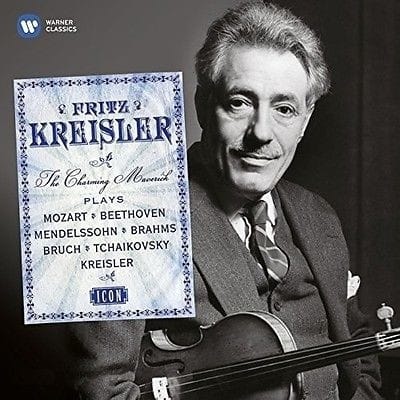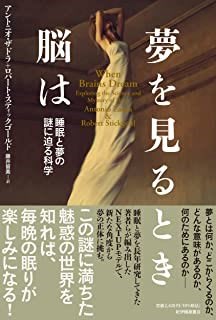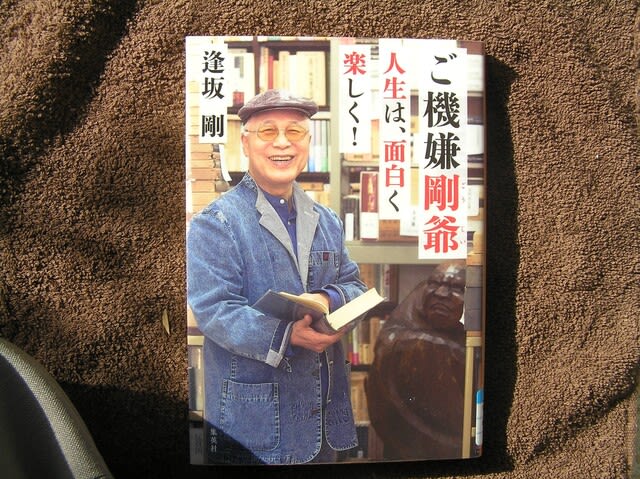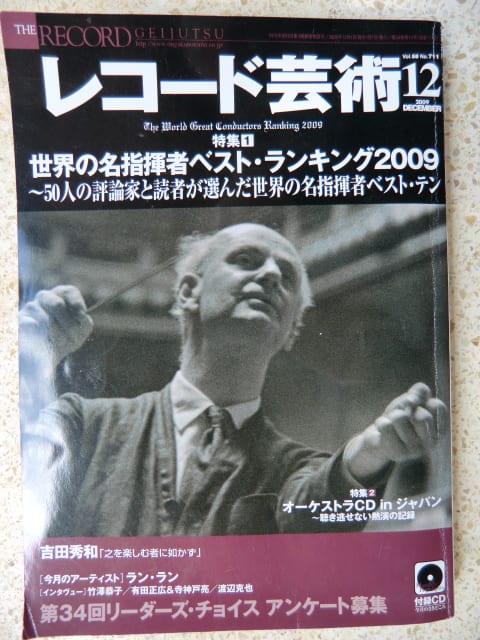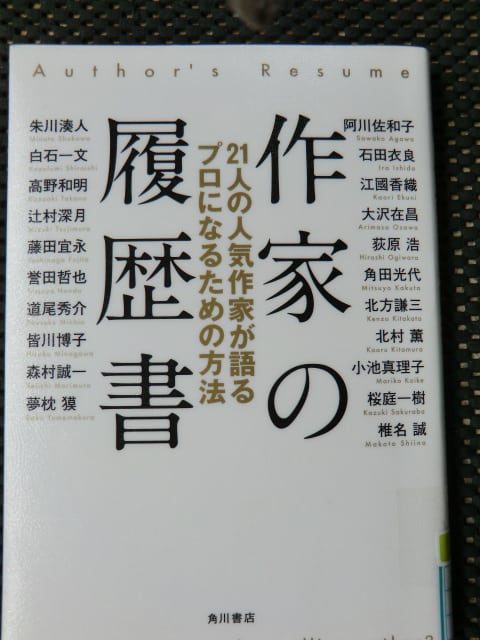「AXIOM80」にウッドホーンを取り付けてからルンルン気分の毎日が続いている。以前にも増して「ええ音楽やなあ・・」とウットリしながらクラシックを聴く機会が多くなった。
もちろん自己満足に過ぎないけどね~(笑)。
いろいろと理論的には 問題があるかもしれない と脳裡の片隅で常に身構えながら自問自答しているのはたしかである。オーディオは 一筋縄ではいかない ことをこれまで嫌というほど経験してきたから~。
で、その第一の課題はホーンの出口の音流の乱れが挙げられる。いろんな資料で指摘されているし、まったく目に見えないだけに始末が悪いが、違和感があるかないか 耳ひいては脳 を最大限に働かせる必要がある。
試しにJBLのホーンのようにハチの巣型(左側)を参考に、メチャ細かい網目を持った金網をホーンの出口に二重に張ってみた。見かけなんてどうでもよろし~(笑)。


一聴して、お~、なかなかいいじゃないか! 心なしか音が柔らかくなった感じがする・・(笑)。
これで「音流の乱れ」は素人なりにひとまず解決といこう。
次の課題は組み合わせるアンプだ。
めちゃデリケートな再生を誇る「AXIOM80」だけに、アンプ次第でころっと音が変わる、それはもう面白いくらいに・・。
今のところ我が家には9台の真空管アンプがあるが、つい先日の「AXIOM80を聴かずしてオーディオを語ることなかれ」(13日付)で述べたように、(AXIOM80に)ホーンを付けた途端に「お金のかかったアンプ」が軒並み総崩れの事態へ~。
ホーン効果により「AXIOM80」の能率が向上し、アンプ側の高出力(といってもせいぜい5ワット程度だが)が、かえって仇となっている感じかな。
言い換えると、10の能力を5割程度以下しか発揮できないためにオーバーパワー気味になって いびつな音 になっている・・。
その点、出力1ワット前後の低出力アンプたちが水を得た魚のように生き生きとしてきたのはご愛敬~、ほら、控えの選手たちが一軍に上がってきて延び延びと躍動している感じかな(笑)。
そして、そのうち目下のところこれら3台のアンプたちが しのぎ を削っている。
左側の2台は折に触れ紹介してきたと思うので、割愛することにして今回の 掘り出し物 はいちばん右側のアンプだ。
その概要は出力管「6SN7」をパラレル接続したもので、たまたま「TRIAD」(アメリカ)の出力トランス(プッシュプル用)が手に入ったので、数年前に知人に急遽組み立てもらったものだが、パワー不足でなかなか本格的な出番がやってこなかった。
前段管は「6SL7」(GEのニッケルプレート)、出力管は「6SN7」(アメリカ:レイセオン)、そして整流管は「GZ32」(英国:ムラード)という陣容。
極めてシンプルな構造で出力は1ワット未満だし、 お金がもっともかかっていない アンプだが実にしっくりくる・・(笑)。
これで、実力伯仲のアンプが3台揃って安心して音楽に浸れるなあ。
安心?
というのも、周知のとおり、真空管は消耗品なので使えば使うほど老年期にさしかかって能力が衰えてくるが、「姥捨て山」に行かせるタイミングが実に計りずらい、それに加えて音がいいとされる「ナス管」はもはや製造不能なので二度と手に入る可能性が薄い。
ちなみに、画像の真ん中に位置している「LS7」アンプはナス管だけど、1970年代前後のST管はオークションにもよく出品されているが、これが古い「ナス管」となると、もう滅多に見かけない・・。
このアンプはナス管じゃないと音色も半減、値打ちも半減するのに・・、したがって後生大事に使ってま~す(笑)。
そういうわけで、真空管アンプの場合「理想的な球」が枯渇して手に入らない恐れがあるので、1台に絞って使うのはたいへん危険である、せめて同クラスのものを2~3台揃えておくと安心~。
いわば「対決の構図」として、「三つ巴の戦い」なんて理想的だとおもうんだけどなあ~(笑)。
道徳的なクリックを求めます →