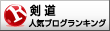今年18回目の木曜会稽古。
四條畷の市民活動センター。少し少なめ、20名ちょい。
六段合格の発表あり。ポイントは「体幹」かな?
稽古は、面、出小手、相小手面、返し胴。
引き出しての間、攻めての間を意識して。
師匠の指導の要点のみ記す。
---------------------------------
五段までが守破離の守。六段七段が守破離の破。七段八段が守破離の離。
守破離の破を修行するには、しっかりとした基本が出来ていなければならない。
基本は左足を基軸とした体幹、左足を基軸とした打突。
左足を基軸とするから間合いがわかる。
遠間、触刃、交刃、一足一刀、打ち間、残心、身構え、気構え。
【構えと間】
左足は真っ直ぐ。ヒカガミは伸ばす。
左足は軸足。蹴ってはならない。
竹刀は左手の小指半掛け、親指は伸ばす。
左拳の位置は真ん中ではなく親指の第2関節が臍前。
左拳は臍前、一拳か一拳半空けて構える。
一足一刀の間で、剣先の向きは、相手の「はれせいがん」「あおせいがん」の当たりに向ける。
相手は距離感が掴めず幻惑される。ここから攻め入って打突する。
間境を身体が越えるのではなく右足だけが越える。左足はパンパンに張っている。
相手が出ようとした時に、こちらは打てる体勢にある。これが先。
間境で、一歩入ろうと、身体が越えてしまうと打たれてしまう。
打てる場所は左足が教えてくれる。ここなら打てるという間。
体軸がズレていると、この間がわからなくなる。
いつ打つか、は相手が教えてくれる。
触刃、交刃の間では、相手をよく見ることが大切。
中心を取ろうと攻め合うのではなく竹刀が交わるところが中心と考える。
打ち間に入る時に中心を取る。
打突の強度、冴えは右手を最後に押し出すことで生まれる。
基本打ちでうまく当たらないのは間合いが間違っているから。
打ち間は自分で思っているより遥かに近い。
一足一刀の間で打てるのは相手が入ってきた場合だけ。
攻め入ってしっかり打つには、相手の鍔元まで入らないと打てない。
だから「どう入るか」が大事になる。左足の引き付けが大事。
遠間では自分の心と身体を作る間、触刃交刃の間は相手を観察する間、
一足一刀、打ち間は攻撃する間、と明確に分けて考えると間合いに明るくなる。
どんな稽古の場合でも、触刃の間では、一回止まること。
間合いを詰める時は小刻みに詰めてはならない。
小刻みに詰めると自分も打てないし相手も守ってしまう。
打つべき機会は「機を見て」。
これは相手が打とうとしたところ。
何かしらの兆しがある。変化の兆しを見て打つ。

(稽古前の風景Ⅰ)

(稽古前の風景Ⅱ)

(稽古後の風景)
四條畷の市民活動センター。少し少なめ、20名ちょい。
六段合格の発表あり。ポイントは「体幹」かな?
稽古は、面、出小手、相小手面、返し胴。
引き出しての間、攻めての間を意識して。
師匠の指導の要点のみ記す。
---------------------------------
五段までが守破離の守。六段七段が守破離の破。七段八段が守破離の離。
守破離の破を修行するには、しっかりとした基本が出来ていなければならない。
基本は左足を基軸とした体幹、左足を基軸とした打突。
左足を基軸とするから間合いがわかる。
遠間、触刃、交刃、一足一刀、打ち間、残心、身構え、気構え。
【構えと間】
左足は真っ直ぐ。ヒカガミは伸ばす。
左足は軸足。蹴ってはならない。
竹刀は左手の小指半掛け、親指は伸ばす。
左拳の位置は真ん中ではなく親指の第2関節が臍前。
左拳は臍前、一拳か一拳半空けて構える。
一足一刀の間で、剣先の向きは、相手の「はれせいがん」「あおせいがん」の当たりに向ける。
相手は距離感が掴めず幻惑される。ここから攻め入って打突する。
間境を身体が越えるのではなく右足だけが越える。左足はパンパンに張っている。
相手が出ようとした時に、こちらは打てる体勢にある。これが先。
間境で、一歩入ろうと、身体が越えてしまうと打たれてしまう。
打てる場所は左足が教えてくれる。ここなら打てるという間。
体軸がズレていると、この間がわからなくなる。
いつ打つか、は相手が教えてくれる。
触刃、交刃の間では、相手をよく見ることが大切。
中心を取ろうと攻め合うのではなく竹刀が交わるところが中心と考える。
打ち間に入る時に中心を取る。
打突の強度、冴えは右手を最後に押し出すことで生まれる。
基本打ちでうまく当たらないのは間合いが間違っているから。
打ち間は自分で思っているより遥かに近い。
一足一刀の間で打てるのは相手が入ってきた場合だけ。
攻め入ってしっかり打つには、相手の鍔元まで入らないと打てない。
だから「どう入るか」が大事になる。左足の引き付けが大事。
遠間では自分の心と身体を作る間、触刃交刃の間は相手を観察する間、
一足一刀、打ち間は攻撃する間、と明確に分けて考えると間合いに明るくなる。
どんな稽古の場合でも、触刃の間では、一回止まること。
間合いを詰める時は小刻みに詰めてはならない。
小刻みに詰めると自分も打てないし相手も守ってしまう。
打つべき機会は「機を見て」。
これは相手が打とうとしたところ。
何かしらの兆しがある。変化の兆しを見て打つ。

(稽古前の風景Ⅰ)

(稽古前の風景Ⅱ)

(稽古後の風景)