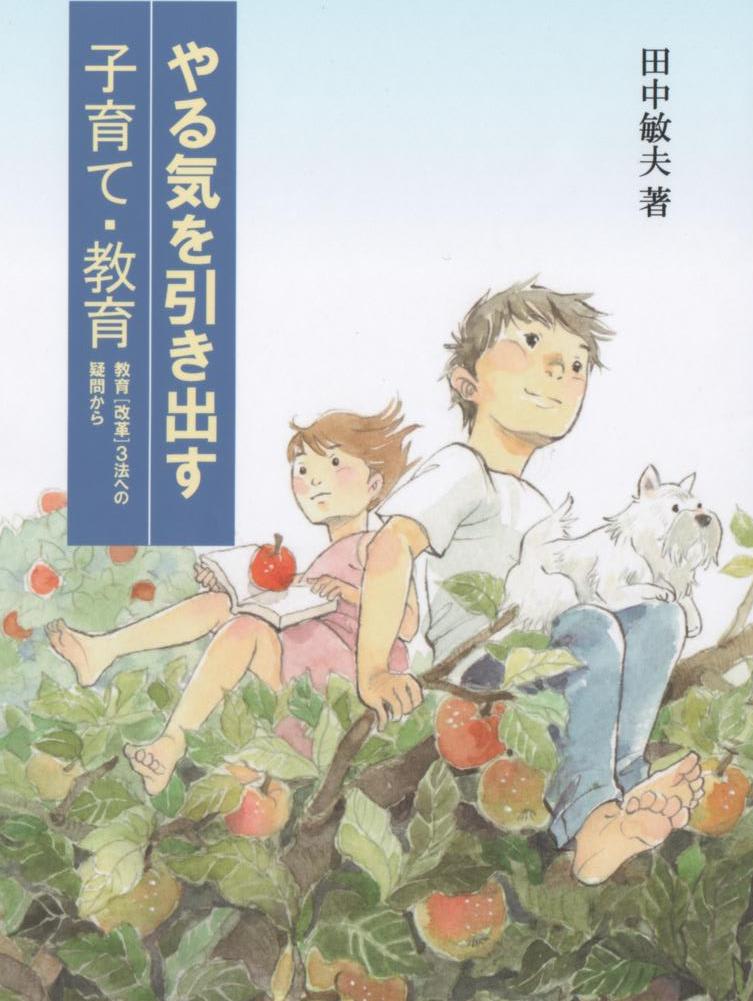中央教育審議会が「学習内容の3割削減」廃止、授業時間増加などを打ち出し「学力」向上対策をまとめました。しかし、授業時間の増加や学習指導要領の見直しで本当に「学力」が向上するのでしょうか。大事なことは、いかにして子どもたちの知的好奇心を旺盛にし、やる気を起こさせるかです。そこでこの本では、子どもたちにどのようにして「やる気を引き出す子育て・教育」をしていくのかを提案します。
『子どものやる気を引き出す子育て・教育』
教育「改革」3法への疑問から
田中 敏夫 著
四六判 216ページ 定価1500円(税込)
ISBN978-88900-848-7
●著者紹介
田中 敏夫(たなかとしお)
・1931年兵庫県で生まれる。1952~1991年神戸市内の小学校に勤務。 1953年秋「神戸作文の会」の創立に加わり、現在に至る。1967年より「神戸子どもを守る会」の活動に加わり、現在副会長。1993年5月~8月国民平和行進 東京~広島間、通し行進者として90日間行進。2002年より「タンポポ親子クラブ」主宰。
・著書 記録集「私の平和行進」(自費出版)「作文どんどん書いたよ――表現意欲を育てる教室」「家族っていいな――お母さん お父さんは素晴らしい」「遊びは成長の糧――瞳が輝くとき、思考も行動も活性化する」(以上、兵庫問題研究所=現、兵庫人権問題研究所)、「子どもが夢中になる50の名場面――小さな子ども王国を地域・学校に」(清風堂書店)、「小学生と非行――指導の道筋と実践例」(共著、民衆社)。
●もくじ
はじめに
第1章 勉強にばかり気をとられていると子どもの真の力を伸ばせない
1 書店にあふれる「学習書」
学力低下はほんとうか?
今も昔も「学ぶ」意欲は変わらない
学習意欲を高めるには
おもしろさと喜びが飛躍のカギ
2 能動的に取り組むそのとき、力を発揮
やらされる勉強は逆効果
子どもの知的欲求が高まるとき
3 世間の風潮に流されず、教育の「ありよう」を考える大切さ
売れなくなった教育関係書
競争させれば学力は伸びるのか
学級内に育った思いやる気持ち
見直すべき学校教育のあり方
第2章 子どもは自分の力が発揮できる場を求めている
1 学習の場に子どもの参加を
「朝の学習」係りを子どもが率先
学習への興味が自然に育つ
希望者多い「当てる係」
みるみる読む力がついた
2 自由意志を発揮する場を
熱心さと根気強さに驚く
遊びを忘れたように一心に
「遊び心」を発揮し活かす場がある
第3章 実体験が子どもの心を育てる
1 子どもの暮らしとメディアの世界
子どもの心の動きに目を向けて
乏しくなる実体験
自らの意思や行為を調整する力
親子の触れ合いと遊びを
2 子どもは自然に触れる機会を求めている
植物観察で喜ぶ子どもたち
よほど楽しかった1日
3 文学作品と自然体験
子どもの感性はみずみずしい
第4章 〈勝ち組〉になる教育は〈競争主義的教育〉から引き継がれてきた
1 曾祖父母・祖父母の世代は〈立身出世主義〉、父母の世代は〈進学〉、そして今、〈勝ち組になる〉教育
教育に競争が必要か
1960年代、塾通いが増加へ
子どもの内なる力と「学び」への欲求
2 能力主義的教育で子どもたちが変わった1970年代
習熟度別学級編成の導入
寂しさ、イライラを綴る
今ではさらに厳しく
3 「勝つ」ための教育から、友達を「思いやる心」は育たない
なぜ社会は荒んだのか
競争に勝つことが目的に
子どもの現実と徳育教育の矛盾
第5章 深刻さ増す「いじめ」・「虐待」
1 「いじめ」は体罰の見直しや出席停止では解決しない
ゼロ・トレランスでは対処できない
満たされぬうっ積した思い
2 なぜ起きる、子どもの虐待
子どもは親の思い通りにはならない存在
心が満たされないままに過ごす子ども期
子どもに心豊かな原風景を
3 競争社会も、親の考えや感情の押し付けも形を変えた虐待
子どもがやる気を失う時
「戦後」のありようを問うこと
平和を大切にする心を育てるカギは
勉強ぎらいになる社会的要因を除く
4 「しつけ」には、子どもの理解が大事
静かに話しか納得させること
大人以上に約束を守る子どもたち
子どもの論理で理解させること
第6章 子どもの「やる気」を引き出すことの肝要さ
1 「やる気」を起こしたとき心が活性化する
脳の発達は、どう育てられたかで決まる
自分が大切にされていることの実感を
第7章 教育「改革」3法の成立で、今後いっそうの困難が予想され
1 教育再生会議と教育再生機構、そして日本会議
「教育の力で清め、再生めざす」
『美しい国へ』と同じ内容
2 『美しい国へ』で本音を述べる
憲法前文は〝詫び証文〟だ
「従軍慰慰安婦に狭義の強制はなかった」
加害の事実から目をそらす歴史認識
歴史の事実は覆い隠せない
3 サッチャー(英国)の教育改革を褒め称える安倍首相
学校査察機関が徹底チェック
「子育て命令法」で親に罰則を
4 授業時間数の増加は「学力向上」につながるか
わかる喜びが大切
特別な意味を持つ長期休業日
5 「ゆとり教育」の狙いを率直に述べた三浦朱門氏
できない子はできないままでよい
「塾」を教育機関と認める
「戦後教育は〝悪平等〟だった」
6 学校教育法を「改正」し、学校評価規定と副校長・主幹・指導教諭を新設
評価基準は上から示される
指導案公開で競争あおる
鍋蓋形の教員構成の崩壊へ
まるで戦前の「視学制度」の復活に
7 教育目標に「国を愛する態度」「公共の精神」など
「徳育」を教科にする
子どもには「毅然たる指導」で対応
徳目の中心に「我が国と郷土を愛する態度」
8 ジェンダーフリー教育禁止を主張する教育再生機構
教育の現在を恣意的に解釈
男女共同参画基本法の廃案をめざす
9 教育職員免許法の「改正」は、物言わぬ教師作りが狙い
大学運営にも新自由主義の波が
教育への介入がねらい
教育の国家管理が最大の目的
第8章 教育基本法が「改正」された今こそ憲法を守る力を
1 「戦後教育は悪平等だった」は憲法の精神に反する
厳然たる格差のあった戦前教育
「特色ある学校作り」でさらに格差拡大へ
2 戦前、「生活綴方教育」は徹底的に弾圧された
弾圧された生活綴方教育
空気のように脈々と生きる憲法
3 小さくても憲法を守る「九条の会」を地域や職場に
近所の人たちが呼びかけ人になって
おわりに
資料編
お問い合わせ、お申し込みはこちらから