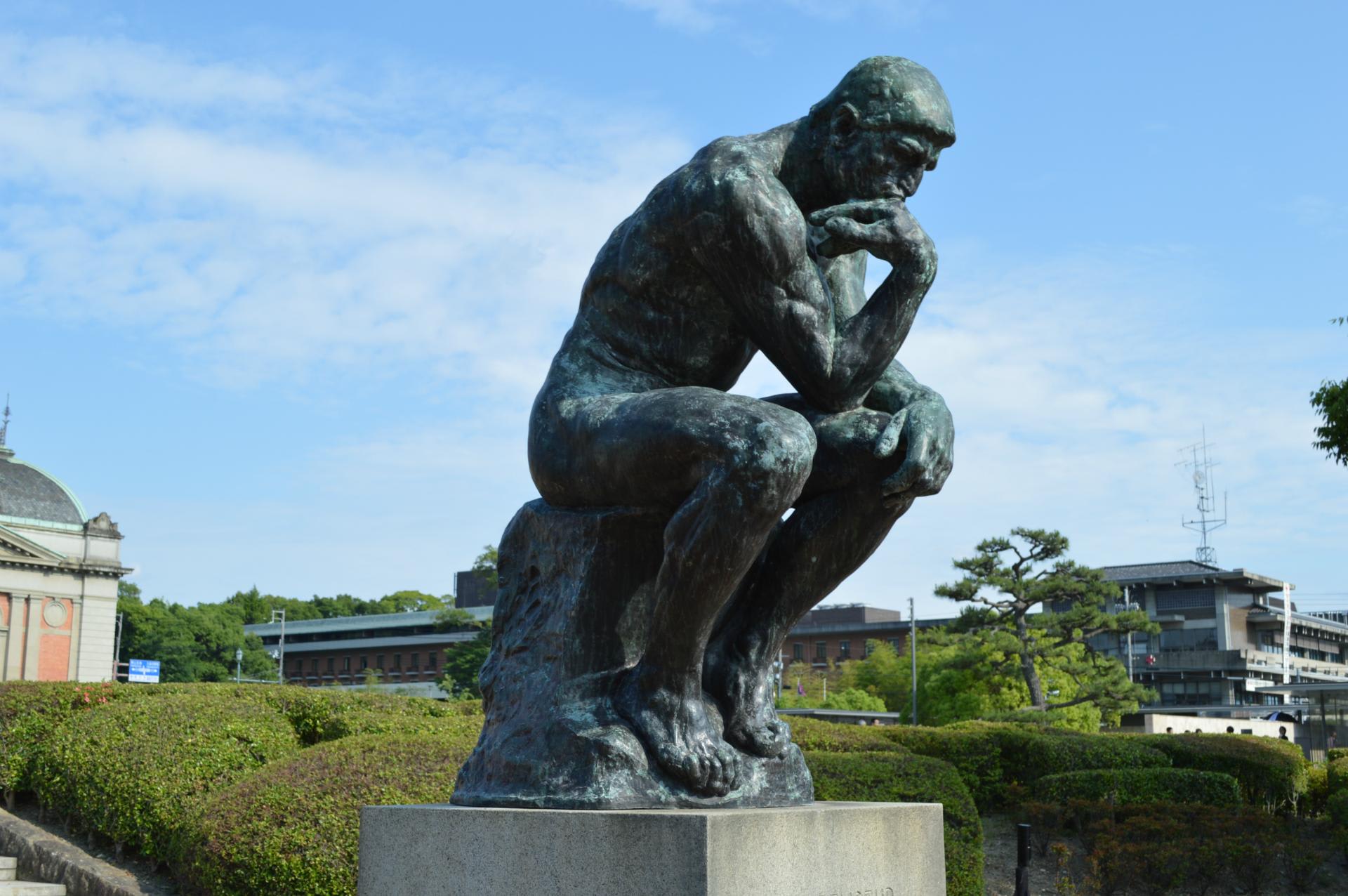門には 北野虫除八幡 と掲げてありました


寳樹寺の開山当時の記録は、
江戸時代二度の火災に遭った為焼失しているので定かではないが、
過去帳序文によると 寛文九年(西暦1668年)の開山と推測される。
境内北側のお堂には弘法大師がまつられ、
七本松通りに面しているため、道行く人の参詣も多い。
戦前は百羽を超える八幡神の使者である鳩が境内を乱舞していたが、
今はその姿はない。通称『鳩寺』の由来です。




南側には子供の『疳の虫封じ』の神として八幡神がまつられている
参考➡ ホームページ 宝樹寺
関通上人
1696~1770 尾張生・浄土宗僧侶 13歳で剃髪、江戸増上寺祐天に学ぶ。
諸国に念仏を広め歩いた。京都轉輪寺(円通寺)にて念仏道場を開く。転法輪寺開山。


關通上人 ➡ ジャンプ 転法輪寺



本公園は,大徳寺の南に横たわる高さ112メートル余の小丘にある公園で,
その地形が船に似ていることから古来船岡と呼ばれ,
眺望が極めてよく,多くの史跡があります。
船岡山は,大内裏の北にあたり御苑に近かったことから,
王朝時代には王候貴人の散策の地とされ,
円融天皇譲位の後は,この山に「子」の日の遊びが催されました。
その後,応仁の乱等の陣地となったこともあります。
明治13年には織田信長をまつる建勲神社
(公園区域外)が中腹に東面して建立され,その後山頂に移されました


階段の途中 右の家 ちょっと ユニークな屋根です
下から 数えると 4階建てのようにも見えます
町中の眺めも いいなあ


洛陽33所観音巡り 第33番札所


第56代清和天皇(在位858~876)ゆかりの寺で、真言宗智山派に属する。平安初期にその後の摂関政治の礎を築いた藤原良房の邸宅「染殿第」の南に仁寿年間既に創建されていた仏心院を基に、清和天皇譲位後の後院として清和院が設けられたのが始まりである。清和院は代々皇子や親王が住し、また在原業平らの歌会の場ともなったが、徳治3年(1308)に再建、仏寺化された。
今も京都御所の東北に「染殿第跡」や清和院御門が現存し、その名残をとどめている。
本尊は、木造地蔵菩薩立像(鎌倉時代・重文)で等身大・玉眼入り、極彩色の精緻を極めた見事な尊像である。玉体地蔵とも呼ばれている。また、傍らには清和天皇坐像、同皇后像と伝える坐像が安置されている。清和天皇が清和源氏の祖であったことから、室町将軍足利氏も深く帰依し、その保護を受けて栄えたが、寛文元年(1661)の御所炎上の際に清和院も類焼し、後水尾院と東福門院によって現在地に移転再興された。また、一条鴨川西岸にあった河崎観音堂が消失後合併されたため、洛陽観音霊場の結願所でもある。京都市


明治30年代の建立

白梅殿 古跡 爪形天満宮








平成27年5月28日 撮影