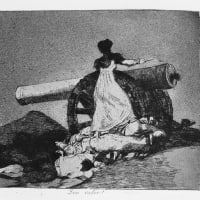この頃の梅雨は,局地的ではげしい。ひと昔前だったら、「しとしと」と優しい雨が、いつまでも静かに降っていた。
大地はたっぷりと水分をふくみ、新緑の青みに深みがます。この時季の木々、葉っぱの匂いは、こころの渇きを癒すようなほっとする潤いをもたらす。
どんなふり方にせよ、大地と植物にとっては恵みの雨には変わりはないはずだが・・。
さて、二、三日前に岳父を見舞いに行き、その後病院関係者と面会するまでの間、バス停で一つ手前の「峯薬師」に足をのばしてみた。
岳父の病室から見下ろすと、こんもりとした小山が見え、そこの新緑の青々しさに目を奪われていた。(病院には3,4回来ている)
東京湾からの海風が、山全体の緑を柔らかくそよがせている。今いかないで、いついくの、と誘われている気がした。
そこが「峯薬師」というお寺さんだということは、妻の方がはやく気がついていて、もはや私が引っ張られるという格好だった。
境内のあふれるばかりの新緑におどろく。大木の銀杏、桜、梅はじめ、樹々の多彩さは圧倒的だ。子細にみると、しっかりと手を入れてい、緑の空間はみごとに調和がとれている。
建物も、手水場、鐘つき堂、本堂ともに立派なもので、年月を重ねた落着きをかもし出していた。
墓参者はいないのでやや淋しさは感じられたが、いつのまにか奥から住職のご母堂がお見えになって、この寺の来歴などいろいろ聞かせて頂いた。
わたしには俄かには理解できなかったが、地面に敷きつめられた絨毯のような、草と苔のはなしには興味をそそられた。クローバーなど地表に生える草グサ、根の張りかた、地面下の植物などの環境をかんがえて、様々な苔を植生させているとのこと。地上のミドリだけでなく、地表のミドリの美しさも手入れされているのはおどろきだ。妻は話にのめりこむが、私は桟敷外となって写真を担当した。
「峯薬師」は通称で、正確には「東光院」といい、奈良時代に行基によって創建されたという由緒ある寺。本尊は薬師如来で有形文化財の秘仏。1980年に解体修理の際、鎌倉時代・文永九年修理の墨書が胎内から発見されたという。
ともあれ、地元藩主の祈願寺だったため江戸時代から檀家はなく、戦後から地元の人々の菩提寺になったという。
ご母堂の懇切丁寧な説明に恐縮するも、いまそこに落ちたばかりの梅を大量に持たせていただき、思わぬお土産となった。
なんという優雅なひととき。九十歳となった岳父とともに、この寺をまた訪れてみたいと強く念じたが・・。
※本堂の入口の右手に大黒様。左手に閻魔象が配置されていた。小ぶりで状態はかなり傷んだ様子だが、なかなかの迫力に魅了された閻魔さまをスナップさせていただく。