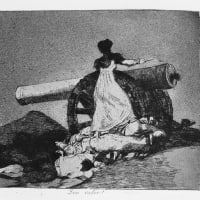渡辺京二の講演を元にした「近代の呪い」(平凡新書)を読んでいたら、眠っていた子が起こされるというか、ハッとする話があった。
幕末の頃、幕藩体制は崩壊の軋みをあちこちに見せ、ペリー来航の前後に多くの外国人が日本に来ていた。坂本竜馬と通じたグラバーは当時二十歳だったか。フリーメイスナリーだったことで、眉唾の都市伝説や様々な憶測が生れたが、そのことを語りたいのではない。
名も残さない、宣教師が横浜に上陸して布教を始めたころのエピソードである。文章にして数行の叙述が私の何かのスイッチを押した。
人間のみを精神をそなえた存在とみなし、他の存在は山川草木はもちろん、人間以外の生物も人間のために神が作ってくれた物質と観じるキリスト教的な精神=物質の二元論、すなわち人間中心主義が前提として存在していたと考えられます。この人間中心主義は、近代ヒューマニズムを生んだのですから、なかなか馬鹿にできないところがあります。しかし、それが一種異様な考え方であることは、幕末に横浜あたりで西洋人の宣教師から聖書を読まされた侍が「おう、おう、人間が草や木より尊いものであろうとは」と感嘆したというエピソードひとつとって明らかでしょう。(149 p)
これだけの逸話で終わる。ただ、この幕末の侍は、草木が人間よりも尊いという価値観なり世界観をもっていることがわかる。宣教師がこれにどう反応したのか、一笑にふしたのか、諦めたのか、聖書の別の教えを示したのか、そのへんの所は書いていない。
渡辺京二自身も、近代文明を成立させたバックボーンである人間中心主義なりヒューマニズムを一種異様なものとして断じている。キリスト教の理解において少々一面的に過ぎはしないかと思われるが、神の創造物としての人間を、確かにキリスト教は別格扱いにしていることは否めないだろう。
自然をすべて資源としてみなし、それを有用活用するという人間の営みは神に担保された。となれば、他の生命を無視しても収奪に向かう。そういう驕りを人間は持つだろうし、力のあるものが全体をコントロールできた例もない。
日本人は草木虫魚、山川、石、樹木などにも生命を感じ、人格として、また神が宿るものとして森羅万象の自然をみてきた。それは西洋的な宗教観からいえばアニミズムだといえよう。が、その世界観・コスモスは、現代のガイア理論や生命の棲み分け論など、現代の最先端にもつながる科学性と通底する。神道はじめいわゆる八百万の神への信仰は、テロを生みだすような一神教とは違って、自然との親和性の高い思想をも備えている。
ま、難しいことは抜きに、神木として樹木を崇め奉る日本人の心性は特有で世界でも類例をみない、ということで落ち着き先を見出したい。
今のご時世だから「人間が草や木より尊い」と宣うなら、「人権はどうなる」などと早速横やりが入りそうなものだが、山に登り、森に入れば、まず気分は変わる。最近そういえばどんぐり集めはやっていないが、ボランティア・グループのどんぐりストラップづくりは継続しているだろうか・・。
とにかく、日本には樹木を大切にする文化があるし、信仰にまで昂める心性をもつ人々は多い。これは世界に誇れることだし、悦ぶべきことだと思う。


▲プラタナスの並木があちこちで伐採の対象になっているらしい。枯葉が多いやら歩行の邪魔になるからとか、要するに何かの効率化だろうな。

▲神木を見ると、なぜか写真を撮りたくなる。良くないことと知りつつ、やってしまう。奥多摩にて

▲神奈川県の大山。下も同じ。

▲阿夫利神社上社の御神木。先日、1000年以上の寿命があるという「醍醐桜」をテレビで見た。桜の神木はほんとに神々しく、畏れおおい美しさがある。