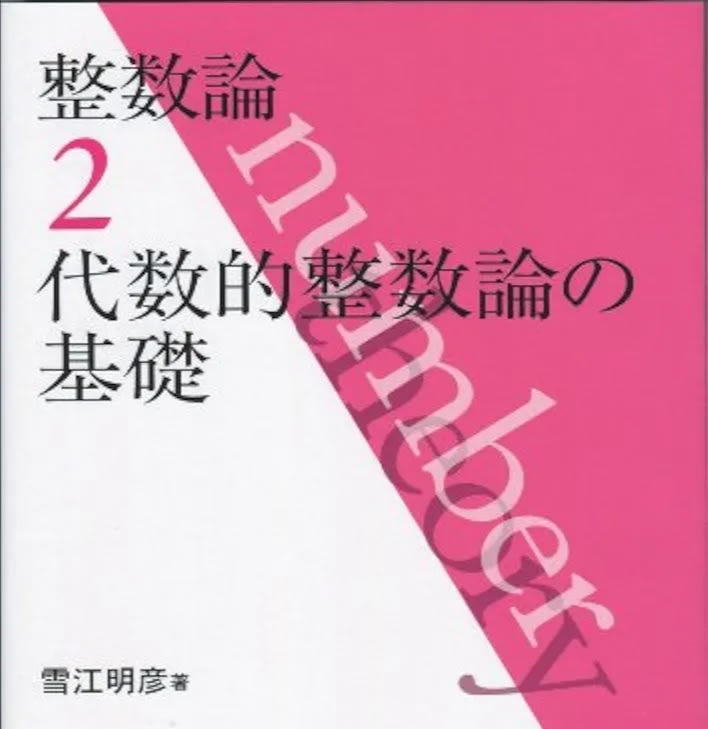
イデアルの概念に慣れ親しんで頂く為に、前回「その4」の最後の補足とその続きを見ていきますが、イデアル類群Cₖ={Pₖ,P₀Pₖ}の計算をK=Q(√(−5))と言う2次体の例を使って説明しました。
更にその応用として、xとyの2元2次形式のx²+5y²で表す事のできる素数pについては、以下の「ラグランジュの定理」が有名でした。
つまり、”素数pに対し、(a)p≡1,9(mod20)の時、p=x²+5y²を満たすような整数x,yが存在する。(b)p≡3,7(mod20)の時、2p=x²+5y²を満たす様な整数x,yが存在する”
事実、イデアル類群はイデアルの概念が定式化されるよりも前に、2次形式の理論として研究されていました。1773年のラグランジュの定理はその最初の例である。
更にガウスは、同じ判別式の値を持つ2次形式の間に演算を定義でき、それが群の公理を満たす事を示します(1801年)。
因みに、(以下で述べる)イデアル類群の位数を類数(ClassNumber)と呼ぶが、歴史的にはイデアル類群の発見より以前に、判別式が等しい2元2次形式に対する同値類の数として、その類数は研究されていた。これが群演算を持つ事はガウスの書籍により示され、実際に、この同値類と群は2次体のイデアル類群に対応する。
それに続いたのが、当時ガウスの円分体を研究してたクンマーですが、彼は1のべき根を用いた分解によってはフェルマー予想が証明できない事に気付いていた。つまり、1の冪根により生成された環において素数分解の一意性が成り立たない事が大きな障害だったのだ。
これこそが、イデアル類群の一端の問題となるが、詳しくは後で説明する。
ラグランジュの定理とイデアル類群
歴史を辿れば、フェルマーはまず、p≡1(mod4)となる素数pは、p=x²+y²の形で書ける事を示した。その後(誰かにより)p≡1,3(mod8)となる素数pがp=x²+2y²の形で表せる事が、更にオイラーにより、p≡1,3,7(mod12)となる素数pがp=x²+3y²の形で書ける事が、それぞれ示された。
どれも、mod4nの条件により、2次形式x²+ny²で書ける素数の種類が決まる事になる。故に、”mod20の条件により、x²+5y²で書ける素数pが決まるのでは・・”と多くの人は考えた。だが、そうはならないのが冒頭で紹介した「ラグランジュ定理」である。
つまり、p≡1,3,7,9(mod20)の時、素数pは2次形式で表せるが、”その形は2つのパターンに分かれる”というのが上の定理の主張だ。
事実、”2つのパターンに分かれる”というのは、イデアル類群の位数|Cₖ|(=類数)が2である事と深く関係する。
というのも仮に、そのイデアルがCₖの類のうちPₖに属せば、(a)の形の2次形式となり、P₀Pₖに属せば、(b)の2次形式となる。従って、イデアルがどちらの類に所属してるかどうかで、出来上がる2次形式の形が変わってくる。
更に言えば、単項イデアルPₖの類であれば、そのまま2次形式で扱えるが、そうでないP₀Pₖの類ならば、一度P₀を掛け、単項イデアルに変換し、2次形式に対応させる必要がある。
そこで、「ラグランジュの定理」の証明ですが
、x,yがp|(x²+5y²)を満たす有理整数(通常の整数)の時、イデアルP=(p,x+y√(−5))を考える。但し、p|(x²+5y²)とはpがx²+5y²を割り切る事で、x²+5y²≡0(modp)を満たす。
が、その前に、[補題]として”p≡1,3,7,9⇒p|(x²+5y²)を満たすx,y∈Zが存在する”事を証明する必要がある。
まず、平方剰余(−5/p)を考えると、その定義”(a/p)=1⇒aはmodpの2次剰余”より(−5/p)=1であれば、x²≡−5(modp)となるx∈Zが存在し、移項し変形すると、x²+5・1²≡0(modp)を得る。ここでy=1とし、p|(x²+5y²)を満たすx,y∈Zが存在する事が示せた。
次に、(−5/p)=1となるpの条件だが、
(−5/p)=(−1/p)(5/p)と分解でき、平方剰余の相互法則より、(−1/p)=1⇒p≡1(mod4)と(5/p)=1⇒p≡1,4(mod5)、又は(−1/p)=−1⇒p≡3(mod4)と(5/p)=−1⇒p≡2,3(mod5)となる。
これらをmod20で考えると、(−5/p)=1となるpは、p≡1,3,7,9(mod20)である事がわかる。平方剰余記号の計算と理解は少し厄介ですが、構わずに先へと進みます。
従って、上の[補題]と”(p)を割る素イデアル”の議論(前回「その4」参照)により、イデアルPが単項イデアル(p)を割り切る事が判る。
ここで、K=Q(√(−5))の時、P₀=(2,1+√(−5))とおけば、Kのイデアル類群はCₖ={Pₖ,P₀Pₖ}となるから、このイデアルPは、P∈PₖかP∈P₀Pₖの何れかである。
従って、(a):P∈Pₖの時の証明だが、Pは単項イデアルより、a,bを有理整数とし、P=(a+b√(−5))と出来る。一方、Pのノルムはpとなるより(その定義から)、N(P)=p⇒PP’=a²+5b²=(p)となる。また、左辺≥0なのでa²+5b²=p―①を得る。
ここで、式①を満たす素数pはmod5では、p≡1,4(mod5)となり、mod20でこれに該当するのは、p≡1,9(mod20)である(証明終)。
次に、(b):P∈P₀Pₖの時の証明ですが、Pは単項イデアルではないので、CₖにおけるP₀Pₖの逆元はP₀Pₖであるから、P₀は類Pₖに属する。従って、P₀Pは単項イデアルで書けるから、a,bを有理整数とし、P₀P=(a+b√(−5))とおける。
ここで、P₀Pのノルムは、N(P₀P)=(P₀P)(P₀P)’=P₀P’₀PP’=(2)(p)=(2p)より、a²+5b²=±2pを得る。先と同様にノルムは非負整数より、a²+5b²=2p―②となる。
式②を満たす素数pはmod5では、2p≡1,4(mod5)となり、mod20でこれに該当するのは、p≡3,7(mod20)である(証明終)。
以上、定理の証明は前回同様「2次体Q(√(−5))について」を参考にしましたが、ここまで来れば、イデアル論もそう遠くには感じない筈です。
そこで、イデアルに少しは慣れた所で、上で少し触れたクンマーのアイデアを追ってみる事にします。
クンマーのノルムと理想数のアイデア
前回「その4」で取り上げた2次体K=Q(√(−5))ですが、この整数環Oₖは𝑍[√(−5)]となりますが、6=2⋅3=(1+√(−5))(1−√(−5))となり、通常の整数の様に一意的に素因数分解出来ない。
従って、2,3,1+√-5,1-√-5は何れも𝑍[√(−5)]の”素元”にはなり得ないが、 単数である±1以外の数では割り切れないので、整数環Oₖ上の素数となる。
因みに、”素元”とは環の元pにより生成される(単項イデアル(p)が0でない)”素イデアル”の事である。但し、整域(a,b≠0⇒ab≠0なる可換環)にては全ての素元は既約元だが、逆は一般には正しくない。が、一意分解整域にては、素元と既約元は同じものとみなせる。
故に、整数環Oₖ上に素元ではないが素数である元が混在しては、数学の世界ではとても困るのだ。
そこで、クンマーは”ノルム”(距離)という非負整数を使い、”素因数分解の一意性”に似た概念をもたせ、”イデアル”という(実在しない)理想数を発明し、この問題にケリをつけた。
つまり、素イデアルに一意的に分解する事に成功します。事実、クンマーはノルムの形になる素数の分解を何通りも計算し、ノルムの形にならない素数を理想数(イデアル)を使って分解します。
因みに、クンマーはこの実在しない数を”理想複素数”(ideale complexe zahl)又は”理想因子”(ideal primfactor)と名付け、理想数の理論を築き、デデキントにより”平たく”定式化され、イデアルの導入へと繋がる。
クンマーが最初に取り組んだのは、素数lと原始l乗根αに関する円分体Q(α)の整数環における素因す分解の問題だった。膨大な計算を積み上げた論文の中で、”p≡1(modl)を満たす素数pはQ(α)の整数環O'(=Z[α])の中で素元の積として一意的に表せる”と主張した。
が、ヤコビがl=23の時の反例を示した事で、クンマーはラメが犯した(Z[α]におけるpの)”素元分解の限界”を再度思い知る。
そこでクンマーは、pがZ[α]で素因数分解できる条件を明らかにしようとした。つまり、Z[α]でpがどの様に因数分解できるか?に目をつけ、lが奇素数の時、f(α)∈Z[α]に対し、(l-1)個の積:f(α)f(α²)…f(αˡ⁻¹))で定義されるf(α)の”ノルム”(非負整数)という数(距離)に注目した。
結果、ヤコビの反例を”l=23の時、素数p=47はノルムにならないので素元分解はできない”と結論づけた。更に、ノルムの形になる(991までの)素数の分解を何通りも計算し、L=23の時は47の他に4つの素数(139,277,461,967)がノルムにならない事を示し、ノルムの限界に行き詰まる。
だが、そこで彼が思い付いたのが理想数であった。つまり、架空の複素数を導入し、代数体の素元(素イデアル)分解を可能にする。
例えば複素数の世界では、2=(1+i)(1−i)や3=(1+√(−2))(1−√(−2))と素数は更に分解できる様に、架空の複素数を使い、整数環上の素数は更に素元(素イデアル)に一意的に分解できると考えた。
事実(前回「その4」で見た様に)、1+√(−5)=(2,1+√(−5))(3,1+√(−5))において、1+√(−5)は整数環Oₖ上の素数であり、(2,1+√(−5))と(3,1+√(−5))は素イデアルとなる。更に言えば、(この目に見えない)架空の分解はノルムのお陰で判別でき、一意的素数分解が壊れる事を”分解が完全ではない”と考える事で、その分解を完全(可能)にした。
つまり、クンマーの理想数というアイデアは、ノルムの限界を超えて初めて花開いたと言える。
但し、素元と素数を混同しがちで、性質は素数や既約元とよく似てるが、注意が必要となる。まず、素元であるか否かは、元が属する環によって異なる。通常の整数Zでは2は素元(素数)だが、ガウス整数環Z[i]では、2=(1+i)(1−i)となり、2は素元とならない。
そこでクンマーは素元分解にて、素元の不足を理想数(イデアル)で補う事で、更なる分解を考え、イデアルによる完全な分解に至った。
従って、クンマーのアイデアは、理想数同士を掛け合わせ、実在する複素数を作り出す事にあり、こうした新たな理想数の体系は、デデキントにより定式化され、イデアル論へと大きく羽ばたく事になる。
まさに、ノルム(距離)という型に拘ったクンマーの離れ業であり、それをフォルム(定式化)にしたデデキントの偉業とも言える。
2次体と素イデアルの分解
こうしたクンマーのアイデアを簡単に言えば、”数の計算では(一意的に素数分解できないので)問題が厄介になるから、イデアルの計算に全てを置き換えよう”というものである。
具体的には、6そのものではなく、そのイデアル(6)を考え、このイデアルを分解すると、以下の式の様にP,P′,Q,Q′の4つの素イデアル(イデアルの素数に相当する概念)の積に分解する事が出来るというものだ。
つまり、(6)=(2)(3)=(1+√(−5))(1−√(−5))=PP′QQ′に分解できるとした。但し、P,P′,Q,Q′は、PP′=(2)、QQ′=(3)、PQ=(1+√(−5))、P′Q′=(1−√(−5))という4つの関係式を満たす。
従って、(2),(3),(1+√(−5)),(1−√(−5))は、数の世界では素数に見えるが、イデアルの世界ではまだまだ分解できる先がある。
結論から言えば、(2),(3),(1+√(−5)),(1−√(−5))は素イデアルではない。
以上では、6により生成される単項イデアル(6)を考え、このイデアルの素イデアル分解を考えた。前回「その4」の計算例で上げた2つの素イデアル、P=(2,1+√(−5))とQ=(3,1+√(−5))は、(6)の素イデアル分解の候補である。
事実、P,Qの共役をそれぞれP’,Q’とすると、PP′=(2)、QQ′=(3)となる事は前回の計算でも示した。更に、PQ=1+√(−5)の共役をP’Q’とすれば、P’Q’=1−√(−5)となる。
故に、単項イデアル (6)=(2)(3)=(1+√(−5))(1−√(−5))=PP′QQ′と、P,P′,Q,Q′の4つに素イデアル分解でき、その分解は一意に定まる事も確認できた。従って、(2),(3),(1+√(−5)),(1−√(−5))は素イデアルではない事が判る。
つまり、素因数分解の鍵はこのイデアルの世界の中にあり、イデアルのノルム(距離)という概念こそが、その本質だったのである。
話を元に戻すが、虚2次体K=Q(√m)の代数的整数全体は環をなし、このK上の整数環Oₖは𝑍[√(−5)]={a+b√m、a.b∈Z(整数)}で定義される。
そこで、Oₖの元としては、6,2,3,1+√(−5),1−√(−5)などがあるが、何度も述べた様にそれら元の間には、6=2⋅3=(1+√(−5))(1−√(−5))の関係式が成り立ち、一意分解整域ではないので、2,3,1+√-5,1-√-5は何れも𝑍[√(−5)]の素元にはなり得ない。
だが、単数である±1以外の数では割り切れないから、整数環Oₖ上の素数となる。
一方で、こうした整数環上の元が素数である事を確認する時も、ノルムを考える事で判断できる。
例えば、前回「その4」でも説明した様に、2次体K=Q(√m)の任意の数をα=a+b√mとし、イデアルA=(α)のノルムは、N(A)=αα’=(a+b√m)(a−b√m)=a²−mb²で表せる。故に、Q(√(−5))の元:a+b√(−5)のノルムは、a²+5b²となる。
そこで、2次体K=Q(√(−5))の整数環Oₖは𝑍[√(−5)]となるが、6=2⋅3=(1+√(−5))(1−√(−5))となり一意分解整域ではないので、2,3,1+√-5,1-√-5は何れも𝑍[√(−5)]の素元にはなり得ないが、 単数である±1以外の数では割り切れないから、整数環Oₖ上の素数となる。
故に、先の4数のノルムはそれぞれ、N(2)=2²+5⋅0²=4、N(3)=3²+5⋅0²=9、N(1+√(−5))=1²+5⋅(−1)²=6、N(1−√(−5))=1²+5⋅1²=6となる。
だがノルムの定理には、”αがβで割り切れるなら、N(α)はN(β)で割り切れる”というのがある。従って、上の4数を割り切る数が存在するとすれば、その数のノルムは±2,±3のいずれかである。
また虚2次体のノルムは正なので、2, 3だけとなるが、この様な数を持つノルムはOₖには存在しない。なぜなら、もし存在するとすれば、a²+5b²=2又はa²+5b²=3を満たす整数a,bが存在する必要がある。が、存在しない事は明らかなので、先ほどの4つの数は素数となる事が判る。
従って、整数環Oₖの元6が2通りの素因数分解を表す事がイデアルのノルムを使い、確認できる事となる。
結局、イデアル論を理解するには、イデアルそのものではなく、イデアル類群というイデアルを構成する類(クラス)の仕組み、言い換えれば、単項イデアルとそうでないイデアルとの距離(=ノルム)の指標を知る事で、見えないイデアルの世界を判別する事が可能となる。
つまり、イデアルとても所詮は架空の数の集合に過ぎないのだから・・・










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます