2005年9月4日(日)
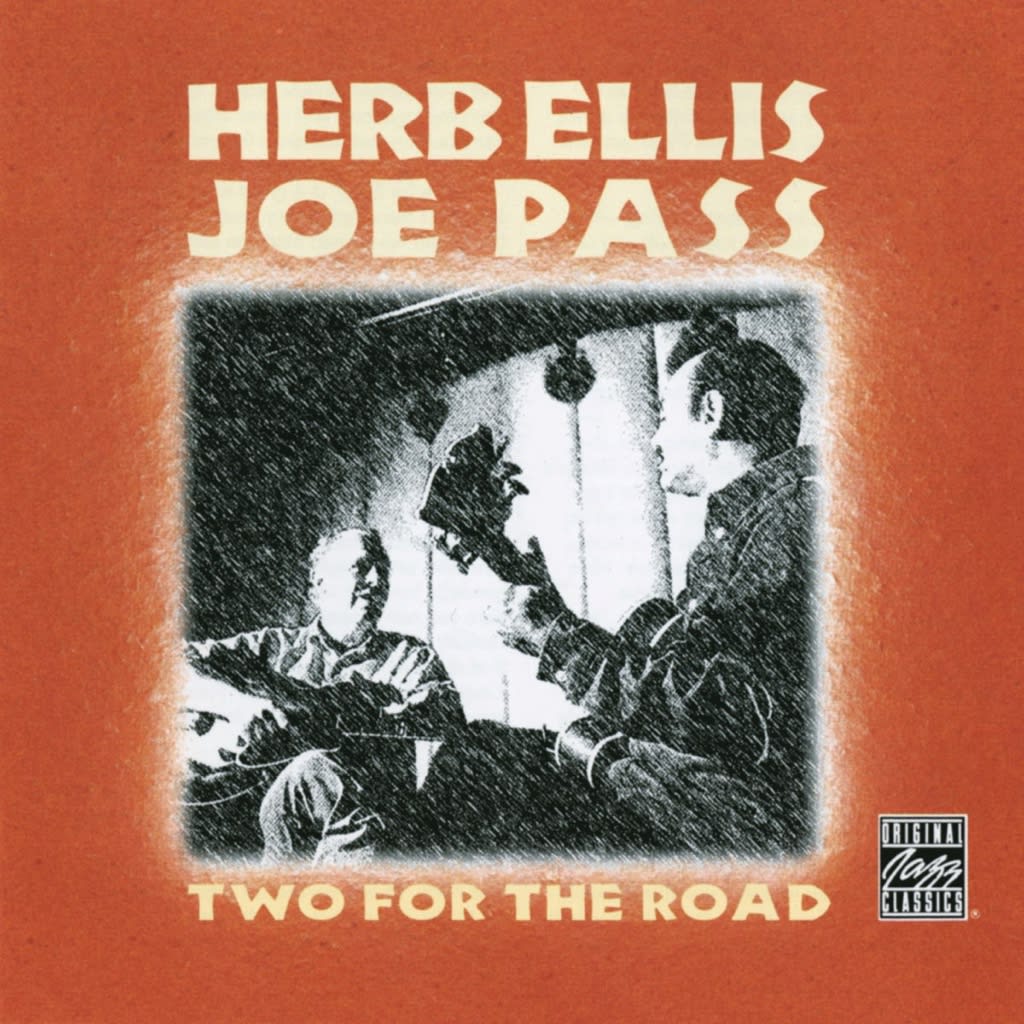
#281 ハーブ・エリス&ジョー・パス「TWO FOR THE ROAD」(PABLO OJCCD-726-2)
ジャズ・ギタリスト、ハーブ・エリスとジョー・パスによるデュオ・アルバム。74年リリース。ふたりによるプロデュース。
ギター・デュオも数々あれど、このふたりほど、技術的にもフィーリング的にも高水準、しかもぴったりと息の合ったコンビネーションは、そうはいないだろう。
当アルバムは彼らのデュオ録音としては三枚目(前二作はともにライブ盤)、最後の一枚にあたるが、コンビとしての究極の完成形を見せてくれている。
まず、なんといっても、選曲がすばらしい。メロディアスで、しかも粋で大人のムードがあるナンバーが満載なのだ。
オープニングは「ラヴ・フォー・セール」。コール・ポーターの名曲だ。
ゆったりとしたテンポでふたりが紡ぎ出す世界は、ファンタスティックのひとこと。ソロ・ギタリストとして既に超一級であるふたりが、ときにはせめぎ合い、ときには相手に一歩譲ってバッキングに徹し、見事なコンビネーションを見せてくれる。
続くは、ボサ・ノヴァの大家、ルイス・ボンファの作品「カルナヴァル」。
アップテンポで軽快なブラジリアン・サウンドを、絶妙の指使いで生み出してくれるふたり。聴いていると、思わず、体が動き出しますな。
「アム・アイ・ブルー」は、ミディアム・テンポのスウィンギーなナンバー。グラント・グリーンあたりも演っていました。
このロマンティックな雰囲気の小唄を、分別ざかりのふたり(当時エリスは52才、パスは45才)がいい感じにプレイしとります。いやー、大人やな~。
「セヴン・カム・イレブン」は、彼らの高度なテクニックが堪能出来るナンバー。もちろん、ベニー・グッドマンの代表曲だ。既に同題のライブ盤でも取り上げているので、再演にあたる。
速いパッセージを、一糸乱れず弾き切るふたりに、驚嘆を禁じえない。
「ギター・ブルース」はタイトル通りのミディアム・テンポのブルース・ナンバー。ふたりの共作。いかにもスタジオ・ワークの合間に生み出されたという感じの、即興的な趣きの曲である。
それぞれの持ち味を繰り出してのソロや掛け合いが、なんともカッコいい。
ギターだけ、なんのリズム楽器もなくても、絶妙な「間」のとりかたで実にスウィンギーなリズムを刻み出しているのは、さすがだ。
「オー・レディ、ビー・グッド」はごぞんじガーシュイン兄弟の作品。ミディアム・テンポで、まったりとしたサウンドを聴かせてくれる。なんともリラックスしたムードが溢れている。まるで、スタジオで一杯やりながら、演奏しているかのよう。
「チェロキー」は、さまざまなアーティストにカバーされている、レイ・ノーブル作の超スタンダード。これを二通りのコンセプトで弾き分けてくれる。
コンセプト・ワンは、アップ・テンポで威勢よく。コンセプト・トゥーはミディアム・テンポでしっとりと。それぞれに魅力的な演奏である。
続く「SEULB」(はて、どう読んだらいいのか)は、ふたりの共作。たぶん、BLUES(ブルース)を逆さまにしたのだろう。確かに、ミディアムスロー・テンポのブルースではある。
こちらも即興性の高いナンバー。スタジオ入りしている間に、こういう小曲をいくつもひねり出して、遊び感覚でレコーディングしてしまう。いいねえ。
このアルバムの白眉は、やはりこれだろう。十曲目の「ジー・ベイビー、エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー」。
ドン・レッドマンとアンディ・ラザフによるスタンダード・ナンバー。この曲は支持層が広く、ロック系も含めてさまざまなアーティストにカバーされている。ブルーズィなメロディと、ジャズィなコードが絡み合った、実に粋な曲調が、その人気の秘密だと思う。
エリスとパスのふたりも、この名曲の持ち味を最大限生かしながら、それぞれのカラー、リリシズムを盛り込んでプレイしている。聴いていると、ホント、いいお酒が飲みたくなります。
続くはオーティス・レディングほかでおなじみの、R&Bの名曲、「トライ・ア・リトル・テンダーネス」。古いスタンダード・ジャズばかりでなく、こういう曲にも挑戦しているのはうれしいもんだ。
エリス&パス版の「トライ~」は、他のアーティストとはひと味ちがって、ムーディといいますかロマンティックなスロー・バラード。ひたすらスウィートなサウンド、オーティスみたいな汗の匂いはまったくしないのですが、これもまた十分ありってことで。
「アイヴ・ファウンド・ア・ニュー・ベイビー」は、チャーリー・パーカー、ディズィ・ガレスピー、ソニー・ロリンズら多くのジャズマンが好んで演奏したナンバー。オリジナルはファッツ・ウォーラーである。
速いテンポで演奏されることの多いナンバーだが、彼らは少し抑えめのミディアム・テンポでプレイ。
技巧に走り過ぎず、スウィングな「ノリ」をあくまでも大切にした丁寧な演奏。そう、たしかなリズム感こそが、このデュオの最大のウリなのだ。
ラストは「エンジェル・アイズ」。粋なシンガー/ピアニストにして、コンポーザーとしても優れた仕事を残した、マット・デニスの代表作である。
ブルーズィでメランコリックなAメロディから一転、甘美でのびやかなBメロに変わり、そして再びAメロに戻るという構成。
ふたりの繊細にして緻密なプレイは、この曲の二面的な魅力をあますところなく掬い上げている。原作のデニスにもまさるとも劣らぬ出来ばえだ。
「名人芸」とは、こういうのをいうんだろうなぁ。
最高の技術、フィーリング、そして豊かなイマジネーション。まさに、究極のギター・デュオ。
歌はまったく歌っていなくとも、そのプレイは歌心にあふれている。一杯飲りながら聴けば、至福のひとときが味わえますぞ。
<独断評価>★★★★★









