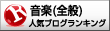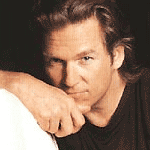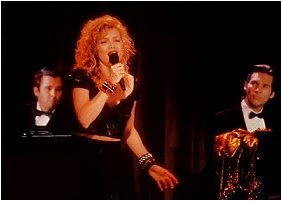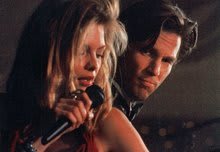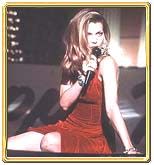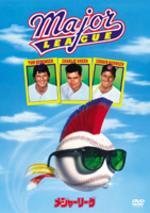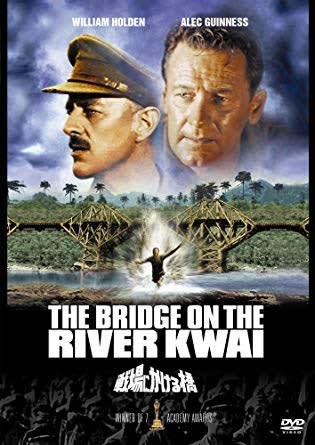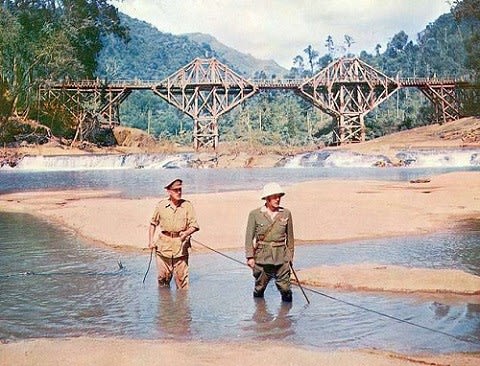♪お気に入り映画(その22)
■戦場のピアニスト [The Pianist]
■2002年 ポーランド・フランス合作
■監督…ロマン・ポランスキー
■音楽…ヴォイチェフ・キラール
■出演
☆エイドリアン・ブロディ(ウワディスワフ・シュピルマン)
☆トーマス・クレッチマン(ヴィルム・ホーゼンフェルト大尉)
☆フランク・フィンレイ(シュピルマンの父)
☆モーリン・リップマン(シュピルマンの母)
☆エド・ストッパード(ヘンリク・シュピルマン)
☆ジェシカ・ケイト・マイヤー(ハリーナ・シュピルマン)
☆ジュリア・レイナー(レジーナ・シュピルマン)
☆エミリア・フォックス(ドロタ)
☆ルース・プラット(ヤニナ)
☆ミハウ・ジェブロスキー(ユーレク)
☆ロイ・スマイルズ(イサク・ヘラー) etc・・・
戦争がもたらす不幸のひとつは、人間の尊厳が徹底的に踏みにじられることだ。あるいは、人間が、同じ人間の尊厳を惨たらしく踏みにじることだ、とも言えるだろう。その最悪の例のひとつが、ナチス・ドイツが行った、ユダヤ人に対する大量虐殺(ホロコースト)である。
この作品は、ユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ(ウワディク)・シュピルマンが、第二次世界大戦(1939~1945)中に、ナチス・ドイツ占領下のポーランドで体験した恐怖の日々を映画化したものだ。

ウワディスワフ・シュピルマン(1911~2000)
1939年9月にポーランドを占領したナチス・ドイツは、対ユダヤ人政策を強化する。ダビデの星のついた腕章の着用強制をはじめ、所持金額、立ち入り場所、就職、教育、結婚などの制限など、ありとあらゆるところでユダヤ人を迫害してゆく。そのうえ激しい「ユダヤ人狩り」を行うのだ。逮捕するのに理由はない。ただユダヤ人だから、というだけだ。逮捕されたユダヤ人の行く先は、収容所である。

ユダヤ人たちは、1940年には居住地さえも制限されるようになる。
劇中では、シュピルマン一家が強制的に移住させられたワルシャワ市内のゲットー(ユダヤ人居住区)の極限状態が生々しく描かれている。
ゲットーと一般区域の間には壁が造られるが、この壁にはユダヤ人の命を絶望のふちに追いやるかのような残酷さがある。
ゲットー内には、略奪、搾取はおろか、同じユダヤ人を「売って」まで生き延びようとする人もいれば、人間の尊厳をかけてナチスに抵抗しようとする人もいる。
その中でひっきりなしに襲ってくる飢えの恐怖と、ナチスによる「選別」の恐怖。ナチスの軍人たちはユダヤ人の人間性など認めていないのだ。
これらの悲惨な様子は、この映画でメガホンを取ったポランスキー監督の実体験も反映されている。シュピルマンと同じユダヤ系ポーランド人のポランスキー監督には、ゲットーでの生活と、そこからの脱出の経験がある。

1942年8月、ゲットーの大半の人間は、悪名高いトレブリンカ絶滅収容所へ送られる。この時シュピルマンの家族も移送列車に詰め込まれるが、シュピルマンは友人の助けによって、ゲットーに残る。
静まり返ったゲットーの中には殺された同胞の遺体や荷物類が散乱しているだけである。その中を力なく泣きながら歩くシュピルマンの姿を観ると、もはや言葉も出ない。

その後シュピルマンはゲットーを脱出する。隠れ家に身を潜めているとはいえ、見つかれば一巻の終わりなのだ。死の恐怖に怯える毎日。そんな中でシュピルマンが人間らしくいられたのは、ひとえに音楽に対する思いだったのだろう。
ある時は隣室から聴こえるピアノに耳を澄まし、ある時は隠れ家に置いてあったピアノを見て、音楽に対する思いをはせる。そして、廃墟と化した病院に隠れながらも、頭の中で鳴っている音楽に合わせて指を動かすシュピルマン。
自分がこういう極限状態にあったとしたらどうだろう。愛するものの存在を大切に胸にとどめておくことができるだろうか。

1943年4月のワルシャワ・ゲットー蜂起の場面
1944年8月、ワルシャワ蜂起。ポーランド人たちはナチス・ドイツに対して反乱を起こすが、20万人以上の犠牲を出したうえ、ワルシャワ市内はほとんど破壊される、という悲惨な結果に終わった。廃墟と化したワルシャワ市内の中にシュピルマンがただひとり彷徨っているさまは、凄惨でさえある。
この時に身を隠した建物の中で、シュピルマンはドイツ軍の大尉に出会うのだ。
大尉に発見されたシュピルマンは死を覚悟したことだろう。
しかし大尉は静かにいくつかの質問をシュピルマンに投げかけ、シュピルマンがピアニストだと知ると、「何か弾いてみろ」と命ずる。
シュピルマンは半ば怯えながらピアノの前に座る。少しためらったのち、鍵盤に指を置くシュピルマン。しかしいったん弾き始めると、全身全霊をピアノに込める。曲はショパンの「バラード第1番ト短調 作品23」である。
大尉が立ち去ったのちシュピルマンは嗚咽をもらす。まだ生きていられる安堵感なのか、再びピアノを弾くことができた喜びなのか。おそらくその両方なのだろう。

もしこの映画が、「ユダヤ人の命を助けたドイツ軍大尉」という美談仕立てになってしまっていたら、感動も半減したと思う。そういうドイツ軍人がいたからといって、それはナチス・ドイツの犯罪に対する免罪符にはならないからである。
大尉とシュピルマンにまつわるエピソードは、人間と人間のひとつの邂逅だと捉えるべきだと思う。大尉の名前が劇中では出てこないことの理由も、大尉をひとりの人間として描こうとしているからではないだろうか。(実際に名乗らないままだったかもしれないけれど)
映画の終わり近くで、ソ連軍に拘束された大尉が、偶然通りかかったシュピルマンの友人(彼もユダヤ人として囚われていた)に、「私はシュピルマンを助けた。彼に私を救って欲しいと伝えてくれ」と必死で頼むシーンがある。大尉の運命を思うと、胸の痛むシーンである。
戦後シュピルマンは手を尽くして大尉の行方を探したそうだが、大尉は1952年にソ連の捕虜収容所で亡くなっている。
この大尉の名は、ヴィルム・ホーゼンフェルト。
大尉の人間らしい振る舞いは、ナチズムに凝り固まっていたSS(ナチス親衛隊)の所属ではなく、軍人としての誇りを持つ国防軍の軍人であったこと(国防軍の内部にはヒトラーを軽蔑している者がかなりいた)、平時には教職に就いていたことなども関係があるのかもしれない。
大尉がシュピルマンに別れを告げる時に言った「生きるも死ぬも神のご意思だ。そう信じなくては」という言葉、これも大尉がナチズムに毒されていなかったことの証明だ。当時のドイツのキリスト教会の教義は、ナチズムに都合のよいようにねじ曲げられていたにもかかわらず、きっと大尉は神の前に謙虚な人間でい続けたのだろう。

人間として立派に振舞う大尉に出会ったことはシュピルマンの幸運であり、大尉がドイツ軍人だったことは大尉にとっての不運だったとも言えるかもしれない。
この作品の重みは、シュピルマン役のエイドリアン・ブロディの抑えた演技や、大尉役のトーマス・クレッチマンの威厳のある素晴らしい演技はもちろん、ゲットー内の大勢のユダヤ人役のエキストラの存在によるところも大きいと思う。
また、ゲシュタポの残虐さ、ゲットー内のユダヤ人の蜂起、ワルシャワ蜂起などの様子が、シュピルマンの視線で描かれているため、描写がドキュメンタリーを見ているかのような真に迫ったものになっている。
ひとつだけ注文があるとすれば、ポーランド人同士、ユダヤ人同士の会話が英語でなされていることだ。ここはやはり、ポーランド語やイディッシュ語を使って撮影して貰いたかった。
第二次世界大戦前のポーランドのユダヤ人の人口は推定約330万人。そのうち終戦時に生き残っていた者は、推定わずか30万人だったという。ヨーロッパ全体でも、約600万人(ヨーロッパのユダヤ人の67%)のユダヤ人が殺されたそうである。
この作品は、歴史の貴重な証言だと思う。
人気blogランキングへ←クリックして下さいね