人種差別に対する抗議、徴兵制度や戦争、現代に生きる若者の価値観や感情を大胆に盛り込んだロック・ミュージカルが1960年代後半に大ヒットしました。そのタイトルは『ヘアー』。ヒッピーなどの若者の長髪がそのタイトルの由来です。この作品は、従来のブロードウェイ・ミュージカルの枠を破った異色作・意欲作と言えるものです。
1967年10月からオフ・ブロードウェイで上演されて評判となり、1968年4月29日からはブロードウェイで1742回に渡って上演されました。さらに、日本を初めとして、世界各国でも上演されるなど、大ヒットを記録しました。
このミュージカルの中で歌われていたのが、「輝く星座(アクエリアス)」です。
「輝く星座(アクエリアス)」は、劇中ではロナルド・ダイソンによって歌われていました。この曲を、同じく『ヘアー』の挿入歌である「レット・ザ・サンシャイン・イン」とメドレーにしてヒットさせたのが、「フィフス・ディメンション」という黒人R&Bヴォーカル・グループです。

たまたま我が家に、レコード会社の企画物で、カヴァー曲専門のインストゥルメンタル・レコードがありました。いろんなロック、ポップスが収められていたレコードです。その中にこの曲が入っていて、メドレー部分のカッコよさに惹かれたものでした。
その頃(高校時代です)、よく通っていたレコード店の顔なじみの店員さんに「アクエリアスって知ってますか?」と聞いてみると、「レコードは在庫にないけれど、よかったらぼくの家にあるレコードを貸してあげるよ」という温かい返事。そして貸して貰ったのが、「フィフス・ディメンション」のベスト・アルバムだったんです。
その頃のぼくにとっては、黒人のコーラス・グループはちょっとした「大人のサウンド」で、正直良さがわからなかったんです。だから、せっかく借りたレコードもひと通り聴いただけですぐ返してしまいました。
何年かして、これもレコード会社の企画モノの、LPレコード10枚組くらいの「ポップス大全集」(よく新聞紙上に広告が載っていますね)を買った時に、久しぶりにこの曲に接してみて、改めて「アクエリアス」にハマったんです。
黒人コーラス・グループに対して、何かしら固定観念を持っていたぼくにとって、スペーシーなイントロ、ちょっとエキゾチックな歌い出しは少し意表を突かれたものでした。メロディーやホーンのアレンジもとくに「黒っぽい」わけではなく、まさに「ミュージカル」的な、洗練されたものだからです。
しかし対照的に、後半の「レット・ザ・サンシャイン・イン」では、強力なグルーヴ感を醸し出しているベース・ライン、リズミカルなホーン・セクション、ゴスペルっぽいコーラス、ホットにフェイクしまくっているリード・ヴォーカルがダイナミックな、とってもファンキーな世界が広がっています。
メドレーならではの、前後半の対比がまたカッコいいんですよね。

「Aquarius(アクエリアス)」とは水瓶座のことで、星座占いでは1月21日から2月19日までに生まれた人を指しますね。水瓶座は10月中旬の夕方、南の中天に見える星座です。
ギリシア神話によると、トロヤに全身が金色に輝くガニメーデという美少年がおり、その美しさを気に入った大神ゼウスがワシに姿を変えてガニメーデをさらい、自分に酌をさせるため天に連れ帰った、ということです。ガニメーデの持つ水瓶には神々の英知の源となる飲み物があふれんばかりに湛えられています。つまり水瓶座人は、水瓶から注がれた神々の恩恵を与えられている、というわけです。
ちなみに水瓶座人は判断力に富み、推理力と科学的知恵にあふれ、人間の自由という価値観と、芸術を愛する心を大切にしているそうです。
フィフス・ディメンションは、1966年から1970年半ば頃まで活動を続けました。のちメンバーのうちの二人が「マリリン・マックー&ビリー・デイヴィスJr.」として独立しています。
[歌 詞]
[大 意]
月が第七宮にあり、木星と火星が並んだ時
その時こそ平和は惑星を導く
そして愛が星座を動かし進める
これが水瓶座の時代の黎明だ
調和と理解 同情と信頼
虚偽や嘲笑はなく 理想の夢が輝く
神秘的に澄んだ神の黙示 そして心の真の解放
水瓶座、水瓶座よ
◆輝く星座~レット・ザ・サンシャイン・イン/Aquarius~Let The Sunshine In
■歌
フィフス・ディメンション/5th Dimension
■シングル・リリース
1969年3月8日
■作 詞
ジョージ・ラグニ & ジェームス・ラド/George Ragni&James Rado
■作 曲
ガルト・マクダーモット/Galt MacDermot
■プロデュース
ボーンズ・ハウ/Bones Howe
■録音メンバー
[フィフス・ディメンション/5th Dimension(vocals)]
●ビリー・デイヴィスJr./Billy Davis Jr.
●マリリン・マックー/Marilyn McCoo
●ロン・タウンソン/Ron Townson
●ラモンテ・マクレモア/Lamonte McLemore
●フローレンス・ラルー/Florence LaRue
トミー・テデスコ/Tommy Tedesco(guitar)
デニス・ブディミール/Dennis Budimir(guitar)
ラリー・ネクテル/Larry Knechtel(keyboards)
ジョー・オズボーン/Joe Osborn(bass)
ハル・ブレイン/Hal Blaine(drums)
■収録アルバム
輝く星座/The Age of Aquarius(1969年)
■チャート最高位
1969年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位(1969年4月12日~5月17日 6週連続)、イギリス13位
1969年年間チャート アメリカ(ビルボード)2位
 フィフス・ディメンション『輝く星座~レット・ザ・サンシャイン・イン』/Aquarius~Let The Sunshine In
フィフス・ディメンション『輝く星座~レット・ザ・サンシャイン・イン』/Aquarius~Let The Sunshine In
小4の時にビートルズを聴いてショックを受けて以来、ロックに浸って大きくなったぼくにとって、オアシスの音楽は違和感がなく、すんなり受け入れることができるものです。
オアシスは、ノエルとリアムのギャラガー兄弟を中心としたバンドです。
兄のノエルはギタリストで、ほとんどの曲を書いています。弟のリアムはヴォーカリスト。兄弟そろってビートルズ・フリークなのはよく知られた話です。
このふたりの仲の悪さは有名で、そのためバンドは何度も解散の危機にさらされました。
そのうえステージをすっぽかしたり、暴力沙汰を起こしたり、暴言でバッシングされたりと、数々のスキャンダラスな出来事でマスコミを賑わせ続けてきました。
ファンをやきもきさせ続けている「お騒がせバンド」と言ってもいいでしょうね。

ノエル・ギャラガー(g,vo)
しかし彼らの生み出す音楽は、不思議な魅力に満ちています。
独特の暗さと重さを持っていますが、そのシンプルなのに印象的なメロディーは、聴いているぼくをある種の快感の渦の中に導いてくれます。
ノイジーだけれども、グルーヴィーで分かりやすいギターはツボをしっかり心得ていて、ギターだけを聴いていても心地良い。
力強くて攻撃的なヴォーカルは、どこかジョン・レノンを彷彿とさせます。
ミディアムの、似たようなテンポの曲が多いのですが、それさえも一種の快感です。
アレンジを聴いていると、やはりビートルズの大きな影響が感じられますね。

リアム・ギャラガー(vo)
多様化したポピュラー音楽の中にあって、ギター中心のサウンドを作り続けているオアシスは、正統派のロック・バンドと言えるでしょう。
「誰からも束縛されたくない」という奔放な姿勢を保ち続けているからでしょうか、どこかパンクっぽさをも醸し出しているオアシスですが、そのパンクなフィーリングと、ノエルの書く曲のポップでちょっとサイケデリックな部分とがうまく溶け合っていますね。
ぼくのオアシスの愛聴曲は、「シガレッツ・アンド・アルコール」「サム・マイト・セイ」「オール・アラウンド・ザ・ワールド」、そしてもちろん「ドント・ルック・バック・イン・アンガー」などなど、です。

相変わらず高い人気を誇っているオアシス、昨年(2005年)は6枚目のアルバム「Don't Believe The Truth」がヒット、健在ぶりを示してくれました。
願わくはトラブルメイカーぶりもほどほどにして、バンドを維持し続けて貰いたいものです。
そういえば、現在はあのリンゴ・スターの長男のザック・スターキーがサポート・ドラマーを務めているんですね。知らなかったな~
映画「ブリジット・ジョーンズの日記」(2001年)の冒頭で、主人公のブリジット・ジョーンズ(レネー・ゼルウィガー)が歌手になりきったように陶酔して、夜中にひとりで曲に合わせて絶唱するシーンがありましたね。その曲を歌っているのはジェイミー・オニール、曲のタイトルは「オール・バイ・マイセルフ」です。
失恋の後悔や、ひとりぼっちになってしまった自分の心の葛藤を描いた曲ですが、それが、30歳を過ぎても彼氏もいない自分の身の上を嘆いているブリジット・ジョーンズの心境にピッタリなんですね。
「オール・バイ・マイセルフ」は、もともとはエリック・カルメンが1975年に発表したバラードです。この曲は、「20世紀に残したい歌・ベスト100」にも選ばれたことがあるほどの名曲として知られています。
ジェイミー・オニールのほか、セリーヌ・ディオン、シェリル・クロウ、ジュエル、シャーリー・バッシー、カーメン・マクレエ、日本では中村あゆみなど、多くのアーティストに取り上げられている曲です。
最近では、1995年の映画「誘う女」(ニコール・キッドマン主演)や、自動車メーカーのCM(ダイハツCopen)に使われていましたね。
「オール・バイ・マイセルフ」は、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番第2楽章をモチーフにしています。エリックはこのほかにも、「Never Gonna Fall In Love Again(恋にノー・タッチ)」でラフマニノフ(交響曲第2番ホ短調第3楽章)を、「Love Is All That Matters」ではチャイコフスキー(交響曲第5番第2楽章)をモチーフにして曲を書いています。
エリックは高校の時に、テレビで見たビートルズやザ・フーに衝撃を受けてロック・ミュージックにどっぷり浸ることになるのですが、それまでは少年時代からずっとクラシック・ピアノを専門的に学んでいて、将来を嘱望されてもいたようです。そのクラシックの素養が、エリックの作る音楽にさまざまに影響を及ぼしているのでしょう。
重厚な雰囲気に包まれた、ほの暗くてとても美しい曲です。
イントロの静かなピアノの上に、抑えたヴォーカルがそっと入ってきます。
サビでの歌声はとても伸びやか。エリックの声には必要以上の悲愴感はありません。メロディアスで、どこか寂しげなスライド・ギターのソロ。中間部のピアノ・ソロがとてもクラシカルできれいです。
エリック・カルメン『サンライズ』
自分のことしか見えず、気がついた時には大切なものを失くしていたということ、誰しも経験があるのではないでしょうか。(もちろん、ぼくにも何度もあります)この曲には、それに気づいた時の苦くてせつない想いがこもっているのですね。だからこそ、ぼくはこの曲に共感を覚えるのでしょうね。
エリック・カルメンは、1970年代前半には「ラズベリーズ」というグループに在籍して多くのヒット曲を残したのち、1975年にソロとなります。「オール・バイ・マイセルフ」は、エリックのソロ・デビュー作でもあります。
一時はニュースの途絶えていたエリックですが、1999年には「リンゴ・スター・オール・スターズ」の全米ツアーに参加。2004年11月には31年ぶりに再結成された「ラズベリーズ」に参加するなど、精力的に活動しているようです。
[歌 詞]
[大 意]
若かった頃 ぼくは誰のことも必要としてはいなかった
恋をするなんて ほんの遊びにすぎなかった
日々は過ぎ ひとり寂しくすべての友のことを想うが
電話をしても 誰もこたえてくれない
ぼくはひとり
そうはなりたくない
ひとりで生きていくのはつらい
確信を持てず 時には不安になる
愛は遠くに去り おぼろになりながら
心の救いとして残っている
◆オール・バイ・マイセルフ/All By Myself
■歌・演奏
エリック・カルメン/Eric Carmen
■シングル・リリース
1975年12月1日
■収録アルバム
サンライズ(原題『Eric Carmen』 1975年11月発表)
■作詞・作曲
エリック・カルメン/Eric Carmen
■プロデュース
ジミー・レナー/Jimmy Lenner
■チャート最高位
1976年週間チャート アメリカ(ビルボード)2位、イギリス12位
1976年年間チャート アメリカ(ビルボード)40位
ライヴハウスでジャズを聴くのは、ぼくの楽しみのひとつです。ミュージシャンの息遣いとか熱気がダイレクトに感じられるので、ホールよりもライヴハウスで聴く方が好きなのです。とはいえ、スケジュールが合わなくて、行きたくても断念せざるを得ないことが多いんですけれど。
今夜は「椎名豊トリオ」のライヴが倉敷市でありました。
現在のジャズ・シーンを牽引するピアニストのひとりである椎名豊氏のピアノは前から一度聴いてみたかったので、このライヴは必ず行くつもりにしていました。
場所は、倉敷の老舗ジャズ・クラブ「アヴェニュウ」です。

コーヒーを飲みながら(ぼくはお酒はほとんど飲まないんです )しばし開演を待ちます。この開演前の期待感も「ライヴのうち」なんですよね。
)しばし開演を待ちます。この開演前の期待感も「ライヴのうち」なんですよね。
お客さんも三々五々とお店に入ってきます。外はやはり冷えるようで、みんな背中を丸めて入ってきます。でも、寒い冬だからこそ、アツいジャズで温まりたいんです。(夏は夏で、ジャズが合うのです )
)
ライヴの2時間は、アッという間でした。
『サマー・ミスト』、『魅惑のリズム』、『ミスター・T』、『ジョイ・オブ・スプリング』、『トゥ・ビー・エス』など、オリジナル曲、ジャズ・オリジナル、スタンダードを交え、アンコールを含めて演奏は全11曲。存分にピアノ・トリオによるジャズを堪能できました。
椎名氏の弾くピアノは、音で情景を描写しているかのような、美しくて存在感のある音色でした。おそらくタッチが柔らかいのでしょう、ハードな曲を弾いてもピアノの音色が耳に心地良い。
繊細な音から豪快な音まで、いろんなピアノの表情を見ることができたのも楽しかったな~。スケールの大きさを感じました。
即興性というか、現場での「音の化学反応」も見逃せないところです。
期待通りの濃密な音にじっくり浸ることができて、とても満足です。

椎名 豊(pf)
椎名氏の紡ぎ出す曲をいろんな色で色づけしているのが大坂氏のドラムです。ごくごくシンプルなセットなのですが、そこから叩き出す音色の種類のなんと多いこと。そして、自在にリズムで遊び、苦もなくリズムを操る様子は、まるでドラム・セットと戯れているかのようです。見事なまでにドラム・セットを歌わせている大坂氏のドラミングを聴いていると、ドラムが別の楽器のように感じられるほどでした。
この二人の熱いプレイを、「堅実」という言葉がぴったりくるような上村氏のベースが温かく支えます。非常に穏やかで、安定感抜群のベースでした。こういうプレイだからこそ、椎名氏も大坂氏も安心して音と「遊べる」んでしょうね、きっと。

大坂昌彦(drs)&上村 信(b)
ライヴを楽しむことができた後は、なんとなく夢見心地です。「つわものどもが~」ではないけれど、さっきまで熱い演奏の中に自分の身を置いていたのが夢みたい。
でも、熱い演奏を楽しむことができたからこそ、「またライヴ・ハウスに行ってみよう」という気持ちが沸き起こってくるんですね。
さて、次はだれのライヴに行ってみようかな~
◆椎名豊トリオ Live at 倉敷アベニュウ
2006年1月24日
椎名 豊(piano)
上村 信(bass)
大坂昌彦(drums)
1月19日はジャニス・ジョプリンの誕生日だったんですね。
今夜はなんとなくジャニスの歌が聴きたくなって、CD棚から「パール」を取り出して聴いています。
ちなみに、宇多田ヒカル、松任谷由実、ロバート・プラントらのそうそうたるシンガーたちも、ジャニスと同じ誕生日だそうですね。
「パール」は1970年8月末から制作に取り掛かりましたが、レコーディング途中の10月に、ジャニスはヘロインの過剰摂取のため、わずか27歳で急逝してしまいます。アルバム中、ヴォーカル・トラックの入っていない曲が1曲あるのはこのためです。
その曲のタイトルは、「生きながらブルースに葬られ」(Buried Alive In The Blues)。ちょっとビックリしますね。
しかし、このアルバムはジャニスの最高傑作、というより、ロック史上に残る名作といえるでしょう。

このアルバムは、ジャニス自身のニックネーム「パール」をそのままタイトルにしています。
ジャケットで微笑んでいるジャニス、人生を謳歌しながらもどこか悟ったような、とてもいい表情をしています。その写真は紫色で縁取られていますが、紫はジャニスが好きだった色だそうです。
収められているものは、名曲・名唱のオン・パレード。
ジャニス自身の作で、ハード・ロックの古典ともなっている『ムーヴ・オーヴァー(ジャニスの祈り)』、ハードでブルージーな『クライ・ベイビー』、ファンキーなギターが大活躍する『ハーフ・ムーン』、恋人と言われたクリス・クリストファーソン(近年は俳優として活躍していますね)が書いたカントリー・バラードの名作『ミー・アンド・ボビー・マギー』、アカペラで迫る『メルセデス・ベンツ』、トラディショナル・フォークの味わいもあるR&B風ナンバー『トラスト・ミー』、ジャニスの息遣いと温もりが感じられるソウルフルな『愛は生きているうちに』など、どの曲もとてもグレードの高いものばかりです。
なかでもぼくが好きなのは『寂しく待つ私』。ピアノとオルガンから漂ってくる寂寥感と、ジャニスの熱気と感情のこもった抜群の歌唱力がたまらないのです。

このアルバムのジャニスは、さらに表現力に磨きがかかっています。まさに、シンガーとして脂の乗り切った頃だったのでしょう。
ジャニスのあのしゃがれた歌声には、ジャニスの音楽性だけではなく、彼女の持つ埋めがたい寂しさだとかコンプレックス、そして彼女自身の生き様が詰まっているような気がします。
きっと彼女は、ブルースを歌うために生まれてきたのでしょうね。

◆パール/Pearl
■歌・演奏
ジャニス・ジョプリン/Janis Joplin
フル・ティルト・ブギー・バンド/Full Tilt Boogie Band
■リリース
1971年1月11日
■プロデュース
ポール・ロスチャイルド/Paul A. Rothchild
■収録曲
[side-A]
① ジャニスの祈り/Move Over
② クライ・ベイビー/Cry Baby ☆(全米42位)
③ 寂しく待つ私/A Woman Left Lonely
④ ハーフ・ムーン/Half Moon
⑤ 生きながらブルースに葬られ/Buried Alive in the Blues
[side-B]
⑥ マイ・ベイビー/My Baby
⑦ ミー・アンド・ボビー・マギー/Me & Bobby McGee ☆(全米1位)
⑧ ベンツが欲しい/Mercedes Benz
⑨ トラスト・ミー/Trust Me
⑩ 愛は生きているうちに/Get it While You Can ☆(全米78位)
☆=シングル・カット
■録音メンバー
ジャニス・ジョプリン/Janis Joplin (lead-vocals, backing-vocals, acoustic-guitar⑦)
[Full Tilt Boogie Band/フル・ティルト・ブギー・バンド]
リチャード・ベル/Richard Bell (piano, backing-vocals)
ケン・ピアソン/Ken Pearson (organ, backing-vocals)
ジョン・ティル/John Till (guitar, backing-vocals)
ブラッド・キャンベル/Brad Campbell (bass, backing-vocals)
クラーク・ピアソン/Clark Pierson (drums, backing-vocals)
[guests]
ボビー・ウーマック/Bobby Womack (acoustic-guitar ⑨)
ボビー・ホール/Bobbie Hall (congas, percussion)
フィル・バデラ/Phil Badella (backing-vocals)
ジョン・クック/John Cooke (backing-vocals)
ヴィンス・ミッチェル/Vince Mitchell (backing-vocals)
サンドラ・クロウチ/Sandra Crouch (tambourine)
■チャート最高位
1971年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス20位、日本(オリコン)10位
1971年年間チャート アメリカ(ビルボード)4位
元ベイ・シティ・ローラーズのイアン・ミッチェルが結成した「ロゼッタ・ストーン」というグループがありました。
当時人気絶頂だったベイ・シティ・ローラーズ関連のバンドということでメディアの耳目を集めて華々しく登場し、デビュー曲は当時ひんぱんにラジオでオンエアされていました。
すぐに消えてしまったバンドだったけれど、デビュー曲のメロディーだけは妙に耳に残ったままでした。その曲のタイトルは『サンシャイン・ラヴ』。いわずと知れた「クリーム」の名曲です。
ぼくは「クリーム」という名のグループを、ロゼッタ・ストーンの登場で初めて知ったんです。
1960年代のロックは、熱気と大きな可能性をはらんでいましたが、その時代を体現するグループのひとつが、「クリーム」です。
「クリーム」は、エリック・クラプトン、ジャック・ブルース、ジンジャー・ベイカーという、それぞれが一国一城の主とでも言うべき三人によって結成された、ロック史上初のスーパー・グループです。



左からエリック・クラプトン、ジャック・ブルース、ジンジャー・ベイカー
ヒット曲産出の手段としてのレコーディングとツアーをこなすのがそれまでのロック・バンドのあり方でしたが、クリームはライヴでの即興演奏をも重視していたグループです。そのあたりの方法論は、ロックというよりも、むしろジャズに限りなく近いと思います。各々のプレイそのものに創造性を見出そうとしているのですが、これは抜きん出た技量を持つこの三人だからこそできたことなのでしょうね。
だからといって、彼らはスタジオ録音をないがしろにしている訳ではありません。レコーディングの場合、そのスタンスを踏まえながら、「クリーム」ならではの音楽観をしっかり構築しています。
ブルースに大きく影響されている「クリーム」ですが、スタジオ録音のアルバムを聴くと、それだけにこだわらず、曲のメロディーや構成にも重きを置いているようです。『ホワイト・ルーム』や『バッヂ』などの名曲を聴くと、「クリーム」のポップな側面がよく見えます。

ライヴ・アルバムを聴くと、彼らの演奏は非常にワイルドで、攻撃的なのがわかりますね。自由で、創造性に満ちたインタープレイが存分に展開されています。スリリングなバトルとでも言ったらいいのでしょうか。ギター・トリオというシンプルな編成がより自由度を高めているとも言えるでしょう。そのタフな演奏は、このトリオがハード・ロックのルーツのひとつであることを示しています。
『クリームの素晴らしき世界』に収録されている『クロスロード』や、『グッバイ・クリーム』の中の『アイム・ソー・グラッド』などは聴いているだけで背筋がゾクゾクしてきますね。
若々しくてブルージーなエリック・クラプトンのギター、縦横無尽のジャック・ブルースのベース・ライン、ジャジーで幅広い音楽性の垣間見えるジンジャー・ベイカーのドラム、どれをとっても聴き飽きることはないのです。
そして、ヴォーカリストとしてのジャック・ブルースの、張りとツヤのあるパワフルなヴォーカルもぼくは結構好きなんです。

ぼくの「クリーム」の愛聴曲は、
『クロスロード』、『ホワイト・ルーム』、『スーラバー』、『アイム・ソー・グラッド』、『ストレンジ・ブリュー』などでしょうか。
アルバムの一番のお気に入りは、『クリームの素晴らしき世界』です。
昨年5月には実に37年ぶりに再結成し、そのニュースは世界中のロック・ファンを喜ばせましたね。ジャック・ブルースは2003年夏頃から体調を崩し、一時はニュースも途絶えてファンを心配させていましたが、見事に復活をとげました。
できれば日本にも来て欲しいのですが、それは叶わぬ願いなのかな。いずれにせよ、まだまだ元気にプレイし続けて貰いたいものですね。

2005年5月の再結成ライヴ
聴いた瞬間から心を揺さぶられるような曲があります。
素晴らしい曲であることはもちろんだけれど、それ以上に、曲の持つエネルギーと自分の感情との波長がうまく合うのでしょう。
リズム&ブルースの名曲である「男が女を愛する時」も、ぼくの心を揺さぶってやまない曲のひとつです。
当時、パーシー・スレッジは、好きな女性のことで悩んでいたそうです。そして、パーシーが当時所属していたセミプロ・バンドのベーシストとオルガン奏者が、パーシーのその気持ちを元にして書いたのがこの曲だということです。自主制作したレコードが認められたパーシーはメジャー・デビューし、この曲も全米1位に輝く大ヒットとなりました。
イントロで静かに流れるオルガン。
伸びやかなボーカルがかぶってきます。
何かを訴えるような、情熱がほとばしるような歌声。
時には絞り出すように、
時には吐息のように
時には語りかけるように。
なんて熱くて、なんてソウルフルなのでしょう。
ギターのカッティングがとてもグルーヴィー。
感情を抑えたかのようなコーラスがまるでゴスペルのようです。
愛する女性のためならば(それが悪女であっても)、自分がつらい目に遭うことも厭わず、すべてを女性に捧げようとする、一途である意味盲目的な愛情が歌詞に歌われています。その一途さがあるからこそ、聴いているぼくの心が激しく熱く揺さぶられるのだと思うのです。
考えてみると、女性に対してこれだけストレートに気持ちをぶつけることは年とともになくなってしまったような気がします。
そのストレートな気持ちを持っていた頃はまだまだ精神的に幼かったけれど、その幼さが懐かしくもあり、同時に、そういう熱い気持ちを失ってしまいたくない、とも思うのです。
この曲、1991年にはマイケル・ボルトンがカヴァーして、大ヒットさせていますね。ロッカ・バラードっぽくてよりワイルドなボルトン・ヴァージョンもカッコいいですね。
[歌 詞]
[大 意]
男が女を愛する時 彼の心にはそれ以外に何もない
男は世界でさえ 自分が見つけたいい物と取り換えてしまう
彼女が悪い女でも 男にはそれが見えない
女に悪いことはできない、と思い込み
女が機嫌を損ねると 男は自分の親友にさえ背を向ける
男が女を愛する時 最後の一銭を使い果たしても
必要なものを繋ぎとめようとする
心地よい宿さえ諦め 雨の中で寝ることも厭わない
男はそうするものだ 女に言われれば
男が女を愛する時 僕のものなら何でも君にあげよう
大切な君の愛を繋ぎとめたいんだ
ベイビー、お願いだから意地悪しないでくれ
男が女を愛する時
女は、男の心の奥深くに惨めさを味わわせることができる
女は遊び心で男をからかっても 男は最後まで気づかない
愛する瞳には決して見えないから
男が女を愛する時 男の気持ちが僕にはよくわかる
だってベイビー、僕は男だから
◆男が女を愛する時/When A Man Loves A Woman
■歌
パーシー・スレッジ/Percy Sledge
■シングル・リリース
1966年3月
■作詞・作曲
カルヴィン・ルイス/Calvin Lewis、アンドリュー・ライト/Andrew Wright
■プロデュース
マーリン・グリーン/Marlin Greene、クイン・アイヴィー/Quin Ivy
■録音メンバー
パーシー・スレッジ/Percy Sledge(vocal)
マーリン・グリーン/Marlin Greene(guitar)
スプーナー・オールダム/Spooner Oldham(organ)
アルバート・ロウ/Albert "Junior" Lowe(double-bass)
ロジャー・ホーキンス/Roger Hawkins(drums)
■収録アルバム
When a Man Loves a Woman(1966年)
■チャート最高位
1966年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位(5月28日~6月3日 2週連続)、イギリス4位(6月25日)
1987年週間チャート イギリス2位
1966年年間チャート アメリカ(ビルボード)20位
パニック映画の超大作として非常に有名な作品ですね。
総製作費は、実に1400万ドル。
もともとは、ワーナー・ブラザーズと20世紀フォックスが、それぞれビル火災をテーマにした映画を企画していました。しかし両社の間で、「多額の投資で競い合うよりは共同出資して大作を作る方が良い」という判断が下され、ハリウッド史上初めて大手2社によって共同製作されることになったのです。
出演者の顔ぶれもとても豪華です。ポール・ニューマンとスティーヴ・マックィーンの両巨星の共演ということで、当時はたいへんな話題になりましたが、共演陣にも、主演クラスの名前がズラリと並んでいますね。
ちなみにこの映画では、後年「ブルース・ブラザーズ」などで監督を務めるジョン・ランディスが、墜落死する男性役で出演しています。


撮影は、実際に高さ33mのビルを建てて行われました。使った水の量は4000キロリットルにものぼるそうです。
またスタジオに57部屋のセットを作り、うち49部屋を火攻め水攻めにして撮影しています。
この映画の製作はアーウィン・アレンですが、彼はあの「ポセイドン・アドヴェンチャー」を手がけた人でもあるんですね。
今の映画と違って、CGを使用したところもなく、実際に俳優やスタントマンが危険なシーンを演じているため、かえってリアルで重厚感が感じられるんです。
爆発して炎が一瞬にしてフロアーを走るシーン、火の中を走るシーン、ヘリコプターによるエレベーターの宙吊り、そしてそこでオハラハン隊長が落ちかけた消防士を片手で支えるシーン、クライマックスの給水タンク爆破など、ハラハラさせられるシーンの連続で、たいへん面白い娯楽作品です。
しかし、面白いだけでなく、多くのメッセージを含んでいる作品でもありますよね。
 燃える「グラス・タワー」
燃える「グラス・タワー」
原題は「そびえたつ地獄」という意味ですが、その名の通り、サンフランシスコに完成したばかりの138階建て超高層ビルの81階で火災が発生するという設定です。
工費を浮かせようと、指定されたものより質の落ちる電線を意図的に使用したため、電気系統に負荷がかかり、配電盤がショートして出火するのですが、これ、明らかに人災ですよね。安全性より利潤を追求しようとすることが災害に繋がる、ということを示唆しているようです。この部分、はからずも今の日本で騒がれている耐震偽造問題の本質を30年も前に予言しているかのようです。
ロバーツがダンカン社長にこう詰め寄る場面があります。
「人々が安全に過ごせる建物になるはずだったのに…。コストを削るならなぜ階数を削らないのだ!」と。
その時ロバーツはこうも言っています。「人を殺せば何と呼ばれる?」

フェイ・ダナウェイ(左)、ポール・ニューマン(右)

ジェニファー・ジョーンズ(左)、フレッド・アステア(右)
高層ビル火災の恐ろしさも当然テーマのひとつでしょう。オハラハン隊長はロバーツに「確実に消せるのは7階までなのに、設計屋は高さを競い合う」と吐き捨てています。
ビルの防災設備を過信しているダンカン社長は、オハラハン隊長に「ボヤ程度でそう慌てることはないだろう」と笑顔で話しかけます。この時オハラハンは「安全な火事などない」と素っ気なく答えていますが、この言葉もとても教訓的だと思いますね。
また、ビルの住人で耳が不自由なオルブライト夫人には火災の知らせが伝わらないというエピソードは、小さいけれども見過ごすことのできない部分だと思います。実際、耳の不自由な人には危険の知らせが伝わりにくいので、災害の時には逃げ遅れる危険性が高いのだそうですね。

ウィリアム・ホールデン(左)、リチャード・チェンバレン(右)

スーザン・フラネリー(左)、ロバート・ワグナー(右)
最後のシーンでのそれぞれの言葉も印象的でした。
ダンカンは、「今はただ神に祈るのみだ。この惨事を繰り返さぬように」とつぶやきます。
ロバーツは「このビルをこのまま残すべきかな。人間の愚かさの象徴として」とスーザンに語りかけます。
そしてオハラハンはロバーツに「運よく死者は200名以下だ。しかし、今にこんなビル火災で1万人の死者が出るぞ。俺は火と戦い、死体を運び続ける。誰かに安全なビルの建て方を聞かれるまで」と、問いかけるように話すのです。
これらの言葉も、ある意味「予言」ともとれそうです。

ポール・ニューマン(左)、スティーブ・マックイーン(右)
現実に高層ビルが乱立する時代となり、防災設備も進化しましたが、同時に高層ビル火災は悲惨さを増しています。
この作品は、単なるパニック映画ではなく、火災に対する危機管理の見直しや、安全性の最優先などのさまざまな問題を、30年も前にぼくらに提言してくれています。
映画の冒頭で、「人命を救うために自分たちの命を犠牲にする全世界の消防士にこの映画を捧げる」という言葉が出てきますが、消防士にだけではなく、ビルを造る人たち、ビルを利用する人たちすべてへの教訓が含まれている作品なのだと思います。

◆タワーリング・インフェルノ/The Towering Inferno
■1974年 アメリカ映画
■製作
アーウィン・アレン
■配給
米国=20世紀フォックス
日本=ワーナー・ブラザーズ/20世紀フォックス
■監督
ジョン・ギラーミン
■音楽
ジョン・ウィリアムス
■出演
スティーヴ・マックィーン(マイケル・オハラハン隊長)
ポール・ニューマン(ダグ・ロバーツ)
ウィリアム・ホールデン(ジェームス・ダンカン社長)
フェイ・ダナウェイ(スーザン・フランクリン)
フレッド・アステア(ハーリー・クレイボーン)
スーザン・ブレイクリー(パティ・シモンズ)
リチャード・チェンバレン(ロジャー・シモンズ)
ジェニファー・ジョーンズ(リソレット・ミュラー)
O.J. シンプソン(ハリー・ジャーニガン警備主任)
ロバート・ヴォーン(ゲイリー・パーカー上院議員)
ロバート・ワグナー(ダン・ビグロー広報部長)
スーザン・フランネリー(ローリー)
ノーマン・バートン(ウィル・ギディングス工事主任)
ジャック・コリンズ(ロバート・ラムゼイ市長)
シーラ・マシューズ(ポーラ・ラムジー市長夫人)
グレゴリー・シエラ(バーテンダーのカルロス)
ドン・ゴードン(カピー消防士)
フェルトン・ペリー(スコット消防士)
アーニー・F・オルサッティ(マーク・パワーズ消防士)
カリーナ・ガワー(アンジェラ・オルブライト)
マイク・ルッキンランド(フィリップ・オルブライト)
キャロル・マケヴォイ(オルブライト夫人)
ジョン・クロフォード(キャラハン地下機械室主任)
ダブニー・コールマン(消防署副署長1)
ロス・エリオット(消防署副署長2)
ノーマン・グラボウスキー(フレイカー)
・・・etc
■上映時間
165分
■主題歌
愛のテーマ/We May Never Love Like This Again(歌:モーリン・マクガヴァン)
ジャズ・ピアニストの本田竹広氏が、急性心不全のため1月12日に亡くなりました。今年3月には、鈴木良雄(bass)、森山威男(drums)の両氏と組んでレコーディングするというニュースを知ったばかりだったので、あまりの突然な訃報には驚かされました。
本田氏は1969年に初リーダー作を発表してからは、日本ジャズ界のホープと期待されていました。ソロ活動のほか、渡辺貞夫グループなどにも参加しています。1978年には「ネイティヴ・サン」を結成し、フュージョン・シーンをも席捲しました。
ジャズ界を牽引するひとりとして精力的に活動していましたが、1995年、1997年の二度にわたって脳内出血のために倒れました。とくに1997年は左半身不随となるほどの重体に陥ったのです。そのうえ人工透析をも続けなければならない本田氏は、一時は社会復帰さえ危ぶまれていました。
しかし療養先の病院のリハビリ室に真新しいピアノを置いてあるのを見つけた本田氏は、復帰を目指してそれを必死で弾こうとします。
驚異的な回復をとげた本田氏は、2000年には実子の本田珠也(drums)氏らと組んで、ニュー・アルバムを発表し、その後も着実に活動を続けていました。
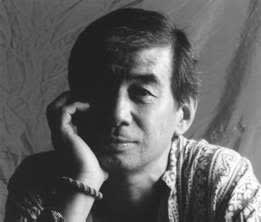
『ジス・イズ・ホンダ』は1972年に発表された、本田氏の8枚目のアルバムです。(当時は「本田竹曠」)
ぼくはこのアルバムのもつ不思議な緊迫感が好きです。
原曲のメロディーを大事にしたうえで、本田氏の中から湧き上がってくる「歌」が、指先を通じてピアノへ流れ込んでゆくのが見えるような気がするのです。
とくにバラードにおける、熱くてエモーショナルな演奏には、心を打たれるものがあります。
二度の脳内出血という大病、しかも左半身の自由が利かなくなるという事態に、ピアニストである本田氏はどれだけ衝撃も受けたでしょう。しかし現実を受け入れる勇気があったからこそカムバックができたのでしょうし、何より復活するという目的に向けて努力を惜しまなかったであろう本田氏の生き方にも強く尊敬の念を覚えます。
昨年は夏に心臓肥大のため長期入院していたようですが、幾度となく襲いかかって来るアクシデントにめげることなく、精一杯ミュージシャンとして生き続けたのではないでしょうか。

本田氏の生き様は、ぼくになんらかの元気を与えてくれたという気がしています。
ぼくは、本田氏が「まだ60歳の若さで亡くなった」と言うより、「最後まで前に向いて進み続けた」と思っていたいのです。
◆ジス・イズ・ホンダ/This is Honda
■演奏
本田竹曠
■録音
1972年3月14日 東京イイノホール
■プロデュース・録音エンジニア
菅野沖彦
■録音メンバー
本田竹曠(piano)
鈴木良雄(bass)
渡辺文男(drums)
■収録曲
① 恋とは何か君は知らない/You Don't Know What Love Is (Don Raye, Gene de Paul)
② バイ・バイ・ブラックバード/Bye Bye Blackbird (Mort Dixon, Ray Henderson)
③ ラウンド・アバウト・ミッドナイト/Round About Midnight (Theloniois Monk, Bernie Hanighen, Cootie Williams)
④ 朝日の如くさわやかに/Softly As In A Morning Sunrise (Sigmund Romberg, Oscar HammersteinⅡ)
⑤ ホエン・サニー・ゲッツ・ブルー/When Sunny Gets Blue (Jack Segal, Marvin Fisher)
⑥ シークレット・ラヴ/Secret Love (Paul Francis Webster, Calamity Jane)
■レーベル
トリオレコード
ここのところ、スティーヴィー・ワンダーのCDを棚から取り出すことが多いです。
改めてじっくりスティーヴィーの曲を聴いてみると、「なんて温かみに溢れているんだろう」と思わずにはいられません。
そしてその温かみは、彼の内面から自然ににじみ出てくる「愛」なのではないか、という気がします。
まさに、スティーヴィーによる「ソウル・ミュージック」です。

スティーヴィーと言えば、ぼくにとっては、あの「ウィ・アー・ザ・ワールド」の中での歌声が強く印象に残っています。とくに、ブルース・スプリングスティーンとの掛け合いは名唱だと思いました。聴いていると心地よい快感と感動が背筋を走りぬけてゆくんです。
ぼくがスティーヴィーの音楽に最初に触れたのは、ベック・ボガート&アピスのレコードで聴いた「迷信」だったはずです。
でもその時は、それ以上聴いてみようという気にはなれませんでした。当時のぼくは、ほぼロック一辺倒だったし、いわゆる「ソウル・ミュージック」の持つ濃い黒っぽさにはまだ馴染めなかったんだと思います。
でも、「ウィ・アー・ザ・ワールド」がきっかけとなって、ぼくはスティーヴィーにより親しみを覚えることになるのでした。
ステージでのレパートリーにスティーヴィーの作品を加えるヴォーカリストも多いようで、オリジナルを聴くより先に、渡された譜面によってスティーヴィーの曲を知ることもしばしばでした。
それは、裏を返すと、スティーヴィーの曲が広く愛されているということの証明にもなるのではないでしょうか。そういうところからも、ぼくはスティーヴィーの「偉大さ」を感じ取るようになったんです。

非常にグルーヴィーなリズム、彼自身が歌と化したようなソウルフルな歌声がとても気持ち良い。
ボーカルのほか、ピアノ、ハーモニカ、ドラムなどをこなすマルチ・プレーヤーとしても知られていますね。
メロディー・メイカーとして超一流なのも多くの人が認めているところでしょう。絶妙な転調の使用、独特の感覚に基づくコード・ワークやヴォイシングには、真似のできない素晴らしいセンスが感じられます。
とりわけ一番ぼくが心地よく感じるのは、スティーヴィーの曲の持つカラフルな感覚です。メロディーを聴いていると、次々にいろんな「色を体感」できる気がするのです。
「サンシャイン」
「マイ・シェリー・アモール」
「オーヴァージョイド」
「心の愛」
「愛するデューク」・・・
お気に入りの曲を書き始めると、これもちょっとキリがありません。

スティーヴィーは、先頃、愛娘を伴って来日しました。
その愛娘が誕生した時、スティーヴィーは「イズント・シー・ラヴリー」という曲を書いています。日本語タイトルは「可愛いアイシャ」。そのアイシャ・ワンダー、現在はシンガーとして活動しており、父のスティーヴィーとステージを共にすることもままあるそうです。
ワンダー親子には、これからもさらに「愛のこもった作品」を生み出して欲しいですね。
大原美術館は、倉敷市にある有名な美術館です。
たいていの観光ガイドに載ってますね。
今日はそこへ行ってきました。
絵を見るのもほんとうに久しぶりです。

アメデオ・モディリアーニ「ジャンヌ・エビュテルヌの肖像」

エル・グレコ「受胎告知」

ギュスターヴ・クールベ「秋の海」
友人のヤヨイさん、ミチヨさんと一緒でした。
ふたりとも「絵画を楽しんでいる」ようでした。
素直に、それぞれの絵の持つ世界に触れているような感じ。
「彼女たちのように絵を楽しみたい」と思いました。

クロード・モネ「睡蓮」

クロード・モネ「積みわら」

ポール・ゴーギャン「かぐわしき大地」
すぐそばで見る絵は、
写真で見るのとは全然違う迫力があります。
絵の具の盛り上がりぐあいとか、
タッチの強弱とか、
そういうものが目の前でこちらに何かを訴えかけてる感じです。
「絵って生きてる」と思いました。

岸田劉生「童女舞姿」

小出楢重「Nの家族」

児島虎次郎「和服を着たベルギーの少女」
絵に囲まれた部屋に入ると
なにものかに圧倒されるような気がします。
まるで、絵から「気」のようなものが出ているみたいです。
音楽にしろ絵画にしろ演劇にしろ、
芸術は「生で」「間近に」ふれるものなんだ、と
しみじみ思いました。
すごく有意義で気持ちの安らぐ時間でした。
人気blogランキングへ←クリックして下さいね
何かと慌しい今の世の中に生きているわれわれですが、時には何もかも忘れてのんびりしたい、と思ったりします。
こういう考え方を持つ人はあちこちにいるとみえて、「変化の早い現代社会における平静と緩慢な時の流れの再発見」というコンセプトをもとに、今、ドイツである曲が演奏されるプロジェクトがゆっくり進行しています。
曲のタイトルは、その名も『できる限りゆっくりと』。
この曲の演奏時間、なんと639年(!)なんだそうです。

正確なタイトルは、『Organ2/ASLSP"(As Slow As Possible)』
作曲者は、アメリカの作曲家ジョン・ケージ。
ん? ジョン・ケージ?
この人、たしかあの稀代の"怪曲"『4分33秒』を作った人ですよ。
うーむ、ジョン・ケージって人、いろいろやってくれますね~。
演奏されている場所は、ドイツのハルバーシュタットにある、ブキャルディ廃教会です。
演奏は2001年9月5日に始まり、2639年まで続きます。
最初の1年半は全くの無音(!)。
2003年2月に、ようやく最初のコード(ソ♯、シ、ソ♯)が鳴らされ、2004年になって新たなオモリが鍵盤に置かれて、1オクターブ下の「ミ」の音が加えられました。
そして今年、演奏開始から5年目にして、今後数年間鳴り続ける予定の第二のコード(シ、ド、ファ♯)へと曲は進行したんだそうです。
この『できる限りゆっくりと』という曲は、もともとは20分間のピアノ曲として発表されたものです。
今回の演奏プロジェクトを推進している「ジョン・ケージ・オルガン・プロジェクト」は、この曲のタイトルに込められた思想を尊重して、演奏を639年もの長きに渡って行うことにしたのだそうです。
「639年」という演奏時間は、この教会に初めてオルガンが設置された1361年から、プロジェクトが開始された2001年までの年月を元に設定された、ということです。
この演奏、何世代にも渡って脈々と受け継がれてゆくんですね。考えてみると、ロマンティックでさえあります。数百年後の人は、何百年もの間鳴り続けるオルガンの音を聴くことができるんですからね。
プロジェクトに参加している人たちは、「3年後にラの音を出すのを忘れるなよ!」なんて言い伝え合うのかな。

ジョン・ケージという人は、尽きることのない数々のアイディアを持っていることで知られています。ケージの師であるシェーンベルクは、彼を「天才的な発明家」と呼んでいたほどです。
代表曲に、音を一切発しない『4分33秒』や何をしてもよい『0分00秒』などを持つケージに対しては、「現代音楽界最大の作曲家」と絶賛する者もいれば、「ただの詐欺師」と言う者もいるようです。
これは演奏というより、もはや「パフォーマンス」といった方がいいかもしれません。それにしても気の長い話です
 。
。でも、時間に追われる一方の現代の中でのこういう発想は、「時間に縛られない自由」もあるということのささやかな主張なのかもしれません。
ひとつだけはっきり言えること、それは「この曲を最初から最後まで通して鑑賞することはできない」ということです。
この廃教会だけが曲のすべてを聴いているのです。
【同プロジェクトの公式サイト】
ASLSP - John-Cage-Orgelprojekt Halberstadt
ページ右上のカウントが残り演奏時間(秒)です。
人気blogランキングへ←クリックして下さいね
不思議と月に何度かは食べたくなるもの。
それはカレー。

ご馳走が並ぶことの多い年末年始ですが、今日の夕食にはカレーを無性に食べたい気分でした。
あ~マンゾク。
好きな食べ物ではあるけれど、特に好物というほどでもないカレーなんですが、今日のような気分の日が必ずやって来るんです。
外で昼食をとる時、何にしようか迷ったりすることってありますよね。そんな時、結局カレーに落ち着くことも多いです。
今は専門店も数多いし、種類も多岐に渡ってますから、なかなか飽きないですね。
カレーのルーツは、ご存知の通りインドです。でも、今ぼくらが普通食べているカレーは本場のものではありません。
インドを植民地としていたイギリス人が、18~19世紀にカレーを自国に持ち帰り、欧風シチューのようにアレンジしました。明治維新で開国したばかりの日本に、他の西洋料理とともに入って来たカレーは、その欧風のものだったというわけです。
ちなみに初めてカレーに出会った日本人は、幕府の遣欧使節一行です。1860年、ヨーロッパに向かう船上で、カレーを食べるインド人に遭遇したんだそうです。
明治中期には徐々に洋食屋のメニューとして広まりましたが、この頃は「文明開化の食べ物」、つまり一種のファッションとして受け止められていたそうで、かなりの高級料理だったようです。
しかし、軍用食のひとつでもあったカレーは、徴兵制度によって軍隊に集まってきた国民に広く知られるところとなり、昭和初期には急激に大衆料理として浸透していきました。
カレー粉の発売は大正初期ですが、昭和30年代には固形ルーが主流となり、昭和40年代になってレトルトタイプが発売されるようになりました。
今では子供の好きな料理の王様として広く愛されている、というわけです。
カレーの隠し味はさまざまですね。各家庭ごとに独自の隠し味がある、といってもいいくらいです。
学生時代にぼくがアルバイトしていたお店では、キャベツの芯をみじん切りにして一緒に煮込むことを教えてもらいました。こうするとキャベツの甘みのおかげでカレーにまろやかさが出るし、キャベツ自体も煮込むとイモのような食感になっておいしく食べられるんです。
隠し味として使われている物には、ヨーグルト、ワイン、とろけるチーズなどがありますが、ぼくはウスターソースととんかつソースを合わせたもの(一日寝かしておけばなお良い)を入れたりします。
おもしろい隠し味としては、トマトジュース、イチゴジャム、ブラックチョコ、コーヒー(酸味の強くないもの)、にんにく、リンゴなどがあります。
夕食の時、好みに合わせていろんな辛さのカレーを作るのも面倒ですよね。
辛いのが苦手な人は、お皿のジャガイモをスプーンでつぶしてルーと混ぜてみましょう。辛味が抑えられますよ。生卵をかけるのが好きな人も多いでしょうね。または、お皿のルーに牛乳を大さじ1~2杯混ぜる、という手もあります。とてもまろやかになりますよ。
バリエーションの多さを味わえるのもカレーの楽しさですね。
使うお肉はビーフ、ポーク、チキン。トンカツとかエビフライをトッピングしたり。マトン・カレーや、シーフード・カレーもいいですね。ナスなどの野菜やキノコも合います。
変わったところで、ネギとカエルのカレー などはいかがでしょう。
などはいかがでしょう。
①ネギ、ニンニク、ショウガをバターで炒める。
②水を加えて煮る。さらにカエルを入れる。
③煮込んだらカレー粉、水で溶いた小麦粉を加える。

これは、明治時代に出版された西洋料理の本で紹介されているそうです。
なぜタマネギではなくネギなのか。この当時は、日本ではタマネギがまだ普及していなかったから、なんですね。
そして、なぜ肉ではなくてカエルを使うのでしょう。(「蛙」と書くとナマナマしすぎるな~ )それは、「当時は食用ガエルが割りと一般的に食べられていたから」なんだそうですよ。
)それは、「当時は食用ガエルが割りと一般的に食べられていたから」なんだそうですよ。
今日はカレーについてのウンチクを語ってみました(笑)
今年4月に、ボン・ジョヴィが来日しますね。
8日の東京ドームを皮切りに、18日の札幌まで6公演が予定されています。
会場は東京、大阪、名古屋、札幌の各ドーム。楽しみにしている方も多いことでしょう。
1984年にデビューして今年で22年目。もうそんなになるのか・・・。
彼らのデビュー・シングルは、「夜明けのランナウェイ」。
ドラマ 1980年代のテレビ界は大映テレビ制作のドラマが一世を風靡しました。その作品のひとつ『乳姉妹』の主題歌となったのが、麻倉未稀が歌う「夜明けのランナウェイ」のカヴァーでした。
当時はアメリカでも一部でしか知られていなかったらしいのですが、この曲によって耳の肥えた日本のファンの支持を受け、折からのヘヴィ・メタル・ロック・ブームに後押しされて、人気に火がついたんでしたね。

メンバーは、
ジョン・ボン・ジョヴィ(vocal, guitar)
リッチー・サンボラ(guitar)
アレック・ジョン・サッチ(bass)、
ティコ・トーレス(drums)、
デヴィッド・ブライアン(keyboard)
の5人でしたが、ベースのアレックは1994年に脱退し、以後はサポート・メンバーを加えて活動しています。
ジョンとリッチーのソング・ライティング・チームによって生み出される曲は、メロディアスで、エネルギッシュで、たいへん劇的です。
とはいえ、決してハード・ロック一辺倒ではなく、ポップス、フォーク、ブルースなど、いろいろなジャンルの要素を内包しているように思えます。
親しみやすいメロディーと確かな演奏力に加え、アイドル並みのルックスを持っていることもハード・ロック・ファンにとどまらず広く支持されている理由のひとつではないでしょうか。

最新アルバム「ハヴ・ア・ナイス・デイ」(2005年)
昨年発表した9枚目のアルバム『ハヴ・ア・ナイス・デイ』も大ヒット、健在ぶりを示してくれました。
いまやベテランいっても差し支えないキャリアを持つグループなのですが、現状に安住することなく、常に次のステップを目指してアグレッシヴに活動を続けるその姿勢があるからこそ、いつまでも若々しさを保つことができているのでしょうね。
大ブレイクして生活が変わったことでメンバー全員がガールフレンドや夫人との別れを余儀なくされましたが、そういう精神的苦痛を乗り越えたこと、自分たちの持つ強い信念に基づいて前身し続けていること、解散の危機を克服していつも最高の音を聴かせてくれることなど、彼らの姿勢にも大きな共感を覚えます。

「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」「ウォンテッド・デッド・オア・アライヴ」「ランナウェイ」などが、ぼくが昔から変わらず聴き続けている曲です。
その他にも「イッツ・マイ・ライフ」「オールウェイズ」「禁じられた愛」などなど、名曲が目白押しですね。

ベスト・アルバム「クロスロード」
近年、ジョンは俳優としても活動の場を広げており、「U-571」「ペイ・フォワード」「アリー・myラブ」などの話題作にも出演しています。
メンバーそれぞれもソロ・ワークをこなしているようです。
活動の幅を広げ、それを自分たちのプラスにし、さらに『ボン・ジョヴィ』としてスケール・アップして長く活動を続けて欲しいものですね。

年末年始はのんびりできる時間が多いので、音楽を聴いたり、映画を観たり、本を読んだりして気ままに過ごしてます。
気の向くままに買って、そのままになっていた本が何冊かあるので、時間にゆとりのあるこういう時に、ゆっくりそれらにに没頭しています。
その中の一冊が、『三谷幸喜のありふれた生活4 冷や汗の向こう側』(朝日新聞社)です。
三谷幸喜氏は「古畑任三郎」や「新撰組!」などを手がけた売れっ子脚本家として有名ですね。そのほか、映画監督としてメガホンをとるなど、幅広く活躍しています。彼の、仕掛けたっぷりの脚本は、ぼくも結構好きなんです。
その三谷氏が、朝日新聞に連載しているのが、『ありふれた生活』です。2000年4月に連載が始まり、単行本もこれが4巻目。

肩の凝らない平易な文章がいいですね。
それでいて、文章には三谷氏の思いが詰まっている、って感じ。
和田誠氏のイラストもぴったりマッチしています。
テレビドラマや舞台の裏側、脚本執筆中の苦労、役者さんたちにまつわるいろんなエピソード、三谷氏の飼い犬秘話を含む私生活などがたっぷりと読むことができます。
テレビ、映画、舞台を問わず、ひとつのドラマが完成するまでの「生みの苦しみ」にやはり心引かれるものがあります。
脚本家の苦しみ、演技者の苦しみ、裏方さんたちの苦労。そして、無事に完成した時の達成感、解放感。
もちろん、軽いエッセイとして読んでも楽しい。
三谷氏の身の周りのエピソードの数々が、三谷氏の語り口と同様のひょうひょうとした文体でちょっとコミカルに書かれています。共感できるところもあれば、クスッと笑えるところ、ジーンとくるところもあって、リラックスしながらも元気がジワジワと出てくること請け合いですよ。































