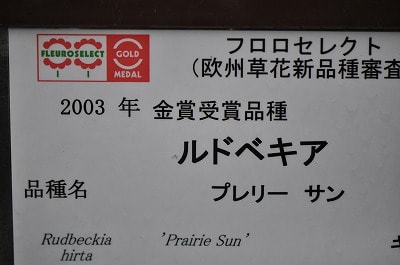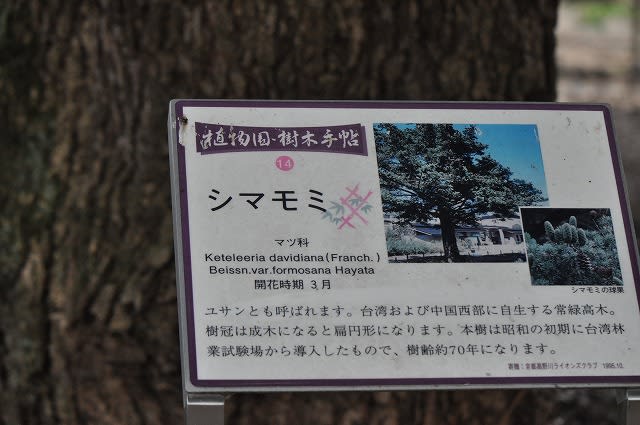京都府立植物園の北山門入口で
"観覧温室夜間開園&クリスマス・イルミネーション"の大きなポスターが目に留まりました。
「ほぉ~~キレイやろうなぁ 夜まで残ってみる?」
「いいよ」
京都府立植物園の中を「松谷名誉園長さんと気まぐれ散歩」してからね、温室で写真撮ろうかな?と・・・
温室に入ると、カメラのレンズが、くもってしまい紗をかけたようになってしまう・・・何回も拭いていたらやっとカメラのレンズが慣れてきましたね。
温室では珍しいお花がいっぱい、名札が頼りなんですよ・・・
2011.12.18京都府立植物園観覧温室PhotoStory1.wmv
アマゾンユリ:ヒガンバナ科 別名:ギボウシスイセン(アマゾン・アンデス山地)
アリストロキア・ギガンテア:ウマノスズクサ科
ウナズキヒメフヨウ:アオイ科 別名:眠れるハイビスカス
オオベニゴウカン(大紅合歓) マメ科
グロクシニア シルウァティカ(Gloxinia sylvatica) イワタバコ科
コリトプレクツス・スペキオスス:イワタバコ科(エクアドル、ペルー)
サリタエア・マグニフィカ:ノウゼンカズラ科(コロンビア)
シャムソケイ. Jasminum rex モクセイ科(タイ)
ツンベルギア・ウォゲリアナ:キツネノマゴ科(西アフリカ熱帯部)
ツンベルギア・マイソレンシス:キツネノマゴ科(インド)
ドムベヤ・セミノール:アオイ科
パキスタキス・コッキネア :キツネノマゴ科 別名:ベニサンゴバナ(紅珊瑚花).(ガイアナ)
フラグミペディウム:ラン科
フリーセア“セプタードオール”:パイナップル科
ヘリコニアヴァグネリアナ:バショウ科
ヘリコニアマリエ:オウムバナ科
ヘリコニアプシッタコルム:バショウ科(西インド諸島~南アメリカ)
ベンガルヤハズカズラ(ベンガル矢筈葛) キツネノマゴ科
ホルムショルディア・サングイネア:クマツヅラ科(インド)
ユメレア・サギタタ:ラン科
リンコスティリス・ギガンテア:ラン科(インド、タイ)
リンコソフロカトレヤ(ラン科)
ポインセチア展開催中でした。


「ポインセチア」 森 未知子
かつて眼差しのなかに
燃える焔(ほのお)をみたことがあった
その日から溢れくるもの 充ちてくるものが
わたしの内部をひたしはじめる
おお輝くわたしの変身よ
木枯しの街の彼方
青いわたしの故郷は何處。
↑ 道草さんからです、アリガトウです。
さて、温室から出ても夜間開園まで少々時間アリ
「どうする?食事にでも行く?」
「そうしよか」
植物園を出ると北山通り、ここは、こじゃれたお店が軒並みに・・・
食事をしておしゃべりしてると程よい時間になりまして・・・
再入園です、
京都府立植物園は60歳以上は年齢証明を提示すると入園料は無料です。
(京都府民だけじゃないですよ、他府県からの人もOKですよ)
いきなり、北山門から入ってすぐの噴水が・・・

暗っぽい園内を歩きながらところどころのカワイイ動物のイルミなど見ながら・・・

↑ クリックで大きくなります
おっと、いきなり明るい場所に・・・
なんと、氷の彫刻制作真っただ中デス。


シャシャシャシャッと手際の良い事、そりゃぁモタモタしてたら氷が融けてしまいますわね。
(社)全日本司厨士(「西洋料理」を専門に従事する料理人)協会京滋地方本部協力とありました。
お題は 「絆」
パチパチパチと拍手喝采
それから、ゆっくり歩きながらステキなイルミネーションを楽しみました





↑ クリックで大きくなります
【おまけ】
今日、こんなニュースを観ました
三陸照らす希望の光、約10万個LEDでイルミネーション
"観覧温室夜間開園&クリスマス・イルミネーション"の大きなポスターが目に留まりました。
「ほぉ~~キレイやろうなぁ 夜まで残ってみる?」
「いいよ」
京都府立植物園の中を「松谷名誉園長さんと気まぐれ散歩」してからね、温室で写真撮ろうかな?と・・・
温室に入ると、カメラのレンズが、くもってしまい紗をかけたようになってしまう・・・何回も拭いていたらやっとカメラのレンズが慣れてきましたね。
温室では珍しいお花がいっぱい、名札が頼りなんですよ・・・
2011.12.18京都府立植物園観覧温室PhotoStory1.wmv
アマゾンユリ:ヒガンバナ科 別名:ギボウシスイセン(アマゾン・アンデス山地)
アリストロキア・ギガンテア:ウマノスズクサ科
ウナズキヒメフヨウ:アオイ科 別名:眠れるハイビスカス
オオベニゴウカン(大紅合歓) マメ科
グロクシニア シルウァティカ(Gloxinia sylvatica) イワタバコ科
コリトプレクツス・スペキオスス:イワタバコ科(エクアドル、ペルー)
サリタエア・マグニフィカ:ノウゼンカズラ科(コロンビア)
シャムソケイ. Jasminum rex モクセイ科(タイ)
ツンベルギア・ウォゲリアナ:キツネノマゴ科(西アフリカ熱帯部)
ツンベルギア・マイソレンシス:キツネノマゴ科(インド)
ドムベヤ・セミノール:アオイ科
パキスタキス・コッキネア :キツネノマゴ科 別名:ベニサンゴバナ(紅珊瑚花).(ガイアナ)
フラグミペディウム:ラン科
フリーセア“セプタードオール”:パイナップル科
ヘリコニアヴァグネリアナ:バショウ科
ヘリコニアマリエ:オウムバナ科
ヘリコニアプシッタコルム:バショウ科(西インド諸島~南アメリカ)
ベンガルヤハズカズラ(ベンガル矢筈葛) キツネノマゴ科
ホルムショルディア・サングイネア:クマツヅラ科(インド)
ユメレア・サギタタ:ラン科
リンコスティリス・ギガンテア:ラン科(インド、タイ)
リンコソフロカトレヤ(ラン科)
ポインセチア展開催中でした。


「ポインセチア」 森 未知子
かつて眼差しのなかに
燃える焔(ほのお)をみたことがあった
その日から溢れくるもの 充ちてくるものが
わたしの内部をひたしはじめる
おお輝くわたしの変身よ
木枯しの街の彼方
青いわたしの故郷は何處。
↑ 道草さんからです、アリガトウです。
さて、温室から出ても夜間開園まで少々時間アリ
「どうする?食事にでも行く?」
「そうしよか」
植物園を出ると北山通り、ここは、こじゃれたお店が軒並みに・・・
食事をしておしゃべりしてると程よい時間になりまして・・・
再入園です、
京都府立植物園は60歳以上は年齢証明を提示すると入園料は無料です。
(京都府民だけじゃないですよ、他府県からの人もOKですよ)
いきなり、北山門から入ってすぐの噴水が・・・

暗っぽい園内を歩きながらところどころのカワイイ動物のイルミなど見ながら・・・

↑ クリックで大きくなります
おっと、いきなり明るい場所に・・・
なんと、氷の彫刻制作真っただ中デス。


シャシャシャシャッと手際の良い事、そりゃぁモタモタしてたら氷が融けてしまいますわね。
(社)全日本司厨士(「西洋料理」を専門に従事する料理人)協会京滋地方本部協力とありました。
お題は 「絆」

パチパチパチと拍手喝采
それから、ゆっくり歩きながらステキなイルミネーションを楽しみました





↑ クリックで大きくなります
【おまけ】
今日、こんなニュースを観ました
三陸照らす希望の光、約10万個LEDでイルミネーション