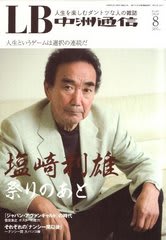土曜日は日本平で「清水対神戸」戦。
午前中のバスで静岡へ向かったのでお昼に到着。七間町あたりをぶらぶらした後、早めにスタジアムへ向かう。
売店で新発売のフラッグ2種と150勝記念Tシャツを購入。んでもって、滅多に引いたことのないサイン会抽選クジ(グッズ1000円分購入ごとに1回引ける)を4枚引いたら、そのうち3枚当たり。
どうよ、この引きの強さ。精度の高さ。
いや、1枚でも…いやいや、むしろオレのキャラクター的には当たらなくていいんですけど…とも思ったが一応受け取り、いつものシートの近くにたまたまいた親子連れに声をかけ、無理やり2枚進呈(やっぱし1枚はもらうことにした)。この日のサイン会は児玉君。サポサンでもツーショット撮ったし、何かの縁だと150勝Tのど真ん中にでっかく書いてもらう。
うむ、今日はツイてる。
詳しくは書かないが、午前中からそんな気がしていたのだ。
物事はロジカルに組み立てていけばすべてが思い通りに収まって行くというわけはなく、運が占める割合は決して低くない。人生と勝負とはそういうものである。
しかし、そんなツキもゲームが始まるまでのことだった。内容は評価できるとは言え、ゲーム終了後は激しく凹んだ。
ロジカルなスポーツである野球などと比較すると、理不尽なスポーツであるサッカーの場合、運に左右される可能性が高い。サッカーというスポーツを数字ですべて表現できるとは思わないが、それでもこの日のゲームは数字が示す通り、内容としては清水のゲームだったと言える。
それでも負ける。
押しまくっていたのに得点が奪えない終了間際の嫌な時間帯に、この日のゲームで何回も中途半端なプレイを繰り返していた苦悩するアオが与えた久々のCK。J's GOALで前島芳雄さんも書いているように、神戸サポを除く、スタンドの観客もとても嫌な予感がしていたはずだ。
そしてそういうときの嫌な予感は的中する。
松田監督「今日特に清水が……セットプレーが何か穴があるなということも感じませんでしたし、ただしセットプレーから点を取られてるという事実はあるので、我々のセットプレーっていうのはやっぱり精度を高めて、確率を高めて行こうという話はしてました」(Sの極み 7月12日付)
フォーメーションと共に、サッカーの気まぐれな運をかろうじてコントロール(得点)できる可能性の高い戦術・戦略がセットプレーで、オフェンスにしてもディフェンスにしても、その可能性と精度を高めていくのがコーチの役割である。チームとしての戦術・戦略度の高い札幌、神戸にしてやられたのはむしろ当然だったと言えるかもしれない。
といっても、それまでゲームの流れの中で神戸に与えた決定機は数えるほどで、逆に清水の決定機はタイムアップへ向かってますます増え続けていた。可能性と確率は増えていたのだ。しかし残念ながらゴールへ迫る確率は増えても、それがゴールへの精度に結びつくとは限らない。シュートを撃たなきゃ何にも始まらないが、いくらミドルを撃っても、ゲーム前の練習でゴールに入らないシュートが本番で入る可能性はとても低いと言わざるを得ない。
健太「ただ勝負事なんで、勝負に負けてしまっては何も意味がないと。最後のセットプレーのところというのは、まあ前節もセットプレーから2失点してですね、選手たちもまあ気をつけてはいたという風に思うんですけど、まだその一瞬の隙を突かれてしまうという弱さはあるのかなと」(Sの極み 7月12日付)
内容は良かったにせよ、やはりこれはあまりにもダメージが大きい。
こうなると、古くから健太の応援横断幕に使われている文句ではないが、過去3年間、強いメッセージとカリスマでチームを引っ張り続けてきた「勝負師」の勝負運が下降気味になっていると思わざるを得ない。
やはり勝負師たるもの、自ら運と空気を引き寄せてナンボである。勝負運を引き戻し、その陰りを払拭するためにも、いよいよここからが勝負師の本当の正念場ではないか。周囲の声に対して対症療法的に振り回されるよりも、「この手」が有効だと信じているのならば、やはり「今の形」を最後まで粘り強く押し通すしかない。勝負事に特効薬などないのだから(いや、本当はあるけれども)、それもひとつの勝負の形である。軸が揺らぐことなく「自分たちのサッカー」を貫き通してきたからこそ、健太と若きプレーヤーは支持されてきたのだとオレは信じている。
名古屋戦のときにも同じようなことを書いたけれども、この日の神戸のプレーヤーたちが口にしているチームへの信頼や自信に満ち溢れた力強いコメントというのは、ほんの少し前に清水のプレーヤーが口にしていたコメントと同じはずだ。それは取り戻せるはずだし、ちょっとだけ取り戻して欲しいだけなのだ。
人間て、バカみたいな自信だけで十分幸せに生きていけるから。
パウロは京都戦の緩慢な動きからは信じられないほどアグレッシヴにプレーしたし、岩下や戸田、そして淳吾の負傷交代で入った兵働の闘志をむき出しにしたプレーもまったく遜色はなく、やはりチームの全体的なポテンシャルが落ちているとは思えない。笛吹けど踊らずならば全体の見直しも止む無しだろうが、決してチームの状態が悪く、内容も悪いとは思えない。1年半に渡ってチームを「支配」してきたフェルなき後の、この1ヶ月で「自分たちのサッカー」は再び見えてきたはずだ(何でこんなに中途半端な状態でおじゃんにする必要があるのか)。
あとは運でしかない。ならば運を引き寄せるための可能性と精度を高めるしかない。
今週木曜日の川崎戦を終えるといよいよリーグも折り返しを迎える。信じられないほど大混戦のJであるからして、上の見通しはまだまだ意外といいが、下の見通しももう絶望的になっちゃうぐらいにいい。今季、これまで何回かあった「契機」だが、さすがに今回の勝負所は逃して欲しくないものである。
木曜日は等々力、日曜日は日本平。ここからが面白くなるぞ。
まだツキがあった土曜日の午前中に購入したtotoを確認してみたら……自分の予想したtotoよりもBIGの方がハズレが少なかった…。予想の精度、低いなあ。
午前中のバスで静岡へ向かったのでお昼に到着。七間町あたりをぶらぶらした後、早めにスタジアムへ向かう。
売店で新発売のフラッグ2種と150勝記念Tシャツを購入。んでもって、滅多に引いたことのないサイン会抽選クジ(グッズ1000円分購入ごとに1回引ける)を4枚引いたら、そのうち3枚当たり。
どうよ、この引きの強さ。精度の高さ。
いや、1枚でも…いやいや、むしろオレのキャラクター的には当たらなくていいんですけど…とも思ったが一応受け取り、いつものシートの近くにたまたまいた親子連れに声をかけ、無理やり2枚進呈(やっぱし1枚はもらうことにした)。この日のサイン会は児玉君。サポサンでもツーショット撮ったし、何かの縁だと150勝Tのど真ん中にでっかく書いてもらう。
うむ、今日はツイてる。
詳しくは書かないが、午前中からそんな気がしていたのだ。
物事はロジカルに組み立てていけばすべてが思い通りに収まって行くというわけはなく、運が占める割合は決して低くない。人生と勝負とはそういうものである。
しかし、そんなツキもゲームが始まるまでのことだった。内容は評価できるとは言え、ゲーム終了後は激しく凹んだ。
ロジカルなスポーツである野球などと比較すると、理不尽なスポーツであるサッカーの場合、運に左右される可能性が高い。サッカーというスポーツを数字ですべて表現できるとは思わないが、それでもこの日のゲームは数字が示す通り、内容としては清水のゲームだったと言える。
それでも負ける。
押しまくっていたのに得点が奪えない終了間際の嫌な時間帯に、この日のゲームで何回も中途半端なプレイを繰り返していた苦悩するアオが与えた久々のCK。J's GOALで前島芳雄さんも書いているように、神戸サポを除く、スタンドの観客もとても嫌な予感がしていたはずだ。
そしてそういうときの嫌な予感は的中する。
松田監督「今日特に清水が……セットプレーが何か穴があるなということも感じませんでしたし、ただしセットプレーから点を取られてるという事実はあるので、我々のセットプレーっていうのはやっぱり精度を高めて、確率を高めて行こうという話はしてました」(Sの極み 7月12日付)
フォーメーションと共に、サッカーの気まぐれな運をかろうじてコントロール(得点)できる可能性の高い戦術・戦略がセットプレーで、オフェンスにしてもディフェンスにしても、その可能性と精度を高めていくのがコーチの役割である。チームとしての戦術・戦略度の高い札幌、神戸にしてやられたのはむしろ当然だったと言えるかもしれない。
といっても、それまでゲームの流れの中で神戸に与えた決定機は数えるほどで、逆に清水の決定機はタイムアップへ向かってますます増え続けていた。可能性と確率は増えていたのだ。しかし残念ながらゴールへ迫る確率は増えても、それがゴールへの精度に結びつくとは限らない。シュートを撃たなきゃ何にも始まらないが、いくらミドルを撃っても、ゲーム前の練習でゴールに入らないシュートが本番で入る可能性はとても低いと言わざるを得ない。
健太「ただ勝負事なんで、勝負に負けてしまっては何も意味がないと。最後のセットプレーのところというのは、まあ前節もセットプレーから2失点してですね、選手たちもまあ気をつけてはいたという風に思うんですけど、まだその一瞬の隙を突かれてしまうという弱さはあるのかなと」(Sの極み 7月12日付)
内容は良かったにせよ、やはりこれはあまりにもダメージが大きい。
こうなると、古くから健太の応援横断幕に使われている文句ではないが、過去3年間、強いメッセージとカリスマでチームを引っ張り続けてきた「勝負師」の勝負運が下降気味になっていると思わざるを得ない。
やはり勝負師たるもの、自ら運と空気を引き寄せてナンボである。勝負運を引き戻し、その陰りを払拭するためにも、いよいよここからが勝負師の本当の正念場ではないか。周囲の声に対して対症療法的に振り回されるよりも、「この手」が有効だと信じているのならば、やはり「今の形」を最後まで粘り強く押し通すしかない。勝負事に特効薬などないのだから(いや、本当はあるけれども)、それもひとつの勝負の形である。軸が揺らぐことなく「自分たちのサッカー」を貫き通してきたからこそ、健太と若きプレーヤーは支持されてきたのだとオレは信じている。
名古屋戦のときにも同じようなことを書いたけれども、この日の神戸のプレーヤーたちが口にしているチームへの信頼や自信に満ち溢れた力強いコメントというのは、ほんの少し前に清水のプレーヤーが口にしていたコメントと同じはずだ。それは取り戻せるはずだし、ちょっとだけ取り戻して欲しいだけなのだ。
人間て、バカみたいな自信だけで十分幸せに生きていけるから。
パウロは京都戦の緩慢な動きからは信じられないほどアグレッシヴにプレーしたし、岩下や戸田、そして淳吾の負傷交代で入った兵働の闘志をむき出しにしたプレーもまったく遜色はなく、やはりチームの全体的なポテンシャルが落ちているとは思えない。笛吹けど踊らずならば全体の見直しも止む無しだろうが、決してチームの状態が悪く、内容も悪いとは思えない。1年半に渡ってチームを「支配」してきたフェルなき後の、この1ヶ月で「自分たちのサッカー」は再び見えてきたはずだ(何でこんなに中途半端な状態でおじゃんにする必要があるのか)。
あとは運でしかない。ならば運を引き寄せるための可能性と精度を高めるしかない。
今週木曜日の川崎戦を終えるといよいよリーグも折り返しを迎える。信じられないほど大混戦のJであるからして、上の見通しはまだまだ意外といいが、下の見通しももう絶望的になっちゃうぐらいにいい。今季、これまで何回かあった「契機」だが、さすがに今回の勝負所は逃して欲しくないものである。
木曜日は等々力、日曜日は日本平。ここからが面白くなるぞ。
まだツキがあった土曜日の午前中に購入したtotoを確認してみたら……自分の予想したtotoよりもBIGの方がハズレが少なかった…。予想の精度、低いなあ。