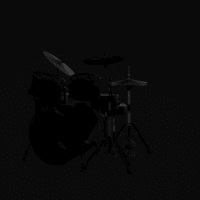レディオヘッドが再始動にむけて動いているといいます。
オアシス再結成に触発されてということなのか……それはわかりませんが、ひさびさに新譜を発表するのではないかという噂がささやかれています。
ちょうど、最近このブログでは90年代UKロックの話をしていたところでもあるので、今回のテーマはレディオヘッドです。
レディオヘッドは、ポスト―ブリットポップのバンドともみなされる、という話を以前書きました。
その心は、ブリットポップ最盛期にはそれほどヒットせず、ブリットポップが終息したころになって頭角をあらわしはじめた、ということだったんですが……その基準でいうと、レディオヘッドは微妙なところかもしれません。デビューしたての90年代前半も、鳴かず飛ばずというわけではなく、むしろそこそこ売れていたといっていいでしょう。わけても、初期の代表曲Creepは、90年代のロックを代表する一曲といってもいいんじゃないでしょうか。
Radiohead - Creep
これはまさに、神曲です。
それは、間違いない。
しかし、この大ヒットがその後のレディオヘッドにとって、一つの足かせとなった側面は否めないようです。
セカンドアルバムを出すまでに2年の時間がかかったのも、その表れでしょう。
そこは、あるいはストーンローゼズに擬せられるかもしれません。
望外のヒットを放った第一作(といっても、レディオヘッドの場合それ以前にEP盤を出しているとか、評価されたのはほぼCREEP一曲だけ、とかいう保留がつきますが)の後の第二作は、デビュー作以上に難しくなります。へたなものを出せば、ストーンローゼズがそうだったように、一気にバンドが終焉となりかねません。
奇しくも、セカンドアルバムのプロデュースを手掛けたジョン・レッキーは、まさにローゼズのファーストアルバムを大成功に導き、セカンドアルバムが大失敗に終わる一因となった人物です。
果たしてレディオヘッドはどうなるのか、一発屋で終わってしまうのか……というところでしたが、結果からいえば、彼らの場合は、そのハードルをクリアすることができました。
セカンドアルバム『ベンズ』は商業的にもまずまずの成功をおさめ、バンドは活動を継続していきます。
そして、そのなかで方向性を模索しながら、レディオヘッドは次第に難解系ロックのほうへ向かっていくことになりました。順を追って聞いていくと、少しずつ変化しているのがわかりますが、ファーストアルバムとたとえば6thアルバムHail to the Thief を聞き比べてみたら、とても同じバンドとは思えないぐらいに変化しているのです。
この点、レディオヘッドは変化に成功したバンドといえるでしょう。
その軌跡は、ビートルズに重なるようでもあります。
デビュー初期のころからみせていたトム・ヨークの厭世的傾向は、難解系ロックとして昇華していきました。
内省的な部分をより深化させていくことによって、レディオヘッドはブリットポップの枠組みを超越することができたのではないでしょうか。
トム・ヨークの名は、正式にはトム・e・ヨークという表記になっています。
これは、e.e.カミングスという詩人にならったのもですが、イニシャル部分が小文字になっているのは、近代文明において個人が匿名化されている、個人の存在が小さいものにされてしまっている、という問題意識によるものとされています。
この問題意識は、音楽性を大幅に変化させつつも、トム・ヨークがずっと持ち続けているものでしょう。
そして、こうした問題意識こそが、レディオヘッドを特別なバンドにしているのです。前にも書きましたが、どこか能天気なブリットポップにはそういう部分が欠けていたのだと思われます。
ここで一つ注釈をつけておくと、能天気なポップロックというのは、決して悪くないのです。それがロックンロールというものの原点であり、ロックが発展してこじらせていくと、やがてその原点に戻るリバイバル運動が起きる……ブリットポップも、その一つとみなせるかもしれません。しかしやはり、能天気なだけの音楽だとみんな次第に飽きてくるので、そういったムーブメントは数年で終わり、また難解な方向へ発展していく……それを繰り返してきたのが、ロックの歴史じゃないでしょうか。
しかし、そういった振り子運動の中でも、貫かれるものがある。それが、私のいうロックンロールのグレートスピリットなのです。
レディオヘッドは、まさにその継承者でした。彼らがつねに社会にむけた視線をもって活動してきたのは、その表れといえるでしょう。そうであるがゆえに、一過性のブームに引きずられて消えてしまいはしなかったのです。
レディオヘッドのバンド名はトーキングヘッズの曲名からとられているわけですが、そのトーキングヘッズから、ジョナサン・リッチマン、そしてヴェルヴェット・アンダーグラウンド……というふうに影響の系譜を遡っていくこともできるでしょう。そこに並ぶ名前からも、レディオヘッドが真にリアルなロックンロールの直系であることがわかるのです。
ここで、先述のセカンドアルバム『ベンズ』について。
今回、レディオヘッドについて書こうということで、ひさびさに聴いてみたんですが……これが、実にいい。
世間的には、たぶん次作『OKコンピューター』あたりからレディオヘッドは“化けた”という認識になっていると思うんですが、実験性とポップス性のバランスということでは、『ベンズ』は結構いい塩梅になっているように私には感じられます。ビートルズでいえば、『ラバーソウル』ぐらいの……
『ベンズ』というタイトルは、“潜函症”のこと。
深いところにもぐっていたダイバーが急に水面近くに浮上すると、強い水圧で抑えられていた血管が膨張して身体に異常をきたすという症状です。
Creepのヒットで急に日の当たる場所に出たトムの当惑を表現しているともとれるでしょう。あるいは、潜在的な抑圧状態におかれた近代人のあり方というふうにもとれるかもしれません。いずれにせよ、能天気なだけのポップロックとは一線を画しているのです。
このアルバムの最後に収録されている曲が、Street Spirit(Fade Out)です。
(※ただし、日本盤ではその後にボーナストラックがあります)
Radiohead - Street Spirit (Fade Out)
この曲を、ピーター・ガブリエルがカバーしたという話を以前書きました。
ピーター・ガブリエルといえば、彼もまた、グレートスピリッツを高い純度で継承するアーティストの一人です。そんなピーターが、「魂を愛に浸せ」と歌われるこの歌をカバー曲集のしめくくりにもってきたというのは、やはり特別な意味合いがあったんじゃないでしょうか。
で、最後に、アルバム『ベンズ』のハイライトともいえる曲Fake Plastic Treesの動画を。トム・ヨークは村上春樹作品の愛読者としても知られますが、まさに村上春樹チックな世界観が美しく哀切に歌われます。
Radiohead - Fake Plastic Trees