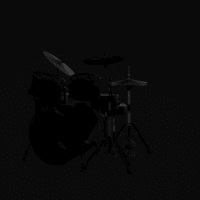今回は、音楽評論記事です。
前回このジャンルでは、モンキーズについて書きました。
そこで、「ロックンロールの変化の波に乗ろうとして失敗したアーティスト」としてビーチボーイズの名前を挙げたのですが……今回は、そのあたりのことについてもう少し詳しく書きたいと思います。
ビーチボーイズ――その名前を聴いたら、何を思い浮かべるでしょうか。
なんといっても、まず「サーフィンUSA」が有名ですね。60年代米ロックを代表する一曲であり、チャック・ベリーの「スウィート・リトル・シックスティーン」を下敷きにしているというその来歴からしても、ロック史に残る一曲といえます。
さらに他にも「サーフィン・サファリ」とか「サーファー・ガール」とかいう曲があったりして、ビーチボーイズといえばサーフィン……という認識は、ひとまず間違っていないでしょう。
初期のロックに、サーフィン/ホットロッドというカテゴリーがありました。ホットロッドというのは、改造車のことで、要はサーフィンと車。サーフィンして、ドライブして、女の子と楽しく遊ぼうというノリです。その能天気さが、私の言う「第一世代」のロックンロールということなんですが、初期のビーチボーイズは、まさにそれでした。ビーチボーイズが最初に出した3枚のアルバムジャケットは象徴的で、サーフィンと車が写っています。難しいことはなにも考えず、とにかく楽しもうぜ――という、そういうロックだったのです。
しかし、そこに第二世代の足音が忍び寄ってきます。
第二世代というのは、なにかもっと、難しいこと、深いことをいうロックです。
音楽的にも、実験性を取り入れたような……ざっくりいえば、“アート”な感じということになるでしょうか。
以前の記事で、モンキーズはそういう方向性に向かおうとしなかったと書きましたが、ビーチボーイズは、それをやろうとしました。
有名な話ですが、ビートルズの影響を受けて、果敢にそういう方向性を打ち出そうとしたのです。
これは、必ずしも無理にブームに乗ろうとしたというような話ではありません。
ビーチボーイズの中心人物であるブライアン・ウィルソンは、もともとそういう傾向を持った人でした。ただ、60年代前半ぐらいのアメリカの状況では、そういう方向性を打ち出せずにいたのです。なにしろ、サーフィン/ホットロッドの時代ですから。
しかし、そんなアメリカにも新しい音楽の波がじわじわと到来します。
それを受けて、ブライアン・ウィルソンは、もともと自分がもっていた内省的な部分をビーチボーイズの音楽に取り入れようとするのです。
直接的には、先述したように、ビートルズの『ラバー・ソウル』が契機になったといわれています。『ラバー・ソウル』に衝撃を受け、自分もこんなアルバムを作ろうということで、これまでとはまったく違うスタイルでアルバム制作を始めた、と。
それでできたのが、かの『ペットサウンズ』でした。

しかし、意外にも……というべきか、当然にもというべきか、このアルバムは発表当初あまり評価されませんでした。
売れたには売れたのですが、それまでのアルバムが大ヒットしていたのに比べると、ぱっとしない成績でした。売れたのも、それまでのファンがとりあえず買ったからでしょう。しかし、多くのファンは、音楽性の変化に困惑したものと思われます。
村上春樹さんも、そんな一人だったそうです。
作家の村上春樹さんは作品中に音楽をよく登場させる人で、それらの曲はジャズやクラシックも多いですが、ビーチボーイズ好きでも知られています。
その春樹さんも、最初に『ペットサウンズ』を聴いたときには、それまでとの違いに当惑したといいます。
『ペット・サウンズ』が逆にビートルズを触発して『サージェント・ペパーズ』を作らせたともいわれてるわけですが、その『サージェント・ペパーズ』の革新性にはすぐに圧倒されたという春樹さんも、『ペット・サウンズ』は最初はぴんとこなかったのです。もっとも、それから次第に評価が高くなっていき、やがて『サージェント・ペパーズ』を凌駕するようになったそうですが。
この春樹さんのケースにも示されるように、『ペットサウンズ』は、「一度聴いただけではその良さがわからない」とよくいわれます。
思えば、これまでにこのブログで紹介してきたロック史上の名曲の多くがそうでした。
「悪魔を憐れむ歌」も、「ボヘミアン・ラプソディ」も、「デトロイト・ロック・シティ」も、発表当初はそれほど注目されなかったんです。ビートルズのように、発表する作品がことごとごく(一部の例外はあれ)高評価されて歴史にも残るというほうが、むしろレアでしょう。
ここで、山下達郎さんの『ペットサウンズ』評を引用しましょう。
山下達郎さんは、ビーチボーイズから多大な影響を受けた人ですが、『ペットサウンズ』の日本盤の一つに解説を寄せています。その解説の中で、山下さんは次のように書いてます。(カッコ内も原文どおり)
ビーチ・ボーイズを好む者は、急激な音楽的変化を少しも望んでおらず(バンドのメンバーですら)、好まざるものにとって、ビーチ・ボーイズがどう変わろうと別に興味が湧くものでもなかった。昔も今もげに恐ろしきは、ミュージシャンにつきまという「イメージ」という名の桎梏(しっこく)であり、この時すでに「ペット・サウンズ」は異端として位置づけられる運命を背負わされていたと言える。
さすが、自身もミュージシャンである山下さんの評は的確です。
『ペット・サウンズ』という実験は、少なくとも短期的には失敗に終わり、圧倒的な人気を誇っていたビーチボーイズが凋落していくきっかけとなりました。この作品が名作と評されるようになるには、もう少し時間が必要だったのです。
さて……
その『ペットサウンズ』のなかでも特に名曲とされているものの一つが「素敵じゃないか」です。
アルバムの一曲目に収録されているナンバーで、ウェディングソングのような感じの歌になってます。
12弦ギターのようなきらきらとしたギターの響きで歌ははじまります(ここで使われているのが実際に12弦ギターかどうかについては、諸説あるようです)。
それから、さまざまな楽器が登場し、厚い音の世界を作ります。フィル・スペクターの“ウォール・オブ・サウンド”に影響を受けたともいわれる音像世界。ブライアン・ウィルソンはフィル・スペクターを強くリスペクトしていたのです。もっとも、フィル・スペクター本人の前でベースを弾いたら「お前は二度とベースを弾くな」といわれたそうですが……
ここで、歌詞について。
私は結構歌詞のほうにも注目がいくタイプなんですが、この歌でもっとも印象的に思える歌詞は、
I wish that every kiss was never-ending
というところですかね。
“すべてのキスが終わることがなければいいのに”――深い印象を残す名フレーズだと思います。
ここでもう少し評論的なことをいうと、この歌詞も、そして歌のタイトルもそうなんですが、仮定法になっているというところがポイントですね。
仮定法……高校の英文法を思い出してください。仮定法というのは、事実ではない仮定や現実にそうではないことへの願望を表す表現です。そこに注目してみてみると、この歌は仮定法だらけです。
もっと大人だったら。一緒に暮らせたら。朝一緒に目を覚ますことができたなら。
結婚できるのに。幸せになれるのに。できないことはなにもないだろうに……
こんな具合です。
仮定法というのは、たいていの場合、いったってしょうがないことなんです。だって、現実じゃないんだから。
仮定法で示される願望というのは、その裏側に、自分を満たしてくれない現実が前提されています。つまり、現実に対して「これは自分の望む世界じゃない」と思う――それが仮定法の表現なんです。
その仮定法の根本を考えると、私のいう“ロックンロール第2世代”の重要なキーワードである「現実への違和感」とつながってきます。
そういうところで、たとえばレディオヘッドなんかにもリンクしてきます。トム・ヨークは、ブライアン・ウィルソンタイプの人だという認識が結構一般的にあると思いますが、レディオヘッドの歌詞にもよく仮定法がでてきます。
たとえば、CREEPに、「俺が特別なやつだったら」という一節があります。そしてこの歌詞は、そのすぐ後に「だけど俺はクズ野郎」と続きます。
まさに、ここなんです。
仮定法のもつ、後ろ向きで、うじうじした感じ――マッチョイズムと対極にあるこの姿勢こそが、ロックンロール第2世代を形作ったものであり、それから今にいたるまでロックの一つの基調であり続けているものなんです。
そのあたりのことは、今後も折に触れて書いてみようかなと思ってます。今回は、長くなったので、このへんで。
ちなみにですが……
この「素敵じゃないか」は、以前このブログでメフィスト賞への挑戦作として紹介した『トミーはロック探偵』のなかで、短編の題材として使われてました。また、やはりこのブログで紹介した、文学フリマ出品作品『WANNABE'S』にもそれが収録されています。そういう意味で、「素敵じゃないか」は私にとっても縁の深い曲なのです。
前回このジャンルでは、モンキーズについて書きました。
そこで、「ロックンロールの変化の波に乗ろうとして失敗したアーティスト」としてビーチボーイズの名前を挙げたのですが……今回は、そのあたりのことについてもう少し詳しく書きたいと思います。
ビーチボーイズ――その名前を聴いたら、何を思い浮かべるでしょうか。
なんといっても、まず「サーフィンUSA」が有名ですね。60年代米ロックを代表する一曲であり、チャック・ベリーの「スウィート・リトル・シックスティーン」を下敷きにしているというその来歴からしても、ロック史に残る一曲といえます。
さらに他にも「サーフィン・サファリ」とか「サーファー・ガール」とかいう曲があったりして、ビーチボーイズといえばサーフィン……という認識は、ひとまず間違っていないでしょう。
初期のロックに、サーフィン/ホットロッドというカテゴリーがありました。ホットロッドというのは、改造車のことで、要はサーフィンと車。サーフィンして、ドライブして、女の子と楽しく遊ぼうというノリです。その能天気さが、私の言う「第一世代」のロックンロールということなんですが、初期のビーチボーイズは、まさにそれでした。ビーチボーイズが最初に出した3枚のアルバムジャケットは象徴的で、サーフィンと車が写っています。難しいことはなにも考えず、とにかく楽しもうぜ――という、そういうロックだったのです。
しかし、そこに第二世代の足音が忍び寄ってきます。
第二世代というのは、なにかもっと、難しいこと、深いことをいうロックです。
音楽的にも、実験性を取り入れたような……ざっくりいえば、“アート”な感じということになるでしょうか。
以前の記事で、モンキーズはそういう方向性に向かおうとしなかったと書きましたが、ビーチボーイズは、それをやろうとしました。
有名な話ですが、ビートルズの影響を受けて、果敢にそういう方向性を打ち出そうとしたのです。
これは、必ずしも無理にブームに乗ろうとしたというような話ではありません。
ビーチボーイズの中心人物であるブライアン・ウィルソンは、もともとそういう傾向を持った人でした。ただ、60年代前半ぐらいのアメリカの状況では、そういう方向性を打ち出せずにいたのです。なにしろ、サーフィン/ホットロッドの時代ですから。
しかし、そんなアメリカにも新しい音楽の波がじわじわと到来します。
それを受けて、ブライアン・ウィルソンは、もともと自分がもっていた内省的な部分をビーチボーイズの音楽に取り入れようとするのです。
直接的には、先述したように、ビートルズの『ラバー・ソウル』が契機になったといわれています。『ラバー・ソウル』に衝撃を受け、自分もこんなアルバムを作ろうということで、これまでとはまったく違うスタイルでアルバム制作を始めた、と。
それでできたのが、かの『ペットサウンズ』でした。

しかし、意外にも……というべきか、当然にもというべきか、このアルバムは発表当初あまり評価されませんでした。
売れたには売れたのですが、それまでのアルバムが大ヒットしていたのに比べると、ぱっとしない成績でした。売れたのも、それまでのファンがとりあえず買ったからでしょう。しかし、多くのファンは、音楽性の変化に困惑したものと思われます。
村上春樹さんも、そんな一人だったそうです。
作家の村上春樹さんは作品中に音楽をよく登場させる人で、それらの曲はジャズやクラシックも多いですが、ビーチボーイズ好きでも知られています。
その春樹さんも、最初に『ペットサウンズ』を聴いたときには、それまでとの違いに当惑したといいます。
『ペット・サウンズ』が逆にビートルズを触発して『サージェント・ペパーズ』を作らせたともいわれてるわけですが、その『サージェント・ペパーズ』の革新性にはすぐに圧倒されたという春樹さんも、『ペット・サウンズ』は最初はぴんとこなかったのです。もっとも、それから次第に評価が高くなっていき、やがて『サージェント・ペパーズ』を凌駕するようになったそうですが。
この春樹さんのケースにも示されるように、『ペットサウンズ』は、「一度聴いただけではその良さがわからない」とよくいわれます。
思えば、これまでにこのブログで紹介してきたロック史上の名曲の多くがそうでした。
「悪魔を憐れむ歌」も、「ボヘミアン・ラプソディ」も、「デトロイト・ロック・シティ」も、発表当初はそれほど注目されなかったんです。ビートルズのように、発表する作品がことごとごく(一部の例外はあれ)高評価されて歴史にも残るというほうが、むしろレアでしょう。
ここで、山下達郎さんの『ペットサウンズ』評を引用しましょう。
山下達郎さんは、ビーチボーイズから多大な影響を受けた人ですが、『ペットサウンズ』の日本盤の一つに解説を寄せています。その解説の中で、山下さんは次のように書いてます。(カッコ内も原文どおり)
ビーチ・ボーイズを好む者は、急激な音楽的変化を少しも望んでおらず(バンドのメンバーですら)、好まざるものにとって、ビーチ・ボーイズがどう変わろうと別に興味が湧くものでもなかった。昔も今もげに恐ろしきは、ミュージシャンにつきまという「イメージ」という名の桎梏(しっこく)であり、この時すでに「ペット・サウンズ」は異端として位置づけられる運命を背負わされていたと言える。
さすが、自身もミュージシャンである山下さんの評は的確です。
『ペット・サウンズ』という実験は、少なくとも短期的には失敗に終わり、圧倒的な人気を誇っていたビーチボーイズが凋落していくきっかけとなりました。この作品が名作と評されるようになるには、もう少し時間が必要だったのです。
さて……
その『ペットサウンズ』のなかでも特に名曲とされているものの一つが「素敵じゃないか」です。
アルバムの一曲目に収録されているナンバーで、ウェディングソングのような感じの歌になってます。
12弦ギターのようなきらきらとしたギターの響きで歌ははじまります(ここで使われているのが実際に12弦ギターかどうかについては、諸説あるようです)。
それから、さまざまな楽器が登場し、厚い音の世界を作ります。フィル・スペクターの“ウォール・オブ・サウンド”に影響を受けたともいわれる音像世界。ブライアン・ウィルソンはフィル・スペクターを強くリスペクトしていたのです。もっとも、フィル・スペクター本人の前でベースを弾いたら「お前は二度とベースを弾くな」といわれたそうですが……
ここで、歌詞について。
私は結構歌詞のほうにも注目がいくタイプなんですが、この歌でもっとも印象的に思える歌詞は、
I wish that every kiss was never-ending
というところですかね。
“すべてのキスが終わることがなければいいのに”――深い印象を残す名フレーズだと思います。
ここでもう少し評論的なことをいうと、この歌詞も、そして歌のタイトルもそうなんですが、仮定法になっているというところがポイントですね。
仮定法……高校の英文法を思い出してください。仮定法というのは、事実ではない仮定や現実にそうではないことへの願望を表す表現です。そこに注目してみてみると、この歌は仮定法だらけです。
もっと大人だったら。一緒に暮らせたら。朝一緒に目を覚ますことができたなら。
結婚できるのに。幸せになれるのに。できないことはなにもないだろうに……
こんな具合です。
仮定法というのは、たいていの場合、いったってしょうがないことなんです。だって、現実じゃないんだから。
仮定法で示される願望というのは、その裏側に、自分を満たしてくれない現実が前提されています。つまり、現実に対して「これは自分の望む世界じゃない」と思う――それが仮定法の表現なんです。
その仮定法の根本を考えると、私のいう“ロックンロール第2世代”の重要なキーワードである「現実への違和感」とつながってきます。
そういうところで、たとえばレディオヘッドなんかにもリンクしてきます。トム・ヨークは、ブライアン・ウィルソンタイプの人だという認識が結構一般的にあると思いますが、レディオヘッドの歌詞にもよく仮定法がでてきます。
たとえば、CREEPに、「俺が特別なやつだったら」という一節があります。そしてこの歌詞は、そのすぐ後に「だけど俺はクズ野郎」と続きます。
まさに、ここなんです。
仮定法のもつ、後ろ向きで、うじうじした感じ――マッチョイズムと対極にあるこの姿勢こそが、ロックンロール第2世代を形作ったものであり、それから今にいたるまでロックの一つの基調であり続けているものなんです。
そのあたりのことは、今後も折に触れて書いてみようかなと思ってます。今回は、長くなったので、このへんで。
ちなみにですが……
この「素敵じゃないか」は、以前このブログでメフィスト賞への挑戦作として紹介した『トミーはロック探偵』のなかで、短編の題材として使われてました。また、やはりこのブログで紹介した、文学フリマ出品作品『WANNABE'S』にもそれが収録されています。そういう意味で、「素敵じゃないか」は私にとっても縁の深い曲なのです。