中学生や高校生の頃は、レコード大賞を見て、それから、必ず『紅白歌合戦』の裏番組を見ていました。『紅白歌合戦』

という、存在はそれほど大きく、ひねくれ者の僕は、リビングのテレビではなく、小さいテレビで、日テレとかを見ていました。ある種の権威に対する反抗心があったのかもしれません。それと裏番組でよくかかっていた映画が『大脱走』。何故『大脱走』は、大晦日の「紅白」の裏に編成されていたのでしょう。多分、一つは長尺ものだという事、映画が好きな人にとって、何回見ても面白い作品だった事・・・この二つでしょうか?で、『紅白歌合戦』が終わると、民放全局で、「ゆく年くる年」をやっていました。その時、どのチャンネルでも、本当に同じ番組をやっているか、確かめませんでしたか?僕はカチャカチャ、チャンネルを切り替えて、確認していました。「ゆく年くる年」の視聴率は、NHKのチャンネル番号に近い局の視聴率が一番高かった様です。今のように、リモコンが発達しておらず、NHKからチャンネルをすぐひねれる局を見る人が多かったのでしょう。だから、東京では、日本テレビ、大阪では毎日放送の視聴率がNHK以外ではトップでした。「ゆく年くる年」は、毎年、制作するキー局が違い、CX場合は、大概「ザ・ドリフターズ」が出ていて、カウントダウンをしていました。TBSは「民放のNHK」と言われるだけあって、「瀬戸内海の離島の灯台に年賀状を届ける郵便配達員」を中継でいれたりしていました。

当然、中継が入る時間は決まっている訳ですから、離島の郵便配達員は、キューを待って画面にフレームイン。そして、カメラが彼の歩きと共にパーンして、灯台が映るという、なんとも言えない「視聴者への感動の押し付け」を堂々としていたのが印象的です。

日本テレビの時は、武道館で「一万人の第九」をやっていたのを憶えています。指揮は、加山雄三。「知ってるつもり!?」「24時間テレビ」と、NTVと加山雄三は関係が深いのはどうしてでしょう。

大晦日の午前中とかに、漫画映画「わんわん忠臣蔵」をやっていたのは、関西エリアだけなのかなあ。こないだビデオで出ているのを発見。即、買いました。手塚治虫も製作に参加していて、「動物版の忠臣蔵」でよくできた面白い映画でした。

 面白い話だとは思いませんか?
面白い話だとは思いませんか?
 面白い話だとは思いませんか?
面白い話だとは思いませんか?










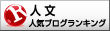
 便意を催すのですが、あれは紙の匂いのせいなのでしょうか
便意を催すのですが、あれは紙の匂いのせいなのでしょうか ?新宿の紀伊国屋書店のトイレって、「大」の方は大概、誰か入っていて、そのおかげでどんどん上の階に行ってしまうのです。皆さん、原因を御存知でしたら、教えて下さい。
?新宿の紀伊国屋書店のトイレって、「大」の方は大概、誰か入っていて、そのおかげでどんどん上の階に行ってしまうのです。皆さん、原因を御存知でしたら、教えて下さい。
 だと思っていたこともあって。普通に考えると、「麺類」でしょうか。「流しタンタン麺」などは、食べにくいだろうなあ。
だと思っていたこともあって。普通に考えると、「麺類」でしょうか。「流しタンタン麺」などは、食べにくいだろうなあ。 「流しマーボ豆腐」はいかが?
「流しマーボ豆腐」はいかが? 「流しタンタン麺・ギョーザ定食」なんかを流すと面白いと思いません?こんなアホな事を考えているのは、きっと日本中で僕だけでしょう。
「流しタンタン麺・ギョーザ定食」なんかを流すと面白いと思いません?こんなアホな事を考えているのは、きっと日本中で僕だけでしょう。
 使って走っています。僕の会社の近くにも鉄道の発祥の地があるのですが、古くは「明治時代」、私鉄でも、大正か昭和の初期に開通した鉄道の、土地の上をどれだけの人数の人が通り過ぎていったかを考えると、その細長い土地は人口密度のとてもとても高い土地になるのではないかと、考えてしまいました。昆虫はフェロモンを出します。人間が゜そんなフェロモンを100年以上出しながら、通り過ぎていった土地というのは凄いのではないでしょうか?フェロモンにたとえば「白い色」がついていたら、線路のひかれているところは真っ白になっているのだろうなあ、と変な事を考えました。
使って走っています。僕の会社の近くにも鉄道の発祥の地があるのですが、古くは「明治時代」、私鉄でも、大正か昭和の初期に開通した鉄道の、土地の上をどれだけの人数の人が通り過ぎていったかを考えると、その細長い土地は人口密度のとてもとても高い土地になるのではないかと、考えてしまいました。昆虫はフェロモンを出します。人間が゜そんなフェロモンを100年以上出しながら、通り過ぎていった土地というのは凄いのではないでしょうか?フェロモンにたとえば「白い色」がついていたら、線路のひかれているところは真っ白になっているのだろうなあ、と変な事を考えました。 これも同じような例ですが、土砂降りの日に車
これも同じような例ですが、土砂降りの日に車 に乗っているのが好きです。周りを雨の音に囲まれた閉塞感と、暖かい車内にいる満足感(傘をもっていない人が走っていたりすると・・・悪魔のような考えですが、車の中の濡れない空間にいる自分と比較したりしませんか?)を感じます。皆さんはどうでしょうか。
に乗っているのが好きです。周りを雨の音に囲まれた閉塞感と、暖かい車内にいる満足感(傘をもっていない人が走っていたりすると・・・悪魔のような考えですが、車の中の濡れない空間にいる自分と比較したりしませんか?)を感じます。皆さんはどうでしょうか。 ちょっと、自己中心的過ぎ・・・ですよね。
ちょっと、自己中心的過ぎ・・・ですよね。
 という、存在はそれほど大きく、ひねくれ者の僕は、リビングのテレビではなく、小さいテレビで、日テレとかを見ていました。ある種の権威に対する反抗心があったのかもしれません。それと裏番組でよくかかっていた映画が『大脱走』。何故『大脱走』は、大晦日の「紅白」の裏に編成されていたのでしょう。多分、一つは長尺ものだという事、映画が好きな人にとって、何回見ても面白い作品だった事・・・この二つでしょうか?で、『紅白歌合戦』が終わると、民放全局で、「ゆく年くる年」をやっていました。その時、どのチャンネルでも、本当に同じ番組をやっているか、確かめませんでしたか?僕はカチャカチャ、チャンネルを切り替えて、確認していました。「ゆく年くる年」の視聴率は、NHKのチャンネル番号に近い局の視聴率が一番高かった様です。今のように、リモコンが発達しておらず、NHKからチャンネルをすぐひねれる局を見る人が多かったのでしょう。だから、東京では、日本テレビ、大阪では毎日放送の視聴率がNHK以外ではトップでした。「ゆく年くる年」は、毎年、制作するキー局が違い、CX場合は、大概「ザ・ドリフターズ」が出ていて、カウントダウンをしていました。TBSは「民放のNHK」と言われるだけあって、「瀬戸内海の離島の灯台に年賀状を届ける郵便配達員」を中継でいれたりしていました。
という、存在はそれほど大きく、ひねくれ者の僕は、リビングのテレビではなく、小さいテレビで、日テレとかを見ていました。ある種の権威に対する反抗心があったのかもしれません。それと裏番組でよくかかっていた映画が『大脱走』。何故『大脱走』は、大晦日の「紅白」の裏に編成されていたのでしょう。多分、一つは長尺ものだという事、映画が好きな人にとって、何回見ても面白い作品だった事・・・この二つでしょうか?で、『紅白歌合戦』が終わると、民放全局で、「ゆく年くる年」をやっていました。その時、どのチャンネルでも、本当に同じ番組をやっているか、確かめませんでしたか?僕はカチャカチャ、チャンネルを切り替えて、確認していました。「ゆく年くる年」の視聴率は、NHKのチャンネル番号に近い局の視聴率が一番高かった様です。今のように、リモコンが発達しておらず、NHKからチャンネルをすぐひねれる局を見る人が多かったのでしょう。だから、東京では、日本テレビ、大阪では毎日放送の視聴率がNHK以外ではトップでした。「ゆく年くる年」は、毎年、制作するキー局が違い、CX場合は、大概「ザ・ドリフターズ」が出ていて、カウントダウンをしていました。TBSは「民放のNHK」と言われるだけあって、「瀬戸内海の離島の灯台に年賀状を届ける郵便配達員」を中継でいれたりしていました。 当然、中継が入る時間は決まっている訳ですから、離島の郵便配達員は、キューを待って画面にフレームイン。そして、カメラが彼の歩きと共にパーンして、灯台が映るという、なんとも言えない「視聴者への感動の押し付け」を堂々としていたのが印象的です。
当然、中継が入る時間は決まっている訳ですから、離島の郵便配達員は、キューを待って画面にフレームイン。そして、カメラが彼の歩きと共にパーンして、灯台が映るという、なんとも言えない「視聴者への感動の押し付け」を堂々としていたのが印象的です。 日本テレビの時は、武道館で「一万人の第九」をやっていたのを憶えています。指揮は、加山雄三。「知ってるつもり!?」「24時間テレビ」と、NTVと加山雄三は関係が深いのはどうしてでしょう。
日本テレビの時は、武道館で「一万人の第九」をやっていたのを憶えています。指揮は、加山雄三。「知ってるつもり!?」「24時間テレビ」と、NTVと加山雄三は関係が深いのはどうしてでしょう。 大晦日の午前中とかに、漫画映画「わんわん忠臣蔵」をやっていたのは、関西エリアだけなのかなあ。こないだビデオで出ているのを発見。即、買いました。手塚治虫も製作に参加していて、「動物版の忠臣蔵」でよくできた面白い映画でした。
大晦日の午前中とかに、漫画映画「わんわん忠臣蔵」をやっていたのは、関西エリアだけなのかなあ。こないだビデオで出ているのを発見。即、買いました。手塚治虫も製作に参加していて、「動物版の忠臣蔵」でよくできた面白い映画でした。 時には、二日酔いにならなくて、朝、まだ酔っている事もあります。一度お試しあれ。
時には、二日酔いにならなくて、朝、まだ酔っている事もあります。一度お試しあれ。
 聞いたら、やはり関西人でした。特徴は「声が大きい」「キョロキョロ周りを絶えず見回している」「何事にも強い好奇心を示す」・・・
聞いたら、やはり関西人でした。特徴は「声が大きい」「キョロキョロ周りを絶えず見回している」「何事にも強い好奇心を示す」・・・ こんなところでしょうか?世界中、どこでも、そんな感じなので、僕にはすぐ分かります。少し、気恥ずかしい位です。
こんなところでしょうか?世界中、どこでも、そんな感じなので、僕にはすぐ分かります。少し、気恥ずかしい位です。





