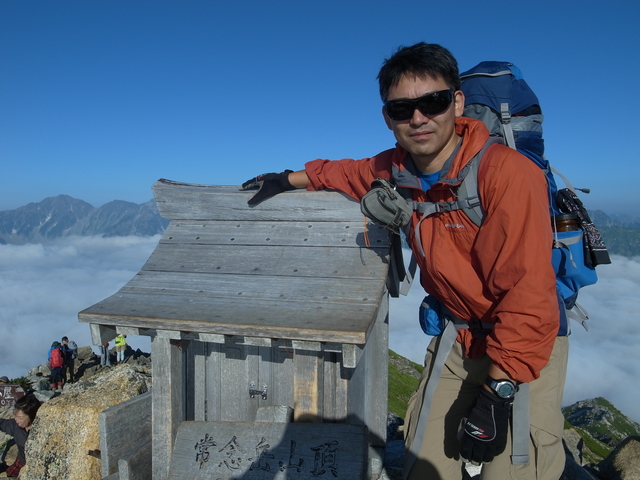22日の夕方、パッパと仕事を終わらせ、早く切り上げて、家に帰る。2,3分でシャワーを浴び、予め準備しておいた着替えに袖を通す。前回の登山の時についた泥だらけの登山靴を履き、重いザックを担いで家を出る。かかった時間はおおよそ10分くらい。ぎりぎり予定の電車に間に合いそうだ。
この時間帯の電車の中には、いかにもこれから登山します、というような格好をした人間は一人も居ない。ビジネスマンか学生か。案の定、ジロジロと見られる。羊の群れの中に紛れ込んだロバみたいなものだ。だけど全然気にしない。こういうところのハートは強い。
今回持ってきた本、「マーティン・ドレスラーの夢」を取り出し、読み始める。マーティンは葉巻屋の息子であるが、最初に出てくる店に関する丁寧な描写を読むのがすこし面倒くさい。そのため何回か読むのを挫折した。ただ、読むのがこれしかないと思うと、ワンセンテンス、ワンセンテンスをじっくり時間をかけて読んでしまう。繊密な描写をイメージし、味わいながら。読書とは本来そういうもので、焦って読むものではない。おかげでこの小説の面白さがだんだんわかってきた。なんせピュリツァー賞をとった作品なのだから、つまらないことはないだろう。
18時すぎに奥多摩駅に着く。もう暗くなっている。

バスの出発時間は、18時50分。まだ時間がある。ぶらぶらしていると、すぐ近くの八百屋が店じまいをしている。
「まだ大丈夫ですか」
「もう閉めるけど、いいよ」
「そのりんご一つください」
「はい、180円」
という感じでりんごを買って食べる。ゴミ箱がないので、全部きれいに食べてしまう。さすがの私も枝の部分は食べれないので、そこだけポイッと捨てさせてもらう。その辺に木の枝が沢山落ちているから、勘弁して。
バスの時間が迫ってきた。中学生くらいの男の子3人がやってきて、バス停のベンチに座る。多分、部活帰りだと思う。東京の本当のはずれの子供たち。なんとなく羨ましい。こんな素晴らしいところで生活できるなんて。まぁ、田舎すぎて本人たちは嫌かもしれないが、いつかそれが良かったと思える日がくるだろう。都会の生活なんていつでもできる。
バスには留浦行きとある。ちなみに、「とずら」と読む。留浦ってどこだと思い、調べてみる。どうやら鴨沢の1つ手前のバス停らしい。留浦は東京で鴨沢は山梨である。ただ、歩いて10分程度らしい。だったら、問題はない。
バス出発。もう完全に暗くなっている。一応、バス内は電気が付いているが暗いので、頭にヘッドライトをつけて本を読む。いまいち集中できない。
少年たちも奥多摩湖付近のバス停で全員降りてしまって、私一人の貸切状態になってしまった。なんとなく寂しい。ただ、運転手にしてみたら、誰も乗っていないより、一人でもいたほうがいいに違いない。
本を閉じて、窓の外の風景を見る。真っ暗で昼間とはぜんぜん違う奥多摩である。木の葉や雑草が生き物の手のようになって道路の方に伸びてきている。もしかしたら、場違いな所に来てしまったのではないかと思えてきた。だけど、もう遅い。来てしまったのだから。
留浦バス停に着く。バスの運転手に何か言われるかなぁと思ったが、「ありがとうございました」以外の言葉も交わさず、また特に何か詮索もされずに降りた。まさか大きなザックを担いで自殺する人間も居ないだろう。
留浦バス停から10分歩いて、鴨沢に着く。19時30分。

今日は、ここから30分かけて小袖の登山口に向かい、登山口から、多分、一時間くらい登った所にある水場の平地でテントを張って寝るつもりである。おおよそ21時くらいに着いて、21時半頃寝れればいいかなぁと思っている。
ヘッドライトを付けて民家の脇の道を登っていく。まだ早いから民家には明かりが付いている。それぞれの人のそれぞれの生活がある。
しかし、こんな時間に山にのぼるのは、当然、私だけである。集落の人に見つかったら止められそうだから、そそくさと登っていく。
集落の一番最後の民家の脇を通りかかったとき、その家の犬が騒ぎ出した。かなりの勢いで吠えている。犬は見知らぬ人間の気配を察している。お前は何ものだ、何をやっているんだと。
犬に吠えられながら山道に入っていく。犬に吠えられたことで、私は山に受け入れられていない人間なのではないかという感じがしてきた。そう思ったら、急に怖くなってきた。
この辺の道はよく知っているし、道は広くて足を踏み外すこともない。特に危険はないはずだ。
ただ、夜は少し違う。闇に包まれた夜の山は、それ自体が生き物のように怪しくうごめいている。何が起こっても不思議でない。
めずらしくビビっている。
呼吸を整え、無駄なことを想像しないように、一歩一歩足を運ぶ。それでも恐怖をコントロールするのは困難だ。それほど、闇に対する人間の反応は強烈である。体がそのような反応を強制している。多分、恐怖を生じさせることで、注意を喚起し戦闘態勢に入らせるのだろう。ただ、恐怖が強すぎると、逃げ出してしまうことになってしまう。私は逃げ出すほどの度胸がないから、仕方なく登る。
闇は視覚を奪う。周りが見えないとそれを補うように嗅覚が敏感になってくる。草の匂い、土の匂い、それだけではなくて獣の臭もする。どこかに鹿か何かがいるのが分る。自分自身の能力にびっくりする。すごいなぁと思う。周りの状況を把握する能力が高まっている。恐怖故に。
小袖の登山口に過ぎて、幽霊屋敷のような空き家を越え、どんどん進む。まだ、水場には到着しない。
そこで、ふといつの間にか恐怖が消えていることに気づく。
えっ、暗いのに慣れたのかと思ったが、ちょっと違う。なんだろうと自分に問いかけてみる。
そうだ、腹が減っているのだ。
そう言えば、昼に時間がなくて弁当半分くらいしか食べれなかったし、それ以外は駅でりんごを一個食べただけである。そのような状態で、一時間も重い荷物を担いで山を登っているから、血糖値が下がってきたのだ。無性に何か食べたくなってきた。
ザックから菓子パンを取り出し食べる。すごく幸せな気分になる。嘘のように恐怖が消えてしまった。
一つ、勉強になった。基本的に、恐怖より飢えのほうが強いんだなぁということである。もちろん、拳銃を頭に突きつけられているときのように、リアルな危機がそこにある場合には、飢えより恐怖の方が強いだろう。だけど、夜の闇程度の恐怖なら飢えの方が強い。
脳が身体に司令を出しているのではない、身体が脳に働きかけているのだ。脳は血糖値が下がっていることを知らない。身体が血糖値が下がっていると脳に知らせる。そして、脳が私に何か食べるように指示をだすのだ。
自然の環境が身体に影響を及ぼす。身体の変化が脳に働きかけ、脳が身体に行動を要求する。逆の流れではない。
人間はアホだから全てをコントロールしていると思ってしまうが、それは幻想である。自然の変化が人間の状態を決定づける。私たちは自然の大きな流れに沿っているに過ぎない。人間は自然の一部だからだ。
水場に到着する。20時40分。予定より早い。怖かったから足取りが早かったようだ。
テントを張って寝袋を出して寝る。
明日から始まる非日常の世界にわくわくしながら。