本棚をふと見たら、ずいぶん前に買ったこの本が目に留まりました。読み終えたつもりが実は未読だったようです。
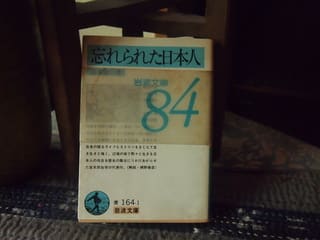
民俗学者・宮本常一の代表作で、昭和14年から戦後のたぶん30年代ころまで、日本各地の辺境に生きる老人たち自身の「語るライフヒストリーをまじえて生き生きと描」(網野喜彦・解説)いたもの。
読み終えていない本は山ほどあるのに、なぜこの本を手に取りそして読み進んだかというと、古老たちの語り口がそのまま載っているところもおおくて、興味深かったことと、本文中にあった「名倉談義」のタイトルに惹かれたことから。
「名倉談義」の取材場所は、稲武の隣村・設楽町の名倉。昔は名倉村として独立していました。昔は生活が苦しくて一の半分が逃亡したという記録も残っているほど、貧しい村だったのが、村人の努力で自作農の多い豊かな農村に作り上げたのだと、筆者は語っています。その名倉で、4人の古老をあつめて世間話をしてもらったものの記録がこれ。
とにかく貧乏で、米だけのご飯を食べることはまずなく、糧飯が当たり前。「ご飯もおかずもみな大根でありました。それでも切干をアラメ、タケノコと一しょに煮〆にしたものを山でたべるのはうまかった」。稗はよく作り、人の食糧にもなり、馬の飼料にもなりました。でも、「馬には稗一升に豆二合をたいて混ぜたものを一日に一回はたべさせた。人間よりは上等のものをたべさせ」たそうです。
びっくりしたのが夜ばいの遠征。「わしら若い時はええ娘がおるときいたらどこまでもいきましたのう、美濃の恵那郡まで行きました…。さァ、三、四里はありましょう。夕飯をすまして山坂こえて行きますのじゃ」「今の言葉で言うと、スリルというものがないと、昔でもおもしろうなかった」恵那郡といっても、車で稲武からでも40分はかかる恵那市市街地ではなくて、岩村あたりのことかな、とおもうのですが、どちらにしろ、ほとんど満腹になることなく、しかも昼間くたくたになるまで働いているのに、すごいバイタリティー。
対馬の話になりますが、村の寄り合いについての記述もおもしろかった。何か話し合うべきことがあると、寄り合いを開くのですが、それが数日かかるのだそう。弁当もちだったり、そのまま集まった家に泊まりこんだりしてつづく。筆者の見聞によると、けっして一つの議題にとどまることはなく、いろんな人がある話題について思い出したことや関連したことをいう、いい続けて話題がなくなると、別の話にうつる。そしてまた戻り、何度かいったりきたりしながら、ようやく結論を出す。全員が話し足りたところで、終了。話し合うとか議論するとか、そういう、下手をするとケンカになるような方法はとらないのが、寄り合いなのだそう。
この寄り合いのやり方は全国あちこちで見られたそうで、昔の農村の人々が、「決して事を荒立てない」ことをもっとも大事なこととしているがために、こういう、時間のかかる効率の悪い方法があたりまえになったのだろう、というようなことを、筆者は書いています。
田舎に住むようになって、都会との文化の違いを痛感することがままあります。
以前、稲武で、新聞種になるような事件が起きたことがあるのですが、その当事者双方の言い分を問題にする以前に、ある決定に異議申し立てをして、稲武に波風を立てたことそれ自体がよくないといって、申し立てをした人物を非難する声を聞きました。
わたしには筋違いとしか思えない非難なのですが、それも文化の違いなのでしょう。こうした、田舎の文化のルーツのようなものをこの本は垣間見させてくれました。
今度は、これまた買っただけで忘れていた彼の本「家郷の訓」を読もうとおもいます。
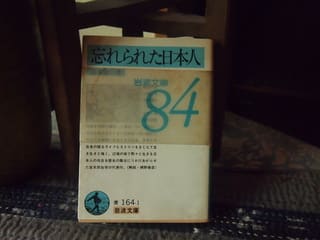
民俗学者・宮本常一の代表作で、昭和14年から戦後のたぶん30年代ころまで、日本各地の辺境に生きる老人たち自身の「語るライフヒストリーをまじえて生き生きと描」(網野喜彦・解説)いたもの。
読み終えていない本は山ほどあるのに、なぜこの本を手に取りそして読み進んだかというと、古老たちの語り口がそのまま載っているところもおおくて、興味深かったことと、本文中にあった「名倉談義」のタイトルに惹かれたことから。
「名倉談義」の取材場所は、稲武の隣村・設楽町の名倉。昔は名倉村として独立していました。昔は生活が苦しくて一の半分が逃亡したという記録も残っているほど、貧しい村だったのが、村人の努力で自作農の多い豊かな農村に作り上げたのだと、筆者は語っています。その名倉で、4人の古老をあつめて世間話をしてもらったものの記録がこれ。
とにかく貧乏で、米だけのご飯を食べることはまずなく、糧飯が当たり前。「ご飯もおかずもみな大根でありました。それでも切干をアラメ、タケノコと一しょに煮〆にしたものを山でたべるのはうまかった」。稗はよく作り、人の食糧にもなり、馬の飼料にもなりました。でも、「馬には稗一升に豆二合をたいて混ぜたものを一日に一回はたべさせた。人間よりは上等のものをたべさせ」たそうです。
びっくりしたのが夜ばいの遠征。「わしら若い時はええ娘がおるときいたらどこまでもいきましたのう、美濃の恵那郡まで行きました…。さァ、三、四里はありましょう。夕飯をすまして山坂こえて行きますのじゃ」「今の言葉で言うと、スリルというものがないと、昔でもおもしろうなかった」恵那郡といっても、車で稲武からでも40分はかかる恵那市市街地ではなくて、岩村あたりのことかな、とおもうのですが、どちらにしろ、ほとんど満腹になることなく、しかも昼間くたくたになるまで働いているのに、すごいバイタリティー。
対馬の話になりますが、村の寄り合いについての記述もおもしろかった。何か話し合うべきことがあると、寄り合いを開くのですが、それが数日かかるのだそう。弁当もちだったり、そのまま集まった家に泊まりこんだりしてつづく。筆者の見聞によると、けっして一つの議題にとどまることはなく、いろんな人がある話題について思い出したことや関連したことをいう、いい続けて話題がなくなると、別の話にうつる。そしてまた戻り、何度かいったりきたりしながら、ようやく結論を出す。全員が話し足りたところで、終了。話し合うとか議論するとか、そういう、下手をするとケンカになるような方法はとらないのが、寄り合いなのだそう。
この寄り合いのやり方は全国あちこちで見られたそうで、昔の農村の人々が、「決して事を荒立てない」ことをもっとも大事なこととしているがために、こういう、時間のかかる効率の悪い方法があたりまえになったのだろう、というようなことを、筆者は書いています。
田舎に住むようになって、都会との文化の違いを痛感することがままあります。
以前、稲武で、新聞種になるような事件が起きたことがあるのですが、その当事者双方の言い分を問題にする以前に、ある決定に異議申し立てをして、稲武に波風を立てたことそれ自体がよくないといって、申し立てをした人物を非難する声を聞きました。
わたしには筋違いとしか思えない非難なのですが、それも文化の違いなのでしょう。こうした、田舎の文化のルーツのようなものをこの本は垣間見させてくれました。
今度は、これまた買っただけで忘れていた彼の本「家郷の訓」を読もうとおもいます。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます