この本のおもしろいところのひとつは、ハダカデバネズミの生態とは別に、研究者の試行錯誤というか、研究のプロセスがかいま見ることができるところにある。
とくに生き物を飼うことが前提の研究だから、失敗も多い。学生たちとともに右往左往するところがエッセイ調につづられ、なかなか楽しい読み物になっている。
そうそう、この著者はハダカデバネズミの生態を研究しているわけでない。音声コミュニケーションとか脳とか、情報認知学とかそんな感じの研究をしている。
ただ、研究そのものは道半ばの感が強い。
おもしろいのは、脳を研究しようとする学者の想定がけっこう外れているところだ。研究者が、地下で生活するデバの脳が、視覚、聴覚とかが、その生態に合わせた脳の発達があるだろうと考えるのは当然のことだが、意外とふつうのラットと形態上は変わらない脳をしてるのだ。
なんだろう、、、こうやって想定がずれるところに研究の醍醐味があるんだろうなと思う。ここから真の研究がはじまるというわけだ(失礼なコメント)。
ついつい、「なんかいろいろおもしろいことが分かるといいですね…」とまったく余計なことを思う。裏表紙には「……その動物で一旗あげようともくろんだ研究者たちの……」のコピーがあるから、まぁ、そう思ってもいいよね…いう感じだが。
その意味では(どの意味?)、岩波はずいぶんと中途半端な本を出したとも言える。デバの一発キャラ勝負というところか。
とにかく、、、上野動物園にデバを見にいこうっと。
とくに生き物を飼うことが前提の研究だから、失敗も多い。学生たちとともに右往左往するところがエッセイ調につづられ、なかなか楽しい読み物になっている。
そうそう、この著者はハダカデバネズミの生態を研究しているわけでない。音声コミュニケーションとか脳とか、情報認知学とかそんな感じの研究をしている。
ただ、研究そのものは道半ばの感が強い。
おもしろいのは、脳を研究しようとする学者の想定がけっこう外れているところだ。研究者が、地下で生活するデバの脳が、視覚、聴覚とかが、その生態に合わせた脳の発達があるだろうと考えるのは当然のことだが、意外とふつうのラットと形態上は変わらない脳をしてるのだ。
なんだろう、、、こうやって想定がずれるところに研究の醍醐味があるんだろうなと思う。ここから真の研究がはじまるというわけだ(失礼なコメント)。
ついつい、「なんかいろいろおもしろいことが分かるといいですね…」とまったく余計なことを思う。裏表紙には「……その動物で一旗あげようともくろんだ研究者たちの……」のコピーがあるから、まぁ、そう思ってもいいよね…いう感じだが。
その意味では(どの意味?)、岩波はずいぶんと中途半端な本を出したとも言える。デバの一発キャラ勝負というところか。
とにかく、、、上野動物園にデバを見にいこうっと。










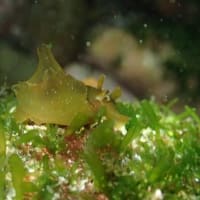





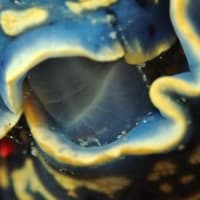



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます