急用ができ七戸十和田まで出かけました。新幹線のこの駅は昨年出来たばかりで、広ーい駅前に何もなく、
唯一道の駅があり、地元の野菜などが売られていました。

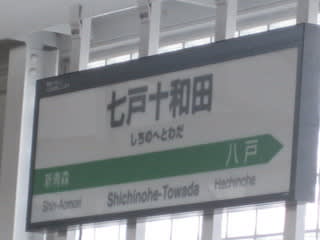

今回の所用は「十和田市駅」十和田観光電鉄終点(三沢~十和田市)の駅、90年の歴史のある鉄道です。
昔から十和田湖へ行く時の1ルートで、この駅から車で1時間半ほどで十和田湖です。
電車は大正11年9月の開通、軌道幅762ミリの狭軌で、機関車2両・客車3両・貨車6両、一日5往復でした。
昭和26年電化を機に、軌道幅を1067ミリに拡張し、現在は十和田市~三沢間を一日17往復(土日祝は12往復)しています。
しかし時代に合わず90年の歴史を閉じ今年末で鉄道を廃止し、バスに切り替えるそうです。
この駅はビジネスホテルもあり、割と大きな町です。
十和田市稲荷神社

稲荷神社 三本木周辺は1855から盛岡藩士新渡戸傳によって開発が行われ1859に上水工事が完成、新たに三本木集落を開村に辺り
元集落の産土神だった千歳森稲荷大明神を現在地に勧請したのが始まり。
稲荷神社も五穀豊穣の守護神として崇敬され明治6年には郷社に列しらっれています。現在の社殿は昭和29年に再建されたものです。
朱色が美しい神社


十和田市駅から約10分ほど歩くと、官庁街。
十和田市現代美術館は「新しい体験を提供する開かれた施設」として、十和田の中核となる施設です。アート作品の展示のほか、
文化芸術活動の支援や交流を促進する拠点となります。
十和田でしかみることができない22の恒久設置作品が展示されている常設展示スペースのほか、ギャラリースペース、カフェ、市民活動サポートスペースなど、
多様な機能を持ちます。
十和田市現代美術館

市民公園



旧陸軍軍馬補充部 三本木支部跡地

青森県が日本有数の馬の産地になった。
まず十和田市では藩政時代の文久3年(1863年)に馬市が開催されて以来馬セリで賑わい、明治17年には軍馬育成所(後の軍馬補充部)も開設され、
馬産地としてしられるようになった。
軍馬補充部三本木支部
明治18年の陸軍軍馬局出張所開設以来昭和20年の解体まで、約60年の長きにわたり町の発展に寄与しました。およそ1700頭強の馬を有し、
軍馬の育成に意を注ぎましたが、軍馬が高値で買い上げられたことから産馬熱を高め、馬のまち三本木として活性していきました。
その馬の町三本木を歩いた。馬のモニュメントが市中心に作られている。


所用を済ませ帰宅したが、今は3時間半の新幹線。30年前は青森へ行くには夜行電車だったことを思い出す。
唯一道の駅があり、地元の野菜などが売られていました。

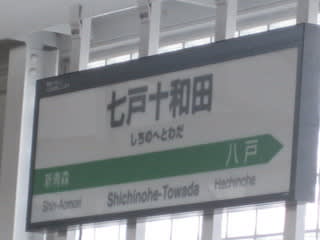

今回の所用は「十和田市駅」十和田観光電鉄終点(三沢~十和田市)の駅、90年の歴史のある鉄道です。
昔から十和田湖へ行く時の1ルートで、この駅から車で1時間半ほどで十和田湖です。
電車は大正11年9月の開通、軌道幅762ミリの狭軌で、機関車2両・客車3両・貨車6両、一日5往復でした。
昭和26年電化を機に、軌道幅を1067ミリに拡張し、現在は十和田市~三沢間を一日17往復(土日祝は12往復)しています。
しかし時代に合わず90年の歴史を閉じ今年末で鉄道を廃止し、バスに切り替えるそうです。
この駅はビジネスホテルもあり、割と大きな町です。
十和田市稲荷神社

稲荷神社 三本木周辺は1855から盛岡藩士新渡戸傳によって開発が行われ1859に上水工事が完成、新たに三本木集落を開村に辺り
元集落の産土神だった千歳森稲荷大明神を現在地に勧請したのが始まり。
稲荷神社も五穀豊穣の守護神として崇敬され明治6年には郷社に列しらっれています。現在の社殿は昭和29年に再建されたものです。
朱色が美しい神社


十和田市駅から約10分ほど歩くと、官庁街。
十和田市現代美術館は「新しい体験を提供する開かれた施設」として、十和田の中核となる施設です。アート作品の展示のほか、
文化芸術活動の支援や交流を促進する拠点となります。
十和田でしかみることができない22の恒久設置作品が展示されている常設展示スペースのほか、ギャラリースペース、カフェ、市民活動サポートスペースなど、
多様な機能を持ちます。
十和田市現代美術館

市民公園



旧陸軍軍馬補充部 三本木支部跡地

青森県が日本有数の馬の産地になった。
まず十和田市では藩政時代の文久3年(1863年)に馬市が開催されて以来馬セリで賑わい、明治17年には軍馬育成所(後の軍馬補充部)も開設され、
馬産地としてしられるようになった。
軍馬補充部三本木支部
明治18年の陸軍軍馬局出張所開設以来昭和20年の解体まで、約60年の長きにわたり町の発展に寄与しました。およそ1700頭強の馬を有し、
軍馬の育成に意を注ぎましたが、軍馬が高値で買い上げられたことから産馬熱を高め、馬のまち三本木として活性していきました。
その馬の町三本木を歩いた。馬のモニュメントが市中心に作られている。


所用を済ませ帰宅したが、今は3時間半の新幹線。30年前は青森へ行くには夜行電車だったことを思い出す。





















































