テレビの対談で、いろいろな分野に顔を出して活動している人に「1日24時間の中で、時間がよく作れますね?」という質問がなされた。その人はニコリと笑われて「ゲームをする時間とSNSに関わる時間を省けば時間って結構ありますよ。世間一般の人がやっていることすべてをやっているわけでないので人からはマルチと言われますが興味のある所にだけ集中しています。」と答えていた。
ゲームには全く興味がないが、孫などの様子を見ているとはまってしまうと随分時間を使うだろうなということは推察できる。しかし、SNSという言葉は私の中になかった。質問者も「そうですね」と苦笑交じりに同意していたところ見ると今世間に広まっている何かだろうというぐらいで調べもせずにいた。
「新潮45・11月号」を読んでいると‟フェイスブックは気持ち悪い”というタイトルでコラムニスト・テクニカルライターの小田嶋隆さんの文があった。そこに知識ゼロの私にもわかるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の概要が書かれていた。フェイスブック、ツイッター、ミクシィなど「社会的な情報」すなわち「交際」を重視した登録制投稿サービスというジャンルの総称とあった。世間より一歩遅く歩んでいる私でもフェイスブックやツイッターという言葉はよく耳にする。実際どういう世界なのかは分からない。NHKの深夜のニュースなどで画面の下にニュースの内容に反応してつぶやきのようなものがテロップで出ている。とても目障りなのだがあれがツイッターかなというぐらいの認識である。
小田嶋さんは自身の経験も含めて「空気を読むことを」を好む日本人が構築」するSNS内「世間」について考察している。おかげで独特の専門用語やシステムの有り様がおぼろげにわかった。この世界で展開される人間関係は苦手だなと直感的に思った。
私の家に電話が来たのが高校生の時であるから、相手の姿が見えない電話も苦手意識がある。音声も消えた文字だけのコミュ二ケーションの世界には住めない気がする。
自分を確かめるために他人の存在は必要である。他人との関わりの中で自分というものを見つめ成長していくことができるので他者とのコミュニケーションの必要性はよくわかる。基本は表情、仕草、目の動き、間の取り方、イントネーションなどがわかる面と向かっての対話であろう。
話の中で小田嶋さんは対人関係に関して面白い表現をされている。
「・・・もっとも、親しい人間同士の会話が無内容な毛づくろいに陥りがちななりゆきは、リアルな社会でも同様だ。わが身を振り返ってみれば思い当たるはずだ。誰であれ、最も親しい人々との間で日常的に行ったり来たりさせている言葉に、さしたる意味はないはずだ。
逆に言えば、中身のある言葉を交換し合っていないとたちまち退屈してしまうような対人関係は、要するに「疎遠」なのである。・・・・」
SNSの本題よりもこの部分が一番アンテナにひかかった。
とりとめのない話を長時間できる、気が置けない関係は貴重である。と改めて思った。
ゲームには全く興味がないが、孫などの様子を見ているとはまってしまうと随分時間を使うだろうなということは推察できる。しかし、SNSという言葉は私の中になかった。質問者も「そうですね」と苦笑交じりに同意していたところ見ると今世間に広まっている何かだろうというぐらいで調べもせずにいた。
「新潮45・11月号」を読んでいると‟フェイスブックは気持ち悪い”というタイトルでコラムニスト・テクニカルライターの小田嶋隆さんの文があった。そこに知識ゼロの私にもわかるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の概要が書かれていた。フェイスブック、ツイッター、ミクシィなど「社会的な情報」すなわち「交際」を重視した登録制投稿サービスというジャンルの総称とあった。世間より一歩遅く歩んでいる私でもフェイスブックやツイッターという言葉はよく耳にする。実際どういう世界なのかは分からない。NHKの深夜のニュースなどで画面の下にニュースの内容に反応してつぶやきのようなものがテロップで出ている。とても目障りなのだがあれがツイッターかなというぐらいの認識である。
小田嶋さんは自身の経験も含めて「空気を読むことを」を好む日本人が構築」するSNS内「世間」について考察している。おかげで独特の専門用語やシステムの有り様がおぼろげにわかった。この世界で展開される人間関係は苦手だなと直感的に思った。
私の家に電話が来たのが高校生の時であるから、相手の姿が見えない電話も苦手意識がある。音声も消えた文字だけのコミュ二ケーションの世界には住めない気がする。
自分を確かめるために他人の存在は必要である。他人との関わりの中で自分というものを見つめ成長していくことができるので他者とのコミュニケーションの必要性はよくわかる。基本は表情、仕草、目の動き、間の取り方、イントネーションなどがわかる面と向かっての対話であろう。
話の中で小田嶋さんは対人関係に関して面白い表現をされている。
「・・・もっとも、親しい人間同士の会話が無内容な毛づくろいに陥りがちななりゆきは、リアルな社会でも同様だ。わが身を振り返ってみれば思い当たるはずだ。誰であれ、最も親しい人々との間で日常的に行ったり来たりさせている言葉に、さしたる意味はないはずだ。
逆に言えば、中身のある言葉を交換し合っていないとたちまち退屈してしまうような対人関係は、要するに「疎遠」なのである。・・・・」
SNSの本題よりもこの部分が一番アンテナにひかかった。
とりとめのない話を長時間できる、気が置けない関係は貴重である。と改めて思った。










 NHKニュース7
NHKニュース7 やっとここにスポットを当ててくれたかという感があった。今、教育界で取り上げられるのは学力問題(主には学力テストの公開のことや英語学習のこと)といじめ、体罰のことであるが、「非正規教員の増加もしくは不足」こそがもっと深刻ではないかと思ってきた。私が退職した2,3年前より「このまま無策のまま進むとやばいのではないか?」と感じ始めたが、退職後、かつての同僚であった校長数名から「講師に来てほしい」という以来の電話を度々受けた。事情を聞くと現場の深刻さは加速度的に進んでいると思った。時々お会いして話を聞く現場の教員からも同様のことがよく出る。
やっとここにスポットを当ててくれたかという感があった。今、教育界で取り上げられるのは学力問題(主には学力テストの公開のことや英語学習のこと)といじめ、体罰のことであるが、「非正規教員の増加もしくは不足」こそがもっと深刻ではないかと思ってきた。私が退職した2,3年前より「このまま無策のまま進むとやばいのではないか?」と感じ始めたが、退職後、かつての同僚であった校長数名から「講師に来てほしい」という以来の電話を度々受けた。事情を聞くと現場の深刻さは加速度的に進んでいると思った。時々お会いして話を聞く現場の教員からも同様のことがよく出る。 継続性の保障がないということが本人にとって一番つらいのではないかと思う。生徒、地域、学校のことを把握して見通しを持って実践に取り組むには3年~5年ぐらいの期間の保障が必要だと思う。仕事を引き継いでいくという面でもそのことは大切である。私の例で言えば、退職を決めたのは55歳の時。受け持った1年生を3年間持ち上がったら定年を待たずに退職という絵を描いた。そのことから逆算して今やるべきことを考え、学校長にも希望を伝えた。1つはクラブ顧問を2年間かけて確保してほしいということ、もう1つは生徒会の仕事を引き継いでいく人員の配置をすることである。生徒会では主に文化委員会に関わっていたが、相棒がずっと講師の方であった。仕事はきちっとやってくれる方ばかりで助かったのであるが、次の年にはいないので覚えたことを活かすことができない。私の希望は数年は勤務する見通しのある正規の方とコンビを組んで一緒に仕事をやりながら引き継ぎたいということであった。校務分掌という仕事は個人経営の店のようなところがある。一番困るのは転勤して前任者がいない分掌を任された時である。今までの流れとかが分からないまま立案、提案をしていくのはとても大変である。出来ることなら避けたいものである。
継続性の保障がないということが本人にとって一番つらいのではないかと思う。生徒、地域、学校のことを把握して見通しを持って実践に取り組むには3年~5年ぐらいの期間の保障が必要だと思う。仕事を引き継いでいくという面でもそのことは大切である。私の例で言えば、退職を決めたのは55歳の時。受け持った1年生を3年間持ち上がったら定年を待たずに退職という絵を描いた。そのことから逆算して今やるべきことを考え、学校長にも希望を伝えた。1つはクラブ顧問を2年間かけて確保してほしいということ、もう1つは生徒会の仕事を引き継いでいく人員の配置をすることである。生徒会では主に文化委員会に関わっていたが、相棒がずっと講師の方であった。仕事はきちっとやってくれる方ばかりで助かったのであるが、次の年にはいないので覚えたことを活かすことができない。私の希望は数年は勤務する見通しのある正規の方とコンビを組んで一緒に仕事をやりながら引き継ぎたいということであった。校務分掌という仕事は個人経営の店のようなところがある。一番困るのは転勤して前任者がいない分掌を任された時である。今までの流れとかが分からないまま立案、提案をしていくのはとても大変である。出来ることなら避けたいものである。
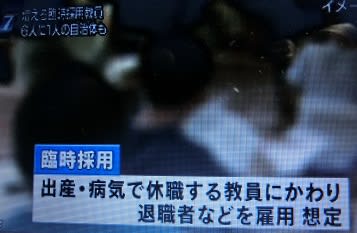
 このため、現在では本来、保障されるべき正規教員の病欠、産休のための慢性的な講師不足があると同時に身分の不安定な講師の数が増大しているという二重苦が現場にはある。番組で取り上げられた20代の女性の方のような例は珍しくなくなってきている。
このため、現在では本来、保障されるべき正規教員の病欠、産休のための慢性的な講師不足があると同時に身分の不安定な講師の数が増大しているという二重苦が現場にはある。番組で取り上げられた20代の女性の方のような例は珍しくなくなってきている。 彼女の場合、6か月でクラスが崩壊し、担任を外されたというが、酷な話である。沖縄県に次いで全国で2番目に臨時採用者が多い埼玉県の教育委員会に取材していたが、抜本的な解決を模索するよりも研修の機会を増やすという方向でお茶を濁しているように思えた。研修の中身と実効性は検証しないといけないのではないか。
彼女の場合、6か月でクラスが崩壊し、担任を外されたというが、酷な話である。沖縄県に次いで全国で2番目に臨時採用者が多い埼玉県の教育委員会に取材していたが、抜本的な解決を模索するよりも研修の機会を増やすという方向でお茶を濁しているように思えた。研修の中身と実効性は検証しないといけないのではないか。
 このこと自体、研修というものの必要性に疑問を抱かせるものである。
このこと自体、研修というものの必要性に疑問を抱かせるものである。  この方の言葉はズシリと重い。この問題にしっかり取り組まないと今、打ち出されている教育施策は砂上の楼閣に過ぎず、教育の未来は開かない。
この方の言葉はズシリと重い。この問題にしっかり取り組まないと今、打ち出されている教育施策は砂上の楼閣に過ぎず、教育の未来は開かない。





