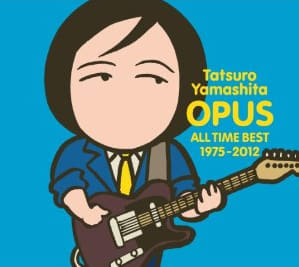2012/11/20 OnAir - 3rd. Week - ジョージ・ハリスン特集 ~伊藤銀次氏を迎えて~
01.The Beatles:Here Comes the Sun
02.George Harrison:My Sweet Lord
03.George Harrison:What Is Life
04.George Harrison:Give Me Love (Give Me Peace On Earth)
05.George Harrison:This Is Love
06.George Harrison:When We Was Fab
07.Traveling Wilburys:Handle With Care
08.Eric Clapton & Paul McCartney:Something (Live)
---------------------------------------------------
■内容の一部を抜粋
・ジョージ・ハリスン特集 ~伊藤銀次氏を迎えて~
「さて、静かなビートルズと言われたジョージ・ハリスン。亡くなって11年が経っています。今月11月29日はそのジョージ・ハリスンの命日にあたります。Motoharu Radio Show、今夜はジョージ・ハリスンを特集します。そしてスタジオには自他共に認めるジョージ・ハリスン通で知られる伊藤銀次氏をゲストに迎えています。ミュージシャンから見たジョージ・ハリスンの魅力について彼とたっぷり語り合ってみたいと思います」と元春。
・Here Comes the Sun
ビートルズの「Here Comes the Sun」。作詞作曲はジョージ・ハリスン。
'80年代にハートランドのギタリスト、バンマスとして活躍した伊藤銀次さん。当時、楽屋で音楽の話になると、ビートルズの話題が出て、銀次さんはジョージ・ハリスンのいろんな楽しい話を元春にしてくれたそうだ。今週はふたりでジョージ・ハリスンの音楽について対話する。
アルバム『Abbey Road』収録曲「Here Comes the Sun」。この当時はニュー・ロックと呼ばれる新しいムーブメント、インストゥルメンタルを中心に聴かせるバンドが出てきた頃に発表されて、『Abbey Road』はそれに対するビートルズの返答のようなアルバムだったそうだ。ただのポップ音楽ではない趣きがあり、それまでのビートルズとちょっと違った感じがしたそうだ。
・ジョージ・ハリスンの印象
ビートルズ第三の男、ジョンとポールがいて目立たない感じだったが、アルバム毎にジョージの色が出てくるようになって、それがとってもうれしかったと銀次さん。
・All Things Must Pass
ジョンやポールにない新境地を切り開こうとして、シタールやインド音楽などをビートルズに持ち込んだ。アルバム『Abbey Road』で成長を窺わせて、ビートルズ解散後に発表した3枚組のソロ・アルバム『All Things Must Pass』でファンを驚かせた。ビートルズ時代にエリック・クラプトンをゲスト・プレーヤーとして呼んだり、レオン・ラッセル、デラニー&ボニーといった人たちといち早く交友した。そうした交友関係が集約されたのが『All Things Must Pass』で、プロデューサーはフィル・スペクター、バッキング・バンドにデレク&ドミノス、当然クラプトンもギタリストとしてセッションに参加している。デレク&ドミノスは同時期に自分たちのレコードも作っていたし、クラプトンもクリームとは違うルーツ・ミュージックに近いような、アメリカ音楽に近い音楽を心がけていた頃にジョージとうまがあって、ちょうど交差点みたいな感じが『All Things Must Pass』とデレク&ドミノスにはあったと銀次さん。
・My Sweet Lord
・What Is Life
アルバム『All Things Must Pass』から「My Sweet Lord」と「What Is Life」。
「ポールやジョンに比べていち早く宗教や哲学に関心を寄せましたね。この当時で言えばインドのハレ・クリシュナに興味を持ち、その関心が音楽に反映されてきましたね。このことに戸惑ったファンもいるし、新しい世界を感じたファンもいたみたいですね」と元春。
「そうだね。インド音楽とかに彼が興味を持ったということは、東洋と西洋を近づけたという意味ではね、後にはひじょうに大きな影響をあたえたと思うね。ある種のサイケデリック・ミュージックのスタート地点にもなったし」と銀次さん。
「'60年代の最初、ポップ・ミュージックというのは一介のキャンディ・ポップに過ぎなかったんだけれども、'60年代中盤ぐらいからミュージシャンが、ロックがロックだけに留まらず、そこにアートを持ち込み、宗教を持ち込み、哲学を持ち込んで、なんしかロック音楽の可能性を広げていこうという運動がありましたよね。その中でジョージ・ハリスンがインド音楽を応用して新しいポップ・ソングを作った、それを広めたというのは功績としては大きいと僕は思いますね」と元春。
「クワイエット・ビートルと言われた人で、一見自己主張がないように思えるんだけれども、とても寛容な人だと思うんだよね。なんでも認めることができて、それを自分なりに受け止めていくというか、プロデューサーかな? ひょっとしたらポール・マッカートニーよりも、ジョン・レノンよりもプロデューサー的な資質がある人なのかもしれない」と銀次さん。
・ジョージ・ハリスンのソングライティング
ジョン・レノンは自分の歌いまわしで曲を作っていた。ポールもそうかもしれない。ジョージはインストゥルメンタリストとして自分の頭の中でメロディを考えて、コード展開、サウンドを含めて全体でひとつの楽曲作りをしていた。バンドマンとして曲を作っていた印象があると銀次さん。
ジョンやポールはものすごく強力なフックを持っていた。張り出しが強いというか、一回聴いただけでどこが魅力的かわかる曲作りをしていた。ジョージは一回聴いただけではわからないが、何度も聴きたくなる、中毒性のあるメロディラインがあったと元春。
「ジョージ・ハリスンの歌っていうのは鳥が鳴いていたりとかね、自然に聞こえてくる美しい音のような気がするのね。彼が宗教的な部分を持ってるせいで、僕が勝手にそう思い込んでるのかもしれない。気持よくて何度も流していたくなる。かといってインパクトが強いかというと、そんなにすごく強い自己主張のようなものを僕たちに押し付けてくるわけでもない」と銀次さん。
「確かにね。そのへんの空気に馴染んでる自然さがありますよね」と元春。
「それはいつの時代も変わらないものだなと思ってる」と銀次さん。
・Give Me Love (Give Me Peace On Earth)
銀次さんがジョージの作品でいちばん好きな曲。
「とっても不思議な曲で、自然の中で響いてくるというのがいちばん合ってる曲。これは作ろうと思っても作れない曲。自然にジョージの中に聞こえてきたんじゃないかと思うような、ものすごくナチュラルな趣きの曲なんだけれども、何度も聴きたくなる」と銀次さん。
曲をかけ終えて。
「いま銀次が語ってくれたように、つかみどころがないけれども何回も聴いてみたくなるような、そういう特徴がありますね」と元春。
「これを作ろうという、そういうかたちで作ってないんじゃないかという気がする。ギターを持って自然に出てきたものをという気がするんですよね」と銀次さん。
・ディランの影響
「曲のテーマにしているものというと、圧倒的にジョージ・ハリスンの場合は愛について多いです。ただ男女の愛を超え、もっと広い意味での愛について言及している、それがリリックにおける彼の特徴だと思う」と元春。
同時代のディランの影響はどうだったのだろうという元春の問いに、
ボブ・ディランはアーティスト、ジョージ・ハリスンはギタリスト、プロデューサーとして、ふたりはとてもいい影響をあたえあっていた印象があると銀次さん。
・ポールとの関係
ビートルズのエンジニアだったジェフ・エメリックの回顧録によると、「Taxman」のギターを弾いたのはポールなんだとか。レコーディングでジョージがギターを弾いていたがうまくいかず、ちょっとスタジオを離れたときにポールがトライしたらうまく弾けたとか。映画『Let It Be』ではポールがジョージにギターの弾き方、チョーキングをゆっくりしてくれと指定する場面があり、ジョージはすごく嫌な顔をしていたそうだ。「僕はもう昔のビートルじゃないんだぞ。それを君は未だに言うのか」という思いが表情に出ていたとか。ジョンとジョージは3歳年が離れていて高校生と中学生ぐらいの違いがあった。でもポールとジョージは1歳違い、でも学年で言えば同じ。とても微妙な関係だった。
・This Is Love
・When We Was Fab
2曲ともプロデュース、アレンジはジェフ・リン。ジェフ・リンはビートルズ・フォロワー。銀次さんは同じビートルズ・フォロワーとして共感するところがあるそうだ。
「ジェフ・リンのソロ・ワークを聴いて思うのは十分にアメリカ音楽を意識している。アメリカの古い曲やロックンロールやブルース、それを一度自分の手元に引き寄せて、そこにブリティッシュ風味、イギリス人らしさを付け加えて再アウトプットするというかね、そこの技術というのが並外れて高いプロデューサーですよね。ですのでディラン、トム・ペティといったひじょうにアメリカ的なシンガー・ソングライターを扱っても、出てくるサウンドはブリティッシュなポップ・サウンドと言えますよね」と元春。
「そうだね。ある種、彼の中にビートルズ的なブリット・アメリカンな出口というのが、理想的なものだというのが確立されてるのかもしれないね」と銀次さん。
・Handle With Care
ディラン、トム・ペティ、ロイ・オービソン、ジョージ・ハリスンといったソングライターたちが集まったユニット、トラヴェリング・ウィルベリーズの「Handle With Care」。
「あのロイ・オービソンのパートは、もう見事にロイ・オービソンの特徴を捉えてるよね。いいところを」と銀次さん。
ジョージ・ハリスンは残念なことに今から11年前病気で亡くなった。ビートルズで現存するのはポール・マッカートニー、リンゴ・スターの二人。亡くなる前に二人はジョージを見舞って深い話をしたそうだ。一説には不仲説もあったが、それが払拭されたニュースだった。
「'60年代世界を変えたと言われたビートルズのメンバー同志の、そうした思い出というものは、僕たち凡人の思い出と比べたら、計り知れないくらい深いものがあったんじゃないかと僕は思います」と元春。
「喜びも苦しみも、それからちょっと憎悪もあったり、なんかそういうものも計り知れないものだったんだろうね、きっとね」と銀次さん。
・エリック・クラプトン
その昔は奥さんをめぐって恋の鞘当てみたいなものがあった。でも音楽的には親友関係が最後まで続いた。ジョージが亡くなったときに追悼会「コンサート・フォー・ジョージ」の発起人になったのはクラプトンだった。
「エリック・クラプトンの見事な幹事ぶりというのかな、コンサートを仕切って、息子のダーニーをみんなに紹介して、いちばん僕が感銘したのはインド・セクションが出たでしょ。ジョージ・ハリスンのいちばん興味のあったインド音楽をやっている人たちを出すときに、エリック・クラプトンは紹介して、ステージ上に椅子を置いて、そこに座ってお客さんとインド音楽を聴いてるわけ。もしあそこでエリック・クラプトンが引っ込んじゃったら、たぶん関心のない人は聴かないかもしれないけれど、そこにいて一生懸命聴いてるというね、それがすごくなんかこう、ジョージ・ハリスンの気持ちをちゃんとわかって、みんなに見てもらいたい、すべてを見てもらいたいというのがね、微に入り細に入りというか、見事なプロデュースで。それが逆にクラプトンのジョージに対する気持ちを感じたのね。クラプトンもポップスを知ったのはジョージからなんだよね。クリームのバッジという曲の後奏のところにビートルズが出てくるんです。ブルースからはじまったクラプトンがはじめてポップスをジョージから知り、そしてジョージはクラプトンからブルースやスライドギターや、そういったものを教わったということでは、お互いに人生の岐路でものすごい大切なものをお互いに共有しあったというところで、それがコンサート・フォー・ジョージに現れていたのがとてもうれしかった」と銀次さん。
「自分にとっていちばん感動的なシーンはポール・マッカートニーとエリック・クラプトンの共演でしたね。聞くところによるとジョージ・ハリスンはウクレレを弾くのがとても上手だったという話。これはポール・マッカートニーの話なんですけれども、よくビートルズ時代にポール・マッカートニーの家にジョージ・ハリスンがウクレレを持ってきて、一緒にウクレレで曲を作ったことがあるというインタビューがありました。その話が僕、頭の中にあったんですね。そしてコンサート・フォー・ジョージのDVDを観たらポール・マッカートニーがウクレレを持ってジョージ・ハリスンのSomethingを歌い出すという。僕はこのシーンを観たときに本当の意味での友情というかな、深いものを感じましたね」と元春。
・Something (Live)
エリック・クラプトンが発起人となって開催された『コンサート・フォー・ジョージ』のライヴ盤から。ポール・マッカートニーのウクレレからはじまってクラプトンに繋がってゆくという感動的な演出。
・番組ウェブサイト
「番組ではウェブサイトを用意しています。是非ご覧になって曲のリクエスト、番組へのメッセージを送ってください。待ってます」と元春。
http://www.moto.co.jp/MRS/
・伊藤銀次フェイスブック
「なにか銀次のフェイスブックでいつもMotoharu Radio Showの二元中継をやってくれてるという話を聞いたんですけれども(笑)」と元春。
「ははは。そうなんだよね。なんかはじめたらみんなが喜んでくれてて。なんか佐野くんから言われると不思議な感じがする。ははは。でもとってもみんな一生懸命聴いてくれてるので」と銀次さん。
「銀次のフェイスブック・コミュニティのみなさんによろしく伝えてください」と元春。
・次回放送
12月4日火曜日、午後11時。