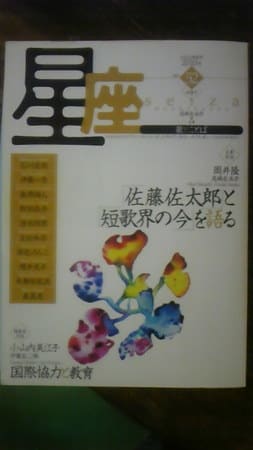「ブナの木通信」『星座』73号
『星座』の作品批評を書くにあたって、僕は斎藤茂吉、佐藤佐太郎の歌論を踏まえて書いている。また「詩人の聲」で培った抒情詩としての普遍性も参考にしている。
(秋の光を浴びながら坂道をのぼる歌)
坂道をのぼる。ただそれだけなのだが、背後に孤独な作者像が浮かぶ。ドラマ性が感じられる。多くの詩人が、人間や社会の掘りさげを目指し、吉本隆明は斎藤茂吉の作品を「背後に自己劇化を感じさせる、すぐれた象徴歌」と評している。短歌を抒情詩と考えるからには、これらの詩人の言葉にも学びたい。
(瀬戸内の浦島伝説の歌)
二つの固有名詞が効いている。作品の背後に、地域の風土や歴史が感じられ、それをかみしめている作者がいる。
(乱舞する蝶の歌)
かなりインパクトのある言葉遣いによって幻想的な抒情を表現している。初句の字余りには、そういう作品を作るうえでの必然性がある。
(友人との心のすれ違いの歌)
対人関係の屈折した心情を切りとった。友の返事の内容、それを受けた、作者の発言の詳細が、省略されているのに注目したい。
(冬瓜が転がる畑に人を待つ歌)
(光の動く天井を眺める歌)
(消える風花の歌)
人を待っている。天井を見ている。風花を掌に受ける。ただそれだけなのだが、場所の設定や、対象の表現の的確さが、作者の心情を投影している。
(消息の絶えた人の死を、訃報欄の隅に見つける歌)
誌上では批評出来なかったので、ここで批評する。おそらく新聞の批評記事なのだろう。消息の絶えた人。この人が作者とどういう関係かはわからない。ここが省略されているのだ。作者とかつて親しかった人なら、その人との人間関係に軋轢のようなものがあったことを、連想させる。そうでなければ、作者の発見、驚きが表現されている。いずれにしても人間の命に限りがあるのを、ひしひしと感じさせる作品だ。
【フェイスブックで短歌作品が読みたいとのご意見を頂きました。出版社と相談しましたが、著作権の問題もあり、掲載しないこととしました。是非にと言う方は、鎌倉春秋社まで『星座』73号を御注文ください。書店で注文できます。】