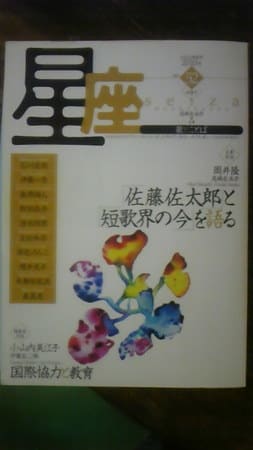「ブナの木通信」(「星座68号より)
短歌は一人称の文学、とよばれます。自己を凝視するということです。今号はそういう作品に先ず、注目しました。
(モーツアルトを聞きながらの感慨の歌)
哀しみの仔細は分かりません。しかし、そこを暗示にとどめたことによって、情感の深い作品となりました。
(午後の日を受けての感慨の歌)
この作品も何を断罪したいかが、表現されていません。しかし忸怩たる思いは的確に伝わって来ます。
(反論を胸におさめての感慨の歌)
この作品も、反論の内容は書かれていません。短歌はまた暗示の文学とも呼ばれましから、詳しく説明する必要はないのです。それに加えて、この一首は、下の句の比喩に独自性があります。
(満たされぬものをもって夕餉を作る歌)
(忘却に心の救いを感じる歌)
この二首も、何に満たされないか、何を忘却するのかが書かれていません。暗示されているだけ、読者の連想力を引き出す余地を残しています。ただ事実を書いただけでは詩にならない、と言われるのはこのことでしょう。
一方、叙景歌にも特徴のあるものがありました。
(枯れおちた桜葉の中に残る蜻蛉の翅の歌)
「枯れおちしさくらば」「蜻蛉の翅」。何だか、生のあわれをあらわしているようではありませんか。
(日没の光が埃の当たる歌)
(午後の庭に揚羽の幻影の揺れる歌)
目で見たものを詠んでいるのですが、幻想的な景が浮かび上がりました。「写生を突き詰めてゆけば、象徴や幻想にはおのずから至る」と斎藤茂吉が言ったのはこのことでしょう。
また時代性を感じさせる作品もありました。
(ほどほどに貧しく不便だったころの思いやりの歌)
高度成長期にはいる前のことでしょう。過去のことを詠うことによって、現代社会への問いかけともなっています。