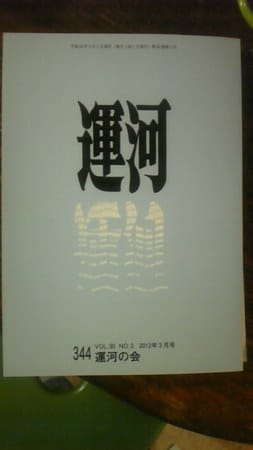<加賀・能登の伝統と風土への讃歌>
作者の住まいは石川県。かつて加賀、能登と呼ばれた地方だ。そして作者の家は、伝統ある道家であるという。歌集は三部構成になっているが、全作品を通じて共通の抒情がある。それは地方の伝統と歴史への讃歌ということだ。
・窯神に祈りて成りし五彩なり古九谷の秘技まとふ大窯
・けやき材つやつやとして急階段のぼりて北前船主の書斎
・加賀の国治めし一向宗徒らの一すぢの川水分(みくまり)厳し
まず前半より三首挙げた。古九谷とは古九谷焼で、江戸時代に加賀を治めた前田氏がこの地に根付かせたもの。北前船は江戸時代の西廻り航路を運航した船で、蝦夷や奥羽の産物を載せ、大阪まで航行した。それ以前の戦国時代は一向一揆がこの地を統治した。
この様な歴史が詠み込まれているが、事実報告とならないのは、作者の世界観から滲み出る言葉と感性で作品化されているからだろう。
巻末近くに、作者の世界観を表現した作品がある。
・秋茜うすき銀翅をきらめかせ彼岸此岸(ひがんしがん)の風を聞かしむ
・ある夜半の宇宙神話にあをじろき彗星おもひを遂げ得ず滅ぶ
彼岸は仏教用語で、生死の海を超えた理想郷。此岸はこちら岸のこと。俗に言えば「あの世」と「この世」である。秋茜の銀翅が、彼岸と此岸とを自在に吹き渡る風を思わせるというのである。宇宙神話の歌は、地球を宇宙の中の一つの小天体と見る宇宙観が感じとられる。そうした作者の世界観に基づいて作品化しているので、そこに独自なものの見方と、表現の独創性が出ているのだ。
歴史と伝統を表現した作品をいくつか挙げよう。
・白山の雪解水にて春耕の整ふ水田にうつる神山
・紙漉きの村といはれし二股に伝統細り冬桜さく
・五世紀の遠きかなたに心留め古墳にのぼり手取川のぞむ
・人のこゑかそけき山上の宿坊に夜霧あつめて墨すりはじむ
世界観、宇宙観と言ったが、それらが理窟になっていないのは、それらが作者の心の中で祈りにも似た心情となっているためだろう。
・ふるさとの湯宿に黒き糸とんぼ魑魅(すだま)のごとく部屋ぬけてゆく
・森深くまがたま池に菖蒲咲き神のいぶきの夕霧ながる
・人音のなべて静まる夜深く太古の冬の海神吠ゆる
ここには宗教的で敬虔な祈りが感じられる。魑魅(すだま)は、山林、木石の精気より生ずる神。
また、作品の根底に、叙景歌の着実な表現があるのも忘れてはならないだろう。紙数の関係で、一首のみ抄出する。
黒々と板状節理の押しあへる窪みに湧ける泉かすけく
御上梓を改めてお喜びしたい。