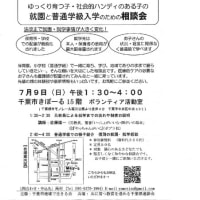親と子に、「ついていく」も「いけない」もない。
きょうだいにも、子どもたちの出会いにも、ない。
「つながり」に、「ついていく」も「いけない」もない。
無条件の安全は、「いるだけ」のつながりのなかにある。
学ぶべき子どもとしてでなく。
変わるべき子どもとしてでなく。
私たちが求めたのは、「いるだけでいい」と子どもが感じてくれる安全だった。
□
「ついていけないなら、一緒にいる意味がない」?
「条件が整えば、一緒にいてもいい」?
「ついていけるか」という怖れは、大人が設定する条件からはじまる。
そこでは、《子どもの声を聞く》ためには、言葉の獲得が必要といわれる。
それを「本当の教育」というなら、そんなものはいらない。
「あなただけ、ここにいてはいけない」とは絶対に、言わない。
「いるだけでいいのか」と言う教師に、期待はない。
「ただ、よけないことはしないで」
「子どものつながりをじゃましないで」
それが「いるだけでいい」の真意だった。
□
ふいに子どもに抱き着かれた瞬間や、振り向いて笑ってくれる子どもの表情。
言葉にならない怖れも叫びも、子どもの声であり、ことばだった。
言葉より確かな声は、子ども時代の主要な言語である「あそび」のなかにある。
教師が設定した課題がないからこそ生まれる、つながりがある。
目を合わせること、声をかけること、笑いあうこと、隣の子が手をつないで授業を受けること。
すべてがことばであり、あそびであり、まなびであり、つながりだった。
学ぶべき子どもとしてでなく。
変わるべき子どもとしてでなく。
今ここに「いること」のかけがえのなさを忘れない。