

久しぶりにヒモワタカイガラムシを見た。
これはメスで、このドーナツに似た蝋質(卵のう)の中には大量の卵が入っているという。
中にある卵は黄色で、その数は一雌当たり3000個にも達するという。
雄虫は体長約1.2mm、細長くて黄色、胸部はやや色濃く、立派な翅を持つというがネットではとうとう見つからなかった。


久しぶりにヒモワタカイガラムシを見た。
これはメスで、このドーナツに似た蝋質(卵のう)の中には大量の卵が入っているという。
中にある卵は黄色で、その数は一雌当たり3000個にも達するという。
雄虫は体長約1.2mm、細長くて黄色、胸部はやや色濃く、立派な翅を持つというがネットではとうとう見つからなかった。




トウネズミモチハマキワタムシはトウネズミモチの葉を巻いて中で吸汁するという。
甘露を出してアリを呼び、護衛につけている。
隙を狙ってナナホシテントウが幼虫を食べに来ている。
白い塊の中には幼虫がいる。
2015年05月07日に撮ったトウネズミモチハマキワタムシの幼虫。


都立薬用植物園の温室にて。
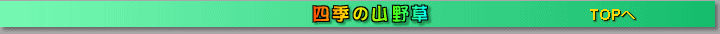 様に葉次のようにある。
様に葉次のようにある。
珊瑚色の玉が数珠状に付くことからの名前で、熱帯アメリカ原産。このジュズサンゴは ヨウシュヤマゴボウ などと同じ、ヤマゴボウ科。
別の方のページには
落葉しますが、寒さには5℃くらいまでは耐えるので比較的強く、温暖地では戸外で越冬できます。室内に保護しておいてもいいでしょう。
とある。

都立薬用植物園の冷温室にて。5月24日に撮影。
ガラス越しなので画質は悪い。
本属中もっとも大きな径10cmあまりの花を咲かせ、ベトニキフォリア同様多年生で栽培が容易なため本種も園芸用によく栽培される。
主産地はヒマラヤで、中国には産しないのでヒマラヤの青いケシの名はM. betonicifoliaよりもむしろ本種にふさわしい。
地域や個体による変異が大きく、それらの要素により花色も薄い紫から深い青までと、様々に変化する。
とある。

いつも葉の裏側にピタリと張り付いて隠れるオオシラホシアツバ。
今回は何とか撮ることができた。
------------
5月30日はゴミゼロの日だそうで、昨日の日曜日は住んでいる自治会の清掃の日だった。
普段、鳥や虫ばっかり追っかけているので、こんな日は大変だ。
まず自分の住まいの周りをきれいにしないと皆さんに笑われそうだ。
さすがに一日は撮影を休んで片付けた。

本当は縦に止まっていたが、横の方が見やすいので。
食樹はミズナラ、コナラだという、灯りが好きらしい。
2015年05月30日に野外で撮ったウスイロギンモンシャチホコ。

160530

昨日 閲覧数1,717 訪問者数212