7月18日朝日新聞は「オピニオン&フォーラム」という欄に、政治学者の境家史郎(サカイヤシロウ)東京大学教授に対するインタビュー記事を掲載しました。”「55年体制」の行方”と題されていました。そのなかに、「非常に逆説的ですが、支持率が低く、人気のない政権であっても、あれだけのことが出来てしまうことは、首相、あるいは政権与党中枢へ権力がいかに集まっているかを示しているともいえるでしょう」という指摘がありました。そして、「長期的には、憲法改正問題が政党間の大きな争点であり続けていることをどうするかが、日本の政治にとって大きな課題ではないでしょうか。改憲発議を阻止するには国会議席の三分の一超を占めれば足りるわけですが、このことが過半数を取れない野党にある種の満足感を与えていて、現状維持的な路線を採らせ、結果として政権交代を遠ざけています。『ネオ55年体制』を本当に終わらせるためには、避けて通れない課題だと私は思います」とありました。
私は、日本の政治課題に関し、敢えて、的を外したことを言っているのではないかと思いました。なぜ、”政権与党中枢へ権力が集まっているのか”を明らかにすることが大事であり、その権力集中を何とかしないと、憲法改正問題がどうなろうと、日本が大きく変わり、民主的な国になることはないと思いました。
そして、現在の日本の重要問題は、日米関係であり、「日本国憲法」の上にあると言われる、「日米安保条約」や「日米地位協定」を放置せず、日本を利するものにすることだと思います。そこに踏み込まなければ、日本が大きく変わることはないと思うのです。
1994年、社会党は「55年体制」で対決してきた自民党と連立を組み、村山富市委員長が首相に就任しました。でもその時、村山氏は「自衛隊は合憲」とし「非武装中立は政治的役割を終えた」と表明して、社会党の基本政策を大転換しました。なぜでしょうか。
また、立憲民主党政権は、自民党時代の日米密約の問題の調査に取組みましたが、事実を明らかにしただけで、現実的な日米関係の見直しや、沖縄の在日米軍基地問題については、何も踏み込んだ政策に結びつけることができませんでした。なぜでしょうか。
私は、そうしたことが、「日米安保条約」や「日米地位協定」が、現実に、「日本国憲法」の上にあることを示しているように思います。
現在、岸田政権が進めている中ロを敵視する日米や近隣諸国との関係強化の政治は、日本の外交はもちろん、国内政治の大枠を決定し、日本人が日本の針路を自由に決められない状況をつくりだしていくように思います。
先だって、国の指示権を拡大する改正地方自治法が成立しましたが、国だけではなく、地方も独自の政策決定ができない状況に陥る可能性があると思います。とくに有事の場合は、地方の自治権はなくなるように思います。すべて「アメリカまかせ」になるような気がします。
したがって、日本のことは日本人自身が決める、あるいは、自分のことは自分が決めるという、民主主義の大原則に立ち返り、軍事同盟や特定の国を敵視するような対外関係を解消していくことが、日本の課題であると思います。そして、それが、政治に対する日本人の関心を高め、日本人の政治的主体性を復活させることにつながると思います。
現状を追認すると、日本が独自の外交や政策決定ができず、日本人の政治に対する関心は薄れ、民主主義が意味を持たなくなると思います。
また、メディアが西側諸国を主導するアメリカの戦略に追随するような報道しかしなければ、政権が変わる可能性は少なく、たとえ政権が変ったとしても、その政策に大きな変化は期待できないと思います。
現在国際社会は、アメリカを中心とする西側諸国とブリックス(BRICS)や上海協力機構(Shanghai Cooperation Organization、略称: SCO)に結集する国に分かれつつあるように思いますが、それは、大雑把に言えば、かつて植民地支配をした国々(欧米)と支配された国々および社会主義革命を経験した国々に分かれつつあるということだと思います。
下記抜粋文で、ケニアにおいてイギリスが何をしたのか、また、ケニアの人たちの思いがその後どのような政治活動につながっていったのかを知ることができるように思います。私は、下記のような記述を見逃すことが出来ません。
”若者層の怒りは、ケニアの現代史において常に極めて決定的な意味をもってきた。その典型的な例として、1950年代末、英国が白人入植事業で、ケニアの最も肥沃な土地が集中するケニア山周辺の地域をギクユ人から奪ったことに抗議した、英国当局がマウマウと呼んだ蜂起(ないし戦争)がある。”
ギクユ人は、ケニア中央部に住むバントゥー系農耕民だといいます。その農耕民から、ケニアに入り込んだイギリス人が土地を奪ったから、彼らは「ケニア土地自由軍」を組織し蜂起しました。でも、ギクユ人の蜂起は、イギリス植民地当局の圧倒的な軍事力で潰されてしまったのです。そうした歴史が現在につながっていることを忘れてはならないと思います。
アメリカを中心とする西側諸国が、国際社会に素晴らしい文化・文明をもたらしたことは誰も否定できないと思いますが、それを支えたのが、現在の法や道義・道徳に反する植民地支配や新植民地支配であったこと、そして、そうした搾取・収奪に基づく他国支配が、もはやできない状況に変わっていることは、アメリカを中心とする西側諸国が封建的・絶対主義的国家体制を解体する市民革命を経て発展させた、文化・文明、法や道義・道徳が示していると思います。
今もなお、ケニアにおけるイギリスのような振る舞いが、西側諸国によって、国際社会を欺瞞するかたちで続けられているために、著しい経済格差が生まれ、国際社会が対立を深めているのだと思います。イスラエルによるパレスチナにおける蛮行が、許されないことは、西側諸国が発展させた法や道義・道徳が示していると思います。西側諸国が中心のICJが、イスラエルのパレスチナ占領を違法と判断するに至っているのです。
岸田首相は先だって、アメリカのワシントンで開かれた北大西洋条約機構(NATO)首脳会議で演説し、NATO加盟国がインド太平洋への関心と関与を高めていることを歓迎したといいます。どのように中国やロシアと関係を改善し、平和的に共存するかという視点を欠落した法や道義・道徳に反する演説だと思います。
下記は、「新・現在アフリカ入門 人々が変える大陸」勝俣誠(岩波新書)から「第二章 民主化20年」の 「4 ケニアの民主化と暴力の系譜」 の一部を抜萃しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第二章 民主化の20年
4 ケニアの民主化と暴力の系譜
マウマウ戦争の現代的意味
若者層の怒りは、ケニアの現代史において常に極めて決定的な意味をもってきた。その典型的な例として、1950年代末、英国が白人入植事業で、ケニアの最も肥沃な土地が集中するケニア山周辺の地域をギクユ人から奪ったことに抗議した、英国当局がマウマウと呼んだ蜂起(ないし戦争)がある。マウマウの語源は諸説あるが、ケニア人はケニア土地自由軍と呼び、その戦いはケニア人なら誰でも知っている出来事である。
白人入植者に土地を奪われたギクユ人、とりわけ土地へのアクセスがほとんどなくなってしまったギクユ人の若者にとって、それは何よりも将来への絶望につながった。土地を持ち、結婚し、親孝行をするという男子のメンツが、この植民地政策下では実現不可能になったのだ。
彼らの武装蜂起は一時広がりを見せ、英国民植民地当局は、村落の空爆、マウマウの活動地域での強制移動、拷問など、その後のアルジェリアやベトナムでの民族自決運動抑圧のお手本となるような過酷な措置に出た。結果、この蜂起は、植民地当局の圧倒的な軍事作戦で潰されてしまう。
1956年の英国植民地当局の発表によれば、マウマウの戦死者は約1万人、ヨーロッパ人95人、さらに2000人近いアフリカ人やインド系などのアジアの死者が出たとされた。しかしマウマウ戦争を検証した歴史家キャロリン・エルキンズは、アフリカ人側の犠牲者は実際は数十万人に上ると示唆している。
これを機に、ケニア社会には世代間対立の種が蒔かれていった。すなわちマウマウ蜂起が鎮圧され、ケニアが63年に英国植民地から独立して行くプロセスの中で戦って、結局報われなかった若者と、英国の植民地総局と妥協することによって、自らの地位を維持・拡大していった新興政治エリートとの間の亀裂である。この亀裂は、今日のケニアの政権の性格を規定する重要な要因であろう。
盗まれ続ける若者の革命
他の多くのアフリカ諸国のポスト独立期と同様、ケニアのポスト独立期も、独立期の権力のとり方によってその方向が決められたと言っても過言ではない。
独立時に「英雄」として登場した穏健派のケニア政府ケニヤッタ政権は、マウマウ戦争の犠牲者の名誉回復を葬り去ろうとした。それを受け継いだモイ政権時代。マウマウの復権を一応はかりながらも、同じ民族集団の貧困層からは必ずしも支持されなかったキバキ政権……。これらすべてが、独立以降の国富の処分と私物化に膨大な権力を行使できる政治エリートという特権層と、選挙のたびに期待を裏切られた若年層との溝を深めたと言っても過言ではないであろう。
マウマウ蜂起に参加した人々が要求した土地は、独立後、政治エリート主導でほぼ私物化され、命を落とした戦士はほとんど得ることがなかった。この現実は、2007年の「ポスト選挙暴動」後、ライバル同士が権力を分ち合う政権を発足させ、政治エリートは一応利害を調整したが、より公正な選挙で、よりましなケニア社会を求めた若者は、相変わらず貧しいという現実と重なり合う。
ケニア地域を専門とする人類学者小馬徹は、この2007年の危機を「盗まれた若者革命」と名づけた(『神奈川大学評論』2008年第61号)
2008年、以前マウマウの戦士が隠れたケニア山の麓を案内してくれた元戦士の孫である案内人の青年は、戦争が終わって、何ら報償らしい恩典もなく、現在にいたるも細々と農業を続ける祖父から聞いた言葉を筆者に教えてくれた。
「マウマウの戦士は土を掴んで死んでいった」
かくして、ケニアは90年代の民主化、07年の「ポスト選挙暴力」で大きな挫折を味わうことになった。そこで改めて浮き彫りになったのは、独立以来の政治エリート中心の議会民主主義の限界とともに、自国の富の分配の民主化こそが、独立以来、未完のアジェンダになっているということである。















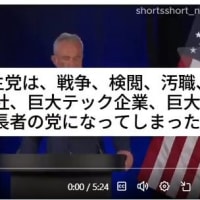












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます