

少年時代に神父から性的虐待を受けた男性が告発を始める。
最初は教区の枢機卿への手紙だったが、
謝罪と赦しで終わらせようとする教会に不信を抱いた男性は証言をつのり、
やがては警察の捜査が入る。
ドキュメンタリーではないけれど、
事実にかなり基づいているんだろうな、という作り。
盛り上がりのないのが仏映画らしいけど、
その淡々としているところがロジックを明確化している。
なにが問題か、誰を対象か、終着点がどこか、が、わかりやすい。
「大したことではない」
「子供時代の些細な出来事は、大人になって忘れたと思っていた」と、
親から軽く言われるのは辛いよね。
「変態にヤラれた」のレッテルを怖がるのもわかる。
被害者の苦痛は性別も年齢も国境も関係なく同じなんだろうな。
神父が自分の行いを認めているのが怖い。
小児性愛者で病気だと思う治そうと努力した、
その言葉だけで被害者に許されると思っており、
被害者に微笑みかけ、子供と触れ合う仕事を辞めない。
どうしてそうなるのか。
不思議だ。
運動に加わった人の話だからだろうけど、
配偶者や子供が支持しているのが救い。
寄り添う家族がいるというのは、これほどに力強いのか。
神父から、という点で、加害を突き詰めるのは、
信仰を捨てることに繋がる場合があるというのがなんとも。
精神の支柱を捨てるかどうかと向き合うのも難しいね。
ある被害者の兄も、
最初は「そんな些細なこと」と片付けているのかと思ったら、違って。
被害者、そしてその家族、と影響はどんどん広がるんだなあ。
映画としては加害者神父の芝居に鳥肌。
そこで、その笑顔。
凄かった。







































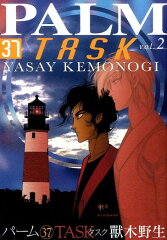



![Wings (ウィングス) 2013年 06月号 特別付録 永久保存版小冊子「プチ・パームブック」[雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61in8ViynvL._SL160_.jpg)


