(17)哲学堂公園

東洋大学の創始者である井上円了が、哲学の普及のために開設した哲学堂が、この公園の始まりである。園内は通年公開されているが、建物内部は春と秋の特定日のほか、文化財ウイーク中にも公開されている。所在地は中野区松が丘1-34-28。最寄駅は西武新宿線新井薬師前駅。
(18)中野区立歴史民俗資料館

中野区立歴史民俗資料館に併設されている旧山崎家住宅が、古建築公開・旧名主茶室書院公開として、文化財ウイーク前後の2ケ月の間、荒天時と休館時を除いて公開されている。中野区立歴史民俗資料館では常設展示のほか企画展、特別展も行っている。今期は、「哲学堂と配水塔」、「ミニチュア玩具の世界」を開催。所在地は中野区江古田4-3-4。最寄駅は西武新宿線沼袋駅。山崎家は当ブログのカテゴリー「江戸近郊小さな旅」の「石神井の道くさ」に記載あり。
(19)旧粕谷家住宅

昨年から文化財ウイークの参加企画として、古民家めぐりが行われるようになったが、旧粕谷家住宅も古民家の一つとして参加している。旧粕谷家住宅は徳丸脇村の名主粕谷家の隠居所として建てられて、180年ほど経っているという。この住宅は近年まで居住していたようで、台所など一部が改造されている。しかし、全体としては建設当初の部材が多く残り、江戸時代の農家の形式を良く残している。この住宅にも、火の神として台所に祭られる荒神様の棚があるが、この時期には特別の飾り付けをするようで、荒神松のほかに榊と南天が供えられていた。旧粕谷家住宅は、通常、非公開だが、文化財ウイーク近くに期間を定めて公開されている。所在地は板橋区徳丸7-11-1。最寄駅は都営三田線高島平駅。
(20)正福寺地蔵堂

正福寺地蔵堂は、鎌倉の円覚寺舎利殿と同じ禅宗様建築で、建造物としては都内唯一の国宝に指定されている。この地蔵堂は、1934年の復元解体工事の際に発見された墨書銘から1407年の建立と考えられている。内部の公開は11月3日のみ。以前、公開日に訪れたことがあるが、堂内は土間で、本尊の地蔵菩薩のほか、木彫りの地蔵菩薩の小像が、所狭しと並べられていた。祈願する事がある時は、この小像を持ち帰り、願いが叶った時はもう一体をつけて戻すという習慣があったからのようで、地蔵の数が多い事から千体地蔵堂とも呼ばれている。所在地は東村山市野口町4-6-1。西武新宿線東村山駅が最寄駅である。
(21)八国山たいけんの里

天気が良ければ、正福寺地蔵堂から北山公園を経て、八国山たいけんの里まで足を伸ばすのも悪くない。八国山を眺めながら、のんびり歩ける。ここには都有形文化財の下宅部(しもやけべ)遺跡の出土品が展示されており、通年公開の文化財の扱いになっている。所在地は東村山市野口町3-48-1。最寄駅は西武園線西武園駅。
(23)金剛寺不動堂(高幡不動)

重要文化財の金剛寺不動堂、仁王門、木造不動明王及び二童子像と、都有形文化財の旧五部権現社殿、絹本着色弁財天十五童子像、高幡山金剛寺文書が対象で、何れも通年公開の文化財になっている。文化財ウイークの期間は、菊まつりが開催されている。境内は紅葉の時期も良いが、紫陽花の咲くころもお勧めである。所在地は日野市高幡733。最寄駅は高幡不動駅。
(24)八王子城跡
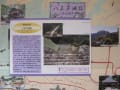
少し前のことになるが、文化財ウイーク期間中、八王子城跡に出かけたことがある。高尾駅から途中まではバスもあるが、天気が良いので歩いた。ただ、近い距離ではなかった。山の麓でポストカードと小冊子を入手し、標高460mほどの山頂に向かってひたすら登る。本丸のあった頂上は、神社の場所から、もうひと登りである。帰りはやや荒れた感じの別の道をとって一気に下る。麓で暫く休んだ後、もと来た道を歩いて高尾駅まで戻る。文化財の見て歩きというより、ハイキングである。八王子城跡は国指定の史跡で、通年公開の文化財である。八王子城が築かれたのは戦国時代の終わり。城主の北条氏照が小田原城に詰めていた時に、前田利家・上杉景勝の軍勢により攻められて、あっけなく落城したと伝えられている。八王子城は山頂部の要害地区、麓の居館地区、城下に相当する根古屋地区に分かれるが、居館地区の御主殿跡には石垣や橋などが復元されている。所在地は八王子市元八王子町3と下恩方町、西寺方町にかけて。最寄駅は高尾駅。居館地区は、霊園前バス停から片道20分ほどである。

東洋大学の創始者である井上円了が、哲学の普及のために開設した哲学堂が、この公園の始まりである。園内は通年公開されているが、建物内部は春と秋の特定日のほか、文化財ウイーク中にも公開されている。所在地は中野区松が丘1-34-28。最寄駅は西武新宿線新井薬師前駅。
(18)中野区立歴史民俗資料館

中野区立歴史民俗資料館に併設されている旧山崎家住宅が、古建築公開・旧名主茶室書院公開として、文化財ウイーク前後の2ケ月の間、荒天時と休館時を除いて公開されている。中野区立歴史民俗資料館では常設展示のほか企画展、特別展も行っている。今期は、「哲学堂と配水塔」、「ミニチュア玩具の世界」を開催。所在地は中野区江古田4-3-4。最寄駅は西武新宿線沼袋駅。山崎家は当ブログのカテゴリー「江戸近郊小さな旅」の「石神井の道くさ」に記載あり。
(19)旧粕谷家住宅

昨年から文化財ウイークの参加企画として、古民家めぐりが行われるようになったが、旧粕谷家住宅も古民家の一つとして参加している。旧粕谷家住宅は徳丸脇村の名主粕谷家の隠居所として建てられて、180年ほど経っているという。この住宅は近年まで居住していたようで、台所など一部が改造されている。しかし、全体としては建設当初の部材が多く残り、江戸時代の農家の形式を良く残している。この住宅にも、火の神として台所に祭られる荒神様の棚があるが、この時期には特別の飾り付けをするようで、荒神松のほかに榊と南天が供えられていた。旧粕谷家住宅は、通常、非公開だが、文化財ウイーク近くに期間を定めて公開されている。所在地は板橋区徳丸7-11-1。最寄駅は都営三田線高島平駅。
(20)正福寺地蔵堂

正福寺地蔵堂は、鎌倉の円覚寺舎利殿と同じ禅宗様建築で、建造物としては都内唯一の国宝に指定されている。この地蔵堂は、1934年の復元解体工事の際に発見された墨書銘から1407年の建立と考えられている。内部の公開は11月3日のみ。以前、公開日に訪れたことがあるが、堂内は土間で、本尊の地蔵菩薩のほか、木彫りの地蔵菩薩の小像が、所狭しと並べられていた。祈願する事がある時は、この小像を持ち帰り、願いが叶った時はもう一体をつけて戻すという習慣があったからのようで、地蔵の数が多い事から千体地蔵堂とも呼ばれている。所在地は東村山市野口町4-6-1。西武新宿線東村山駅が最寄駅である。
(21)八国山たいけんの里

天気が良ければ、正福寺地蔵堂から北山公園を経て、八国山たいけんの里まで足を伸ばすのも悪くない。八国山を眺めながら、のんびり歩ける。ここには都有形文化財の下宅部(しもやけべ)遺跡の出土品が展示されており、通年公開の文化財の扱いになっている。所在地は東村山市野口町3-48-1。最寄駅は西武園線西武園駅。
(23)金剛寺不動堂(高幡不動)

重要文化財の金剛寺不動堂、仁王門、木造不動明王及び二童子像と、都有形文化財の旧五部権現社殿、絹本着色弁財天十五童子像、高幡山金剛寺文書が対象で、何れも通年公開の文化財になっている。文化財ウイークの期間は、菊まつりが開催されている。境内は紅葉の時期も良いが、紫陽花の咲くころもお勧めである。所在地は日野市高幡733。最寄駅は高幡不動駅。
(24)八王子城跡
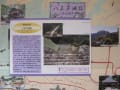
少し前のことになるが、文化財ウイーク期間中、八王子城跡に出かけたことがある。高尾駅から途中まではバスもあるが、天気が良いので歩いた。ただ、近い距離ではなかった。山の麓でポストカードと小冊子を入手し、標高460mほどの山頂に向かってひたすら登る。本丸のあった頂上は、神社の場所から、もうひと登りである。帰りはやや荒れた感じの別の道をとって一気に下る。麓で暫く休んだ後、もと来た道を歩いて高尾駅まで戻る。文化財の見て歩きというより、ハイキングである。八王子城跡は国指定の史跡で、通年公開の文化財である。八王子城が築かれたのは戦国時代の終わり。城主の北条氏照が小田原城に詰めていた時に、前田利家・上杉景勝の軍勢により攻められて、あっけなく落城したと伝えられている。八王子城は山頂部の要害地区、麓の居館地区、城下に相当する根古屋地区に分かれるが、居館地区の御主殿跡には石垣や橋などが復元されている。所在地は八王子市元八王子町3と下恩方町、西寺方町にかけて。最寄駅は高尾駅。居館地区は、霊園前バス停から片道20分ほどである。














