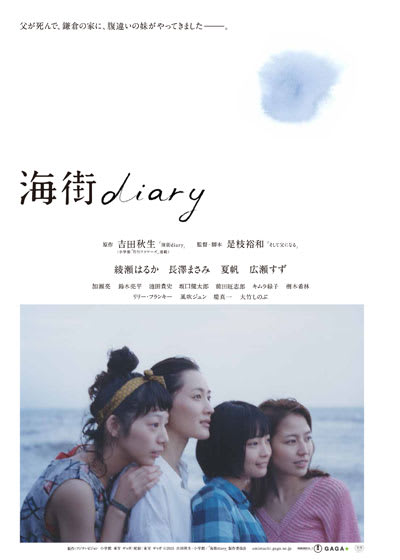ビジネスジャーナルに、以下のコラムを寄稿しました。
フォロワー数の増減は
実生活になんの影響もない…
24時間ソーシャル状態、しんどくない?
実生活になんの影響もない…
24時間ソーシャル状態、しんどくない?
テレビ番組もそうだが、CMは時代を映す鏡だ。その時どきの世相、流行、社会現象、そして人間模様までを、どこかに反映させている。この夏、流されているCMのなかから、注目作を2本選んでみた。共通するのは「喚起するチカラ」だ。
●JR東日本『行くぜ、東北。
「女川(おながわ)の今」篇』
CMの効用のひとつに、「思い出す」がある。JR東日本『行くぜ、東北。』シリーズはそんな1本だ。2011年3月から5年と5カ月。被災地に対する「どうしているだろう」の気持ちを、さりげなく刺激してくれる。
前回までの木村文乃さんに代わる、新たな旅人は松岡茉優さん。NHK連続テレビ小説『あまちゃん』の地元アイドル役でブレイクし、昨年の『She』(フジテレビ系)、今年の『水族館ガール』(NHK)と連ドラ主演作が続いている。どんな役柄も自然に自分のものにしてしまう演技力。またバラエティーでも崩しすぎない親しみやすさが持ち味だ。
今回、松岡さんが歩くのは宮城県女川町。地震と津波で沿岸部の被害は壊滅的といわれたが、昨年末にはテナント型商店街「シーパルピア女川」もオープンした。ナレーションの通り、「東北は前へ進んでいる」のだ。
間もなくやってくる今年の秋、旅に出るなら、ぜひ東北へ。
●武田薬品工業『アリナミン7シリーズ
「乙です、ソーシャルちゃん!」篇』
家でもスマホ、会社でもスマホ。教室でも、そして電車の中でもスマホ。そんな風景が当たり前になっている。
多分、「普通の携帯電話(ガラケーって言葉、あまり好きじゃないので)」を愛用している者にはうかがい知れぬ、何かとんでもない秘密の“楽しみ”が手のひらの中にあるのだろう。でも、“24時間ソーシャル状態”って、しんどくないのかな?
そんなことを思っていたら、武田薬品『アリナミン7』のWEB限定CMで、“さや姉(ねえ)”ことNMB48の山本彩さんが、画面から語りかけてきた。
「意識高い投稿してるけど、モテたいだけでしょ?」
「キミの『いいね!』のハードル、いくらなんでも低すぎません?」
「タグ付けは慎重にね。それで人生が終わる人もいるんだよ」
「フォロワー数が増えても減っても、実生活にはなんの影響もないよ。楽になって!」
いやあ、よくぞ言ってくれました。お疲れ気味になっている世の“ソーシャルちゃん”たちへの救いの言葉であり、同時に一種の警鐘でもある。
もちろん、「つながること」自体は悪くはない。でも、「つながりかた」や「つながりすぎること」の危うさも、しっかり視野に入れるべき時代だと思う。
できれば、さや姉のメッセージが多くの人に届きますように。
(ビジネスジャーナル 2016.09.03)