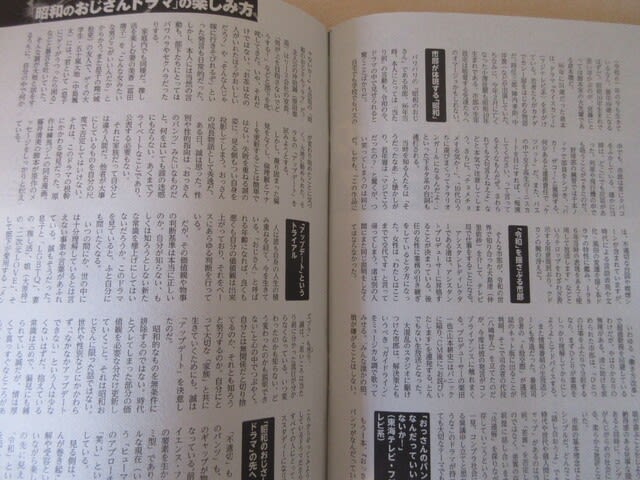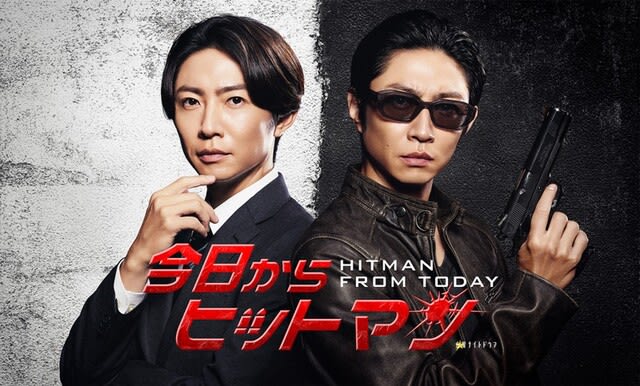「記憶喪失ヒロイン×イケメン3人」
王道ラブコメと思いきや…
ドラマ『くるり』がおじさんに刺さるワケ
火曜ドラマ『くるり~誰が私と恋をした?~』(TBS系)。記憶喪失のヒロインと彼女を知る3人の男が登場するドラマだ。
当初、美女とイケメンたちの物語は、よくあるラブコメの王道かと思われた。だが、それだではないものがこのドラマにはある。
また視聴率としては可もなく不可もない5%台の数字が続いているが、決して下落してはいない。この状態をキープするのに貢献しているのは、固定のファン層がついているからだと思われ、その中に少なからず「おじさん」の視聴者もいるらしい。彼らを惹きつけているのが、主演の「めるる」こと生見愛瑠(ぬくみ める)の存在だ。
本稿では、「ホップ・ステップ・ジャンプ」ともいえる生見の軌跡を振り返りながら、おじさんたちをも巻き込む彼女の魅力を探ってみたい。
◆ホップ:
「発見ドラマ」としての『日曜の夜ぐらいは…』
生見の快進撃は、2023年春のドラマ『日曜の夜ぐらいは…』(ABCテレビ・テレビ朝日系)から始まった。
この作品は、どこにでもいそうな3人の女性が織りなす、異色の友情物語だった。サチ(清野菜名)は、足の不自由な母(和久井映見)を支えながら働いている。翔子(岸井ゆきの)は1人暮らしのタクシー運転手だ。
そして地方在住の若葉(生見)は、祖母(宮本信子)と同じ工場に勤務している。共通するのは、それぞれが鬱屈を抱えながら日々を生きていたことだ。
会うはずのない3人が知り合ったのは、あるラジオ番組のリスナー限定バスツアーだった。初対面なのにどこか気が合い、互いに友だちを得たように感じる。
その一方で、「友情」に対して、「後悔」や「裏切り」といったネガティブな言葉が思い浮かぶ3人は、無理をしてまで互いに距離をとったりする。このあたりの微妙な感情を、脚本の岡田恵和が繊細にすくい上げていた。
バスツアーの最中、一緒に買った3枚の宝くじ。その中の1枚が3000万円当たったことで物語にドライブがかかる。再会して均等に分け合うが、その後は慣れない大金に戸惑い気味だ。結局、「共同出資でカフェを開こう」という話になる。
若葉の有り金を持ち去る母親(矢田亜希子)や、サチに金の無心をする父親(尾美としのり)といった“障害”を乗り越え、翔子の口癖である「つまんねえ人生」を変えることはできるのか。生きることに不器用で、幸福になることを恐れているような彼女たちが、何とも切なく愛おしかった。
中でも若葉は、自分の美しさや目立つことがコンプレックスという「ねじれ感」が痛々しい。何もしていなのに異性の関心を集めたり、そのことで周囲の同性から嫉妬されたり、いじめられたりしてきたからだ。
等身大の女性の喜怒哀楽をナチュラルな演技で表現した生見は、第33回「TV LIFE 年間ドラマ大賞」助演女優賞を受賞した。多くのおじさんたちが生見愛瑠を「発見」したのが、このドラマだ。
◆ステップ:
「成長ドラマ」としての『セクシー田中さん』
次に生見が挑んだのが、後に原作漫画家の死をめぐる騒動が起きてしまった、23年秋の『セクシー田中さん』(日本テレビ系)だ。
派遣OLの朱里(あかり、生見)は、同じ会社の経理部で働く「田中さん」こと田中京子(木南晴夏)の秘密を知る。仕事は完璧だが、見た目は地味で暗いアラフォーだ。ところが、彼女にはセクシーなベリーダンサーという「別の顔」があった。
子どもの頃から周囲とうまく交わることが出来ず、自分を封印しながら生きてきた、田中さんが言う。「ベリーダンスに正解はない。自分で考えて、自分で探すしかない」と。
一方の朱里は、誰からも好かれる「愛され系女子」だ。しかし、誰からも好かれるが、誰かから「本当に好かれた」という実感がなく、モヤモヤしていた。また、不安定な派遣の仕事を続ける中で、不幸にならないための「リスクヘッジ」ばかりを意識してきた。
他人にどう思われようと気にしない田中さんに対する「推し活」を通じて、朱里は徐々に変わっていく。自分の価値観に従って生きようとし始めるのだ。
その様子が、どこか生見自身の進化と重なって見えた。朱里はもちろん、生見の「成長物語」としても秀逸だったこのドラマで、第118回「ザテレビジョンドラマアカデミー賞」助演女優賞を受賞する。
◆ジャンプ:
「主演ドラマ」としての『くるり~誰が私と恋をした?~』
現在放送中の『くるり~誰が私と恋をした?~』は、生見のゴールデン・プライム帯での連ドラ「単独初主演」となる作品だ。
まこと(生見)は階段からの転落事故で記憶を失ってしまう。名前はもちろん、自分に関する情報は皆無。唯一の手掛かりは、ラッピングされた男性用の指輪だった。
やがて、彼女を「知っている」という男たちが現れる。会社の同僚で「唯一の男友達」と称する朝日(神尾楓珠)。フラワーショップの店主で、「元カレ」だという公太郎(瀬戸康史)。さらに偶然出会った年下の青年・律(宮世琉弥)だ。
自分が何者で、何をしてきたのか。周囲の人たちにとっての自分は、一体どんな人間だったのか。それが分からないことが一種のサスペンス性を生む。まことは自分のことを知りたいが、同時に「少し怖い」とも思っている。記憶を失くした今の自分から見て、「好ましい自分」かどうか、分からないからだ。
その一方で、別の考え方があることも知った。記憶喪失は、「自分らしさ」という呪縛から自由になることであり、人生の「リセット」が出来るかもしれないのだ。
このドラマ、始まる前は単純な記憶喪失ドラマかと思われた。しかし、そうではなかった。注目すべきは、「過去の自分」探しと「未来の自分」作りが同時進行していく、物語の新しさだ。そこには「本当の自分とは?」という普遍的なテーマが潜んでいる。
しかも、そんなテーマを持ちながら、この作品は暗くもなく、重たくもない。生見が持つ生来の「明るさ」がドラマの基調トーンを支えているのだ。
生見の演技は、「私を見て」とか「私はここにいる」といった自己主張をしない。「自分をよく見せよう」とは思わない、無欲ともいえる究極の「自然体」。自分が演じる女性にひたすら共感することで役柄になり切るのが、生見愛瑠という俳優の魅力だ。見る側は、そんな生見と一体化したヒロインをつい応援したくなる。
ドラマは終盤へと差し掛かってきた。徐々に扉を開きはじめた記憶は、まことに何をもたらすのか。それは分からない。だが、どんな展開が待っていようと、まこと=生見が不幸にならないことだけを、おじさんたちはひたすら祈っている。
(FRIDAYデジタル 2024.05.28)