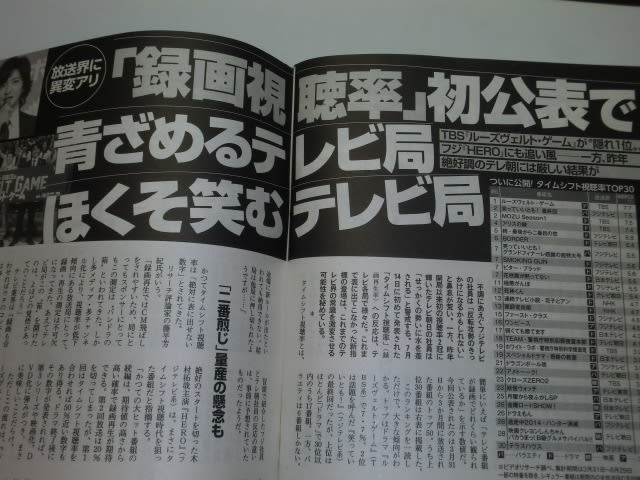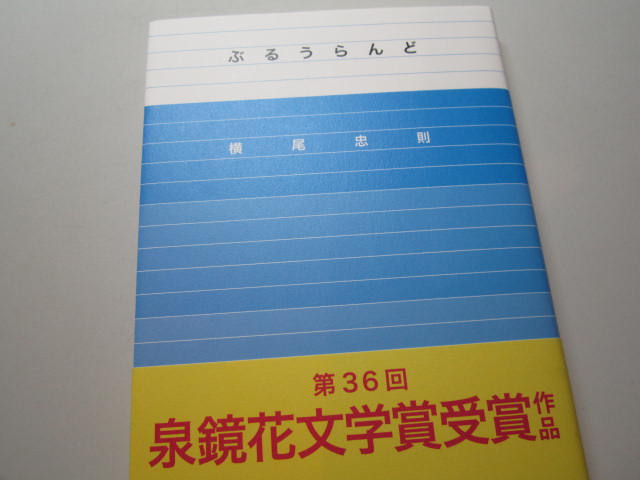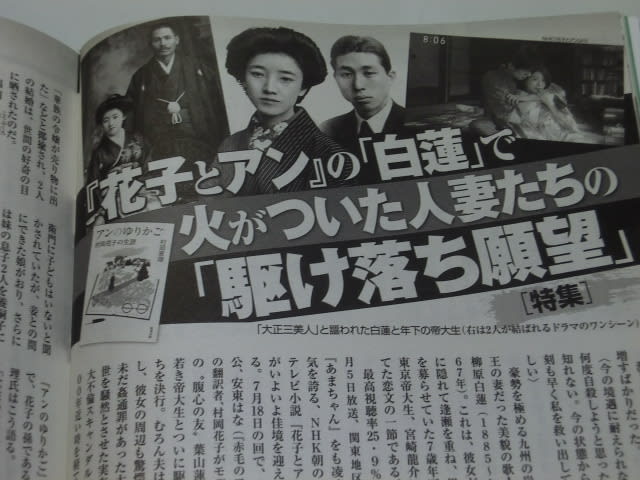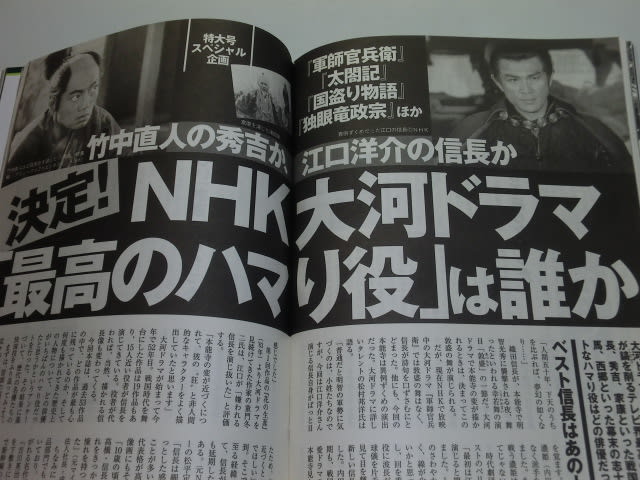この12年間、ほぼ1日1冊のペースで本を読み、毎週、雑誌に
書評を書くという、修行僧のような(笑)生活を続けています。
今年の上半期(1月から6月)に「読んで書評を書いた本」の中から、
オトナの男にオススメしたいものを選んでみました。
今回は、その「パート6」
今年上半期分はこれでラストになります。
閲覧していただき、一冊でも、気になる本が見つかれば幸いです。
2014年上半期
「オトナの男」にオススメの本
(その6)
「オトナの男」にオススメの本
(その6)
東野圭吾 『虚ろな十字架』 光文社
果たして死刑は有効なのか。殺人と刑罰という重いテーマに挑んだ問題作だ。
動物の葬儀社で働く中原正道を刑事が訪ねてきた。別れた妻・小夜子が殺されたという。11年前、中原夫妻は殺人事件の被害者家族となった。当時小学2年生だった娘、愛美が殺害されたのだ。捕まった犯人は、別の殺人で無期懲役となりながら仮釈放で塀の外に出てきていた男で、結局この事件で死刑となった。
中原と離婚した後、ライターの仕事で生計を立てていた小夜子。彼女が遺したノートには娘の死をめぐる考察が記されていた。殺人を犯しても死刑ではなく、有期刑になることが少なくないこの国。「殺人者をそんな虚ろな十字架に縛り付けることに、どんな意味があるというのか」。
娘の死、元妻の死、そして隠された第三の死の謎が徐々に明らかになる。
内田 樹:編著 『街場の憂国会議~日本はこれからどうなるのか』
晶文社
安倍晋三政権下の日本。果たして、このままで大丈夫なのか。答えはもちろんNOだ。では何が、どのように問題なのか。内田樹、小田嶋隆、想田和弘、高橋源一郎、中島岳志、中野晃一、平川克美、孫崎享、鷲田清一という9人の論客が持論を展開する。
巻頭の内田論文のタイトル「株式会社化する国民国家」が、安倍政権が目指すものを端的に示している。国の存在理由を「経済成長」に一元化することだ。しかし、教育や医療が株式会社のように組織されるべきではないのと同様に、国家もまた株式会社とは違う。
また小田嶋は、安倍政権が歴史認識や大局を見た政策ではなく、歴史に対する「気分」によって動いていると指摘する。解釈改憲も、「書き換え」より気分的に簡単な「読み替え」を選んだことになる。今そこにある危うさを撃つ警世の書だ。
荒木経惟 『往生写集』 平凡社
今年74歳となるアラーキーが、半世紀に及ぶ“写業”を一冊に凝縮した写真集。「さっちん」「センチメンタルな旅・冬の旅」「チロ愛死」などの代表作から、「道路」「去年の戦後」といった最新作までが並ぶ。途中、作品によって用紙さえ変える執念が見事だ。
武田邦彦 『政府・マスコミは「言葉の魔術」でウソをつく』
日本文芸社
たとえば「子供に国の借金のツケを回すな」。実際は政府が国民から借りており、国の借金はない。また「原発は経済発展に必要」と言うが、安全性やコストを考えれば石炭火力に勝るものはない。原発を求める他の理由があると著者は言う。目から鱗のトリック解説だ。
小林信彦 『「あまちゃん」はなぜ面白かったか?』
文藝春秋
「週刊文春」連載のエッセイ集2013年版だ。大島渚と大瀧詠一の死、橋本愛の発見、ヒッチコック再考、そして「あまちゃん」。稀代の時代観察者が「これほど辛い年はなかった」と言う1年間を追体験する。文化から国家まで、自分の頭で考えるための参考書だ。
ちばてつや 『ちばてつやが語る「ちばてつや」』
集英社新書
漫画界の重鎮による創作論的自叙伝である。1939(昭和14)年に生まれ、2歳で旧満州に渡り、終戦で命懸けの帰国を果たした少年は、いかにして国民的漫画家となったのか。「理由は単純明快に、お金のためだ」と著者は言う。だが、誰もがなれるものではない。
貸本漫画家としてデビューした後、少女漫画に転じ、次に『おれは鉄兵』や『あしたのジョー』など少年漫画の金字塔となる傑作を発表。やがて『のたり松太郎』といった青年漫画にも進出する。徹底した取材をベースに想像力を羽ばたかせる手法が開陳されていく。
小手毬るい 『アップルソング』 ポプラ社
恋愛小説の名手として知られる著者が、殺戮の世紀といわれる時代を背景に書き上げた壮大な物語だ。
敗戦直前、焼野原の岡山市街。瓦礫の中から救い出されたのは茉莉江という名の赤ん坊だ。10歳になった彼女は母親に連れられてアメリカへと渡るが、待っていたのは過酷な運命だった。大人になった茉莉江の人生を変えたのは写真との出会いだ。戦争報道写真家となってからも、愛する人への思いとカメラを手放すことは決してなかった。
茉莉江と仲間たちが世界に伝えようとしたベトナム戦争、三菱重工爆破事件、チェチェン戦争、そして2011年の同時多発テロ。ある女性編集者が茉莉江に言う。「写真は、そこに写っていないものも含めて、その外には世界が広がっているということを表現し、見た人に世界の広がりを感じさせるもの」だと。
和田誠 『ほんの数行』 七つ森書館
本を読む楽しみの一つは「忘れられない一文」「刺激的な一行」に出会うことだ。それが「自分のための一文」や「自分だけの一行」になれば喜びは倍加する。
本書には100冊の本から抜き出された100個の珠玉の数行が並ぶ。いずれも著者が装丁を手がけた本であり、その内容と魅力を誰よりもわかっているからこそ選ぶことができた“名ゼリフ”ばかりだ。
たとえば、色川武大『うらおもて人生録』の「九勝六敗を狙え」。また、「なんといっても文章は頭の中身の反映ですから」は、井上ひさし『井上ひさし全選評』。そしてドナルド・キーンは言う。「便利さが人間の最高の目標になってよいのでしょうか。私はむしろ文化は不便の上に立つものではないかと思います」(『私の大事な場所』)。
著者の傑作『お楽しみはこれからだ』の拡大版だ。
一橋文哉 『モンスター~尼崎連続殺人事件の真実』
講談社
首謀者・角田美代子が謎の自殺を遂げたこともあり、全容が解明されていない連続殺人事件。複雑に絡んだ多数の関係者がいて、しかも被害者の一部が加害者でもある特異性をもつ。著者は徹底取材で新事実を明らかにするだけでなく、黒幕的存在にまで迫っている。
夢枕 獏 『幻想神空海』 マガジンハウス
空海とは「豊饒なる虚空」だと著者は言う。『沙門空海唐の国にて鬼と宴す』等、長年空海に関する作品を書き続けてきたが、本書は熱い“空海愛”を語り下ろしたものだ。出会いに始まり、最澄との対比、戦略家としての空海、さらに夢枕流密教解釈も開陳している。
佐々木マキ 『ノー・シューズ』 亜紀書房
村上春樹『風の歌を聴け』『羊をめぐる冒険』などの表紙画を手がけた著者の自伝的エッセイ&イラスト集。神戸での幼少期、伝説の漫画誌『ガロ』への投稿からプロになるまで、そしてなってからの悪戦苦闘が洒脱に語られる。長井勝一や村上春樹との交流秘話も必読。
西澤保彦 『下戸は勘定に入れません』 中央公論新社
タイムスリップを題材にした異色のSFミステリだ。何しろ「ある条件のもとで酒を飲むと同伴者と一緒に時空を超える」のだから。
主人公の古徳は大学の准教授。50歳でバツイチの独身だ。しかも生きる意欲を失い自殺願望をもっている。ある日、かつての恋人・美智絵を古徳から奪い、自分の妻にした旧友・早稲本と再会する。2人は酒を酌み交わすうちにタイムスリップしてしまう。着いた時代は28年前。まさに早稲本が美智絵に接近した夜だった。
本書は連作短編集だ。古徳はその不可思議な能力と独特の推理力で、いくつかの事件を解決していく。また同時に、自分と早稲本と美智絵の微妙な三角関係の謎を探っていくのだ。
古徳たちが体験するのは「意識」のタイムスリップ。実体として別の時代に行けるわけではない。そんな設定も物語を面白くしている。
伊藤彰彦 『映画の奈落~北陸代理戦争事件』 国書刊行会
1977年2月、深作欣二監督作品『北陸代理戦争』が公開された。松方弘樹が実在の組長をモデルにした主人公を演じる、東映実録やくざ映画である。公開から2ヶ月後、映画の中で殺人事件が起きるのと同じ喫茶店で組長が射殺された。いわゆる「三国事件」だ。
なぜ映画と現実がリンクするような事態が発生したのか。フィクションであるはずの映画は、進行中のやくざの抗争にどのような影響を与えたのか。著者は丹念な取材と作品分析によって真相に迫っていく。
見えてくるのは、巨大な山口組に挑もうとした北陸の組長・川内弘の生き方であり、新たなやくざ映画の地平を切り開こうとした脚本家・高田宏治の執念だ。
その時々のスキャンダルや事件をライブ感覚でつかみ、映画に取り込んできた東映。本書はその影の映画史でもある。
矢萩多聞 『偶然の装丁家』 晶文社
今は亡き自称スーパーエディター・安原顯をして「天才だよ!」と言わしめた装丁家が著者だ。不登校の中学生は14歳でインド暮らしを始める。帰国して絵を描き、やがて本のデザイナーとなった。気負いのない自然体で語られるのは本作りと暮らしの自分史だ。
宮城谷昌光『三国志読本』 文藝春秋
毎日、原稿用紙1・7枚を書き続けて12年。宮城谷版『三国志』全12巻が完結したのは昨年のことだ。本書は副読本ともいうべき一冊。独自の論考だけでなく、井上ひさしや五木寛之などと語り合う。「歴史は多面体だからこそおもしろい」を再認識させてくれる。
角田光代 『ポケットに物語を入れて』 小学館
読み巧者である著者のブック・エッセイ集。文庫本のの解説を軸に編んでいる。「書くという行為について私はこの作家にもっとも影響を受けている」とあるのは開高健のことで5作品が並ぶ。また江國香織や井上荒野など女流実力派の仕事にも目配りが効いている。
半田 滋 『日本は戦争をするのか―集団的自衛権と自衛隊』
岩波新書
安倍政権が今国会中の閣議決定を目指す集団的自衛権の行使容認。憲法解釈の変更によって「他国の戦争に参加する権利」を手に入れ、この国はどこへ向かおうというのか。だが、戦後最大の危機ともいうべき状況にも関わらず、大手メディアの腰は引けたままだ。
そんな中、「異議あり」の論陣を張り続けているのが東京新聞。論説兼編集委員の著者はその中軸にいる。防衛問題のエキスパートとして、今の自衛隊を変質させるべきではないと強く主張する。「立憲主義の破壊」をくい止めるためにも多くの人が読むべき一冊だ。
藤田宜永 『女系の総督』 講談社
還暦間近の森川崇徳は出版社の文芸担当役員。以前、喉頭がんが見つかったが、大事に至らずに済んだ。妻と死別したことを除けば、まずまず順調な人生だ。
とはいえ、苦労がないわけではない。それは森川家が完全な女系家族であるためだ。母、姉、妹、3人の娘、そして猫まで。何年つき合っても、その思考と行動は予測不能だ。下手に口を出せば大炎上となる。崇徳の家庭内処世術は「控え目に意見を述べ、その後しばらく黙る」だ。
しかし、黙ってばかりもいられない。母の認知症問題、姉の不倫疑惑、妹の離婚騒動、長女との関係も風雲急を告げている。さらに崇徳自身が恋愛に発展しそうな女性と出会ってしまう。
大きな事件が起きるわけではない。だが、人生は小事の連続だ。女系の総督の選択と決断は世の男たちに知恵と勇気を与えてくれる。
安西水丸 『ちいさな城下町』 文藝春秋
著者は今年3月に71歳で亡くなった、村上春樹作品の挿絵や装丁で知られるイラストレーターだ。『村上朝日堂』シリーズなどの共著もあるが、一人の文筆家としても活躍していた。
本書は『オール読物』に連載していた、全国の城下町を訪ね歩く紀行エッセイ。しかし大阪や姫路などは登場しない。新潟県村上市、長野県飯田市、大分県中津市といった、「一番それらしい雰囲気を残している」十万石以下の城下町が著者の好みだったのだ。
その視点も独特で、城址の楽しみは「縄張り(設計)」にあると言う。多くの人が注目する天守閣を、「あんなものは大工工事」だと歯牙にもかけない。また城下町歩きは、歴史を押さえておくことで楽しさが広がることも教えてくれる。
時おり挿入される幼少時代や学生時代の回想も、著者急逝の今、
味わい深い。
泉 麻人 『昭和40年代ファン手帳』 中公新書ラクレ
敗戦から20年。前年の東京オリンピックを経て昭和40年代に突入した日本は、右肩上がりの高度成長時代を迎える。著者の小学3年生から高校3年生までと重なる日々。本書は少年の目と現在の著者の目という複眼で語られる同時代史だ。
たとえば昭和42年に公開された、内藤洋子主演の映画『君に幸福を センチメンタル・ボーイ』と『怪獣島の決戦ゴジラの息子』。これを見て、「青春歌謡とゴジラ映画は終わった」と感じた少年の判断は正しい。巻末の対談の相手は慶應義塾高校での同級生、石破茂・自民党幹事長である。