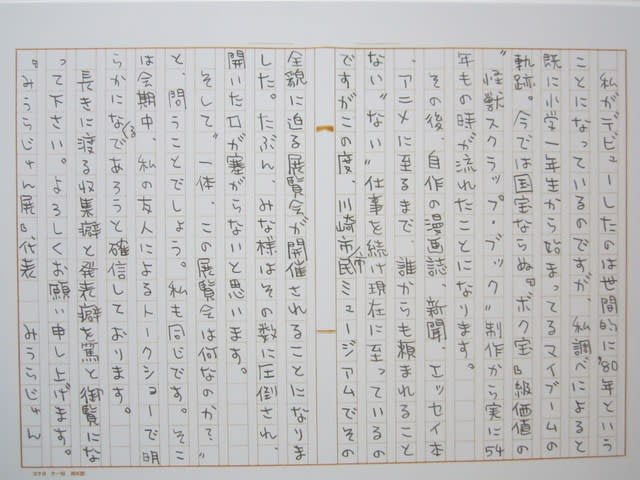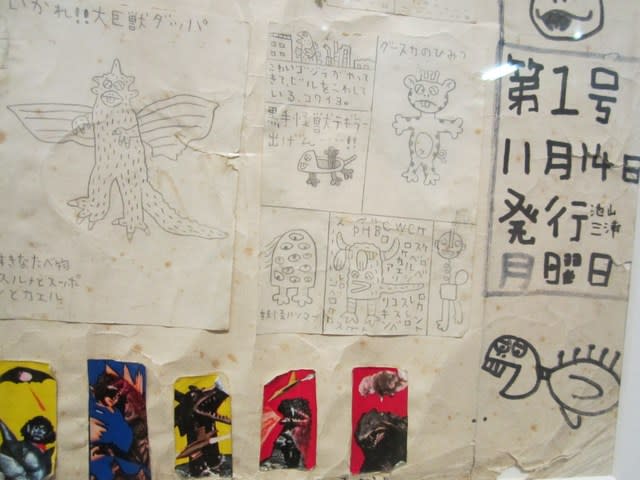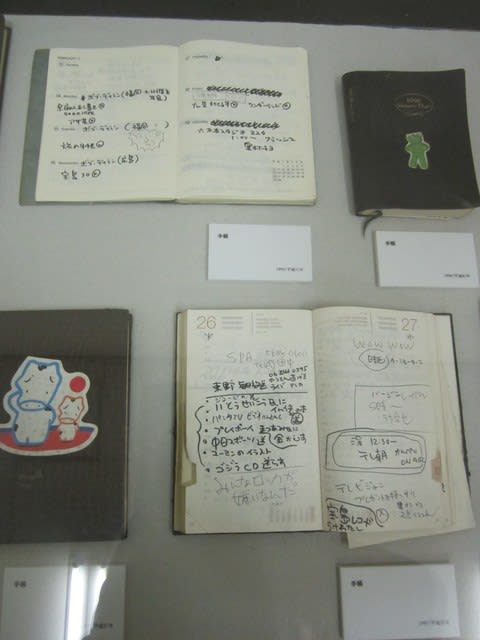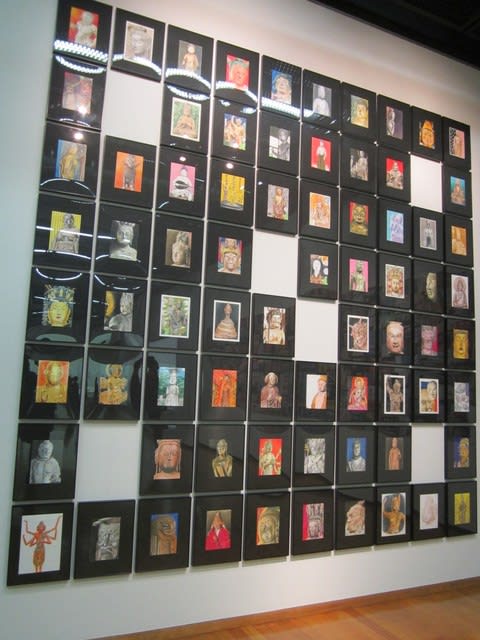しんぶん赤旗のリレーコラム「波動」。
今回は、NHK大河ドラマ「西郷どん」について書きました。
「大河」の王道感あり
昨年のNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」は題材選びに疑問があった。女性が主人公の時代劇は難しいのだ。「八重の桜」(2013年)は新島襄の妻。「花燃ゆ」(15年)が吉田松陰の妹。歴史上の人物を支えた立派な女性たちだが、大河としては不発だった。よく知らない人物が主人公だと見る側の関心は薄い。また本人のエピソードが弱いとダイナミックな物語展開にならないのだ。
その点、今回の「西郷(せご)どん」は安心して見ていられる。知名度は抜群で、幕末・維新の重要人物だ。それでいて西郷の人物像や果たした役割について、誰もが詳しく知っているわけではない。これを機会に学んでみるかという視聴者も多いはずだ。
まず、西郷を演じる鈴木亮平のはつらつとした表情、セリフ、そして動きが気持ちいい。鈴木は朝ドラ「花子とアン」でヒロインの優しい夫役で注目された。しかし鈴木の持ち味はそれだけではない。映画「HK/変態仮面」で見せた、針が振り切れたような全力演技が忘れられない。「西郷どん」でも、気持ちが高揚した際に繰り出す“怒涛の寄り”は肉体派俳優の本領発揮だ。また喜怒哀楽がはっきりした裏表のない西郷の性格も、鈴木はよく体現している。
そしてもう一人、このドラマを熱いものにしているのが、島津斉彬役の渡辺謙である。父親である斉興(鹿賀丈史)に藩主の座から降りるよう迫った時、弾を1発だけ込めたピストルで、なんとロシアンルーレットをやってみせた。頭に銃口を押しつけ、本当に引き金をひく。まさに命を賭けた諫言(かんげん)である。その迫力 は、まさに“世界のケン・ワタナベ”。画面の空気は一気に凝縮し、渡辺がこのドラマの主役に見えたほどだ。
実はこの名場面、林真理子の原作小説「西郷どん!」には書かれていない。脚本の中園ミホのオリジナルだ。こうした力業がズバリと決まるほどドラマは盛り上がる。さらに、かつての大河ドラマ「翔ぶが如く」(1990年)で西郷を演じた、西田敏行を起用したナレーションも成功している。悠揚迫らぬ調子にユーモアが加味されて、見る側をリラックスさせてくれるのだ。全体として大河らしい大河であり、その王道感を楽しめる。
(しんぶん赤旗 2018.02.12)