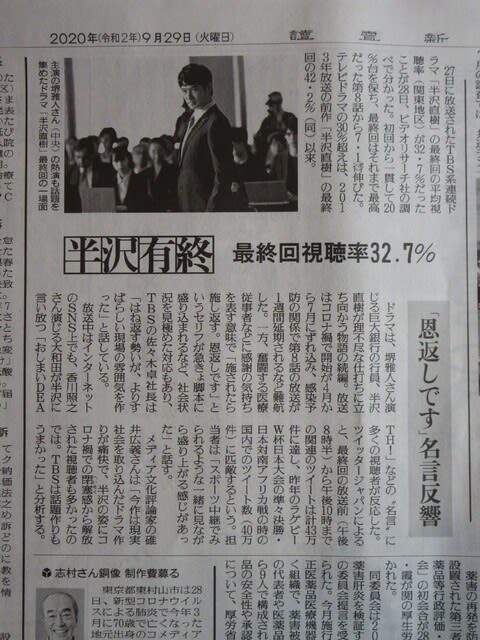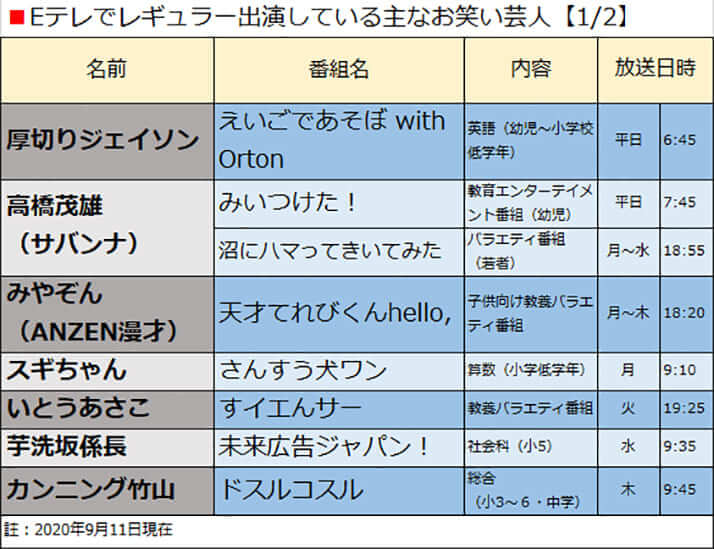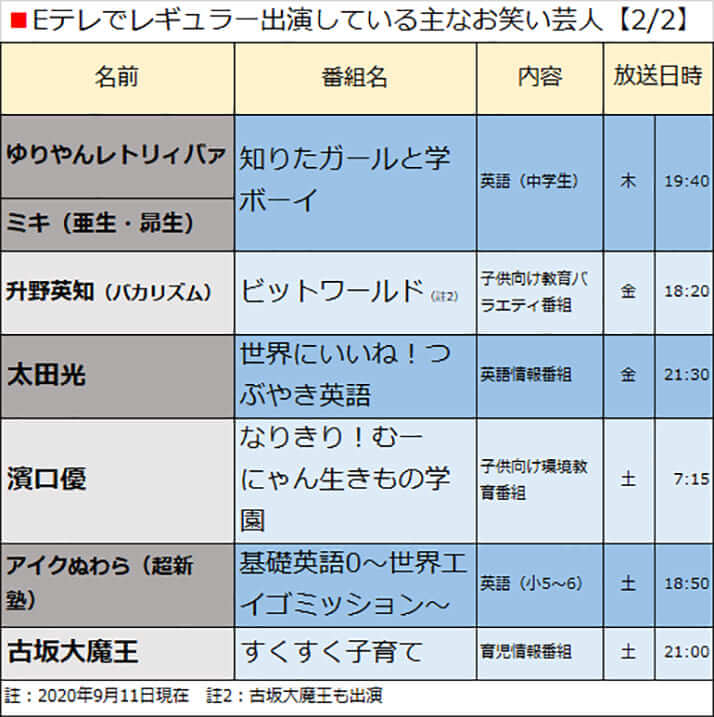財前五郎、吉良上野介、冬彦さん…
名ドラマの名ヒールたち
現在放送中のドラマ『半沢直樹』(TBS系)は、悪役の見本市だ。銀行内の情報を流している裏切り者と判明した紀本平八常務(段田安則)、反発する半沢を徹底的につぶそうとする白井亜希子国土交通大臣(江口のりこ)やその白井の背後にいる“巨悪”の箕部啓治幹事長(柄本明)らの面々が『半沢直樹』の人気を支えている。
「主人公の行動を阻む悪役という障害があり、その立ちはだかる壁を乗り越えていくことで物語が進んでいく。壁が高ければ高いほど、それを乗り越えた時にダイナミズムが生まれてくるという物語論の基本をがっちり抑えているのはもちろん、その壁となる悪役が重厚に描かれている。タイプの違うキャラが次々登場してくるのは、ドラマ作りとして見事だと思います」(メディア文化評論家の碓井広義氏)
しかし何といっても“主役”は大和田暁取締役(香川照之)である。
1作目では、半沢に不正を暴かれ、最終回では頭取の前で屈辱の土下座をさせられたが、今シリーズでは第4話でまさかの“味方”となった。碓井氏は、それゆえに大和田の魅力がいっそう高まったと分析する。
「目的のためなら手段を選ばず容赦しない。しかしそれでいて可愛らしさがあり、人間味がより深まった。単なる私利私欲だけでなく、大和田自身も葛藤を抱えている。そうしたところもしっかりと描かれているので、ドラマに彩りが加わっている」
いい人のイメージを覆した
『半沢直樹』はドラマファンの間で「現代版時代劇」とも評されるが、古くから時代劇に悪役は欠かせない。
「なんといっても何度もドラマ化されてきた『忠臣蔵』の吉良上野介でしょう。特に1982年のNHK大河ドラマ『峠の群像』の吉良(伊丹十三)は見事でした」
そう話すのは、芸能リポーターの石川敏男氏だ。
朝廷勅使の接待役を命じられた浅野内匠頭(隆大介)が、藩財政が火の車の中、必死で費用を工面して準備を整えたところで、吉良が『なぜこのような地味なものを』と一喝する場面をはじめ、伊丹の悪人演技が光った。
「伊丹さんの冷淡ないびりぶりに、視聴者は毎回腸が煮えくりかえったはず。あの目つき、嫌味たらしい言動、憎々しさでは歴代最高でしょう」(石川氏)
1970~1980年代には社会派ドラマも脚光を浴びた。
その金字塔ともいえる『白い巨塔』(1978年・フジテレビ系)は、主役の財前五郎(田宮二郎)自らが悪役という設定が強烈なインパクトを残した。
天才外科医・財前は、出世のためには手段を選ばないダークヒーローとして描かれている。
「財前とは対照的な里見(山本學)と対立するシーンで財前が『教授になるためだったら人殺しだってする』と鋭い眼光で言い放った場面は、鬼気迫るものがあった」(同前)
1980年代の社会派ドラマに登場する悪役として、コラムニストの吉田潮氏が挙げるのは、『少女に何が起ったか』(1985年・TBS系)の川村刑事(石立鉄男)だ。
川村刑事は、使用人として働きながらピアニストを目指す主人公の野川雪(小泉今日子)に執拗な嫌がらせをする。
「いつも深夜12時に現われては、『お前は薄汚ねえシンデレラだ!』などとキョンキョンを罵倒するイヤミな役。
最後には雪と和解しますが、人格否定にセクハラ、言葉の暴力と、生理的嫌悪を催すほどの名悪役ぶりでした。石立は『パパと呼ばないで』(1972年・日本テレビ系)などで築いてきたコミカルな“いい人”のイメージを、この役で見事に覆しました」(吉田氏)
マザコン冬彦さん
1990年代に社会現象を巻き起こした悪役といえば、(1992年・TBS系)の冬彦さん(佐野史郎)だろう。
主人公の美和(賀来千香子)はエリート銀行マンの桂田冬彦と結婚。しかし、七三分けに銀縁メガネの冬彦は、とんでもないマザコンだった。
結婚後、一度もセックスしようとしない冬彦。ある夜、美和が意を決して冬彦のベッドに入ろうとするも、「疲れてる、おやすみ」といって寝ようとする。
「美和が思わず『普通の夫婦なら愛し合うのが当然でしょ』と言うと、冬彦は『淫乱』となじる。その後、大切にしていた蝶の標本をメスで切り刻むシーンには、背筋が寒くなりました」(石川氏)
SMクラブに連れていかれてハマッてしまった冬彦が「君に喜んでもらおうと思って」と、SMビデオを見せ、レザーの拘束衣とハイヒールを渡すなど、衝撃的なシーンが毎回のように展開。
「美和が離婚を決意するのも当然ですが、冬彦本人に悪気はなくて、とにかく一途。だからこそ余計に怖かった」(同前)
また1990年代には野島伸司脚本のドラマが印象に残る悪役を生み出した。
『高校教師』(1993年・TBS系)で、教え子をレイプしたうえビデオを隠し撮りした、英語教師の藤村知樹(京本政樹)。
同じく学校を舞台にした『人間・失格~たとえばぼくが死んだら』(1994年・TBS系)には、堂本剛が演じる生徒を孤立させ、自殺に追い込む社会科教師・新見悦男(加勢大周)が登場する。
「野島作品には、“実はいい人だった”という救いがなく、本当に嫌われる悪役がいた。政治家や警察の上層部といった“巨悪”ではなく、身近なところにいる悪を最大化させる手法が上手かった」(テレビ解説者の木村隆志氏)
近年のドラマでは、『半沢直樹』の大和田をはじめ、どこか“憎めない悪役”が増えている。木村氏がそうしたタイプの代表として挙げたのは、『ドクターX~外科医・大門未知子~』(2012年・テレビ朝日系)に登場する東帝大学病院病院長の蛭間重勝(西田敏行)だ。
「温和そうな顔をして、裏切り者はバッサリと切り捨てる冷血漢。主人公・大門未知子(米倉涼子)に積年の恨みを抱いているが、いつも“返り討ち”にされてしまうのがお決まりのパターン。
はじめは憎らしかったのに、“ヘタレ”な面があるから愛されキャラになっていく。こうした描き方の変化は、シリーズものならではの面白さです」(木村氏)
石川氏が“憎めない悪役”として挙げるのは、『下町ロケット』(2015年・TBS系)の水原重治(木下ほうか)だ。
「イヤミな役、ヒール役としてお茶の間の人気者である木下さんですが、大企業・帝国重工の本部長・水原役では、冷徹に人を切り捨てる一方、社長には頭が上がらない人間味がうまく表現されていた」(石川氏)
木下ほうかが振り返る。
「悪役の場合、台詞がきつく、強く響きがちなのでなるべく過剰にならないように細心の注意を払いました。
相手を罵倒する台詞は、表情と態度は抑えめにしても伝わるので、表現を最小限にする。答えを出しすぎずに、視聴者に解釈を委ねるくらいのほうが悪役の不気味さが伝わるんです。
僕なんか実際に悪い人、怖い人だと思われることも多く、街中で遠くから怯えた目で見られることもありますが、それは自分の演じ方が正しかったという裏返しでもあると思う」
(週刊ポスト 2020年9月18・25日号)