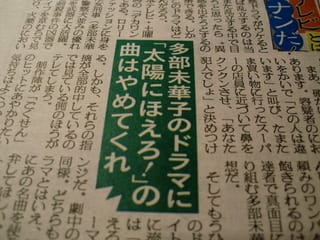産経新聞の「金曜討論」に、プロ野球中継についての発言が掲載されました。
カップリングは漫画家の黒鉄ヒロシさん。
以下は、私の発言部分です。
プロ野球のテレビ中継
プロ野球は今年もキャンプが始まる季節を迎える。ひいき球団の活躍を楽しみにしているファンも多いだろうが、テレビ中継の視聴率は低迷が続いている。昨年は日本シリーズ「中日-ロッテ」(全7戦)の第1、2、5戦が地上波で全国中継されない異例の事態にもなった。
プロ野球中継は今後どのように変わり、プロ野球が国民的スポーツとして愛され続けるには何が求められているのか。上智大学の碓井広義教授と漫画家の黒鉄ヒロシ氏に見解を聞いた。(三宅陽子)
地デジ化が追い風に
--昨年、日本シリーズが一部、地上波で全国中継されなかった
「プロ野球中継は大きな転換期を迎えている。視聴率は低迷しており、昨年は視聴率が1桁台となる試合が相次ぎ、5月18日『日本ハム×巨人戦』(テレビ朝日)4.1%、7月1日『広島×巨人戦』(TBS)3.4%、6月1日『ロッテ×巨人戦』(テレビ東京)3.1%=数値はいずれもビデオリサーチ調べ、関東地区=だった。広告収入を経営基盤とする民放各社からすれば、頭を抱える数字だろう。普通の番組なら即打ち切りでもおかしくない。日本シリーズといえどもこれまでのようにゴールデンタイム(午後7~10時)で放送していいのか、そんな疑念が働いたのではないか」
--視聴率低迷の背景は
「日本中が巨人戦に熱中した時代は終わった。テレビが一家に1台だったころはチャンネルを決めるのはおやじの特権だったが、今は子供たちは好きな番組を自分の部屋で見る。好きな球団も巨人一色ではない。有力選手のメジャーリーグ移籍も進んだ。こうしたさまざまな要素が重なり合ってプロ野球中継の視聴率が下がり、放送枠が削られ、夜7時から試合を観戦する視聴習慣も崩れていった。“デフレ・スパイラル”(連鎖的な悪循環)が起きたという印象だ」
○地上波からBSへ
--中継は減っていくのか
「プロ野球は地上波で商品価値を落としたが、例えば、北海道では日本ハム戦が、名古屋では中日戦の視聴率が非常に高い。今後、全国中継は視聴率が取れる中継に限られ、ローカル局が地元球団の動向を伝えていくことになるのではないか」
「BS(衛星放送)への移行も加速するだろう。地上波のプロ野球中継は基本的に夜7~9時だったが、必ずしも最適とはいえなかった。BSは基本的には初めから終わりまで試合を中継できる。BSデジタル受信機が内蔵された地デジテレビの普及も進み、地上波を見る感覚でBSにチャンネルを合わせる環境が整いつつあることも追い風となるはずだ」
○地方局には有力番組
--昨年の日本シリーズでは全国中継されない日程の“空白”をローカル局が埋めた。一方で、午後9時からはキー局と同じ放送が求められるなど制約もあった
「キー局の系列に入っているローカル局は、番組編成に縛りを受ける。予定している番組を変更して独自編成を組むのはなかなか難しいが、プロ野球中継がローカル局の有力コンテンツに育てば、経営強化につながる。キー局からの自立に役立つとなれば、柔軟な番組編成も増えてくるのではないか」
(産経新聞 2011.01.28)