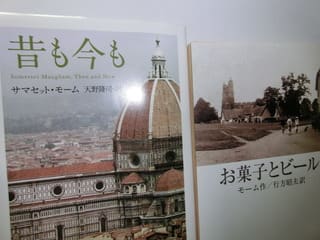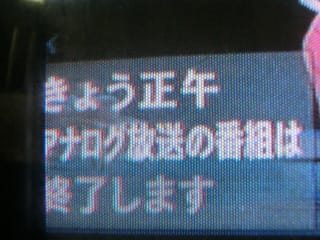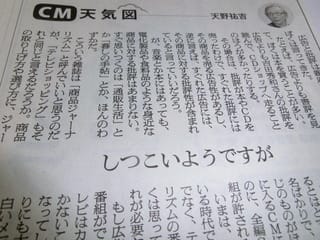本日、オープンキャンパス「体験授業」に参加して下さった高校生の皆さん、そして父母の皆さん、おつかれさまでした。
昨年にも増して多くの参加希望者が集まってくださいました。
関東はもちろん、岩手、富山、長野、静岡、愛知、岐阜、広島などからも。
感謝します。
ただ、スタジオに入るキャパのこともあり、定員100名で2回の授業、つまり200名しか参加してもらえませんでした。
整理券配布の段階で、すぐに満杯となり、たくさんの方をお断りすることになりました。
せっかく来てくださった生徒さんに、“体験”してもらえなかったことは私も残念です。
この場を借りて、「ごめんなさい」。
来年は、何らかの改善を図りたいと思います。
スタジオに入ってもらった生徒さんたちは、とても熱心に、また積極的に参加してくれました。
こちらは、「ありがとう」です。
みんな、プロンプターに表示されたニュース原稿を読むのが、とても上手で、びっくりしました。
カメラの操作にも楽しそうにトライしてくれました。
少しでも、実習の雰囲気を感じてもらえたのであれば、嬉しいです。
そうそう、嬉しいといえば、参加者の1人が、「ブログ、いつも読んでます」「碓井先生がいらっしゃるので上智の新聞学科を受験します」と言ってくれたこと。
実話ですよ(笑)。
それから、先日、出張講義をさせてもらった鎌倉学園高校から2名が来てくれたことも嬉しかったです。










思えば、私が受験生だった1970年代には、オープンキャンパスなどというイベントはありませんでした。
高校3年の夏休みに、信州から一人で上京し、親戚の家に1泊させてもらい、受験しようと思っていた4つの大学を回っただけです。
いずれの大学も夏休み中だったのでキャンパス内は静かで、のんびりと散歩をしたような”一人見学ツアー”でした。
地方で暮らす高校生だった私にとって、受験雑誌などで見るだけだった大学の構内を実際に歩くのは、結構いい刺激になりました。
志望していた大学のキャンパスに立ってみたことで、何となく雰囲気が気に入ったり、その逆もあったりして(笑)、行きたい大学(第一志望)が入れ替わりました。
何事も、「現地」「現物」というのは、なかなかインパクトがあるんですね。
最終的に受験したのは、このときに訪ねた4校のみでした。
本学は各学部、各学科が基本的に少人数制で、新聞学科も定員は60名と小さな枠です。
受験生にとっては大変かもしれませんが、新聞学科に興味のある諸君は、ぜひチャレンジしてみてください。
配布したメッセージにも書いた通り、来年の春、キャンパスで皆さんに会えるのを楽しみにしています。
もう一度、「おつかれさまでした」。
 (体験授業をサポートしてくれた碓井ゼミ生たち)
(体験授業をサポートしてくれた碓井ゼミ生たち)