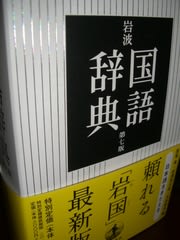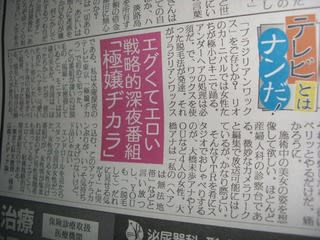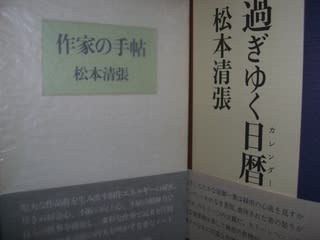本日締切の提出書類(大学は結構多い)があり、晴れてきた日曜日だというのに、昼過ぎまで、ずっとキーボードに向かっていた。
ようやくそれが終わった(WEB提出だ)ので、本来なら、いつもの日曜のように雑誌の書評用の本を読まなくてはならない。
毎週5冊。8年になる。好きな本を読むわけだから楽しい仕事ではあるが、今日のように、提出書類で“出ばな”をくじかれると、普段のペースに乗りきれず、困ってしまう。
それで何をしているかといえば、『岩波国語辞典』を読んでいるのだ。
つまりサボッている。
定期試験前になると、勉強しなくちゃいけないのに、今読まなくてもいい本を読みたくなったり、映画を観たくなったりするようなアレだ。
現実逃避、敵前逃亡(?)である。
で、なんで『岩波国語辞典』かといえば、つい最近、何かの雑誌で長江朗さんが、この辞書のことを書いていた(ような気がする)のだ。
私は、ライターとして、また書評家としての長江さんのファンで、信奉者だから、長江さんが「いい」と言った(書いた)ものは、無条件で後追いしてみる。
昨年の秋に『岩波国語辞典』の最新版が9年ぶりで出たことは知っていたが、クリーム色の表紙の2000年版(第6版)に十分馴染んでいるので、手にしなかったのだ。
しかし、そのどこかの雑誌の、長江さんの文章を目にして、昨日、買ってしまった。
表紙は渋い濃い目のグレーというか深い緑で(どっちだ?)、つるつるしていなくて滑らない(同じか)。
とにかく、しっとり感がいい。
どうやら文字も少し大きくなったのか、老境へと向かう私(すでに初老だね)には、とても見やすい。
こりゃいいや、「さすが長江さんだ」と、何時間もぱらぱらめくってばかりいる。
だが、しかし、ふとこの辞書を収めたケースを見て、あれれ、と思った。
帯に、「頼れる『岩国』最新版」とあるではないか。
「いわくに」って何さ、と不審に思い、よく見ると、「いわこく」とフリガナが振ってある。
岩国=いわこく?
ああ、岩波の国語辞典だから、“いわこく”だ(笑)。
そんな“略”って、私は初耳というか初見というか、知らないフレーズだった。
うーんと、多分ですが、三省堂の『新明解国語辞典』が「新解(しんかい)さん」として親しまれていることに対抗して、もしくはあやかって、編集部内で「通称“いわこく”でいきましょう」、「あ、いいね“いわこく”」てなことになったんじゃないだろうか。
でも、“いわこく”はないでしょう、“いわこく”は(笑)。
何でも略せばいいってもんじゃないよね。
『岩波国語辞典』は『岩波国語辞典』。
「岩国さん」などと呼ばれる必要なんて、ない。
巻頭の「第七版刊行に際して」という序文にいわく。
「この辞書が視野に収めるのは過去百年の(一時的流行ではない)言葉の群れである」。
いいですねえ。自分たちの仕事への矜持、自信がうかがえる。
これだけで読者はついていくというものだ。
というわけで、『岩波国語辞典』は、地デジ、パンデミックなど新たに2600語を加えた総数65000語を収録して、定価3000円のところ、5月末までの特別定価2800円にて、絶賛発売中なのであります(笑)。
さあ、仕事しよっと。