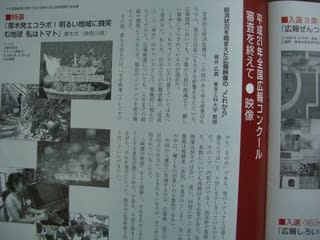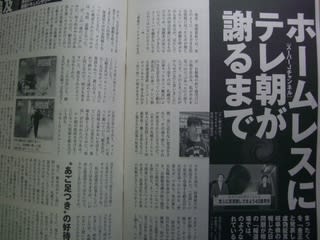新聞・雑誌で、TBSをめぐる記事が目に入る。
なんてったって“名門”(だったはずの)TBSである。
これだけコテンパンに言われえてしまうのも珍しいので、記録しておこう。
まず、昨日発売の『週刊現代』(7/11号)の、6ページにわたる特集記事。
タイトル:
企業研究「TBS その栄光と失速」。
リード:
視聴率最下位転落のピンチ。超一流の人材を抱え、一等地に広大な不動産を持つ民放の雄・TBSが、沈滞感に覆われている。かつての栄光を失ったのは、改革を怠ったためか、官僚主義の弊害か。
小見出し:
・「安上がり」にしたツケ
春の大改編のことなど
・編成部長を更迭
4月編成の責任を負わされ
・分社化で二つの給与体系に
不満も渦巻く
・経営陣支持率は4.7%
社内アンケートの結果
・株主総会で「意外な人事」
これは「経理局長」など“非現場”の方々の取締役昇格の件
・なんでテレビ局に入ったの?
不動産業にからめて
まあ、大体の内容は、上記を見れば分かるはず。
さて、次は、やはり昨日発行の『日刊ゲンダイ』(30日付け)。
みやざき五郎さんのコラム「なっとくテレビ総研」である。
タイトル:
「チャングム」を“調達”するTBSはキー局として恥ずかしくないの?
本文:
何を考えているんだ?TBS。7月改編というから、ようやく「総力報道!THE NEWS」の見直しだと思った。少なくとも小林麻耶キャスターに代わって安住紳一郎アナを持ってくるくらいはやるだろうと。
ところが、どうだ。改編の目玉は午後3時からの “ドラマ再放送枠”。しかも、3時間ぶっ通しである。1本目は「渡る世間は鬼ばかり」だ。次が何と韓琉ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」。そして3本目は「水戸黄門」で、これは「THE NEWS」へと視聴者を導くために5時から放送する。
チャングムだよ、チャングム。驚くより呆れてしまった。だって、そうでしょう。確かに「チャングム」も放送権料さえ払えば誰でも流せる。でも視聴者にすればアレはNHKのものだ。それを「視聴率が見込めるから」とTBSが流すのだ。
地方に行くと、局の系列とは無関係なドラマの再放送を見ることがある。たとえば日本テレビ系列の局なのに、流れているのは東映が作ってテレビ朝日で放送した2時間ものだったりする。権利は制作した会社が持っているから、他の系列でも「購入」可能なのだ。
TBSがやろうとしているのもそれと同じ。いわば他局からの“調達”である。制作力の弱い地方局ならともかく、キー局のやることではない。自分たちで番組を作る意欲も企画もないことを天下にさらすことになる。
3時間枠を「TBSアーカイブス」として、70年代の山田太一作品など名作ドラマを放送するならまだしも、全国のJNN系列各社は「チャングム」で納得なのか。
TBSの企業理念は、<「最強」のコンテンツを創り出す、「最良」のメディアを目指して>。ならば必死で何かを作り出すべきだろう。
(みやざき五郎)
そうかあ、「チャングム」を“調達”(笑)かあ・・・。
これって、かなり“なっとく”な内容なのではあるまいか。
萩元晴彦、村木良彦、吉川正澄といった、今は亡き「TBS出身」の大先輩たちの薫陶を受けた私としては、TBSの現状は、やはり残念。
気持ち的には、「がんばれ、TBS!」なのです。
なんてったって“名門”(だったはずの)TBSである。
これだけコテンパンに言われえてしまうのも珍しいので、記録しておこう。
まず、昨日発売の『週刊現代』(7/11号)の、6ページにわたる特集記事。
タイトル:
企業研究「TBS その栄光と失速」。
リード:
視聴率最下位転落のピンチ。超一流の人材を抱え、一等地に広大な不動産を持つ民放の雄・TBSが、沈滞感に覆われている。かつての栄光を失ったのは、改革を怠ったためか、官僚主義の弊害か。
小見出し:
・「安上がり」にしたツケ
春の大改編のことなど
・編成部長を更迭
4月編成の責任を負わされ
・分社化で二つの給与体系に
不満も渦巻く
・経営陣支持率は4.7%
社内アンケートの結果
・株主総会で「意外な人事」
これは「経理局長」など“非現場”の方々の取締役昇格の件
・なんでテレビ局に入ったの?
不動産業にからめて
まあ、大体の内容は、上記を見れば分かるはず。
さて、次は、やはり昨日発行の『日刊ゲンダイ』(30日付け)。
みやざき五郎さんのコラム「なっとくテレビ総研」である。
タイトル:
「チャングム」を“調達”するTBSはキー局として恥ずかしくないの?
本文:
何を考えているんだ?TBS。7月改編というから、ようやく「総力報道!THE NEWS」の見直しだと思った。少なくとも小林麻耶キャスターに代わって安住紳一郎アナを持ってくるくらいはやるだろうと。
ところが、どうだ。改編の目玉は午後3時からの “ドラマ再放送枠”。しかも、3時間ぶっ通しである。1本目は「渡る世間は鬼ばかり」だ。次が何と韓琉ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」。そして3本目は「水戸黄門」で、これは「THE NEWS」へと視聴者を導くために5時から放送する。
チャングムだよ、チャングム。驚くより呆れてしまった。だって、そうでしょう。確かに「チャングム」も放送権料さえ払えば誰でも流せる。でも視聴者にすればアレはNHKのものだ。それを「視聴率が見込めるから」とTBSが流すのだ。
地方に行くと、局の系列とは無関係なドラマの再放送を見ることがある。たとえば日本テレビ系列の局なのに、流れているのは東映が作ってテレビ朝日で放送した2時間ものだったりする。権利は制作した会社が持っているから、他の系列でも「購入」可能なのだ。
TBSがやろうとしているのもそれと同じ。いわば他局からの“調達”である。制作力の弱い地方局ならともかく、キー局のやることではない。自分たちで番組を作る意欲も企画もないことを天下にさらすことになる。
3時間枠を「TBSアーカイブス」として、70年代の山田太一作品など名作ドラマを放送するならまだしも、全国のJNN系列各社は「チャングム」で納得なのか。
TBSの企業理念は、<「最強」のコンテンツを創り出す、「最良」のメディアを目指して>。ならば必死で何かを作り出すべきだろう。
(みやざき五郎)
そうかあ、「チャングム」を“調達”(笑)かあ・・・。
これって、かなり“なっとく”な内容なのではあるまいか。
萩元晴彦、村木良彦、吉川正澄といった、今は亡き「TBS出身」の大先輩たちの薫陶を受けた私としては、TBSの現状は、やはり残念。
気持ち的には、「がんばれ、TBS!」なのです。