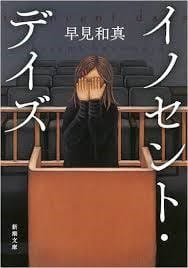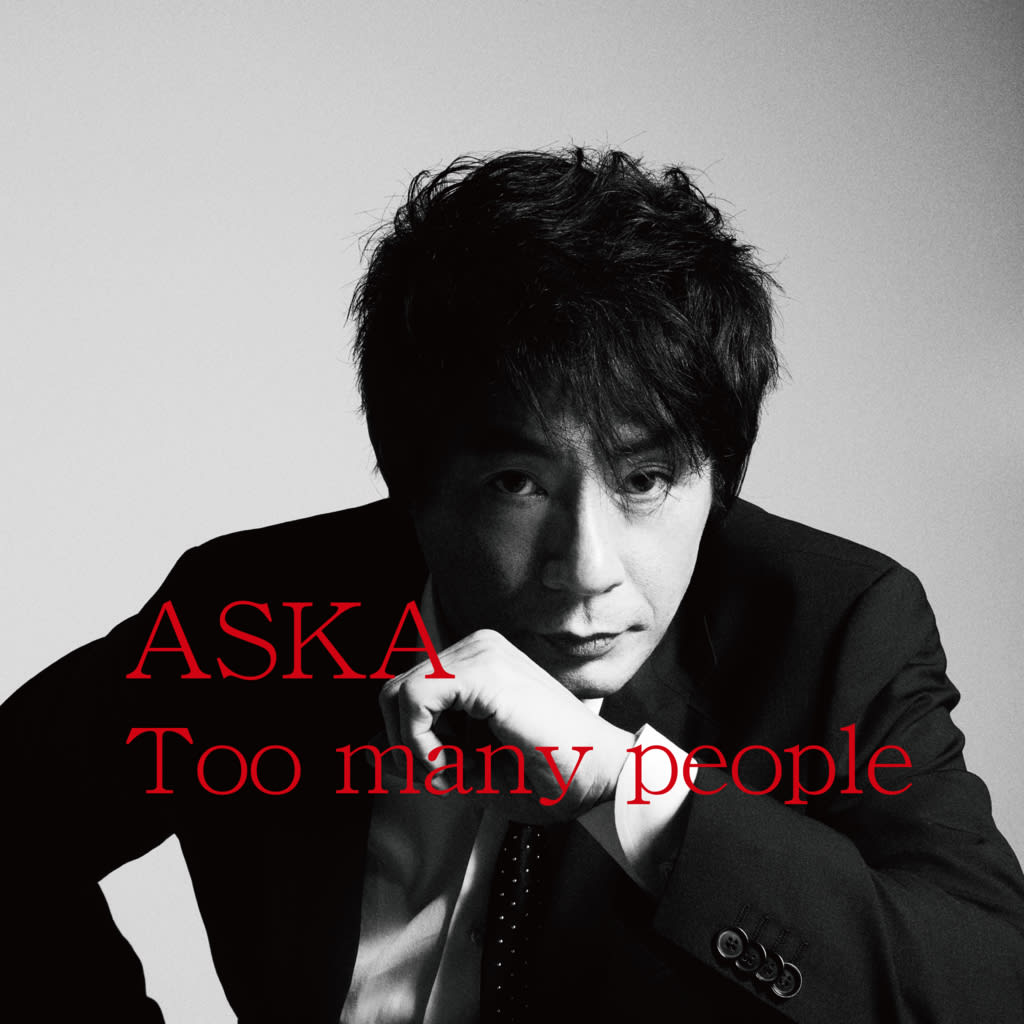その本は、「読んだ後3日寝込みました」という文句とともに
陳列されていました。
想像を絶する孤独。
どんなものなのか興味を持ち、購入したのを覚えています。
結果、読み終えるまでにかなりの時間を要しました。
半年くらいでしょうか?
正直、途中で読むのやめていたので・・・。
物語は、一人の女性「田中幸乃」をめぐり展開していきます。
彼女は、元恋人の家族を放火によって殺害した容疑がかかっており、
死刑を言い渡されます。
しかし彼女はまるであらがうそぶりを見せず、まるでその死刑を
望むかのように、微笑みを見せるのです。
彼女の出征の秘密を知る産科医、義理の姉、中学時代の親友
元恋人の友人、刑務官。
それぞれの視点で語られる内容が章となり構成されています。
とにかく、彼女は世間でいうところの「不幸」を背負って生きてきました。
いや、正しくは、ある時期を境に「不幸」が付きまとうようになったのです。
幼少期。
彼女は幸せの中にいました。
母親以外血がつながっていないとはいえ、温かく見守る家族。
特に義理の姉は、母親譲りの「興奮すると気を失う」という体質を持つ
妹を守る存在として大きかったと思います。
しかし母親の死から、事態は一変します。
母が事故で亡くなると、父親から母親譲りの顔を避けられ、攻められるようになります
本人は傷つく父親を慰めようとするのですが、それが引き金を引いてしまうので。
「お前じゃない、必要なのは母親なのだ」と。
すべての始まりはここだったと思います。
以来、拒絶を恐れるようになりました。
結局、母親を捨てた祖母に引き取られ、愛情も何もない環境に育ち、
中学時代の友人の罪をかぶり少年院で過ごし、
恋人の暴力に耐え続け、
静かにその人生の幕を、ひとり下ろそうとします。
すべて拒絶を恐れるあまり受け入れてきたこと、自分がそうすることによって
相手に見限られないのであればという想いがそうさせます。
ただ、彼女を何とか助けようと動く人たちもいます。
唯一幸せだった幼少期の友達や、元恋人の友人です。
彼らは、唯一といっていいほど、彼女の本音に触れることができた人物です。
その周囲の負を背負いこむ彼女を知り、何とか救い出そうとします。
特に、幼少期を共に過ごした友人は、死刑を宣告された放火事件も
誰かの罪を被ったという真相にたどり着きます。(元恋人の友人の助けもあってですが)
そのため、その真相を明るみに、死刑を免れるように動こうとします。
しかし、結局死刑は実行されます。
彼女は死ぬのです。
ここに向かう最後の章、刑務官の章は少し異質でした。
ほかの章で語られる、とにかく不幸を呼び込む(正しくは不幸を押し付けられる)彼女は
自己主張などほとんどしない人間でした。
求めれば拒絶されてしまうから、必要とされる存在であり続けようとするために
すべてを被ってしまうのです。
しかし、この刑務官の章では、これまでとは違う彼女の姿があります。
死への、確固たる意志。
それがありました。
幼少期の友人が死刑にならぬようあれこれ動く姿に、激しく動揺したり
心動かされたりします。
死を邪魔するものに、抵抗という、強い自己を表すのです。
最後、死刑執行の部屋へ向かう途中、刑務官は最後の希望にすがるように
彼女の中にある生きたいという希望に直接問いかけます。
激しく動揺させれば、「気を失う」。
走すれば死刑を遅らせることができる、その時間でなにか事態が好転するかもしれない。
刑務官は面会に来ていた幼少期の友人の存在を知っていたし、その友人から届いた
手紙を読んでしまっていたため、死刑を免れる期待があることを知っていたためです。
僕も、読みながらなんとか死刑執行を免れ、逆転の無罪、最後の最後で幸せな結末
を迎えることを強く望みながらページを進めました。
しかし、彼女は全身全霊で抗ったのです。
ほんのわずかな読者の期待をも交わし、気を失う一歩手前で、自らの歩みで
死の場所へ歩いてきました。
これまでに見せなかった、強い意志表示。
死ぬために、生きるという、最後の炎のような意思。
彼女の中に幸せだった幼少期のような時の訪れを期待する気持ちは、実は少しばかり
あったように思います。
しかし、その先にまた「見捨てられる」という可能性がある現世よりも
死に安らぎを見出したのです。
最後のその場面は、本当に、死ぬことに執着する情念が、生きていることを
強く浮かび上がらせていました。
まるで光の強さが影の濃さに比例するように。
作者は、ここを一番書きたかったのだろうと、解説にありました。
確かにそう感じます。
彼女にとっては、死ぬことが何よりも幸せだった。
「死ぬことはいけないこと」、そんな当たり前の大前提では語れない価値観が
彼女の中にあったのです。
読み終わって感じたことがあります。
各章で語られる登場人物がほとんどといっていいほど、彼女と向き合っていなかった
ということです。
常に彼女と向き合っていたのは「死」。
後半、ようやく向き合う存在が出てきますが、わずかなすれ違いや、刑務所の中に
いる彼女へ直接かかわることができず、結局彼女は「自分が消えること」としか
人生を通して向き合うことができなかったのだと思います。
期待すれば落胆するし、裏切られることだってある。
生きるとはそういうことで、それ以上に喜びや感動があるから「生きていたい」と
思う気持ちが芽生えていきます。
そのためには、やはり、これはと決めた事や人に対しては心から向き合う覚悟が
必要なのだと思います。
自分にはそれが必要だと感じさせる覚悟が。
ただ一方で、望む死を手に入れた彼女は、幸せだという想いもあります。
欲しいものを得ることができたのですから。
多分ですが、彼女は死を手に入れて本当に安らぎを得たのだと思います。
後悔はしていないと感じるのです。
だって、もう少し生きてみればよかったと感じるのは、僕たち読み手の思考であって
彼女の思考ではないのだから。
彼女が選んだ死を、良いものか悪いものか、何か感じることは良いですが、
批判することはできないのです。
それは、自分の想像の範疇でしか話していないから。
彼女のリアルが置いてけぼりになるから。
先日、読了後に書いたブログ記事で(イノセント・デイズ)
僕はASKAの二度の逮捕に関する一連の報道を目にした時に感じたものとリンクした
と書きました。
それがこの部分なのです。
世の中は、犯した罪に目を向け、多くは非難しました。
二度目もそうです、結局またかという目を向けるのが大半でした。
(某ジャーナリストと情報番組は今思い出しても腹が立ちますね)
もちろん犯した罪は許されるものじゃありません。
非難されることも当然の出来事です。
しかし、その後音楽活動を活発化させると、こんな言葉も見受けられました。
「ちゃんと謝罪すべき」
「裏切られた人の歌は聴けない」
「どれも言い訳じみた曲になっている」
全部その人の価値観が前面に立った言葉です。
ASKAのリアルは置いてけぼりになっています。
いまASKAがどんな気持ちと覚悟をもって音楽活動に臨んでいるのか。
ことあるごとに「形式のように頭を下げるのではなく、真摯に音楽と向き合い
良い音楽を作ることが犯した罪への贖罪となるようにしていきたい」と口にしています。
これを読んでなお、上記のような言葉を口にするのは、ただの批判家だと僕は感じます。
自分の正しさを、大層に掲げて、正義であることを知らしめる。
滑稽で陳腐なドラマに出てくる形ばかりのヒーローのようです。
本人が、犯した過ちを償うために行っていることを、自分や「一般的」という
不透明な物差しで批判して、自分が正しくあることに安心しているのでしょう。
僕が根っからのファンであることも多分にありますが、本人がやろうとしていることを
最後まで見守るくらいの気概は見せましょうよ。
じゃあ、また罪を犯したら裏切られるじゃないかって?
でしょうね。
でも、そうなるかもしれない未来も織り込んで、今の僕の覚悟があります。
話が脱線しすぎましたね。
結局、真実や本心は本人の中にしかないということです。
それをすべてさらけ出すのは簡単なことじゃありません。
親愛なる父親から「お前じゃない」と言われた田中幸乃という少女にとっては、
特にそうだったのではないでしょうか。
北風と太陽。
本心は出させるのではなく、こぼれるくらいがちょど良いのだと思います。
時間はかかるでしょうが、信じて向き合うこと以外それは実現できるもの
ではないかと感じます。
田中幸乃という一人の人間を取り巻く人間が、もう少し強い人間で、
彼女の優しさにつけ込むのではなく、向き合えていたなら。
死を求めず、傷つきながらも生きることに幸せを見出せたかもしれませんね。
これはあくまでも、僕の感じる「幸せ」ですが。
そんなことを感じる小説でした。
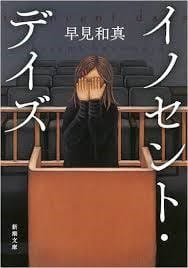
陳列されていました。
想像を絶する孤独。
どんなものなのか興味を持ち、購入したのを覚えています。
結果、読み終えるまでにかなりの時間を要しました。
半年くらいでしょうか?
正直、途中で読むのやめていたので・・・。
物語は、一人の女性「田中幸乃」をめぐり展開していきます。
彼女は、元恋人の家族を放火によって殺害した容疑がかかっており、
死刑を言い渡されます。
しかし彼女はまるであらがうそぶりを見せず、まるでその死刑を
望むかのように、微笑みを見せるのです。
彼女の出征の秘密を知る産科医、義理の姉、中学時代の親友
元恋人の友人、刑務官。
それぞれの視点で語られる内容が章となり構成されています。
とにかく、彼女は世間でいうところの「不幸」を背負って生きてきました。
いや、正しくは、ある時期を境に「不幸」が付きまとうようになったのです。
幼少期。
彼女は幸せの中にいました。
母親以外血がつながっていないとはいえ、温かく見守る家族。
特に義理の姉は、母親譲りの「興奮すると気を失う」という体質を持つ
妹を守る存在として大きかったと思います。
しかし母親の死から、事態は一変します。
母が事故で亡くなると、父親から母親譲りの顔を避けられ、攻められるようになります
本人は傷つく父親を慰めようとするのですが、それが引き金を引いてしまうので。
「お前じゃない、必要なのは母親なのだ」と。
すべての始まりはここだったと思います。
以来、拒絶を恐れるようになりました。
結局、母親を捨てた祖母に引き取られ、愛情も何もない環境に育ち、
中学時代の友人の罪をかぶり少年院で過ごし、
恋人の暴力に耐え続け、
静かにその人生の幕を、ひとり下ろそうとします。
すべて拒絶を恐れるあまり受け入れてきたこと、自分がそうすることによって
相手に見限られないのであればという想いがそうさせます。
ただ、彼女を何とか助けようと動く人たちもいます。
唯一幸せだった幼少期の友達や、元恋人の友人です。
彼らは、唯一といっていいほど、彼女の本音に触れることができた人物です。
その周囲の負を背負いこむ彼女を知り、何とか救い出そうとします。
特に、幼少期を共に過ごした友人は、死刑を宣告された放火事件も
誰かの罪を被ったという真相にたどり着きます。(元恋人の友人の助けもあってですが)
そのため、その真相を明るみに、死刑を免れるように動こうとします。
しかし、結局死刑は実行されます。
彼女は死ぬのです。
ここに向かう最後の章、刑務官の章は少し異質でした。
ほかの章で語られる、とにかく不幸を呼び込む(正しくは不幸を押し付けられる)彼女は
自己主張などほとんどしない人間でした。
求めれば拒絶されてしまうから、必要とされる存在であり続けようとするために
すべてを被ってしまうのです。
しかし、この刑務官の章では、これまでとは違う彼女の姿があります。
死への、確固たる意志。
それがありました。
幼少期の友人が死刑にならぬようあれこれ動く姿に、激しく動揺したり
心動かされたりします。
死を邪魔するものに、抵抗という、強い自己を表すのです。
最後、死刑執行の部屋へ向かう途中、刑務官は最後の希望にすがるように
彼女の中にある生きたいという希望に直接問いかけます。
激しく動揺させれば、「気を失う」。
走すれば死刑を遅らせることができる、その時間でなにか事態が好転するかもしれない。
刑務官は面会に来ていた幼少期の友人の存在を知っていたし、その友人から届いた
手紙を読んでしまっていたため、死刑を免れる期待があることを知っていたためです。
僕も、読みながらなんとか死刑執行を免れ、逆転の無罪、最後の最後で幸せな結末
を迎えることを強く望みながらページを進めました。
しかし、彼女は全身全霊で抗ったのです。
ほんのわずかな読者の期待をも交わし、気を失う一歩手前で、自らの歩みで
死の場所へ歩いてきました。
これまでに見せなかった、強い意志表示。
死ぬために、生きるという、最後の炎のような意思。
彼女の中に幸せだった幼少期のような時の訪れを期待する気持ちは、実は少しばかり
あったように思います。
しかし、その先にまた「見捨てられる」という可能性がある現世よりも
死に安らぎを見出したのです。
最後のその場面は、本当に、死ぬことに執着する情念が、生きていることを
強く浮かび上がらせていました。
まるで光の強さが影の濃さに比例するように。
作者は、ここを一番書きたかったのだろうと、解説にありました。
確かにそう感じます。
彼女にとっては、死ぬことが何よりも幸せだった。
「死ぬことはいけないこと」、そんな当たり前の大前提では語れない価値観が
彼女の中にあったのです。
読み終わって感じたことがあります。
各章で語られる登場人物がほとんどといっていいほど、彼女と向き合っていなかった
ということです。
常に彼女と向き合っていたのは「死」。
後半、ようやく向き合う存在が出てきますが、わずかなすれ違いや、刑務所の中に
いる彼女へ直接かかわることができず、結局彼女は「自分が消えること」としか
人生を通して向き合うことができなかったのだと思います。
期待すれば落胆するし、裏切られることだってある。
生きるとはそういうことで、それ以上に喜びや感動があるから「生きていたい」と
思う気持ちが芽生えていきます。
そのためには、やはり、これはと決めた事や人に対しては心から向き合う覚悟が
必要なのだと思います。
自分にはそれが必要だと感じさせる覚悟が。
ただ一方で、望む死を手に入れた彼女は、幸せだという想いもあります。
欲しいものを得ることができたのですから。
多分ですが、彼女は死を手に入れて本当に安らぎを得たのだと思います。
後悔はしていないと感じるのです。
だって、もう少し生きてみればよかったと感じるのは、僕たち読み手の思考であって
彼女の思考ではないのだから。
彼女が選んだ死を、良いものか悪いものか、何か感じることは良いですが、
批判することはできないのです。
それは、自分の想像の範疇でしか話していないから。
彼女のリアルが置いてけぼりになるから。
先日、読了後に書いたブログ記事で(イノセント・デイズ)
僕はASKAの二度の逮捕に関する一連の報道を目にした時に感じたものとリンクした
と書きました。
それがこの部分なのです。
世の中は、犯した罪に目を向け、多くは非難しました。
二度目もそうです、結局またかという目を向けるのが大半でした。
(某ジャーナリストと情報番組は今思い出しても腹が立ちますね)
もちろん犯した罪は許されるものじゃありません。
非難されることも当然の出来事です。
しかし、その後音楽活動を活発化させると、こんな言葉も見受けられました。
「ちゃんと謝罪すべき」
「裏切られた人の歌は聴けない」
「どれも言い訳じみた曲になっている」
全部その人の価値観が前面に立った言葉です。
ASKAのリアルは置いてけぼりになっています。
いまASKAがどんな気持ちと覚悟をもって音楽活動に臨んでいるのか。
ことあるごとに「形式のように頭を下げるのではなく、真摯に音楽と向き合い
良い音楽を作ることが犯した罪への贖罪となるようにしていきたい」と口にしています。
これを読んでなお、上記のような言葉を口にするのは、ただの批判家だと僕は感じます。
自分の正しさを、大層に掲げて、正義であることを知らしめる。
滑稽で陳腐なドラマに出てくる形ばかりのヒーローのようです。
本人が、犯した過ちを償うために行っていることを、自分や「一般的」という
不透明な物差しで批判して、自分が正しくあることに安心しているのでしょう。
僕が根っからのファンであることも多分にありますが、本人がやろうとしていることを
最後まで見守るくらいの気概は見せましょうよ。
じゃあ、また罪を犯したら裏切られるじゃないかって?
でしょうね。
でも、そうなるかもしれない未来も織り込んで、今の僕の覚悟があります。
話が脱線しすぎましたね。
結局、真実や本心は本人の中にしかないということです。
それをすべてさらけ出すのは簡単なことじゃありません。
親愛なる父親から「お前じゃない」と言われた田中幸乃という少女にとっては、
特にそうだったのではないでしょうか。
北風と太陽。
本心は出させるのではなく、こぼれるくらいがちょど良いのだと思います。
時間はかかるでしょうが、信じて向き合うこと以外それは実現できるもの
ではないかと感じます。
田中幸乃という一人の人間を取り巻く人間が、もう少し強い人間で、
彼女の優しさにつけ込むのではなく、向き合えていたなら。
死を求めず、傷つきながらも生きることに幸せを見出せたかもしれませんね。
これはあくまでも、僕の感じる「幸せ」ですが。
そんなことを感じる小説でした。