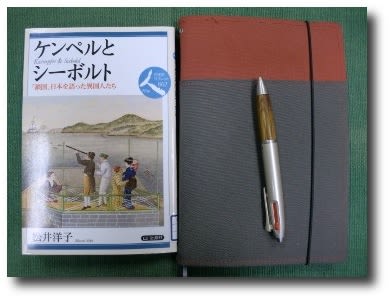山川出版社の日本史リブレットシリーズから、松井洋子著『ケンペルとシーボルト~「鎖国」日本を語った異国人たち』を読みました。長崎の出島は、1周400mほどのトラックを有するグラウンド並の広さであったようで、この中のオランダ商館にやって来た人々を通じて、江戸時代の日本は、辛うじてヨーロッパ諸国とのつながりを保っていたことになります。1690年に来日したケンペルから、1775年のツュンベリー、1779年のティツィング、1823年のシーボルトまで、主な人々の日本との関わりと交流、業績についてまとめている本です。
ケンペルの時代には、あまり理解度の高くなかったオランダ通詞でしたが、ケンペル自身が特別に目を掛けて仕込んだ少年、今村源右衛門英生によって格段にレベルアップし、およそ百年の時を費やして、蘭学という学問の潮流になっていったことを感じます。優秀な若者にありがちな利己主義を典型的に示しているシーボルトの動きも、その流れの中で見れば、やはり大きな役割を果たしたと言わざるを得ません。
中川淳庵や桂川甫周とツュンベリーの交流といえば、『居眠り磐音江戸双紙』シリーズに登場するような軽めの描かれ方がありますし、『JIN~仁~』や吉村昭『ふぉん・しいほるとの娘』に登場するオランダおイネこと楠本イネ、あるいは『長英逃亡』などに見るシーボルト事件や蛮社の獄などの硬派の事件まで、その背景を知る上でたいへん有益な小著でした。
ケンペルの時代には、あまり理解度の高くなかったオランダ通詞でしたが、ケンペル自身が特別に目を掛けて仕込んだ少年、今村源右衛門英生によって格段にレベルアップし、およそ百年の時を費やして、蘭学という学問の潮流になっていったことを感じます。優秀な若者にありがちな利己主義を典型的に示しているシーボルトの動きも、その流れの中で見れば、やはり大きな役割を果たしたと言わざるを得ません。
中川淳庵や桂川甫周とツュンベリーの交流といえば、『居眠り磐音江戸双紙』シリーズに登場するような軽めの描かれ方がありますし、『JIN~仁~』や吉村昭『ふぉん・しいほるとの娘』に登場するオランダおイネこと楠本イネ、あるいは『長英逃亡』などに見るシーボルト事件や蛮社の獄などの硬派の事件まで、その背景を知る上でたいへん有益な小著でした。