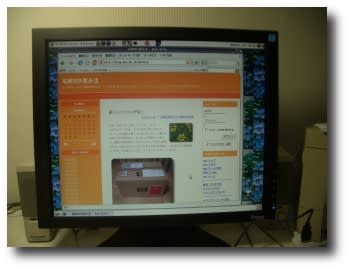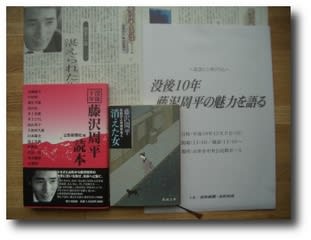昔、高校で、化学と世界史を同学年の同学期に習い始めた頃、原子論を唱えた古代ギリシアの哲学者たちのことを知りました。万物は原子からなり、様々な物の性状は原子の組み合わせに由来する、という考えに、根っからの理系人間として親近感を持つとともに、その学派の実際の文章を読んでみたいと興味を持ちました。
受験勉強を経て入学した大学生活、★二つの岩波文庫で『エピクロス~教説と手紙』を手にしてパラパラとめくったときに目にした文章の断片。当時流行の難解な書物よりも、ずっと心に残りました。現在の某中古書店の最低価格よりも安価な小冊子ですが、本棚の奥から数十年ぶりに見つけ、現在の目で読み返すとき、年を取った分だけ、なお興味深く感じられるものが数多く見つかります。
いわゆるエピキュリアンという言葉とはずいぶん違うようですが、考えさせられる内容の本です。
受験勉強を経て入学した大学生活、★二つの岩波文庫で『エピクロス~教説と手紙』を手にしてパラパラとめくったときに目にした文章の断片。当時流行の難解な書物よりも、ずっと心に残りました。現在の某中古書店の最低価格よりも安価な小冊子ですが、本棚の奥から数十年ぶりに見つけ、現在の目で読み返すとき、年を取った分だけ、なお興味深く感じられるものが数多く見つかります。
「不正を犯しながら発覚されずにいることはむつかしい。そして、発覚されないことについての保証を得ることは不可能である。」 p.89、「断片」7
「なんぴとも、悪を見て、あえてこれを選ぶわけではない。むしろ、それをより大きな悪と比べて善であるかのように思い、これに惑わされて、悪を追い求めるのである。」 p.89、「断片」16
「われわれの生まれたのは、ただ一度きりで、二度と生まれることはできない。これきりで、もはや永遠に存しないものと定められている。ところが、君は、明日の<主人>でさえないのに、喜ばしいことをあとまわしにしている。人生は、延引によって空費され、われわれはみな、ひとりひとり、忙殺のうちに死んでゆくのに。」 p.89、「断片」14
「われわれが必要とするのは、友人からの援助そのことではなくて、むしろ、援助についての信なのである。」 p.92、「断片」34
「質素にも限度がある。その限度を無視する人は、過度のぜいたくのために誤つ人と同じような目にあう。」 p.99、「断片」63
「自分で十分に用が足せるものごとを、神々に請い求めるのは、愚である。」 p.99、「断片」66
「"長い人生の終わりを見よ"と言うは、過去の善きことどもに対する忘恩の言葉である。」 p.101、「断片」75
いわゆるエピキュリアンという言葉とはずいぶん違うようですが、考えさせられる内容の本です。