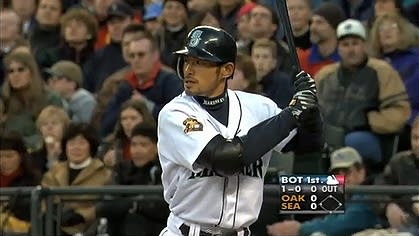SL(蒸気機関車)というのは、どうしてかくも人を興奮させるのだろうか。山田洋次監督の初テレビドキュメンタリー「復活 ~山田洋次・SLを撮る~」が今夜NHKスペシャルで放送された。旧満鉄のSL技術者を父に持つという山田監督が、SLの修復から復活までを記録したドキュメンタリーは、特に“鉄チャン”というわけでもない僕もわくわくさせるものがあった。しかもナレーションは吉永小百合さんという何とも豪華なキャスティング。今回、復活したのは伊勢崎市華蔵寺公園で展示されていたSL、C6120。もう40年近く使われていなかったSLが、職人たちの手でいったん解体され、丹念に磨き上げられて再び組み上げられていく様は、機械にうとい僕でも画面に引き込まれた。そして18世紀から19世紀にかけての産業革命の原動力ともなった蒸気機関という技術の凄さをあらためて思い知らされた気がした。思えば1961年、初めて上京した時に乗った列車は「急行阿蘇」。もちろん蒸気機関車だった。熊本から東京まで約24時間、すすだらけの顔で東京駅のホームに降り立った日のことを想い出した。それが今日では新幹線で東京まで6時間ほどで着いてしまう時代。技術の進歩は目を見張るものがある。でもやっぱりアナログ技術には人間らしさがあって素晴らしい!
















 スタジオジブリの最新作アニメ映画「コクリコ坂から」の試写会に行った。ノスタルジックなストーリーと主題歌として使われている「さよならの夏」に惹かれて観てみたいと思っていた映画だ。何かの記事に今回の作品について宮崎吾朗監督は「ファンタジー性を排した」と述べていたが、僕にとっては十分にファンタジーである。なぜなら、1963年当時の電車や車や街並み、そして人々の暮らしぶりなどが丁寧に描かれており、それはすべて今となっては見ることができないものばかりだ。それを再現してくれているのはファンタジー以外の何ものでもない。「ALWAYS 三丁目の夕日」と同じことである。それから特筆すべきは武部聡志が担当した音楽。「さよならの夏」や「上を向いて歩こう」などを選んだセンスは抜群だ。ここ数年に観た映画音楽の中でも出色だと思う。取り壊される運命の、由緒ある建物が「カルチェラタン」という名前なのはご愛嬌、作者は「神田カルチェラタン闘争」に関わった人なのだろうか。それはさておき、もう一つ身も蓋もないことを言わせてもらえば、実写版を見たい。
スタジオジブリの最新作アニメ映画「コクリコ坂から」の試写会に行った。ノスタルジックなストーリーと主題歌として使われている「さよならの夏」に惹かれて観てみたいと思っていた映画だ。何かの記事に今回の作品について宮崎吾朗監督は「ファンタジー性を排した」と述べていたが、僕にとっては十分にファンタジーである。なぜなら、1963年当時の電車や車や街並み、そして人々の暮らしぶりなどが丁寧に描かれており、それはすべて今となっては見ることができないものばかりだ。それを再現してくれているのはファンタジー以外の何ものでもない。「ALWAYS 三丁目の夕日」と同じことである。それから特筆すべきは武部聡志が担当した音楽。「さよならの夏」や「上を向いて歩こう」などを選んだセンスは抜群だ。ここ数年に観た映画音楽の中でも出色だと思う。取り壊される運命の、由緒ある建物が「カルチェラタン」という名前なのはご愛嬌、作者は「神田カルチェラタン闘争」に関わった人なのだろうか。それはさておき、もう一つ身も蓋もないことを言わせてもらえば、実写版を見たい。
 熊日紙で懐かしい名前を見た。「高倉照幸」西鉄ライオンズ黄金時代の1番バッターで「切り込み隊長」と異名をとった、あの高倉さんである。なんでも熊日紙の「わたしを語る」という連載コラムに寄稿するらしい。1970年に引退以来、これまでほとんど表舞台には出られなかったので、テレビに中西太さんや豊田康光さんなどが出て来られると、いつも高倉さんはどうしておられるのかな、と思っていた。写真を拝見するとすっかり好々爺になられた感じだが、そのはずでもう76歳だそうだ。僕の父が高校野球の審判をやっていた頃、熊本商業で活躍していて、父は生前、「あれはいい選手だった」とよく言っていたのを憶えている。さて、どんな話が聞けるのか楽しみだ。
熊日紙で懐かしい名前を見た。「高倉照幸」西鉄ライオンズ黄金時代の1番バッターで「切り込み隊長」と異名をとった、あの高倉さんである。なんでも熊日紙の「わたしを語る」という連載コラムに寄稿するらしい。1970年に引退以来、これまでほとんど表舞台には出られなかったので、テレビに中西太さんや豊田康光さんなどが出て来られると、いつも高倉さんはどうしておられるのかな、と思っていた。写真を拝見するとすっかり好々爺になられた感じだが、そのはずでもう76歳だそうだ。僕の父が高校野球の審判をやっていた頃、熊本商業で活躍していて、父は生前、「あれはいい選手だった」とよく言っていたのを憶えている。さて、どんな話が聞けるのか楽しみだ。



 NHKが松下奈緒主演で向田邦子の「胡桃の部屋」をやるという。「胡桃の部屋」は短編集「隣の女」の中に収められている一篇。僕は原作は読んでいないのだが、30年ほど前、いしだあゆみ主演のドラマを見た記憶がある。向田さんの実体験をもとにした話というが、内容的には、「父の詫び状」や「向田邦子の恋文」などと重なる部分があったように記憶している。当時のいしだあゆみと言えば、映画では「駅 STATION」や「男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋」など、ドラマでは「阿修羅のごとく」や「北の国から」など女優としてのピークを迎えた時期で、僕も当時最も好きな女優さんだったので、この「胡桃の部屋」も印象に残っている。その後、竹下景子も同じ役をやったらしいが、そちらの方は見ていない。さて、今度の松下奈緒はどうだろうか。一見、いしだあゆみとはかなり印象が異なるので、ちょっと違和感はあるがはたしてどうなることやら。
NHKが松下奈緒主演で向田邦子の「胡桃の部屋」をやるという。「胡桃の部屋」は短編集「隣の女」の中に収められている一篇。僕は原作は読んでいないのだが、30年ほど前、いしだあゆみ主演のドラマを見た記憶がある。向田さんの実体験をもとにした話というが、内容的には、「父の詫び状」や「向田邦子の恋文」などと重なる部分があったように記憶している。当時のいしだあゆみと言えば、映画では「駅 STATION」や「男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋」など、ドラマでは「阿修羅のごとく」や「北の国から」など女優としてのピークを迎えた時期で、僕も当時最も好きな女優さんだったので、この「胡桃の部屋」も印象に残っている。その後、竹下景子も同じ役をやったらしいが、そちらの方は見ていない。さて、今度の松下奈緒はどうだろうか。一見、いしだあゆみとはかなり印象が異なるので、ちょっと違和感はあるがはたしてどうなることやら。

 どこのメディアも報道してくれないのでネットで調べるしかない。今、フランスのリールで行われている「世界ユース陸上」のことだ。万全とはいえないコンディションで、この大会に参加している野林祐実(九州学院)のことが気になる。たしか100mの予選がもう行われたはずだと思ってIAAF(国際陸上競技連盟)のサイトにアクセスしてみる。やはり予選が終わっていた。野林は第8組に出場し、12秒11のタイムで3着。無条件で準決勝に進める2着以内には入れなかったが、3着以下全員のタイムによるプラス8によって救われ準決勝に進出していた。ホッとひと安心。一方のライバル土井杏南(埼玉栄高)はというと、第1組で11秒83と堂々の1位で準決勝に進出していた。野林は予選のタイムでは決勝進出はかなり厳しそうだが、自己ベストに近いタイムを出せば上位入賞も夢ではない。200mもあるので何とか復調のきっかけを掴んでほしい。
どこのメディアも報道してくれないのでネットで調べるしかない。今、フランスのリールで行われている「世界ユース陸上」のことだ。万全とはいえないコンディションで、この大会に参加している野林祐実(九州学院)のことが気になる。たしか100mの予選がもう行われたはずだと思ってIAAF(国際陸上競技連盟)のサイトにアクセスしてみる。やはり予選が終わっていた。野林は第8組に出場し、12秒11のタイムで3着。無条件で準決勝に進める2着以内には入れなかったが、3着以下全員のタイムによるプラス8によって救われ準決勝に進出していた。ホッとひと安心。一方のライバル土井杏南(埼玉栄高)はというと、第1組で11秒83と堂々の1位で準決勝に進出していた。野林は予選のタイムでは決勝進出はかなり厳しそうだが、自己ベストに近いタイムを出せば上位入賞も夢ではない。200mもあるので何とか復調のきっかけを掴んでほしい。

 健康志向の高まりで、市民ランナーの聖地、皇居一周のコースを走る人が急増、事故やトラブルが頻発しているという。だいたい走る時間帯は同じになるため、一周5kmのコースに数千人が殺到する時もあるという。人が多くなればなるほど、マナーに欠けた人も多くなることは容易に想像できる。これは何も皇居一周のランニングに限らない。かつて東京勤務の頃、週に二日は、帰宅途中に中野のスポーツクラブ、TACに立ち寄り、ひと泳ぎして帰っていた。プールにはコースロープが張ってあり、同じコースを往復する場合は右側通行で泳ぐことと決められていた。しかし、泳ぐスピードには個人差があるため、前を泳いでいる人に追いつくことがある。そんな場合、いったん止まって状況を確認し、対向者がいなければ左側を追い越すというのがマナーになっていた。ところが中には1000m泳ぐと決めたら、何がなんでも止まってなるものかとばかり、前を泳いでいる人がいようが、対向者が来ようがお構いなしに人をかき分けて泳ぐ奴もいた。当然、ぶつかって口論になることもあった。日本には欧米のようにスポーツクラブでフィットネスをするという歴史が浅いので、クラブライフのマナーが育っていないのだとよく言われる。皇居一周のランニングは誰でも参加できるが、これも一種のクラブライフ。外国の人たちに笑われないようにしたいものだ。
健康志向の高まりで、市民ランナーの聖地、皇居一周のコースを走る人が急増、事故やトラブルが頻発しているという。だいたい走る時間帯は同じになるため、一周5kmのコースに数千人が殺到する時もあるという。人が多くなればなるほど、マナーに欠けた人も多くなることは容易に想像できる。これは何も皇居一周のランニングに限らない。かつて東京勤務の頃、週に二日は、帰宅途中に中野のスポーツクラブ、TACに立ち寄り、ひと泳ぎして帰っていた。プールにはコースロープが張ってあり、同じコースを往復する場合は右側通行で泳ぐことと決められていた。しかし、泳ぐスピードには個人差があるため、前を泳いでいる人に追いつくことがある。そんな場合、いったん止まって状況を確認し、対向者がいなければ左側を追い越すというのがマナーになっていた。ところが中には1000m泳ぐと決めたら、何がなんでも止まってなるものかとばかり、前を泳いでいる人がいようが、対向者が来ようがお構いなしに人をかき分けて泳ぐ奴もいた。当然、ぶつかって口論になることもあった。日本には欧米のようにスポーツクラブでフィットネスをするという歴史が浅いので、クラブライフのマナーが育っていないのだとよく言われる。皇居一周のランニングは誰でも参加できるが、これも一種のクラブライフ。外国の人たちに笑われないようにしたいものだ。
 熊本名物としてあげられるのは、近年では「馬刺し、からし蓮根、熊本ラーメン、太平燕(タイピーエン)」などである。しかし、この中で歴史的に見て真の熊本名物と呼べるのは「からし蓮根」だけだろう。馬刺しは僕の記憶では、昭和40年代半ばまでは、ごく限られた場所でしか食べることはできなかったし、馬刺しがなぜ熊本名物になったかという加藤清正にまつわる俗説も、どうも後付けのにおいがする。熊本ラーメンは昭和20年代の終わり頃に久留米ラーメンを祖として生まれたもので、広町に「こむらさき」が開店した日のことを憶えている。太平燕に至っては、平成に入ってから新しい熊本名物を作ろうという業界などの働きかけで始まったものだ。これらに比べて「からし蓮根」には400年近い歴史がある。改易された加藤家に代わって肥後の藩主となった細川忠利公(細川忠興、ガラシャの三男)は病弱だったため、健康食として考案されたのが「からし蓮根」で、それを考案したのが細川家の賄方だった森平五郎である。森家は現在も新町に老舗の「森からし蓮根」として続いている。実は僕の高校の同級生に森家の息子がいて、一時、同じ職場で働いたこともあった。懐かしい想い出だ。
熊本名物としてあげられるのは、近年では「馬刺し、からし蓮根、熊本ラーメン、太平燕(タイピーエン)」などである。しかし、この中で歴史的に見て真の熊本名物と呼べるのは「からし蓮根」だけだろう。馬刺しは僕の記憶では、昭和40年代半ばまでは、ごく限られた場所でしか食べることはできなかったし、馬刺しがなぜ熊本名物になったかという加藤清正にまつわる俗説も、どうも後付けのにおいがする。熊本ラーメンは昭和20年代の終わり頃に久留米ラーメンを祖として生まれたもので、広町に「こむらさき」が開店した日のことを憶えている。太平燕に至っては、平成に入ってから新しい熊本名物を作ろうという業界などの働きかけで始まったものだ。これらに比べて「からし蓮根」には400年近い歴史がある。改易された加藤家に代わって肥後の藩主となった細川忠利公(細川忠興、ガラシャの三男)は病弱だったため、健康食として考案されたのが「からし蓮根」で、それを考案したのが細川家の賄方だった森平五郎である。森家は現在も新町に老舗の「森からし蓮根」として続いている。実は僕の高校の同級生に森家の息子がいて、一時、同じ職場で働いたこともあった。懐かしい想い出だ。