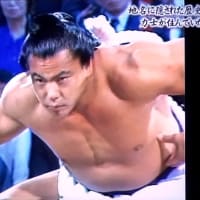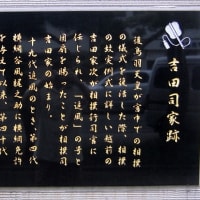昨日、子飼へ車の給油に行った帰り、泰勝寺跡の前を通ったのでちょっと立ち寄った。昨年、一時干上がった池の現状が気になっていたからだ。満水まではいかないが4分の3くらいまで水位が戻っていて安心した。
2016~2017年に開催された夏目漱石記念年事業の一環として出版された「漱石の記憶」(熊日出版)の中に、中村青史先生(元熊大教授、2023年8月没)の「草枕 鏡が池のモデル」という小論が掲載されていて、漱石の「草枕」に登場する「鏡が池」は泰勝寺の池がモデルではないかと推論されている。
「草枕」の「鏡が池」のくだりでは、画工と那美さんのやりとりの後、「鏡が池」の描写がある。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「あなたはどこへいらしったんです。和尚が聞いていましたぜ、また一人散歩かって」
「ええ鏡の池の方を廻って来ました」
 「その鏡の池へ、わたしも行きたいんだが……」
「その鏡の池へ、わたしも行きたいんだが……」
「行って御覧なさい」
「画にかくに好い所ですか」
「身を投げるに好い所です」
「身はまだなかなか投げないつもりです」
「私は近々投げるかも知れません」
余りに女としては思い切った冗談だから、余はふと顔を上げた。女は存外たしかである。
「私が身を投げて浮いているところを――苦しんで浮いてるところじゃないんです――やすやすと往生して浮いているところを――奇麗な画にかいて下さい」
「え?」
「驚ろいた、驚ろいた、驚ろいたでしょう」
女はすらりと立ち上る。三歩にして尽くる部屋の入口を出るとき、顧りみてにこりと笑った。茫然たる事多時。
鏡が池へ来て見る。観海寺の裏道の、杉の間から谷へ降りて、向うの山へ登らぬうちに、路は二股に岐かれて、おのずから鏡が池の周囲となる。池の縁には熊笹が多い。ある所は、左右から生い重なって、ほとんど音を立てずには通れない。木の間から見ると、池の水は見えるが、どこで始まって、どこで終るか一応廻った上でないと見当がつかぬ。あるいて見ると存外小さい。三丁ほどよりあるまい。ただ非常に不規則な形で、ところどころに岩が自然のまま水際に横たわっている。縁の高さも、池の形の名状しがたいように、波を打って、色々な起伏を不規則に連ねている。
池をめぐりては雑木が多い。何百本あるか勘定がし切れぬ。中には、まだ春の芽を吹いておらんのがある。割合に枝の繁まない所は、依然として、うららかな春の日を受けて、萌え出でた下草さえある。壺菫(つぼすみれ)の淡き影が、ちらりちらりとその間に見える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中村先生曰く「吾輩は猫である」の舞台となっている立田山麓の、寺田寅彦の下宿先や泰勝寺や五高などの描写から、漱石が泰勝寺の池を見ていたことは間違いなく、「吾輩は猫である」の「鵜の沼」や「草枕」の「鏡が池」のイメージは泰勝寺の池がモデルになったのではないか。実際に泰勝寺の現地で「鏡が池」の描写を思い浮かべながら池の周囲を見て回って確信されたようだ。一般的に「鏡が池」のモデルは小天の庭池とされているが、そこがあまりにも小説のイメージと異なることに疑念を抱いておられたようだ。

水位を回復しつつある泰勝寺の池

満水だった頃の泰勝寺の池

山本丘人「草枕絵巻」より「水の上のオフェリア(美しき屍)」
2016~2017年に開催された夏目漱石記念年事業の一環として出版された「漱石の記憶」(熊日出版)の中に、中村青史先生(元熊大教授、2023年8月没)の「草枕 鏡が池のモデル」という小論が掲載されていて、漱石の「草枕」に登場する「鏡が池」は泰勝寺の池がモデルではないかと推論されている。
「草枕」の「鏡が池」のくだりでは、画工と那美さんのやりとりの後、「鏡が池」の描写がある。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「あなたはどこへいらしったんです。和尚が聞いていましたぜ、また一人散歩かって」
「ええ鏡の池の方を廻って来ました」
 「その鏡の池へ、わたしも行きたいんだが……」
「その鏡の池へ、わたしも行きたいんだが……」「行って御覧なさい」
「画にかくに好い所ですか」
「身を投げるに好い所です」
「身はまだなかなか投げないつもりです」
「私は近々投げるかも知れません」
余りに女としては思い切った冗談だから、余はふと顔を上げた。女は存外たしかである。
「私が身を投げて浮いているところを――苦しんで浮いてるところじゃないんです――やすやすと往生して浮いているところを――奇麗な画にかいて下さい」
「え?」
「驚ろいた、驚ろいた、驚ろいたでしょう」
女はすらりと立ち上る。三歩にして尽くる部屋の入口を出るとき、顧りみてにこりと笑った。茫然たる事多時。
鏡が池へ来て見る。観海寺の裏道の、杉の間から谷へ降りて、向うの山へ登らぬうちに、路は二股に岐かれて、おのずから鏡が池の周囲となる。池の縁には熊笹が多い。ある所は、左右から生い重なって、ほとんど音を立てずには通れない。木の間から見ると、池の水は見えるが、どこで始まって、どこで終るか一応廻った上でないと見当がつかぬ。あるいて見ると存外小さい。三丁ほどよりあるまい。ただ非常に不規則な形で、ところどころに岩が自然のまま水際に横たわっている。縁の高さも、池の形の名状しがたいように、波を打って、色々な起伏を不規則に連ねている。
池をめぐりては雑木が多い。何百本あるか勘定がし切れぬ。中には、まだ春の芽を吹いておらんのがある。割合に枝の繁まない所は、依然として、うららかな春の日を受けて、萌え出でた下草さえある。壺菫(つぼすみれ)の淡き影が、ちらりちらりとその間に見える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中村先生曰く「吾輩は猫である」の舞台となっている立田山麓の、寺田寅彦の下宿先や泰勝寺や五高などの描写から、漱石が泰勝寺の池を見ていたことは間違いなく、「吾輩は猫である」の「鵜の沼」や「草枕」の「鏡が池」のイメージは泰勝寺の池がモデルになったのではないか。実際に泰勝寺の現地で「鏡が池」の描写を思い浮かべながら池の周囲を見て回って確信されたようだ。一般的に「鏡が池」のモデルは小天の庭池とされているが、そこがあまりにも小説のイメージと異なることに疑念を抱いておられたようだ。

水位を回復しつつある泰勝寺の池

満水だった頃の泰勝寺の池

山本丘人「草枕絵巻」より「水の上のオフェリア(美しき屍)」