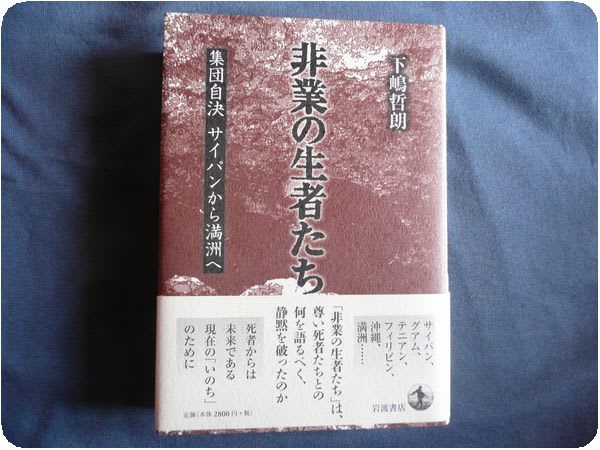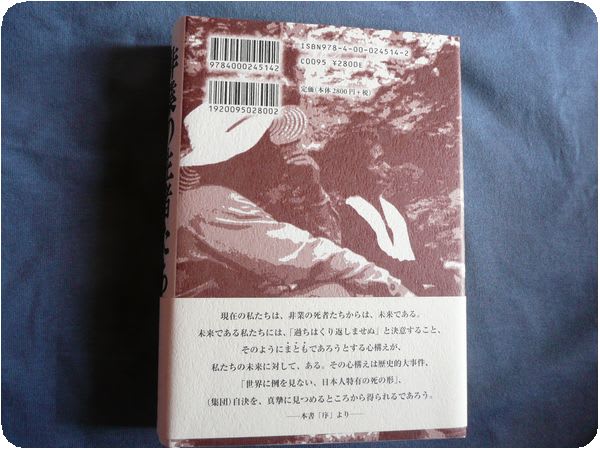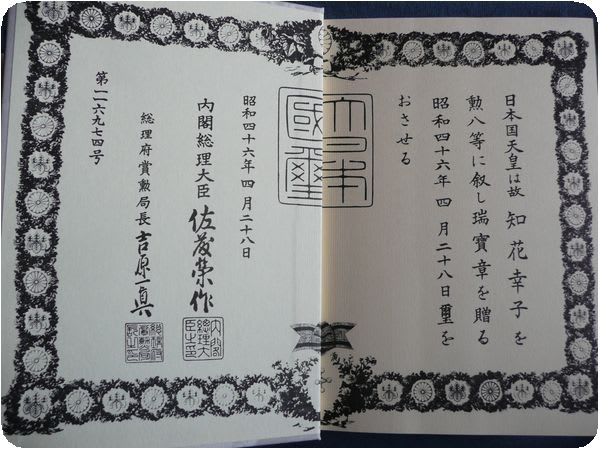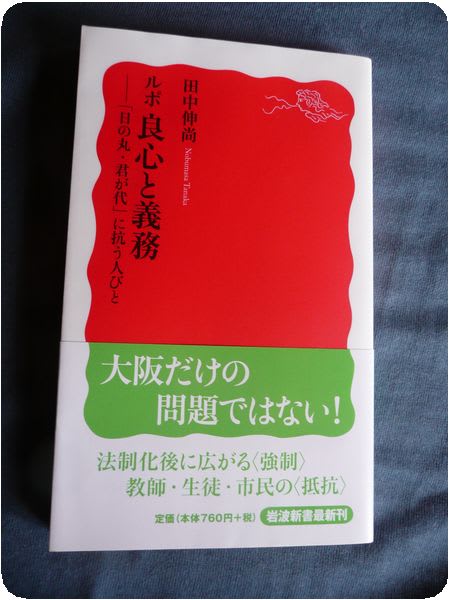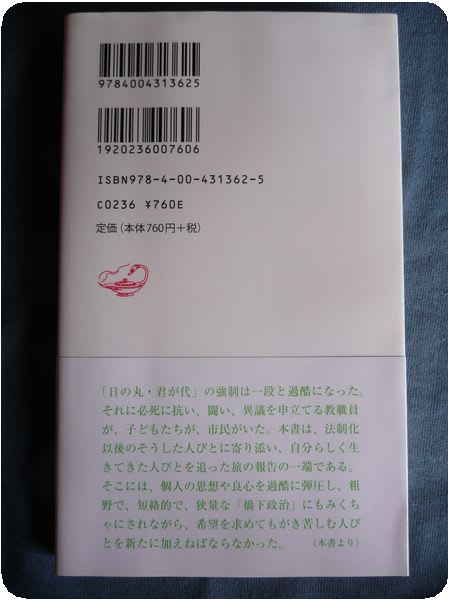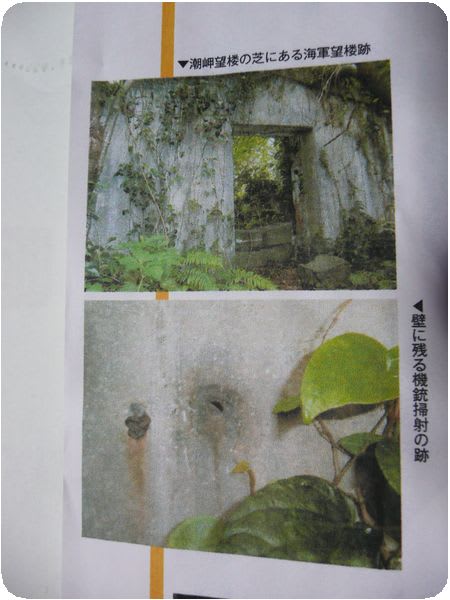8時半ごろに四条畷駅に到着し、9時半の開館には1時間もあるので先に四条畷神社に行ったのですが、あれこれ見たり迷ったりしているうちに、歴史民俗資料館に着いたのは開館時間を5分ほどオーバーしてしまいました。なんと入場は無料、賃労働の収入が無い私にとっては嬉しい限りですが、電車賃の往復で1120円支払っています。目的の資料館の見学にお金が要らないのに、手段になる交通費にお金がかかるなんて本末転倒している気分になります。まぁ、他にも見物しているので1120円は安いと思っておくことにしましょう。

入場すると先客が二人、館長らしき人が二人を案内し、いろんな説明をしていました。もう少し待ってくれれば私も説明に加えてもらえたのに、独りで見て回るのは得策ではありません。おまけにそう広くも無いので館長や二人の見学者の質問などが耳に障り、気が散るのです。

讃良郡条里遺跡と呼んではいるものの、今回はこの辺りでは見られなかった弥生前期の水田跡が発掘されたことがメイン、条里制が敷かれた奈良時代とは1000年くらいの差があるので、条里遺跡と名付けるのは如何なものかと思ったりもするのです。前にも述べたように上町台地と生駒山系に挟まれた北河内一帯は太古から海であり、縄文早期~中期にかけては河内湾、縄文晩期~弥生中期は河内潟、弥生後期~古墳中期は河内湖と変化してきたことが明らかになっています。
当に弥生初期の稲作は目の前に河内潟があった時代であり、海へと幾筋もの川が流れ込んでいたのでしょう。当時の稲作は海抜1m以内の水準で行われ、人々は少しだけ高い所に住んでいたようです。
古墳時代に入ってからですが、海で繋がっていたのですからこの地に中国大陸から馬が輸入されたのも頷けますし、その馬を運搬した船の廃材を使って、井戸を作ったりもしていた跡がありました。馬を飼育するには多量の塩が要るらしく、製塩に使った土器が見つかっていることも海辺であった証です。

資料館に入ってすぐに渡されたパンフレット、写真をふんだんに使った上質の紙で30ページもあり、資料代としても何らかの金額を請求されそうですが、市立の資料館ですからその公共性を如何なく発揮していると思いますね。発掘順とすれば逆なのでしょうが、弥生前期から室町時代の発掘物を紹介してあり、なかなか貴重な一冊です。

おまけに海獣葡萄鏡のレプリカまでくれました。オリンピックの銅メダルではありませんよ、発掘時に出た粘土で作ってありますから、鏡としては使用できるものではありません。
私は四条畷市民ではありませんが、明治22年の町村制のより、南野・中野・岡山・砂・清瀧・逢坂・蔀屋の7ヶ村を甲可郷の名から甲可村に、明治29年には北河内郡甲可村に、昭和7年に高名になった四条畷神社の名を取って四条畷村に改称、36年に現在長男が住んでいる田原村を合併し、45年に市制が敷かれたことに興味が惹かれます。明治の話とは言え、甲可村などという村があったことなど知りませんし、今はその名跡すらありません。

イオンが出店するのを契機としてこの遺跡を再調査したようなのですが、金の亡者如きに土地を提供することなく、貴重な遺跡を是非保存しておいてほしいものです。独占資本主義型再開発と歴史の保存は相容れないものなのかも知れません。