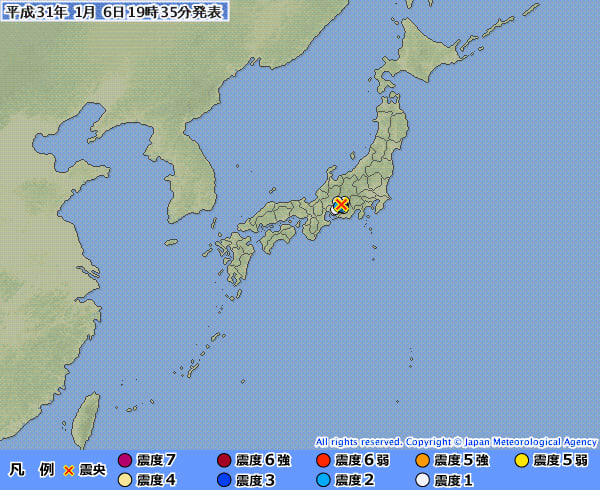(東京・新宿のビル群)

1月4日、日本は平成30年間の大部分をバブル崩壊後の負の遺産への対応に追われ、低賃金の若者を生み出し、それが少子化という現在の社会的な構造問題を作り出したと、三菱総合研究所・チーフエコノミストの武田洋子氏は指摘する。写真は東京・新宿のビル群。2016年3月撮影(2019年 ロイター/Issei Kato)
① ""オピニオン:平成に積み残した3つの宿題、技術革新が新時代のカギ=武田洋子氏""
2019年1月4日 / 15:02 / 2日前
武田洋子 三菱総合研究所 チーフエコノミスト
[東京 4日] -
日本は平成30年間の大部分をバブル崩壊後の負の遺産への対応に追われ、低賃金の若者を生み出し、それが少子化という現在の社会的な構造問題を作り出したと、三菱総合研究所・チーフエコノミストの武田洋子氏は指摘する。
負の遺産の処理は進み、デフレではない状況まで経済は回復したものの、次の時代には持続可能な財政と社会保障制度の構築、国際競争力の回復という、未来に対して責任ある政策に取り組む必要があると話す。日本社会が人口減少に直面する中で、こうした問題を解決するには技術革新が欠かせず、労働市場の改革がカギになると分析する
同氏の見解は以下の通り。
🌸 <「就職氷河期」という人的資源の損失>
平成の30年間は日本にとって試練の時代で、大きく2つの特徴がある。
1つは1991年のバブル経済崩壊がもたらした負の遺産の処理に、多大な年月を費やしたことだ。1997年の山一証券、1998年の日本長期信用銀行と日本債券信用銀行の破たんは、不良債権問題がいかに深刻であったかを示している。りそな銀行が実質的に国有化された2003年辺りから株式市場はいったん回復に向かったが、デフレという失われた20年が続いたのも、結局はバブル崩壊の後処理に膨大な時間がかかったことに起因する。
重要なのは、これが単に金融システムの問題にとどまらなかったことだ。日本企業は「雇用を守った」と言われるが、それはあくまで既存の雇用についてであり、新卒採用は相当抑制された。若者が希望の仕事に就けない「就職氷河期」を生み、非正規雇用も拡大した。
彼らが今、40歳代になっている。人的資源の大きな損失だ。バブル崩壊のしわ寄せは、好景気の恩恵を受けた世代を通り越して次の世代に行った。当時の経営者は、目の前にある雇用は守ったものの、その下の世代を犠牲にしたことをはっきりと認めなければならない。
このことが社会にもたらした悲劇は大きい。日本の人口ピラミッドは団塊の世代と、その子供たちである団塊ジュニアが2つのこぶになった「ひょうたん型」をしている。団塊ジュニアの子供世代がもう1つこぶを作っているべきだが、そうなってはいない。雇用が不安定化し、賃金も抑制された結果、団塊ジュニアの世代で出産が増えなかったためだ。日本の人口構造のゆがみはバブル崩壊と無関係に見えるかもしれないが、実はそれぞれ底流でつながっている。
2つ目は自然災害だ。1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災、ほかにも多数の大地震や水害が発生し、もはや自然災害は異常事態ではなくなりつつある。多くの人命を奪った災害が相次いだにもかかわらず、その教訓はあまり生かされていない。
日本は高度成長期に住宅地を無制限に拡大させてきたが、人口減少社会を迎える中、今後も続くであろう災害を想定した国土利用を検討すべき時期に来ているのではないだろうか。
🌸 <積み残した宿題>
平成の終盤で安倍晋三首相が打ち出した経済政策によって、バブル崩壊後の負の遺産の処理は進み、デフレではない状況まで経済は回復したが、次の時代に積み残した課題も多い。1つは財政健全化だ。政府債務残高の対国内総生産(GDP)比は、2018年に236.0%と、第2次世界大戦末期の水準を上回っている。持続可能でないことは明らかだ。
高齢化社会への対応も求められる。現在の医療・社会保障制度は、平均寿命が72歳だった50年以上前に作られたものだ。現在は寿命が84歳に延びる一方、団塊ジュニアに子供が少ないため、確実に支え手が減っていく。
団塊の世代が75歳以上になる2022年以降、医療費の自己負担が原則1割という後期高齢者の仕組みを続けられるのか、早急な見直しが必要だろう。同時に、生涯を通じて現役でいられる社会が実現できるよう地域レベルでシニアが活躍する場を作るほか、自立生活支援ロボットや、予防医療・介護のためのバイタル・データの有効利用など新技術の活用促進を組み合わせることが肝要だ。
さらに国際競争力の回復も焦眉の課題だ。スイスのビジネススクール、国際経営開発研究所(IMD)の世界競争力調査によると、日本のランキングは平成元年(1989年)の1位から2018年には25位まで低下した。
最近では、次世代通信規格「5G」などを巡る米中の激しいつばぜりあいが注目を集めている。究極的には世界の覇権争いだ。日本は技術面で脅威を与える存在ではなくなってきているため覇権争いに巻き込まれていない、という側面があることを深刻に受け止めるべきだ。
中国は2017年に国際特許出願件数で日本を抜き、米国に迫ろうとしている。量子コンピュータと人工知能(AI)では米中がしのぎを削り、次世代のスーパーコンピュータは中国が優位と言われている。
人口が減少していく日本は今後、経済規模でのプレゼンス後退は避けられない。世界への投資という点でも中国の巨大経済圏構想「一帯一路」に対抗できるような影響力の行使には限界がある。その中で日本が国際的なプレゼンスを維持するには、自由貿易の旗振り役としての姿勢を世界に示し続けること、そして、技術力・国際競争力の回復が重要になる。政府は次の世代に向け、ここに徹底的に力を入れるべきだ。
🌸 <避けて通れない労働市場改革>
日本経済は人口減少という厳しい逆風にさらされてはいるが、労働や資本の量の伸び以外の全要素生産性(TFP)の伸びが、先進国のなかでも低いのは説明がつかない。社会的な課題を解決するために技術革新(イノベーション)を起こすことが、企業が追い求める成長の意義であり、そうしたイノベーションの結果として、大きな新市場を生み出すという考え方が大事だろう。
次々とイノベーションを生むために日本がもっとも構造を転換しなければならないのは、労働市場の在り方だ。職種間・企業間で円滑な労働移動が進まない限り、これからの環境変化に対応できない。
まず、少子高齢化や長寿化から労働供給の構造が変化する。また、需要面では、AIやロボティックスなどの新技術が人間のタスクを代替していく動きが広がる一方で、技術を活用し新たなビジネスを生み出す人材の需要が高まる。
これらの労働需給の両面を考慮した三菱総合研究所の分析では、労働需給の不足超過幅は2020年代前半まで広がるが、後半は不足幅が縮小し、2030年には解消に向かうとの試算結果が得られる。
しかし、問題は職種別のギャップだ。事務職や生産職における雇用の余剰感が増す一方、専門人材が170万人不足するとの結果が得られる。つまり、日本の労働市場の本質的な課題は、「人材の大ミスマッチ時代」を迎えることにある。
三菱総研では、今後必要となる人材像を明確化するため、「タスクの特性」に着目して人材を二軸上にマッピングし、日本の人材ポートフォリオの姿を描き出すことを試みた。日本では「定型的・手仕事的なタスク」の占める割合が44%と高い一方、「創造的・分析的なタスク」は16%と低い。モノのインターネット(IoT)やAI、ロボットよる業務自動化が進むことを考えれば、より創造性が求められる仕事にシフトしていかなければならない。
その対策として、まず、仕事の内容を細かく規定した「ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)」の明確化が必須となる。そのうえで、質の高い学び直しを奨励し、新たに習得したスキルや知識を企業が評価する処遇制度へと、雇用慣行を見直し、より柔軟な労働市場を実現していく必要があろう。
平成の時代は負の遺産の処理に追われてきた分、これから迎える次の時代では、より持続可能な社会を求め、前向きな挑戦をしていく流れを作る必要がある。
安倍政権の「アベノミクス」で、負の遺産の処理は進み、現在の経済情勢は大幅に改善した。ここからは未来に対して責任ある政策がより重要となる。包括的で持続可能な社会を作るために長期的なビジョンを描き、企業も個人も、意志を持って、次の時代を切り拓いていく。そのような新時代の幕開けとなることを願っている。
武田洋子 三菱総合研究所 チーフエコノミスト (写真は筆者提供)
*武田洋子氏は、三菱総合研究所 政策・経済研究センター長、チーフエコノミスト。1994年日本銀行入行。2009年三菱総合研究所入社。米ジョージタウン大学公共政策大学院修士課程修了。
☀ このリポートは自明なことなのに目を背けて面倒な事を避ける政治屋とエリート
官僚、それに刹那的な楽しさに生きる多くの国民という組み合わせでは、行く着く先
は見えています。既に将来を嘱望されている若手研究者は海外留学から閉鎖的な日本の
大学や研究室には戻って来ない人数が年々、増加しています。そして、海外で起業しよう
とする若者も増えています。
なにしろ少子高齢化で老化し縮小する日本に何もこだわる必要は彼らにとっては
ないのです。
そして、現実は何かというと明治は良かったというお頭(つむ)が過去にトリップ
している老害の権力者やトップが満ち溢れている国で、国内で社会改革や政治改革と
いう茨の道を歩くより自分の才能に賭けて海外に飛翔しようとするのは当然の成り行き
です。
寂しい事ですが、これが現代の日本に存在する滔々たる大河の如き時世の流れです。