京都の長岡京、そこは、全国でも、竹の子が有名・・・・・・
・
・
竹が育つ絶好の環境・・・・・ でも、山は荒れてきています!
でも、山は荒れてきています!
・
・
やはり、人が入って、整備しなければ、いけないんでしょうね・・・・
・
・
長岡京市も、里山を守る為に、着々と、活動をされています。
・
・
私は、小さい頃は、たけのこ、あまり好きではありませんでした。
・
・
何故なら、・・・・・・毎日 竹の子が食卓に出てくるからでした。
竹の子が食卓に出てくるからでした。
・
・
昔は、ワカメと竹の子煮が主流で、毎日それを食べていたからです。・
・
今、私にとって、竹の子は、春の旬・・・・
・
・
食べ方も、工夫して、 美味しく食べてる次第で、ごじゃります!
美味しく食べてる次第で、ごじゃります!
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
京都の竹の子・・・ アクが少ない・・・・・
アクが少ない・・・・・
・
・
今日は、我が家の竹の子の湯がき方と、竹の子の刺身風にチャレンジします!
・
・
昨日、仲間の方から、「竹の子取りにおいでと」・・・
・
・
今年は、去年の秋に雨が少なかったので、不作 だと・・・・・
だと・・・・・
・
・
ほんと、少ない・・・・・
・
でも、手入れのされてない山の中の竹の子は、良い感じで、育ってる・・・???
・
・

・
・
何故かと聞くと、
・
・
「山の、竹林は、落ち葉が多く、雨が少ない年でも、落ち葉が、水分を含んでいるので、
・
・
竹に、十分な、水分が行き渡るらしいです」・・・・「ほんまかいなぁ~」・・・
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
「これ、持って帰り」・・・と・・・「デカ!」・・・・
・
普通売ってる竹の子とは、形も色も違いますが、味は、同じ・・・十分です!
・
・
それよりかは、竹の子は、鮮度が命・・・・
・
・
朝掘りの物で、出来るだけ、早く、湯がく、・・・それが、秘訣です!・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 私が、やってる、手抜き、竹の子の湯がき方です!
私が、やってる、手抜き、竹の子の湯がき方です!
・
・
基本!・・通常は、ぬかで、茹でるのですが、ここのは、必要ありません!
・
・
基本!・・通常は、少し、皮をむき、皮ごと、茹でるのですが、
・
・
なんせ、鍋に、入らないぐらいの大きさ・・・・
・・
「ええい!皮をむいてやれぃ~」・・・
・・
・
・

 「ぜ~んぶ、むいてやったわ~」・・・「わははははー」・・
「ぜ~んぶ、むいてやったわ~」・・・「わははははー」・・
でも、大丈夫!
・
・
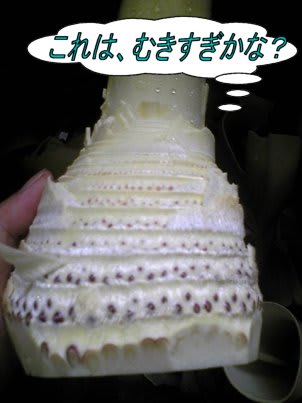
・
・
むいた、 皮も一緒に茹でるのだぁ~・・・・(これ、重要)・
皮も一緒に茹でるのだぁ~・・・・(これ、重要)・
・

・
・
普段は、入れませんが、念のために、「コメの、とぎ汁なんて、面倒くさい!」・・・ コメを少々入れてやれ!・・
コメを少々入れてやれ!・・
・
・

・
・
最初は強火で、沸騰したら、弱火で、30分~1時間(この時は大きかったので、1時間)
・
・
「後は、ひたすら、 1時間まつのである・・・・」・
1時間まつのである・・・・」・
・
竹串をさして、通るようであれば、Okです!
・
・

・
・
ここからが、 重要ポイント・・・・!・
重要ポイント・・・・!・
・
火を止めたら、そのまま、(お湯もそのまま、皮もそのまま、一切取り出さない)
・
・
1晩寝かしてさます・・・・(なんでも、寝ると元気になる)・・
後は、お好きなように、調理に使えます!
・
・
保管方法は、水に漬けた状態で、冷蔵庫に保管・・・・
・
・
注意・・・・水は、毎日変えてください!
・
・
注意2・・・・日にちが経つほど、香りが減っていくので、早く使うのがベスト!・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
では、お次に、竹の子の刺身風の作り方です!
・
・
通常、刺身は、生で食べる物・・・・・
・
・
私も、竹の子の刺身を食べた事はありますが、
・
・
私の作り方の方が、美味しいかも・・・・(採りたての物)
・
・
スーパーなどで売っているパック詰めはダメですので・・・・・
・
簡単です!
・
・
湯がいた、竹の子の頭の先の方を使用・・・・・
・
・
縦に、薄く切るだけです!
・
・
薄ければ薄いほど、美味しいです!・
・
ワサビ醤油で、美味しさバツグン!
・
・
 みんな、騙される・・・「美味しい美味しい!」と・・・・
みんな、騙される・・・「美味しい美味しい!」と・・・・
・
・
 器も、どうせなら、竹で作った、自家製皿・・・・・簡単に作れますよ!
器も、どうせなら、竹で作った、自家製皿・・・・・簡単に作れますよ!
・
・
エコにもなりますし、雰囲気も楽しめます!
・
・
竹の皿・・・最初は、緑で、竹の香りもしますが、徐々に、色は、変わって,いきます。
・
・
この、自家製器、もう、4年ぐらい使っています!
・
・
徐々に愛着が、わいてきます!
・
・

・
・
山椒の葉を乗せれば、まるで、 料亭の雰囲気・・・・・・
料亭の雰囲気・・・・・・
・
この、山椒の葉は、落ち葉で作った自家製腐葉土で、育ててる、山椒の木です!
・
・
身近にある、竹を利用して、家族で作った、うつわは、子供の勉強にもなりますし、なんといっても、思い出と、
・
・
 雰囲気が最高です!・・
雰囲気が最高です!・・

・
・
初物の竹の子は、美味しいですね!
・
・
子供達も、普通のお皿で、出すより、竹のうつわの方が、美味しそうに感じているようです!
・・
京都の竹の子(刺身風)でした!・
・
・
いげのやま ランキング順位は↓から確認出きます!(携帯からも、閲覧できます)
・
・

にほんブログ村
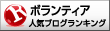
・
・
竹が育つ絶好の環境・・・・・
 でも、山は荒れてきています!
でも、山は荒れてきています!
・
・
やはり、人が入って、整備しなければ、いけないんでしょうね・・・・

・
・
長岡京市も、里山を守る為に、着々と、活動をされています。
・
・
私は、小さい頃は、たけのこ、あまり好きではありませんでした。
・
・
何故なら、・・・・・・毎日
 竹の子が食卓に出てくるからでした。
竹の子が食卓に出てくるからでした。・
・
昔は、ワカメと竹の子煮が主流で、毎日それを食べていたからです。・
・
今、私にとって、竹の子は、春の旬・・・・
・
・
食べ方も、工夫して、
 美味しく食べてる次第で、ごじゃります!
美味しく食べてる次第で、ごじゃります!・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
京都の竹の子・・・
 アクが少ない・・・・・
アクが少ない・・・・・・
・
今日は、我が家の竹の子の湯がき方と、竹の子の刺身風にチャレンジします!

・
・
昨日、仲間の方から、「竹の子取りにおいでと」・・・
・
・
今年は、去年の秋に雨が少なかったので、不作
 だと・・・・・
だと・・・・・・
・
ほんと、少ない・・・・・
・
でも、手入れのされてない山の中の竹の子は、良い感じで、育ってる・・・???
・
・

・
・
何故かと聞くと、
・
・
「山の、竹林は、落ち葉が多く、雨が少ない年でも、落ち葉が、水分を含んでいるので、
・
・
竹に、十分な、水分が行き渡るらしいです」・・・・「ほんまかいなぁ~」・・・
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
「これ、持って帰り」・・・と・・・「デカ!」・・・・
・
普通売ってる竹の子とは、形も色も違いますが、味は、同じ・・・十分です!

・
・
それよりかは、竹の子は、鮮度が命・・・・
・
・
朝掘りの物で、出来るだけ、早く、湯がく、・・・それが、秘訣です!・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 私が、やってる、手抜き、竹の子の湯がき方です!
私が、やってる、手抜き、竹の子の湯がき方です!・
・
基本!・・通常は、ぬかで、茹でるのですが、ここのは、必要ありません!
・
・
基本!・・通常は、少し、皮をむき、皮ごと、茹でるのですが、
・
・
なんせ、鍋に、入らないぐらいの大きさ・・・・
・・
「ええい!皮をむいてやれぃ~」・・・
・・

・
・

 「ぜ~んぶ、むいてやったわ~」・・・「わははははー」・・
「ぜ~んぶ、むいてやったわ~」・・・「わははははー」・・でも、大丈夫!
・
・
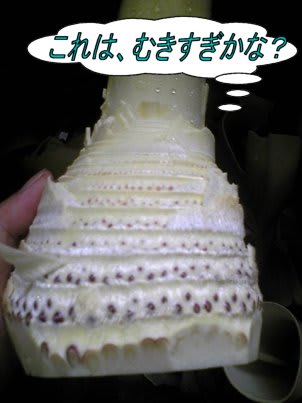
・
・
むいた、
 皮も一緒に茹でるのだぁ~・・・・(これ、重要)・
皮も一緒に茹でるのだぁ~・・・・(これ、重要)・・

・
・
普段は、入れませんが、念のために、「コメの、とぎ汁なんて、面倒くさい!」・・・
 コメを少々入れてやれ!・・
コメを少々入れてやれ!・・・
・

・
・
最初は強火で、沸騰したら、弱火で、30分~1時間(この時は大きかったので、1時間)
・
・
「後は、ひたすら、
 1時間まつのである・・・・」・
1時間まつのである・・・・」・・
竹串をさして、通るようであれば、Okです!
・
・

・
・
ここからが、
 重要ポイント・・・・!・
重要ポイント・・・・!・・
火を止めたら、そのまま、(お湯もそのまま、皮もそのまま、一切取り出さない)
・
・
1晩寝かしてさます・・・・(なんでも、寝ると元気になる)・・
後は、お好きなように、調理に使えます!
・
・
保管方法は、水に漬けた状態で、冷蔵庫に保管・・・・
・
・
注意・・・・水は、毎日変えてください!
・
・
注意2・・・・日にちが経つほど、香りが減っていくので、早く使うのがベスト!・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
では、お次に、竹の子の刺身風の作り方です!
・
・
通常、刺身は、生で食べる物・・・・・
・
・
私も、竹の子の刺身を食べた事はありますが、
・
・
私の作り方の方が、美味しいかも・・・・(採りたての物)
・
・
スーパーなどで売っているパック詰めはダメですので・・・・・
・
簡単です!
・
・
湯がいた、竹の子の頭の先の方を使用・・・・・
・
・
縦に、薄く切るだけです!
・
・
薄ければ薄いほど、美味しいです!・
・
ワサビ醤油で、美味しさバツグン!
・
・
 みんな、騙される・・・「美味しい美味しい!」と・・・・
みんな、騙される・・・「美味しい美味しい!」と・・・・・
・
 器も、どうせなら、竹で作った、自家製皿・・・・・簡単に作れますよ!
器も、どうせなら、竹で作った、自家製皿・・・・・簡単に作れますよ!・
・
エコにもなりますし、雰囲気も楽しめます!
・
・
竹の皿・・・最初は、緑で、竹の香りもしますが、徐々に、色は、変わって,いきます。
・
・
この、自家製器、もう、4年ぐらい使っています!
・
・
徐々に愛着が、わいてきます!

・
・

・
・
山椒の葉を乗せれば、まるで、
 料亭の雰囲気・・・・・・
料亭の雰囲気・・・・・・・
この、山椒の葉は、落ち葉で作った自家製腐葉土で、育ててる、山椒の木です!
・
・
身近にある、竹を利用して、家族で作った、うつわは、子供の勉強にもなりますし、なんといっても、思い出と、
・
・
 雰囲気が最高です!・・
雰囲気が最高です!・・
・
・
初物の竹の子は、美味しいですね!
・
・
子供達も、普通のお皿で、出すより、竹のうつわの方が、美味しそうに感じているようです!
・・
京都の竹の子(刺身風)でした!・
・
・
いげのやま ランキング順位は↓から確認出きます!(携帯からも、閲覧できます)

・
・
にほんブログ村











