
一昨年から取り組んでいるミスト栽培。気になっていることがひとつありました。
それが水滴の跳ね上げ。安価な装置のため、小さな噴水になる時があるのです。
そこで見つけたのが装置に取り付ける傘。噴霧口の真上につけ、水滴の飛散を防ぎ、
ミストだけを傍から排出させる部品です。これは付属品ですが簡単に手作りできそうです。
ドライミストは微細な水粒ですが、水蒸気より大きいので目に見えます。
したがって水粒が放出されると、重いのでゆっくり下方に落ちていくのがわかります。
とはいっても微細なので水面付近を浮遊しています。
この浮遊している水粒が溜まっていくと、ミストの層は次第に厚くなっていきます。
FLORAの実験では30秒ほどで13cmぐらいの高さになり
発生を止めると2分ぐらいで消えていくことがわかりました。
しかし面白いのはその後。蓋を開けた状態で噴霧しても
すぐ蒸発してしまうので、湿度は高くなりませんが
密閉容器の中だと数時間もの間、高湿度を保っているのです。
いろいろな文献や専門家の意見から考察すると、ミストが噴霧され、
根に付着し水滴となり濡れている時に、植物は養水分を吸収しているようです。
水滴のサイズはあまり養水分吸収には関係ないようなのです。
しかしミストは15分で止まってしまいます。次の噴霧は早くて1時間後、
夜間では5時間も水分が供給されません。おそらくこの我慢の時間を
密閉容器内の高い湿度とそれを吸収できる湿気中根で乗り切っているのではないかと
現在FLORAは推測しています。つまりミストを断続的に発生させることで
作物の吸水を制限(節水)するとともに、高い湿度で生命が維持できる環境を提供。
それに植物が湿気中根で応えていると現在考えています。
不思議なミストの振る舞いに興味津々のFLORAです。










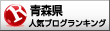
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます