
Arctic amplificationという専門用語がある。
1951年から1980年にかけての気温分布と、2000年から200年にかけての気温分布を比較すると、全体の平均では0.6℃気温が上昇しているのに対して、北極圏ではほぼ倍の2℃上昇しているという。
つまり、北極圏の気温増幅が他の地域に比較して著しく高いことを意味している。
一番大きな要因としては、アルベドの変化だと言われている。
海洋のアルベドは0.06である。
つまり太陽エネルギーの94%を吸収する。
氷だけの場合だと、アルベドは0.5である。
50%が反射され、50%が透過する。
氷の上に雪が積もると、アルベドは0.9になる。
90%の太陽エネルギーが反射される。
したがって、雪や氷が融け始めると急速に太陽エネルギーが海洋に取り込まれ、さらなる水温上昇につながるというのだ。
一方、NASAの気象学者は、熱帯域における積乱雲の発達が熱の鉛直輸送をもたらすので、結果的に熱帯域では海面水温が上昇しにくいと言っている。
そう言えば、今年は台風や竜巻の発生が多かった。
暑くなりすぎると熱的な調節機構が働きだすのだろう。
こんな膨大なエネルギーの一部を拝借できないのだろうか。
そこで、Natural Energy Lensという考えを提唱してみたい。
自然エネルギーレンズとでも言うのだろうか。
暑くなることによって運動エネルギーが狭い領域に集約される系を見つけて、そのエネルギーの一部を利用しようというものだ。
境界層の厚さ=1.3×摩擦速度÷[f+(1+(N^2/f^2))^(1/4)]という関係がある。
ここで、fはコリオリパラメーターであり、Nは浮力周波数である。
表面水温が上昇するとNが増大するので、境界層の厚さは薄くなる。
もし外部から与えられる運動エネルギーが同じなら、境界層が薄くなるほど流速は速くなる。
そんな場所があれば、そこに発電機をおく。
実は、びわ湖がその有力な場所の一つではないかとひそかに思っているのだが。










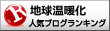

 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken





